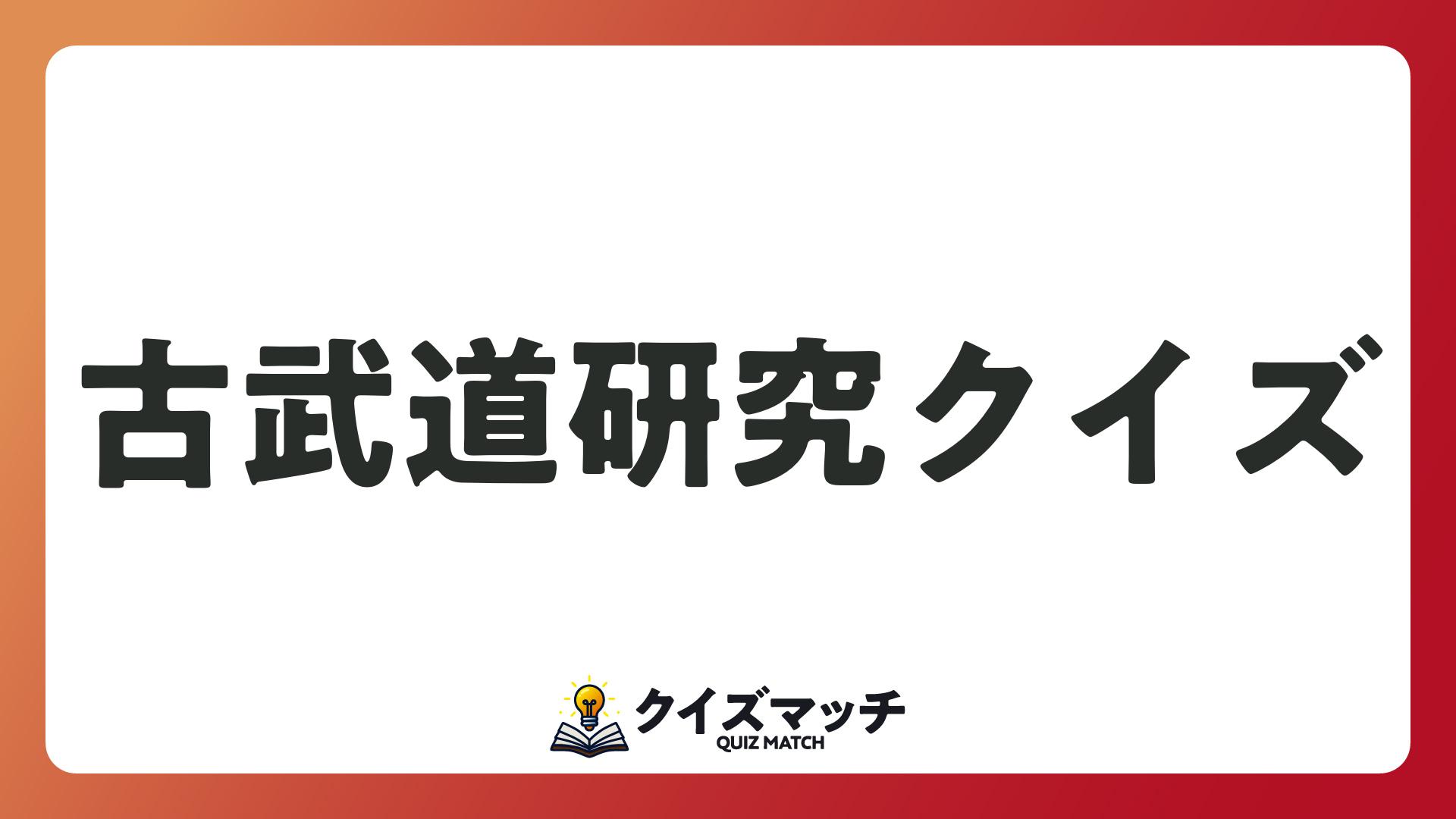古武道の奥深さに迫る 10 問の究極クイズ
日本の伝統武術の歴史は、時代とともに変化を遂げ、様々な流派が生み出されてきました。その中から国の重要無形文化財にも指定されている最古の流派から、近代に至るまで、多彩な古武道の世界を探ってまいります。古武道愛好家はもちろん、歴史や伝統文化に興味のある方も必見の、10 問の究極クイズにご挑戦ください。
Q1 : 江戸初期に夢想権之助が創始した神道夢想流の主武器はどれか?
神道夢想流は関ヶ原合戦後の1600年代初頭に夢想権之助勝吉が創始したと伝えられ、徳川家光の時代に旗本甲斐庄正房の庇護を受けて発展した。流派の中心は四尺二寸一分約128センチの杖で、刃物を持たない木杖一本で刀を制する理合を追究している。基本形表から始まり裏、影、五行、六合など全64手が体系化され、後世に附帯する剣、短杖、鎖鎌などの科目も加わったが、あくまで杖術が核である。警視庁武道の逮捕術や現代の杖道競技の源流としても評価が高い。
Q2 : 1532年に竹内久盛が創始したと伝わり、日本最古級の柔術流派とされるのはどれか?
竹内流は備中国の武将竹内久盛が天文元年に山中の祈願所で得た神託をもとに柔術と小具足術を体系化したとされる古流で、捕手、武器取り、奥伝に甲冑組討など多彩な科目が伝わる。江戸初期には藩校や諸国の道場で教授され、嘉永年間に書かれた竹内流伝書には関節技や当身技が詳細に記録されている。古武道研究では柔術の源流を探る際に不可欠な素材であり、今日も岡山県と山形県を中心に宗家系統が活動している。
Q3 : 柳生新陰流の「無刀取り」の思想形成に影響を与えた臨済宗の高僧は誰か?
柳生宗矩の師である柳生宗厳は京都大徳寺の沢庵宗彭と親交を結び、その禅的教えから敵刃先を受ける前に勝ちを取るという無刀取りの心法を深化させたと伝えられる。沢庵は不動智神妙録において心が動けば体が遅れるという理を説き、これは後に宗矩が将軍家に指南する際の理論的支柱となった。宗矩の日記玉栄拾遺にも沢庵との往来が記載され、剣と禅の交流事例として古武道研究者の注目を集めている。
Q4 : 鎖鎌術を専科とし、創始者正木膳兵衛尉が下総関宿で編み出した後に土佐藩にも伝わった流派はどれか?
正木流鎖鎌術は江戸前期の武芸者正木膳兵衛尉豊繁が鎌と鎖分銅を組み合わせて考案したとされる。鎌で相手の視線を誘い、分銅鎖で打ち絡め、最後に鎌刃で止めを刺す三段構えが特徴。下総関宿藩を中心に広まったが、土佐藩の上士警護隊へ技術供与されたことで幕末の志士たちにも影響を与えた。現在は高知県と千葉県で稽古が続けられ、鎖鎌研究の貴重な生資料となっている。伝書には鎖の長さを身長の一・二倍とし遠心力を得る理合が詳細に記され、現代の物理解析でも合理性が指摘されている。
Q5 : 宮中儀式「百々手式」を現在も奉仕し、弓馬礼法を今に伝える流派はどれか?
小笠原流は鎌倉武家社会の礼法を司った小笠原長清を始祖とし、射礼や歩射など弓馬儀礼を体系化してきた。明治期には宮内省に礼法教授を委嘱され、毎年一月に明治神宮で行われる百々手式はその古式射法を公開する場となっている。射技だけでなく装束、作法、所作が細密に定められており、現代弓道で行われる礼法の骨格にも大きな影響を与えた。『弓馬礼式指図』や『当流射法巻』など関連文献も豊富で、武家礼法研究の基礎資料として評価が高い。
Q6 : 幕末に近藤勇・土方歳三ら新選組隊士が学んだ兵法流派はどれか?
天然理心流は多摩地方の農兵近藤周助が開いた実戦剣術で、素朴な打太刀と当身を重視するのが特色。四代目を継いだ近藤勇は試衛館道場を江戸に構え、土方歳三や沖田総司が腕を磨いた。1863年、彼らは浪士組として京都に上り新選組を結成、池田屋事件など市中警護で流派の技を実戦に供した。流派名は「天然水の理に従う剣」を意味し、当世流行の試合稽古よりも実用性を重んじる。現在も日野市で演武会が開かれ、幕末剣術史研究で欠かせない存在である。
Q7 : 二天一流を熊本藩に伝え、『独行道』最古写本を残した宮本武蔵の高弟は誰か?
寺尾孫之允は宮本武蔵晩年の直弟子で、細川家に仕える熊本藩士であった。武蔵の逝去直前に『兵法五輪書』とともに託された『独行道』を写し取り、これが現存最古の写本として国文学的にも価値が高い。孫之允は武蔵から二刀一流の免許を授かり、後に二天一流と改称して藩校時習館で教授した。藩士の試合記録には太刀と小太刀を同時に操る形が記され、西南戦争時にまで稽古が継続された。武蔵研究や近世兵学史を考察する上で、寺尾本系譜の文献は一次資料として極めて重宝される。
Q8 : 日本で現存する流派の中で国の無形文化財に指定されている最古の総合武術流派はどれか?
天真正伝香取神道流は室町時代の飯篠長威斎家直を祖とし、剣術を中心に槍、薙刀、棒、居合、手裏剣などを網羅する体系を有する。1960年に流派保存会が結成され、1967年に千葉県、1968年に国の無形文化財保持団体に認定された。現存最古とされる理由は、それ以前に伝書が確認できる流派の中で途絶せず連綿と続いている点にあり、古武道研究では基準点とみなされる。また海外への普及も早く、欧米の大学での教習例が多いことから、体系保存と国際研究の両面で大きな影響を与え続けている。
Q9 : 宝蔵院流槍術を創始し、十文字槍で名を馳せた奈良興福寺の僧は誰か?
宝蔵院覚禅房胤栄は奈良興福寺の僧で、室町末期に槍術の研究を深め、十文字穂先を持つ鎌槍を考案したことで知られる。胤栄の槍は突出と薙ぎを同時に行えるため剣術家に対しても優位を取れるとして評判を呼んだ。史料『胤栄記』によれば柳生宗厳や宮本武蔵との交流も示唆され、後に宝蔵院流は幕末まで多くの道場で教授された。現在でも奈良市で形が伝承され、槍術研究には欠かせない流派である。
Q10 : 江戸初期にまとめられた兵法書『兵法家伝書』の著者は誰か?
『兵法家伝書』は大和国の大名柳生宗矩が徳川家光に進呈するために記した兵法書で、柳生新陰流の理合を平易な文体でまとめたものとして有名である。書中では心の持ち方を活人剣の理念に基づき説くとともに、太刀の間合や足遣いを図解なしで言語化する工夫が見られる。宗矩は幕府兵法指南役を務めたため、この書は江戸武家社会で広く読まれ、後世の流派設立にも思想的影響を与えた。研究者は本文の語彙や書体から宗矩晩年の自筆と判断している。
まとめ
いかがでしたか? 今回は古武道研究クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は古武道研究クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。