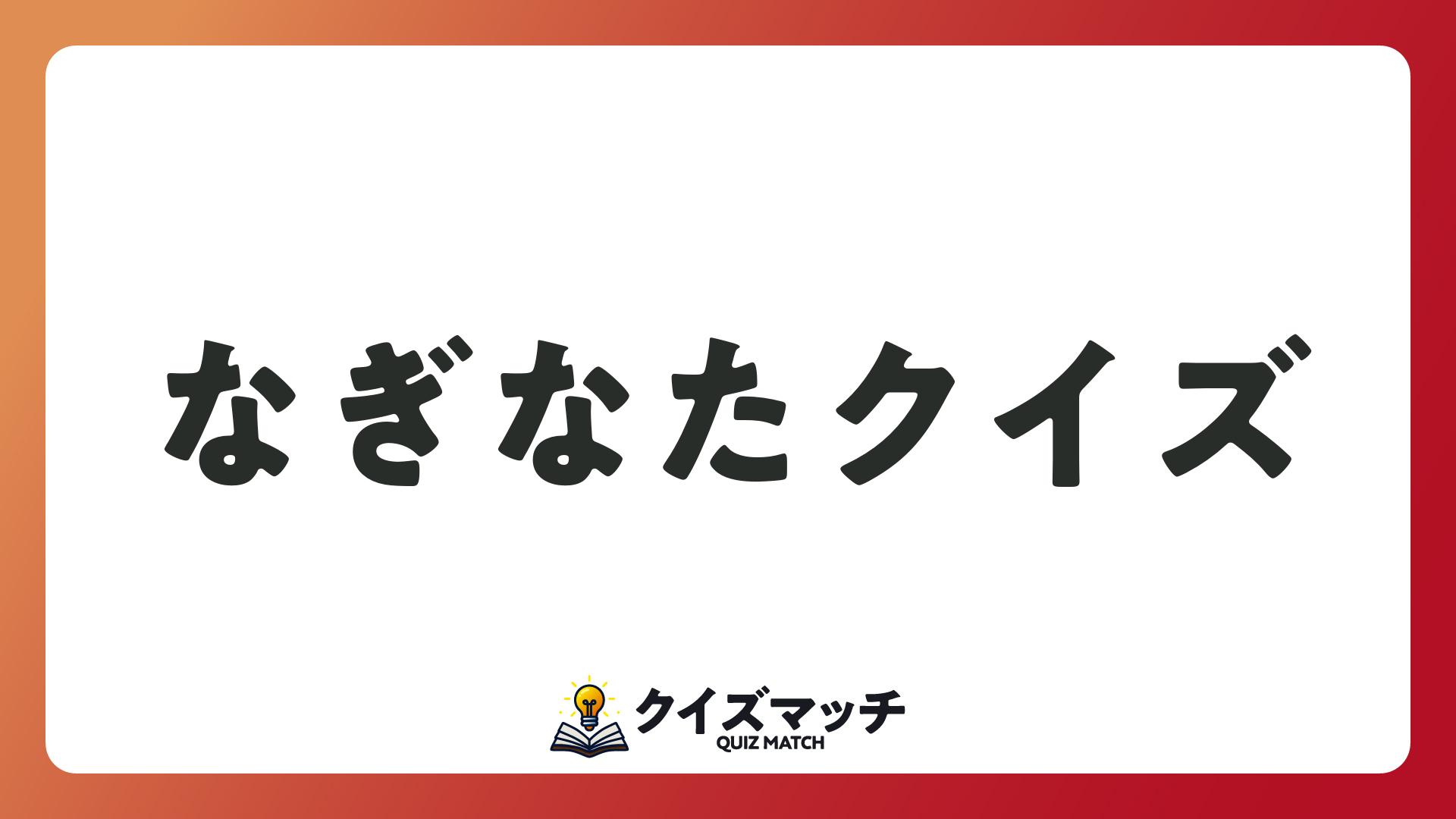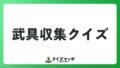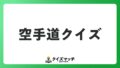現代なぎなた競技の有効打突部位は「面」「小手」「胴」「すね」の四カ所に限定されています。これらの部位を正しい間合い、姿勢、刃筋で打突し、気勢と残心を示したときに一本が認められます。一方で足の甲や足先は安全面と伝統的な技法の観点から除外されており、いかに的確に当たっていても得点にはなりません。本クイズでは、この競技ルールを中心に、なぎなたの歴史、用具、試合形式などについて10問お届けします。なぎなた競技に関する知識を深めていただければ幸いです。
Q1 : 全日本選手権個人戦(成人)の試合時間は通常何分か?
全日本なぎなた選手権など成人個人戦の試合時間は3分と定められている。3分間で2本先取した側が勝者となり、時間内に決しない場合は延長戦に入る。2分では技の組み立てが単調になり、4〜5分では体力差が際立つため、攻防の緊張感と安全性のバランスを考慮して3分が採用された。限られた時間内で間合い調整、気勢、残心を示しつつ有効打突を取る必要があるため、選手には高い集中力と戦術眼が求められる。
Q2 : しないなぎなたで竹を束ねた先端の有効打突部は何と呼ばれるか?
しないなぎなたの先端から約30センチの範囲は竹を革で包み実際の刃に見立てられ、「物打ち」と呼ばれる。有効打突は物打ちで正確に打ち込むことが条件のため、選手は常にその部分が相手の有効部位に当たるように刃筋と軌道を整える必要がある。さややはばきは刀の部品名で、現代競技用具としては用いられない。裏刃は古流の概念で正式名称ではない。物打ちの理解は、安全かつ的確な技を行うための基礎知識である。
Q3 : 国際なぎなた連盟(INF)が設立された年はいつか?
国際なぎなた連盟(INF)は、日本国外でも普及し始めたなぎなたを統括する国際組織として1990年にジュネーブで設立された。現在はアメリカ、フランス、オーストラリア、ブラジルなど約20か国が加盟し、4年ごとに世界選手権を開催している。設立以前は各国が独自に活動していたため用具規格や審判法にばらつきがあったが、INFの発足により統一ルールが採択され、国際交流と技術水準の向上が大きく進んだ。
Q4 : 全日本なぎなた連盟の段位制度で現在の最高段位は何段か?
全日本なぎなた連盟の段位制度は初段から七段までで構成され、七段が最高位である。七段審査では形・試合の熟達度に加え、指導力、礼儀作法、学科試験など総合的な評価が行われるため合格率は数パーセントにとどまる。剣道や居合道では八段が存在するが、競技人口や審査基準の違いから薙刀では七段で最高位とされる。七段取得者は連盟の要職や審判長を務めることが多く、競技普及と後進育成の中心的役割を担っている。
Q5 : 試合や稽古で使われるしないなぎなたは竹を何枚組み合わせて作られているか?
しないなぎなたは竹を4枚に割り、それらを革紐と金具で束ねて作る構造を採用している。4枚とすることで弾力、軽量性、耐久性のバランスが最も良好になるとされる。3枚ではしなりが不均一になり折損しやすく、5枚以上では重量が増して操作性が低下する。各竹片は乾燥度と厚みを揃え、打撃時に均等にしなるよう精密に加工される。大会前の検量では割れや剥離がないか厳しく確認され、規格外の用具は安全のため使用を禁止される。
Q6 : 現代なぎなた競技の有効打突部位に含まれないものはどれ?
現代なぎなた競技では、有効打突部位として定められているのは「面」(頭頂部)、「小手」(手首)、「胴」(正中線を含む胴体)、「すね」(脛)の四カ所のみである。これらの部位を正しい間合い、姿勢、刃筋で打突し、気勢と残心を示したときに一本が認められる。足の甲や足先は安全面と伝統的な技法の観点から除外されており、いかに的確に当たっていても得点にはならない。したがって足先は有効打突部位には含まれないことを理解しておく必要がある。
Q7 : 成人用しないなぎなたの全長は規定で何センチメートル以内と定められているか?
全日本なぎなた連盟の競技規則では、成人が試合で用いるしないなぎなたの全長は225センチメートル以内と定められている。古流の長大な木製薙刀を模しつつも体育館内で安全に扱える上限として設定された数値で、検量で1ミリでも超過すると失格となる。長過ぎる用具は回転半径が大きく危険性が増すため厳格に制限される一方、短過ぎる用具は技の再現性が損なわれるため推奨されない。規格を守ることは選手の責務であり、公平な競技運営に欠かせない。
Q8 : 全日本なぎなた連盟制定の「なぎなたの形」は全部で何本あるか?
全日本なぎなた連盟制定形は実戦の攻防理合を体系的に学ぶために制定された七本で構成されている。前半五本の仕掛形は先に動いて攻撃を仕掛ける理合を、後半二本の応じ形は受けから反撃に転じる理合を示しており、合わせて七本で一組となる。各形では打突部位だけでなく足運び、間合い、気迫、残心が厳格に求められ、段位審査や演武会でも重視される。七本全てを習得することで、薙刀特有の円の理合と刃筋の使い方を身につけられるとされる。
Q9 : 脛を守るために装着する防具の正式名称はどれか?
なぎなたの防具は剣道に似ているが、下段からの斬り下ろしや斜め打ちが多いため、脛を守るための「すね当て」が追加されている。すね当ては硬質樹脂や強化繊維で作られ、膝下から足首までを覆い、打突の衝撃を骨に直接伝えないよう設計されている。大会では安全確保のため着用が義務付けられ、装着していない選手は出場できない。垂や胴は胴体を、小手は手首を守るが、脛には対応していないため名称を混同しないことが重要である。
Q10 : 薙刀の名手として『平家物語』にも登場する女性武者は誰か?
平安末期の女武者・巴御前は、源義仲に仕えた逸話で知られ、『平家物語』では長大な薙刀を自在に操り数騎の武者を討ち取ったと描かれている。彼女は武家の女性が戦場で活躍した象徴的存在とされ、のちに薙刀が婦人武芸として受け継がれる際の精神的支柱となった。静御前は舞の名手、北条政子や淀殿は政治的・文化的手腕で有名だが、薙刀の腕前を示す記述は乏しい。歴史と武芸の両面から、薙刀と深く結びついて語られるのは巴御前である。
まとめ
いかがでしたか? 今回はなぎなたクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はなぎなたクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。