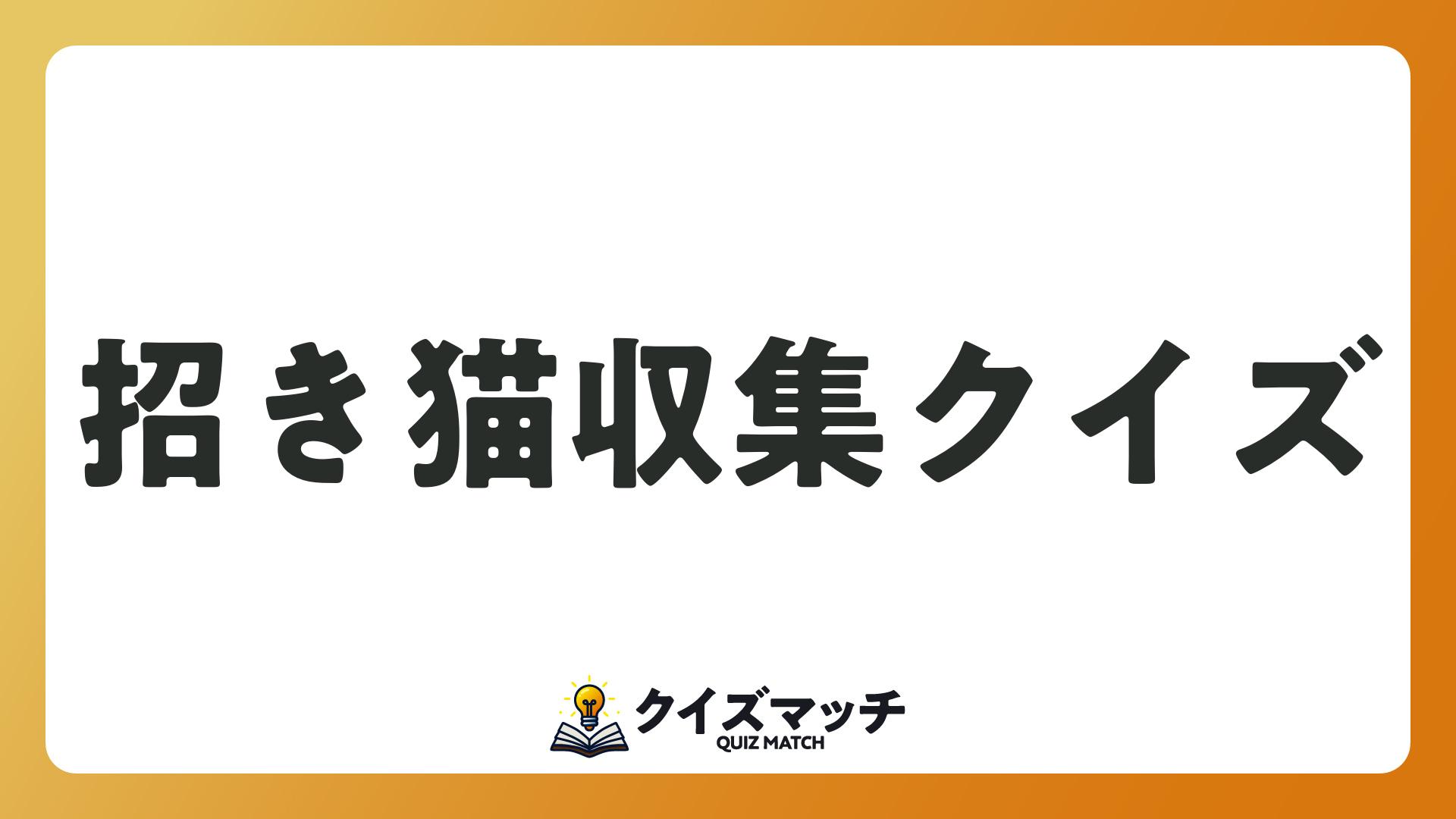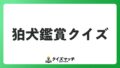招き猫は日本の縁起物として古くから親しまれており、その豊かな意匠と由来から収集家の関心を集めています。右手を上げれば金運や商売繁盛を、左手なら客を呼び込む効果があると信じられ、さらに両手を挙げた「欲張り招き」は双方の願いを叶えてくれると期待されます。色や手の向き、ヒゲの本数にも象徴的な意味が込められ、江戸時代から今日に至るまで工芸品としての発展を遂げてきました。この記事では、招き猫コレクションの醍醐味を味わえるクイズを通して、その奥深い世界を探っていきます。
Q1 : 三毛柄の招き猫が最も縁起が良いとされる理由として正しいものはどれ?
三毛柄は日本猫固有の毛色で、遺伝上ほとんどが雌となり雄が極めて稀少であるため、昔から滅多に出会えない幸運の象徴とされた。職人はその希少性を縁起の良さに重ね、最も標準的な招き猫の彩色に用いた。博物館の収蔵例を見ても初期作品はほぼ三毛で、他の色バリエーションは明治後期以降に増える。三毛が基本と知っておくと、制作年代や由来を推測する手掛かりになる。
Q2 : 左手を挙げた招き猫が象徴すると言われるご利益はどれ?
左手は人や客を招くとされるため多くの飲食店や居酒屋の入口に置かれる。江戸期の瓦版には『左は人を招き右は金を招く』と記されており、当時から棲み分けがあったと分かる。さらに手を高く上げれば遠くの客、低く上げれば近くの客を呼ぶという細かな解釈もある。収集の際に手の高さや向きを観察すると、作り手が願いに合わせてどんなメッセージを込めたかを読み解け、鑑賞が一段と深まる。
Q3 : 磁器製招き猫の大量生産地として明治期から知られ、現在も『招き猫ミュージアム』がある愛知県の焼き物産地はどこ?
愛知県瀬戸市は平安期から続く日本有数の陶産地で、明治に入ると石膏型による成形技術を取り入れ大量生産が可能になった。軽量で丈夫な磁器の招き猫は行商にも扱いやすく、全国へ出回ったことで定番縁起物として定着した。現在も瀬戸蔵ミュージアムには明治から現代までの型や彩色見本が展示され、年代ごとのデザイン変遷が一望できる。瀬戸産を基準にすると他産地の特徴も比較しやすい。
Q4 : 多くの招き猫が抱える小判に書かれている金額として最も一般的なのはどれ?
招き猫が抱える小判には『千万両』と書かれることが最も多い。江戸時代の庶民にとって千万両は天文学的な大金で、到底手が届かない額をあえて掲げることで無限の富を呼ぶとの願いを込めた。千両や万両と記す例もあるが、圧倒的に千万両がポピュラーで型も数多い。収集家は文字の書体や縁取りの模様から窯元や時代を判別する手掛かりを得ることができ、観察ポイントとして重要だ。
Q5 : 魔除け・厄除けのご利益があるとされる招き猫の色はどれ?
黒色は古来より魔除けや厄除けの色とされ、江戸後期には夜目に紛れて泥棒を追い払うとの俗信から黒猫自体が厄除けの象徴となった。明治以降、疫病除けの願いが招き猫にも取り入れられ、黒招きが作られるようになった。赤が病除け、金が金運など色によるバリエーションは時代とともに増えるが、黒は現在でも護符的意味合いが強い。色彩の意味を押さえると棚に並べたときのストーリー性が高まる。
Q6 : 日本招き猫倶楽部などが制定した『招き猫の日』はいつ?
『来る福』の語呂合わせから9(く)2(る)9(ふく)として9月29日が招き猫の日に制定された。同日に瀬戸市や伊勢市で大規模な招き猫祭りが開かれ、新作市や作家の実演、奉納式を見ることができる。コレクターにとっては限定品や作家物を入手する絶好の機会で、作品証明書付きの一点ものが多数流通する。祝日ではないため参加には計画が必要だが、現地でしか味わえない熱気と情報交換の価値は大きい。
Q7 : 一般的な招き猫の顔に描かれるヒゲの合計本数は左右合わせていくつ?
招き猫の顔は単純化されているが、左右3本ずつ計6本のヒゲを描くのが最も一般的とされる。六は“無”に通じるとして無病息災や無限を連想させることから縁起が良いと好まれた数だ。加えて偶数は対で福を呼ぶとの思想もあり、職人は6本を基本形とした。ヒゲの太さや先端の形状には工房ごとの個性が表れるため、数だけでなく描き方にも注目すると産地判別や作家特定のヒントになる。
Q8 : 両手(両前足)を挙げた招き猫が一般的に表すとされる意味はどれ?
両手(両前足)を同時に挙げた招き猫は、右手の金運と左手の客招きを合わせ持つと解釈されるのが一般的で、二つの願いを一体で満たす“欲張り招き”とも呼ばれる。昭和中期に観光土産として登場し、海外のフィギュア文化にも影響を与えた。手が耳より高いもの、ハート形に曲げるものなどデザインの自由度が高く、現代作家は創作性を発揮しやすい。収集家は造形のバランスや安定性を見比べるのが楽しみとなる。
Q9 : 右手を挙げた招き猫が特に授けるとされるご利益はどれ?
商売人の間では右手を挙げる猫はお金をつかむ手とされ、主に金運や商売繁盛を願う店の軒先に置かれてきた。一方左手は客を招くといい、飲食店など人を集めたい場所に向く。同じ猫でも左右で意味が違うことを知っていれば、コレクターは場面ごとに最適な個体を選べる。また両手型は二つの願いを欲張って込めた形として近年人気で、手の高さや角度の差異を比べるのも収集の醍醐味だ。
Q10 : 招き猫発祥の地として最有力視され、境内に数千体の招き猫が奉納されている東京都世田谷区の寺院はどこ?
江戸時代後期、世田谷の豪徳寺で和尚の飼い猫が招き入れた武士が雷雨を避けられたという逸話が広まり、門前で招き猫を授与するようになった。浅草寺や今戸神社などにも類似の伝承があるが、豪徳寺は寺の境内に数千体の白い招き猫が奉納される独特の風景があり、資料的にも最古級と認められている。発祥地の有力候補を実地で訪れれば、由来書や奉納方法など学びも多くコレクションの理解が深まる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は招き猫収集クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は招き猫収集クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。