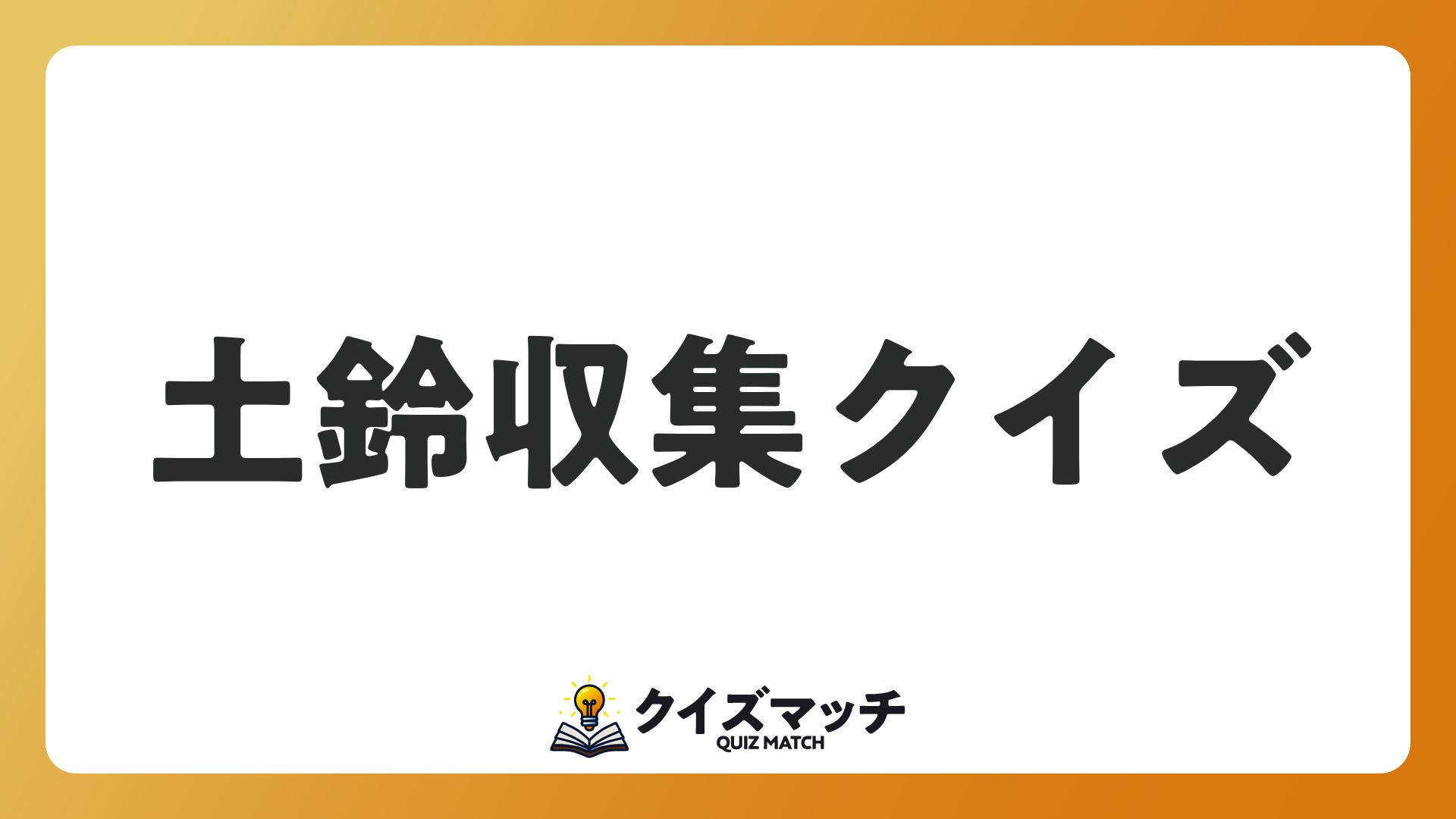土鈴収集クイズ – 玄関に響く伝統の音
土鈴は古くから日本の家々に親しまれてきた素朴な民芸品です。玄関や神棚に吊るされ、悪霊を祓いつつ神祇を迎え入れる役割を果たしてきました。鈴の音色に込められた清めの意味と儀礼性に着目し、今回はさまざまな土鈴ゆかりの知識を問うクイズを用意しました。日本の郷土文化を学びつつ、土鈴の歴史と魅力を探っていきましょう。
Q1 : 福島県会津地方の縁起物「赤べこ」には土鈴の形で作られたものもあるが、赤べこが模している動物は何か。 馬 犬 羊 牛
赤べこは会津の方言で赤い牛を意味し、17世紀の福満虚空蔵菩薩圓藏寺の再建に協力した牛が伝説の起源とされる。疫病を防ぐ守り神として庶民に愛され、鶴ヶ城下の玩具職人たちが張子や土鈴で表現した。首振り構造と共通する柔らかな音色が特徴で、牛以外を題材にした派生品はあるものの、名称そのものが牛に由来しているため正解は牛である。馬や犬をかたどる別種の郷土玩具と混同しやすいが、赤べこの赤は牛の体色を示す。
Q2 : 伏見人形や伏見土鈴が生まれた門前町の総本宮で、稲荷信仰の中心とされる神社はどこか。 北野天満宮 伏見稲荷大社 清水寺 平安神宮
伏見土鈴は伏見稲荷大社の参道沿いで売られる土産物として発達したため、神社と縁が深い。伏見稲荷大社は全国三万社に及ぶ稲荷神社の総本宮で、稲荷大神の象徴である狐を主題にした狐鈴が特に知られる。江戸期の絵図にも境内に並ぶ鈴売りの姿が描かれており、狐のほか千鳥、だるま、干支など多彩なモチーフがここから各地に広まった。北野天満宮や清水寺でも土産物は売られたが、人形土鈴の系譜を生んだのは伏見稲荷大社だけである。
Q3 : 一般的な土鈴の本焼きは何度程度の温度で行うと良いとされているか。 約800〜900℃ 約400〜500℃ 約1200〜1300℃ 約1600〜1700℃
土鈴は軟質の陶土で成形し音色を重視するため、磁器のように高温で焼き締める必要がない。800〜900℃程度で焼成すると胎土が十分に焼きしまって硬度と軽さのバランスが取れ、鈴内部に空洞を残したまま割れにくい強度が得られる。400℃台では脱水が不完全で脆く、1200℃を超えると粒子が溶融してガラス化し、音が鈍くなる。1600℃は磁器用の温度帯で、土鈴本来の柔らかな高音が失われるので避けられる。
Q4 : 2015年の未(ひつじ)土鈴から干支土鈴を集め始めた場合、同じ未の土鈴が再び頒布されるのは西暦何年か。 2024 2025 2026 2027
干支は十二支で構成され、子から亥まで12年で一周する。2015年は未年であり、翌年以降は申、酉…と進む。12年後に同じ干支が巡ってくるため、未の次回は2015+12=2027年になる。土鈴愛好家の間では十二支コンプリートに最低12年かかると言われ、途切れずに神社や窯元から求め続ける根気が必要とされる。2024年は辰、2025年は巳、2026年は午の年にあたるため、いずれも未年ではない。
Q5 : 土鈴はその音色から英語圏でしばしば何と呼ばれるか。 Clay whistle Clay drum Clay bell Clay pipe
英語の民芸玩具分類では鈴系統の鳴り物を bell と呼ぶのが一般的で、焼き物で作られた鈴は clay bell と表記される。whistle は空気を吹き込んで音を出す構造、drum は膜鳴楽器、pipe は管楽器を指すため、振って中の玉を衝突させる土鈴の構造とは異なる。海外の民芸市や博物館でも Japanese clay bell の名称で展示され、伏見、瀬戸、会津など各地の土鈴が紹介されている。また、学術的には idiophone(体鳴楽器)に分類され、振動体自体が共鳴して音を出す点が金属製の hand bell と同じであることも解説に用いられる。
Q6 : 土鈴の成形後に行う「皮乾」工程で最も望ましい乾燥方法はどれか。 急速な乾燥 徐々な自然乾燥 直射日光での乾燥 電子レンジ乾燥
皮乾は造形直後の水分を徐々に抜いて歪みや割れを防ぐ工程で、粘土表面が革のように締まるまで自然乾燥させるのが理想とされる。急速乾燥や直射日光では外側だけが硬化して内部に水分差が生じ、空洞を持つ土鈴は特に亀裂が入りやすい。電子レンジなど人工的な急熱も同様に危険で、音質を左右する空洞形状が崩れる恐れがある。ゆるやかな風通しの良い場所で数日かけ乾燥させることで、均一に収縮し良い音が出る。
Q7 : 備前焼で作られる招き猫土鈴などの表面に薪窯焼成中の灰が溶けて生じる自然釉の斑点は何と呼ばれるか。 桜吹雪 塩焼き 青萩 胡麻
備前焼は釉薬をかけず薪窯で長時間焼成することで窯変が起こることで知られる。松割木の灰が作品に降り注ぎ、1250℃前後で溶けて自然釉としてガラス質の粒状斑点を作り出す。この茶褐色の細かな粒は胡麻を振りかけたように見えることから胡麻と呼ばれ、湯呑や花瓶のみならず招き猫や土鈴にも現れる。桜吹雪や青萩は備前焼の別の窯変名で、塩焼きは陶磁器を塩で還元させる技法であり、胡麻とは別現象である。
Q8 : 土鈴が古来から玄関や神棚に吊るされる主な目的はどれか。 魔除けや厄払い 湿度計として使う 食品の保存容器 香りをつけるための香炉
土鈴は単なる玩具としてだけでなく、神事や民間信仰の道具でもあった。土の素朴な鈴音には清めの意味があると考えられ、邪気を払うとともに神霊を招くと信じられてきた。そのため江戸期の家屋では玄関や軒下に吊るす風習が定着し、特に節分や年越しなど災厄の気が入りやすい時期には音を鳴らして空間を浄めた。湿度管理や容器としての利用例はなく、主目的は一貫して魔除け・厄除けである。
Q9 : 江戸時代から続く代表的な郷土玩具「伏見土鈴」が製作されている都道府県はどこか。 大阪府 京都府 兵庫県 奈良県
伏見土鈴は豊臣秀吉が庇護した伏見稲荷大社の門前町で発達した伏見人形の系譜に属する。京都伏見の良質な粘土と街道を行き交う参詣者の需要が相まって、江戸中期には干支鈴や狐鈴など多彩な作品が量産された。幕末には諸国の土産物として名声を獲得し、明治期には全国の郷土玩具収集家がこぞって買い求めた記録が残る。今日でも京都市伏見区の数軒の窯元が伝統を継承しており、京都府以外で大量生産された事実はない。
Q10 : 土鈴製作で、素焼き後に彩色や釉薬を施し再度焼成する伝統的技法はどれと呼ばれるか。 練り込み 掛け分け 上絵付け ロクロ挽き
上絵付けは一度素焼きを済ませた胎土の上に顔料や釉薬をのせ、800℃前後で低温焼成して発色させる技法で、磁器のみならず土鈴にも広く用いられる。土鈴の場合、素焼きで音色を決定し、その後に行う上絵付けで干支や神獣などの細やかな文様を加えることで、郷土色や信仰的意味合いを視覚的に表現する。練り込みやロクロ挽きは成形法、掛け分けは釉薬を塗り分ける技法で、素焼き後の彩色を指す語ではない。
まとめ
いかがでしたか? 今回は土鈴収集クイズをお送りしました。
今回は土鈴収集クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!