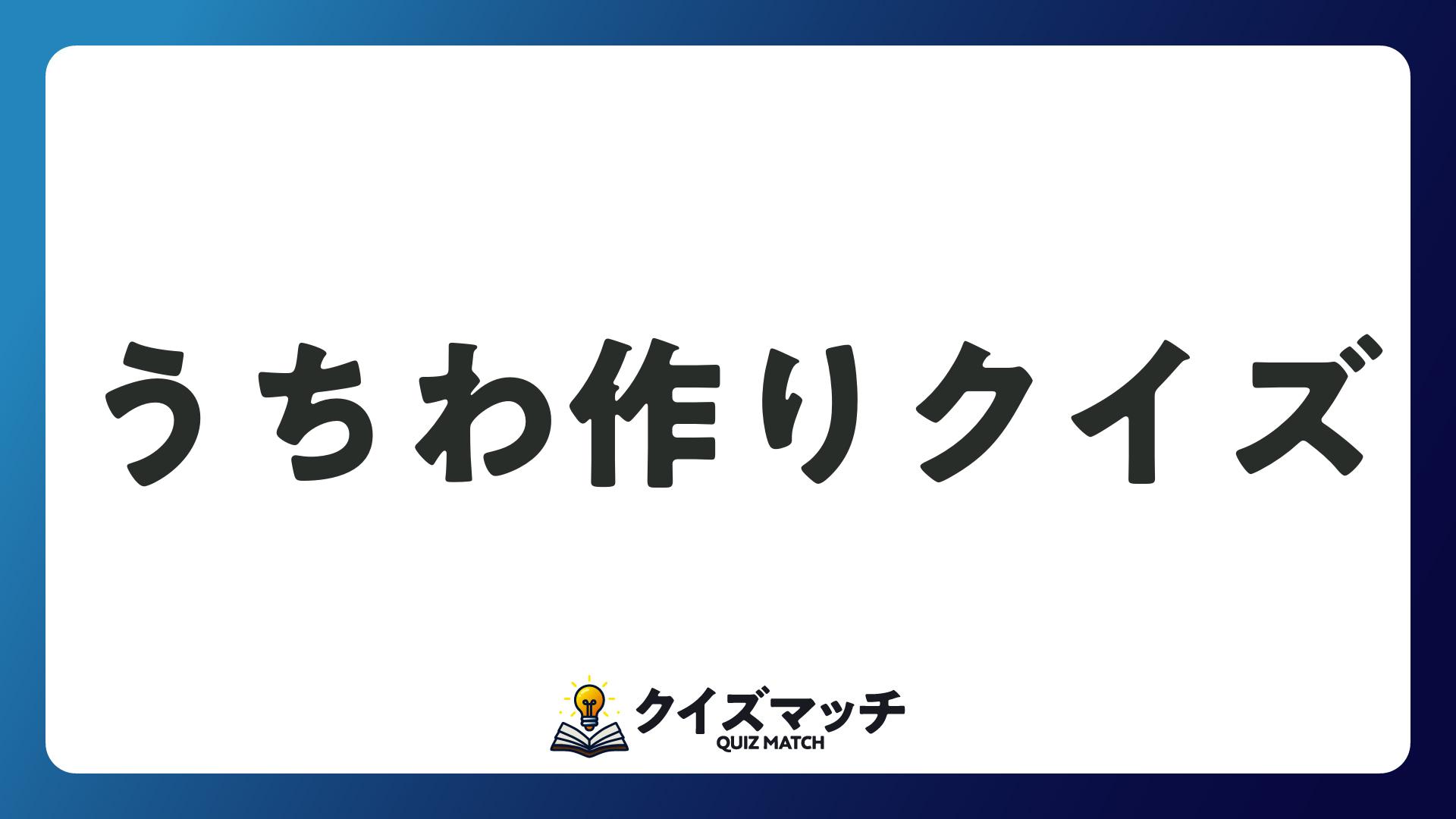夏の風物詩といえば、折りたたんでこぼこっと開くあの扇子、うちわです。しかし、うちわには実は長い歴史と伝統的な作り方があるのをご存知でしょうか? この記事では、うちわ作りのさまざまな知識を問う10問のクイズを紹介します。骨材や製法、染色技術など、うちわの魅力に迫る内容となっております。うちわはもはや単なる夏の必需品ではなく、日本の伝統工芸品としての側面を持つのだと、この機会に再発見していただければ幸いです。
Q1 : 京うちわに見られる“差し柄式”構造とは、柄をどのように取り付ける方式を指す?
京うちわは“差し柄式”と呼ばれる構造で、扇面部分の骨と柄を別々に作り、最後に細長い竹柄を扇面の背後から差し込み接着する。これによって扇面の前面に柄が出ず、平滑な表面に絵絹や和紙を張ることができ、美術性の高い図案を施すのに適している。一体式の丸亀うちわとは逆の発想で、工程は増えるが軽量で風をよく捉える形状が得られる。プラスチック柄や紙管柄は近年の簡易製品の例にすぎない。
Q2 : うちわの図柄を大量に均一に染める方法として江戸時代から普及し、友禅や浴衣の生地にも用いられる技法は?
型染めは防染糊を塗った型紙を布や紙に重ね、刷毛やへらで染料を刷り込む伝統技法で、同じ図案を繰り返し鮮明に再現できるためうちわの大量生産に最適化された。江戸時代後期には伊勢型紙と藍の普及で浴衣や手ぬぐいとともに庶民文化を彩った。墨流しは偶発模様、藍建て染めは浸染、ステンシルプリントは合成樹脂が多く、和紙や絹に風合い良く色を乗せる点で型染めが最も一般的となっている。
Q3 : 和紙を貼った直後のうちわを適切に乾燥させるために最も推奨される方法はどれ?
和紙を貼ったばかりのうちわは、紙が乾く際に縮んで骨に密着し張りが生まれる。急激な乾燥や高温にさらすと紙が波打ったり糊が膨れたりして仕上げ寸法が狂う。伝統的には風通しの良い日陰で立て掛け、扇面を上下に振動しない状態で半日から一日かけて自然乾燥させるのがベストとされる。直射日光・ドライヤーは温度差で骨がゆがみ、密閉袋は乾かずカビの原因となる。
Q4 : うちわ骨を均一な厚みに削る際に用いる、片手で持つ小さなかんな状の道具を何と呼ぶ?
ヒゴカンナは幅1〜2センチほどの小型鉋で、底面の溝に骨を通しながら削るため、均一な厚みで長さの揃った竹ひごを短時間に作れる。裂いた直後の骨は厚みにムラがあり、そのまま貼ると紙面がデコボコして風切り音が増す。ノミやのこぎりは荒割りに用いられる道具、ヤスリは仕上げの研磨用で、微妙な厚み調整には向かない。ヒゴカンナの刃の調整が甘いとささくれが立ち、和紙が破れやすくなる。
Q5 : 夏の京都祇園祭の宵山で、町会所が参拝客に配ることで知られる京うちわの通称は?
祇園祭の宵山で、山鉾町が参拝客に配る『厄除けうちわ』は、町内の商号や献金者名を刷り込み厄災を払う縁起物として江戸時代から続く風習である。京うちわの差し柄式を用い、表裏に祭礼の図柄や御神紋を型染めした華やかな仕立てが特徴。暑さをしのぐ実用と同時に、持ち帰って家の入口に飾れば疫病や火伏せのご利益があると伝えられる。浴衣うちわは商品名、千歳うちわは福井の特産、青もみじうちわは季節限定品で祇園祭固有ではない。
Q6 : うちわの骨組みに最も一般的に用いられる植物は?
うちわの骨は薄く細かく裂いて放射状に広げられなければならないため、しなやかさと強度を両立する素材が不可欠。竹は繊維がまっすぐで均質、割裂がしやすく、乾燥後も狂いが少ない。軽量で手に持ったときの疲労も少なく、防虫性・耐水性にも優れるため、古くから全国でうちわ骨の主材料となってきた。杉や松は柔らか過ぎて裂くと折れやすく、桐は軽いが腰が足りず、細工に向かない。
Q7 : 国の伝統的工芸品に指定され、竹骨を木枠で圧して平らに仕上げる製法が特徴の香川県産うちわは何と呼ばれる?
丸亀うちわは香川県丸亀市で江戸時代初期に金刀比羅参りの土産物として誕生したと伝わる。特徴は一本の竹を扇面から柄まで連続させ、さらに木型と油圧プレスで骨を平らに成形する独自工程にある。量産性と丈夫さから国内生産量の約九割を占め、1997年に国の伝統的工芸品指定を受けた。房州うちわ(千葉)は竹を煮曲げる丸柄式、京うちわは差し柄式、江戸うちわは少量手加工と、構造や製法がそれぞれ異なる。
Q8 : うちわ作りで、竹を均等な幅の骨(ひご)に裂く工程を指す語として最も一般的なのはどれ?
ひご取りは、割った竹をさらに小刀で均等な幅に裂いて骨(ひご)を作る工程で、うちわの強度と形状を左右する最重要ステップの一つ。繊維を壊さないよう節ごとに刃を当て、裂きながら幅を微調整する技術が要る。面取りは角を削ることで持ち心地を良くし、晒しは日光や煮沸で漂白する処理、油抜きは熱を加えて竹の油分を飛ばす処理であり、骨を作る直接工程ではない。
Q9 : 伝統的な紙貼りうちわで、扇面の和紙を骨に貼り付ける際に昔ながらに使われてきた主な接着剤はどれ?
伝統的な紙貼りでは、飯粒をすり潰し水で溶いたでんぷん糊(ごはん糊)が使われる。米由来のでんぷんは乾くと透明で和紙を変色させず、接着力も適度で再湿すると修理が容易。柿渋は塗料・防虫剤、木工用ボンドは化学接着剤で乾燥が硬質過ぎ、紙の伸縮に追従しにくい。米糊にホットメルトを併用すると高温で和紙が波打ち、風合いが損なわれるおそれがあるため、昔ながらのでんぷん糊が最適とされる。
Q10 : 日本三大うちわの一つに数えられる千葉県南房総地方で作られるうちわは?
房州うちわは千葉県南房総市・館山市で作られ、京うちわ、丸亀うちわとともに「日本三大うちわ」に数えられる。丸柄式という方法で、竹を熱で曲げて円柱状の柄を形成し、骨を曲げずに放射状に広げるのが特徴。夏の強い日差しや海風に耐えられる丈夫さから漁師町で重用された。阿波うちわや江戸うちわ、松江うちわなど他産地の製品もあるが、生産量や歴史的評価の面で三大うちわには含まれない。
まとめ
いかがでしたか? 今回はうちわ作りクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はうちわ作りクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。