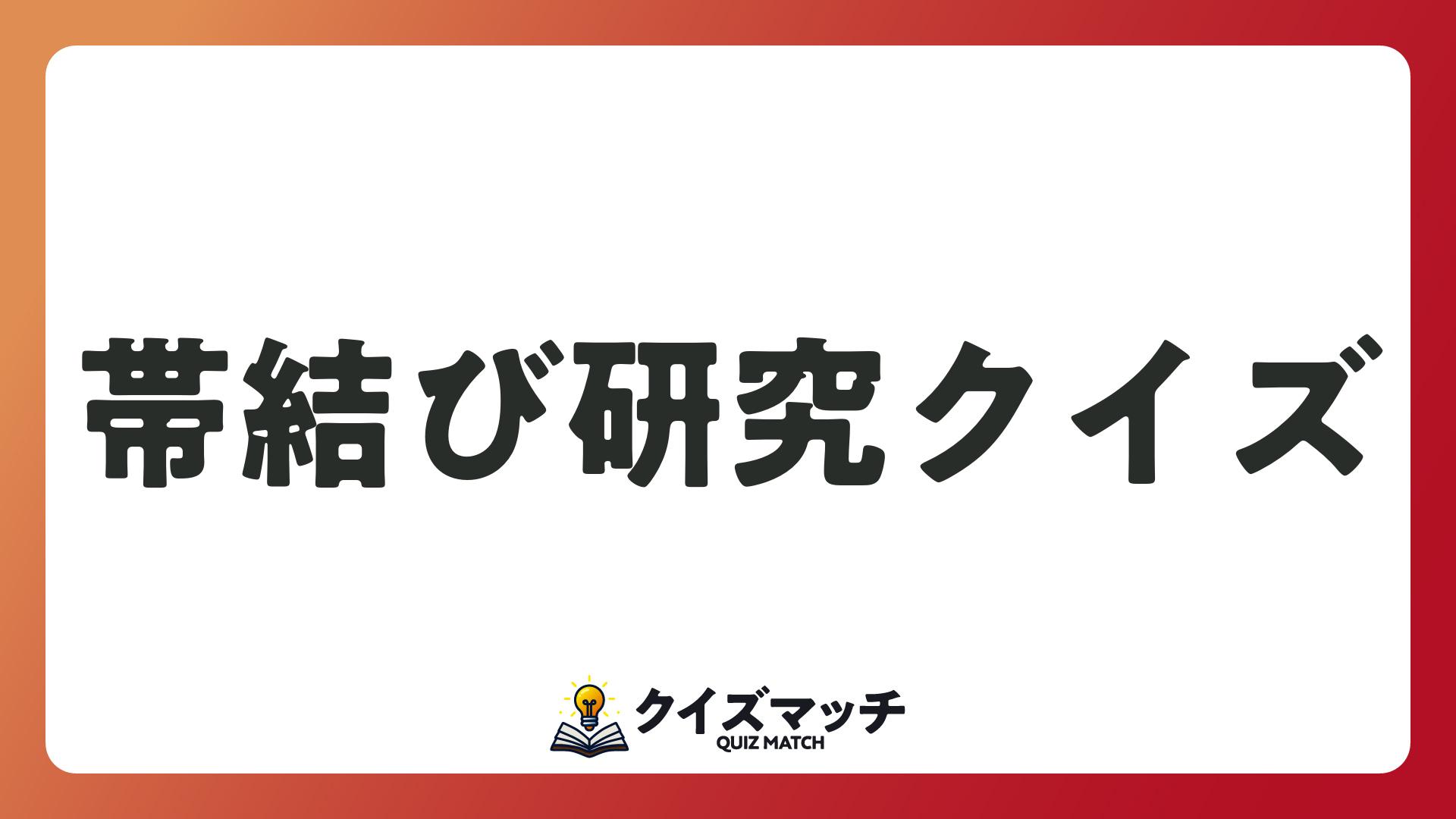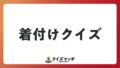着物の帯結びには歴史と技術が秘められています。本記事では、帯結び研究の最新クイズにチャレンジします。基礎から応用まで、さまざまな帯結びの知識を問います。袋帯や名古屋帯、浴衣の半幅帯など、着物の装いに合わせて選ばれる結び方の特徴や歴史的背景を学んでいきましょう。帯結びの奥深さにきっと驚かされるはずです。着物や帯を自在に操る技を身につけ、さらなる装いの魅力を発見してください。
Q1 : 豪華な袋帯を用いて花嫁や留袖に合わせる「立て矢結び」に関して誤っている説明はどれ?
立て矢結びは武家の女性が婚礼で用いた歴史をもち、羽根を扇のように斜め上方へ張り出す豪華さが特徴である。左右の羽根はあえて長さを変え、非対称の動きを付けることで矢が天に向かう勢いを表現するため、両羽根を同じ大きさに揃える説明は誤りとなる。帯枕を高く据えて重心を上げ、帯揚げでしっかり包み固定するのも大きなポイントであり、サイズの大きい袋帯や振袖帯でないと形が保てない。成人式や舞妓の装いでも華やかな演出に用いられる。
Q2 : 礼装向けの袋帯で用いられる「二重太鼓結び」で、一重太鼓と異なる最も顕著なポイントはどれ?
二重太鼓結びは格式を高めたい留袖や訪問着に合わせる際に選ばれる結びで、タレを二重に折り上げることで太鼓部分に明確な二段構造を作る点が最大の特徴である。この段差があることで帯寿命が延び、座礼の際に帯山がつぶれにくい利点もある。帯枕は必須で、帯締めと帯揚げの両方を使い安定させる点は一重太鼓と共通だが、厚みが増す分重くなるため、帯枕の形状や位置取りに注意しないと肩へ負担がかかる。
Q3 : 江戸時代の芸者が考案し現在はカジュアル着物にも結ばれる「カルタ結び」の背面シルエットを最も的確に表す語はどれ?
カルタ結びの名称はトランプや花札を束ねたような長方形の形に由来し、背面のシルエットが角張った「角箱」に見える点が特徴である。手先とたれ先を折り重ねて帯枕を用いず仕上げるため、体への負担が軽く座っても崩れにくい。江戸期の芸者が座敷遊びの邪魔にならないよう帯を低く結んだのが起源とされ、現代では小紋や紬に合わせて軽快な印象を与える。短冊というよりは厚みのある直方体に近いので角箱状が最も的確といえる。
Q4 : 角出し結び(銀座結び)の最大の利点として一般に挙げられるものはどれ?
角出し結びは銀座の芸妓が名古屋帯を簡易に結び直せるよう工夫したもので、背中に角を出す立体的な太鼓が最大の特徴である。太鼓の底が平らで帯山が低いため椅子や車の背もたれに寄りかかっても型崩れが少なく、長時間の外出に向くとの評判が高い。袋帯のような長尺がなくても結べる利点もあるが、最も評価されるのは座姿勢に強いことだ。帯枕は小ぶりなものを用いるが完全に不要ではなく、軽さよりも実用性が重視される。
Q5 : 半幅帯で作る「リボン返し結び」が他の蝶結び系と異なるポイントはどれ?
リボン返し結びは幕末期に考案されたとされる遊び心ある半幅帯結びで、タレ先を帯板の外側に挟み込みながら返して柄や色を見せる技法が特徴である。この返し部分が装飾的なアクセントとなり、後姿に動きを出す。上下に羽根を重ねるだけなら文庫系の一般的な蝶結びでも見られるが、帯板を外側に用いる方法はリボン返し特有であり、柄出しの位置調整が難しい。そのため浴衣だけでなく小紋にも応用される中級者向けの結びとされる。
Q6 : 江戸時代後期に武士の礼装用として生まれ、現在は男性角帯で一般的な「浪人結び」の別名として正しいものはどれ?
浪人結びは一度結んだ後に手先を引き抜くことでほどきやすい構造を持ち、町人にも広がった結びである。別名を浪華結びとも呼び、上方で生まれ江戸へ伝わった歴史を示唆している。片ばさみは女性の帯結び、カモメ結びは船舶のロープワーク、本結びは武士の鎧下帯の結びを指すため誤りである。浪人結びは帯を低い位置で締め、背中側に余り布を斜めに流す粋な形が特徴で、劇中の侍や落語家の着こなしでもよく見られる。
Q7 : 江戸~明治期にかけて考案された「片流し結び」が向かない帯種類は次のうちどれ?
片流し結びは帯の片側だけを大きく垂らして流線形を作る遊び心ある結びで、柔らかく扱いやすい帯地が適している。兵児帯や半幅帯、名古屋帯の芯無し仕立てなどは生地が柔らかく折り込みやすいため形が作りやすいが、博多献上帯は高密度の平織りと張りが強い独特の硬さがあり、片流し特有の流れるタレがきれいに落ちず角ばってしまう。加えて厚手ゆえに背中の結び目が大きくなりがちで座りにくくなるため、博多献上帯は不向きとされる。
Q8 : 名古屋帯で最も一般的な結び方で、箱形の帯枕を使い背中に鼓のような形を作る結びを何と呼ぶ?
一重太鼓結びは昭和初期に考案されたといわれる結び方で、名古屋帯や袋帯を用いて腰よりやや高い位置に台形状の「太鼓」を作るのが特徴である。帯枕と帯板で形を安定させ、帯揚げで枕を覆い、帯締めで全体を固定する。礼装から略礼装まで幅広く用いられ、イス式の生活でも崩れにくいため戦後急速に普及した。二重太鼓と違いタレ先を一巻だけ折り上げるため、軽く短時間で結べる点が人気の理由である。
Q9 : 振袖で格調高い装いを演出する「ふくら雀結び」の形状的な特徴として正しいものはどれ?
ふくら雀結びは江戸末期から続く吉祥文様的な結びで、ふっくらとした雀が羽を休めている姿を模した左右対称の立体感が要所である。タレと手先を広げて袋状に折りたたみ、中央を帯締めでしっかり締めることで丸みのある膨らみが生まれる。特に成人式や結婚式の振袖で用いられ、未婚女性の晴れの日に相応しい華やかさを演出する。形が崩れやすいので帯枕を低めに置き、羽根内部に綿を忍ばせる流派もある。
Q10 : 浴衣用の半幅帯で主に用いられる「貝の口結び」の手順で最初に行う動作はどれ?
貝の口結びは武家の男性が日常着の角帯を素早く締めるために考案された実用的な結びで、現代では女性の浴衣にも応用される。手順はたれ側で胴を二周巻いた後、手先を内側に折り返して輪を作る工程から始まる。ここで作った輪が後に「口」の部分になり、全体の形を決定づける重要なステップである。手先を折らずに交差させると兵児帯のようにまとまりがなくなるため注意が必要で、素早く整えることで粋な印象を与えられる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は帯結び研究クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は帯結び研究クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。