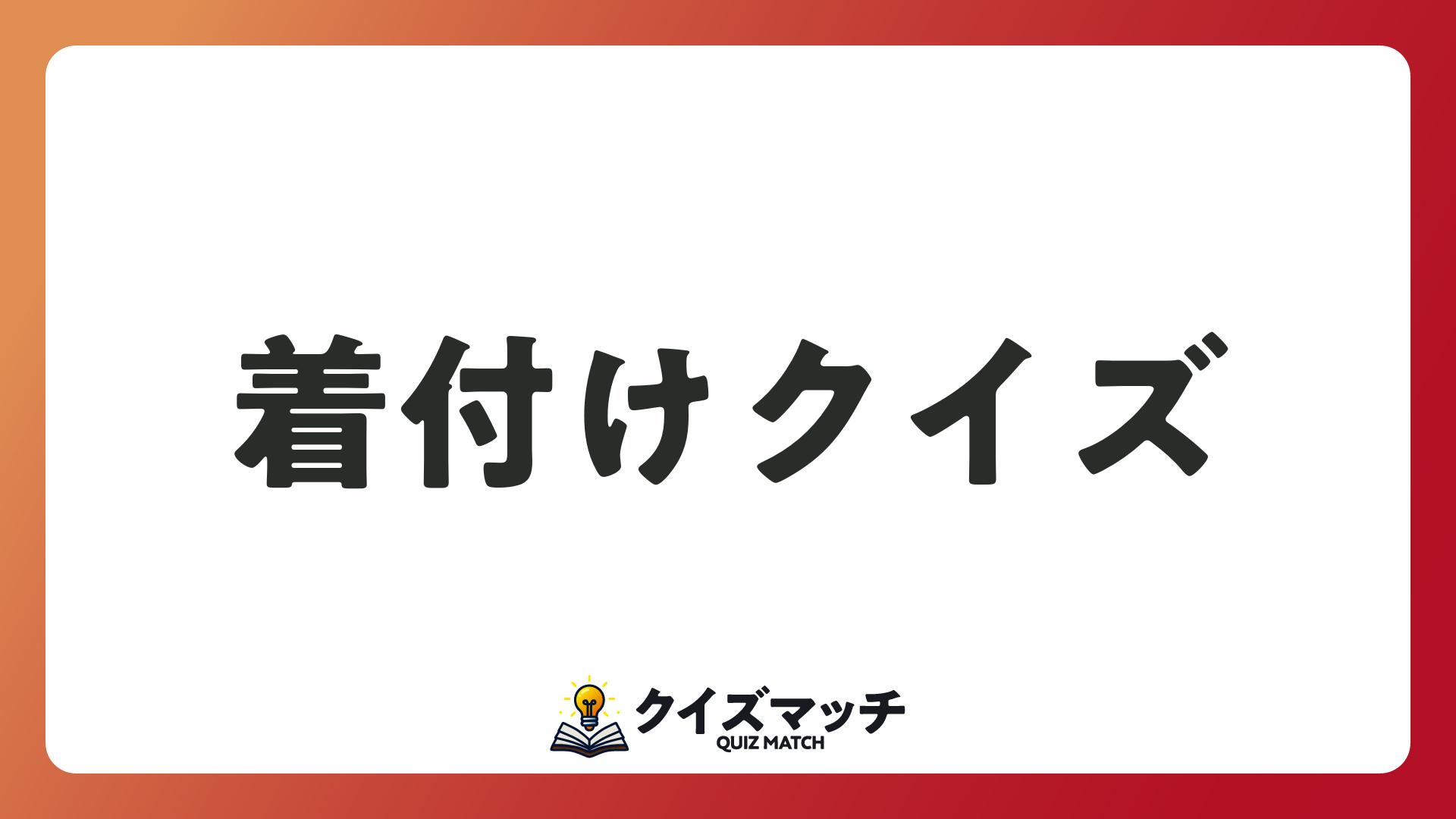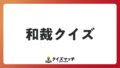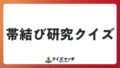着物を着用する上で、正しい着付けは美しい姿を保つ上で欠かせません。本記事では、着物の着用時に守るべきマナーや、着崩れを防ぐためのコツなど、着付けに関するクイズを10問ご紹介します。
着物文化の歴史や機能的な側面にも触れながら、正しい着付けのポイントを学んでいただけます。着物を美しく着こなすための基本を確認し、次の着物の機会に活かしていただければと思います。
Q1 : 袋帯で二重太鼓を作る際、胴に二巻きしたあとに残す“手”と“たれ”の推奨される長さのバランスは?
二重太鼓は礼装から略礼装まで幅広く用いられる結び方で、たれ先で二重山を作るために手より少しだけたれを長く取るのがポイント。目安は約10センチで、これにより太鼓の下線が水平にそろい、手先が内側に隠れて余分なたるみが出にくい。同じ長さだと山が足りず、逆に長過ぎるとたれがたるんで着崩れにつながる。手は山折りにして帯枕を包み、内側で処理されるため短めでよい。長さの差をつくる工程で帯全体のテンションを均一にしておくと、時間が経っても太鼓が落ちにくく後ろ姿が美しく保てる。
Q2 : 夏の浴衣着付けで使用する伊達締めの素材として、最も涼しく着崩れも防ぎやすいものは?
浴衣は素肌に近い状態で着るため、汗処理と滑り止めの両立が重要。メッシュやレース地のポリエステル伊達締めは通気性と速乾性に優れ、汗による蒸れや帯下の湿気を逃がしやすい。正絹博多織は伝統的で締まりは良いが湿気を吸うと緩みやすく、洗濯の手間も増える。フリースや厚地ゴムは保温性が高過ぎて夏場には不向きで、体温上昇による着崩れや肌トラブルの原因になりやすい。ポリエステルメッシュなら軽量で締め心地も柔らかく、浴衣の気軽さを損なわずに衿元と帯周りをすっきりキープできる。
Q3 : 袷の着物を畳むとき、“袖たたみ”に入る直前に行う工程として正しいものは?
着物の畳み方には本だたみ、袖たたみなどがあるが、いずれもまず身頃の幅を整えることが大前提。袷の場合は衽線を合わせて身頃を背中心で折り返し、衣紋の抜き具合を軽く整えておくと体積が均一になり皺が入りにくい。この状態を作ってから袖を身頃の上に折り重ねる“袖たたみ”に入ると、袖山がずれず仕上がりが長方形になる。袖口を先に重ねる方法は単衣では簡便だが袷では胴の厚みで歪みやすい。衿を折るのは最後に形を調える段階で、順序を誤ると保管中に強い折り皺が残ってしまう。
Q4 : 男性用角帯を“貝の口”で結ぶ際、結び目が収まる一般的な位置はどこか?
貝の口は男性帯結びの基本で、腰骨にかけて水平に締めることが粋とされる。伝統的には刀を差す側である左腰を空けるため、結び目は背中よりやや右に寄せるのが正式。真後ろ中央でも間違いではないが、座った際に結び目が脊椎に当たって痛むことがあり、右寄りなら帯が体に沿って安定しやすい。左寄りは武士装束では失礼とされ、市井でもあまり行われない。前結びは舞台装束など特殊なケースを除いて日常着付けでは用いない。右後ろ45度の位置は見た目にも自然で、袴を合わせる場合でも帯結びが干渉しにくい。
Q5 : 振袖の帯結びで文庫系の形を作るとき、帯枕を当てる適切な高さは?
文庫系の振袖帯結びは羽根を大きく立ち上げて華やかさを演出するため、帯枕は帯上線よりわずかに高い位置に据える。1〜2センチ上げることで羽根の重心が高くなり、背中に沿ってふわりと扇状に開く。帯上線と同じ高さだと羽根が寝てしまい、下に置くと重みで帯山が沈む。逆に高過ぎると衿元との間隔が詰まり不自然。帯枕はガーゼや帯揚げで包んで滑り止めと汗取りを兼ね、振袖特有の長尺帯でも位置を微調整しやすい。正しい高さにすると歩いても羽根が揺れて形崩れしにくく、後ろ姿が立体的に映える。
Q6 : 和装ブラジャーを使用する主目的として最も重視される効果は?
着物は直線的な布を体に巻き付けて形作るため、本来の帯や衿の位置は筒状の体形を前提としている。胸や腰の突出がそのままだと衿合わせが浮き、おはしょりが波打つなど着崩れの原因になる。和装ブラジャーは硬めのパッドで胸を抑えつつ脇へ逃がし、上半身の凹凸をフラットに整えることで、伊達締めや帯の締まりを均一にし、長時間の着装でも苦しくなりにくい。洋装のブラジャーのように持ち上げたり寄せたりする設計ではない。くびれや保温を目的とした製品は別途補整具や下着で行うのが一般的である。
Q7 : 着付けの準備で足袋を履く正しい順序はどれか?
足袋はしゃがんで履く作業のため、長襦袢を着た後では裾が乱れたり衿が崩れやすい。そこで肌襦袢と裾除けなど下着を付けた後、まだ腰紐や伊達締めが少なく動きやすい段階で足袋を履くのが基本となる。足袋にはこはぜを留める作業があるため、帯や着物を着た後だと腰を曲げるのが大変で、特に礼装の厚手の帯ではほぼ不可能になる。長襦袢を後にすることで、足袋のこはぜが肌に食い込んでも微調整しやすく、さらに裾を汚さずに済む。順序を守れば時短になるだけでなく、結果として衿元やおはしょりの完成度も高まる。
Q8 : 着物の衿合わせで生きている人が着る際に正しい向きはどれ?
衿合わせは『左前』と覚えるが、着ている本人から見ると左手側の衿が上になり、他者から見ると右側が上に重なる状態になる。これは日本の衣服史において、死装束である右前と明確に区別するために定着した慣習で、鎌倉時代頃にはすでに文献に見られる。左前にすることで懐が右手で開けやすく物の出し入れがしやすいという機能的理由もある。衿合わせが逆になると不祝儀を連想させ失礼に当たるため、浴衣であっても必ず左前を守ることが着付けの基本である。
Q9 : 名古屋帯で一重太鼓を結ぶとき、胴に巻いた帯の“たれ先”を決める長さの目安として最も適切なのは?
一重太鼓は名古屋帯特有の軽装太鼓で、たれ先をわずかに長く取ることで太鼓の下線がきれいにそろい、裏地や芯が覗くのを防げる。一般的に『帯幅より手のひら一枚分=約5センチ』と覚えると失敗が少ない。これより短いと太鼓がしまり過ぎ、長過ぎるとたれ先が跳ね上がってだらしなく見える。長さを決めたら、山折りにして胴に二巻きし、たれを下に、手を上に持つようにすると形が安定し帯山も角が出る。目安通りの長さは初心者でも再現しやすく、着崩れの防止にも直結する。
Q10 : 長襦袢に半衿を付ける際、運針で推奨される表側に出る針目の間隔は?
半衿は顔まわりの清潔感を左右するため縫い目が目立たないように付けるのが理想とされる。表に見える針目は平均して2〜3ミリが適切で、この長さなら衿がたゆまず、洗濯時に糸が切れにくい。1ミリ以下だと時間が掛かる割に布がつれるリスクが高まり、4ミリ以上になると縫い目が目立って美観を損なううえ、着用中に半衿が浮きやすい。運針は表に僅かしか糸を出さず、裏に長めに落とす『ぐし縫い』が基本。約2〜3ミリのリズムを保つと、糸調子が均一になり衿合わせのラインも真っ直ぐに仕上がる。