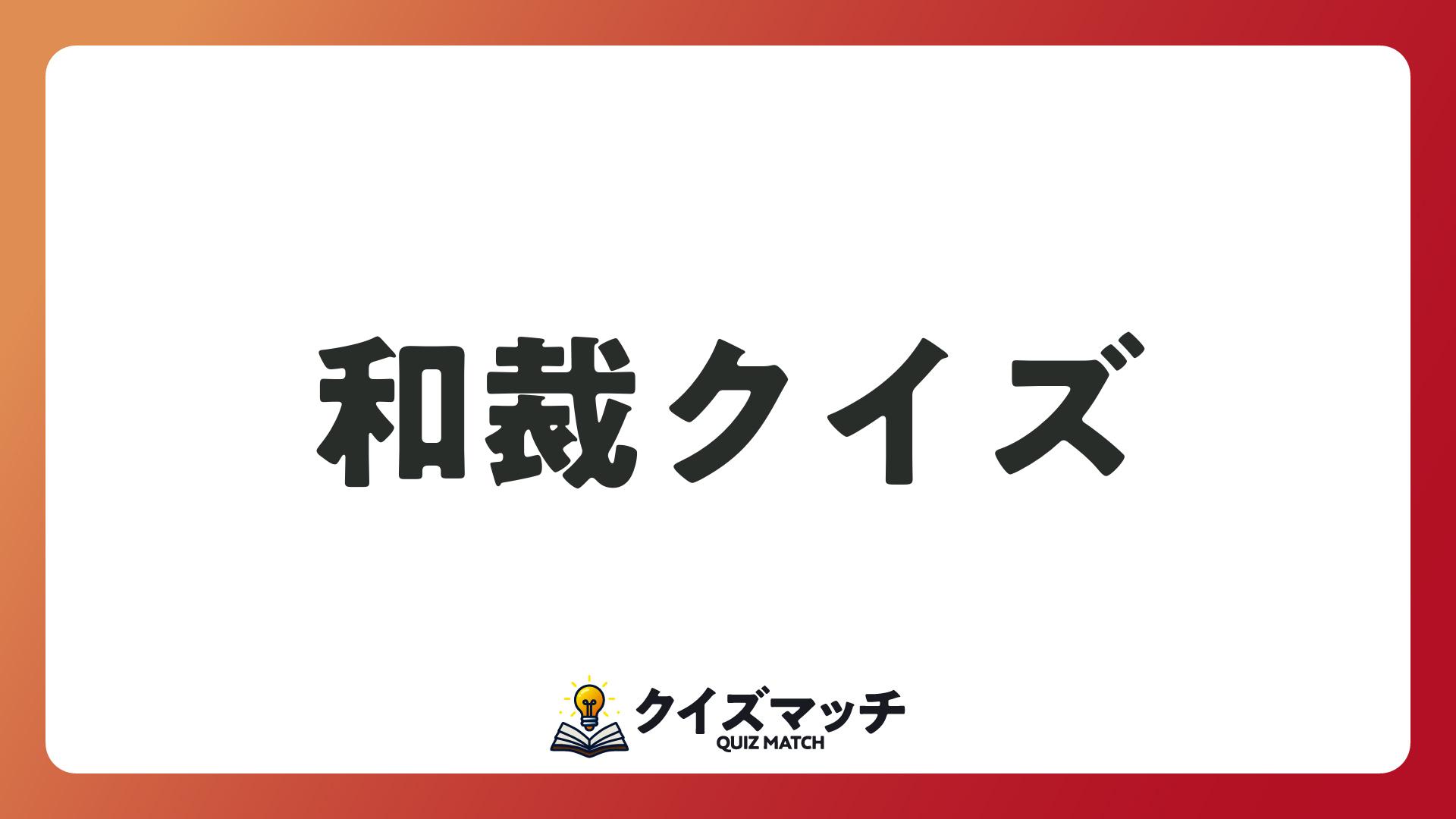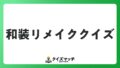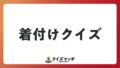和裁は、日本の伝統的な染織技術の一つであり、着物の縫製や修繕に使われてきました。長い歴史の中で培われた技術は、着用者の快適性や美しさを追求するものです。本記事では、そんな和裁の基礎知識を問うクイズをお届けします。着物好きはもちろん、和服に興味のある方も、ぜひ挑戦してみてください。和裁の奥深さと、匠の技に触れることができるはずです。
Q1 : 布端を斜めに拾いながら飾り縫いをする技法として正しいものはどれか。
千鳥がけは左右交互に布を斜めに拾い、鳥が歩いた跡のようなジグザグの縫い目を作る技法である。布端のほつれ止めや裏地の仮止めなどに用いられ、伸縮性と装飾性を兼ね備えている。平ぐけは布端を平行に細かくすくう縫い、まつり縫いは折り山を表に響かせずに止める縫い方、突き合わせは縫い代を開いたまま突き合わせる方法で斜めの目は作らない。よって斜め目で連続する千鳥がけが正答である。
Q2 : 和裁で用いる『運針』の説明として正しいものはどれか。
運針は和裁の基礎技術で、右手の指先で針を上下させながら布を連続してすくい、ある程度針目をためてから一気に糸を引き抜く方法である。縫い目幅は表側を小さく裏側をやや大きく揃え、仕上がりを滑らかにすることが重要だ。玉止めを作らずに終わる場合もあるがそれは始末の一工程にすぎず、返し縫いやアイロン操作とは異なる。和裁の美しさは運針の正確さに大きく左右される。
Q3 : 女物の着物で『身八つ口』をあける長さの標準値として最も近いのはどれか。
身八つ口は前後身頃の脇線を途中で縫い止めて開ける腕通しの穴で、標準は約5寸=19〜20cmとされる。これより短いと腕が通しにくく動作が阻害され、長すぎると胸元が開きやすく着崩れの原因になる。身八つ口は見えない部分だが着心地に直結するため寸法設定はきわめて重要だ。選択肢中では約20cmが最も一般的な寸法に合致するため正解となる。
Q4 : 和裁で縫い代を控えて表に縫い目を出さないようにする『きせをかける』作業に主として用いられる道具はどれか。
きせをかけるとは縫い合わせた縫い代を内側へ少し倒し、縫い目を表に響かせないように布目を整える工程である。熱と蒸気でクセ付けしながら折り山を固定するためには高温を安全に当てられる金属製のこてが不可欠となる。へらは印付けや仮押さえ、まち針は位置決め、裁ちばさみは裁断用と用途が異なる。こてを使いこなすことで仕立て上がりの線が美しくまとまり、和裁技術の質が大きく向上する。
Q5 : 『おくみ』を付ける位置は、身頃のどの部分か。
おくみは前身頃の端に縫い足される細長い布で、打ち合わせを深くするとともに裾に適度な重みを与え着崩れを防ぐ役割がある。取り付け位置は前身頃の縫い代線で、下前・上前ともに同じ位置に付ける。後身頃や袖、衿中央には用いない。幅は約15cmが一般的で、表地と柄合わせを行うため裁ち方にも高度な知識が必要だ。前身頃下前側に沿わせることが正しい付け方となる。
Q6 : 長襦袢に半衿を掛ける際、一般的に用いられる縫い方はどれか。
半衿は長襦袢の衿山に取り付け、肌に触れて汚れや汗を受け止める交換式の衿布である。最も多用されるのが細かい並縫いである『ぐし縫い』で、2〜3mm間隔で布をすくい表に糸目を目立たせないように縫い進める。本ぐけは衿付けや裾ぐけに使う技法、千鳥掛けは布端を斜めに飾る縫い、たてまつりは袋物の口などを閉じるときの縫い方であるため半衿掛けには適さない。
Q7 : 和裁で使用する針のうち、絹地を痛めにくい細長いものを指す名称はどれか。
くけ針は裏くけ・裾くけなど布端を折り込んで止める際に用いる細身でしなやかな針で、絹地を傷めずに布目を拾える点が特長である。長さは約3〜4cm、太さは極細で、番号によって更に細分される。三ノ二は針のサイズ表示、待ち針は仮止め専用、刺し子針は厚手木綿を丈夫に縫う専用であるため、くけ専用針という条件に合致するのは『くけ針』のみである。
Q8 : 袷着物の裾回しに多く用いられる裏地の名称として正しいものはどれか。
袷の着物では表地と裏地の間に裾回しを付けるが、この裾回し用の布を総称して『八掛』と呼ぶ。八掛は裾や衽先、袖口見返しを一続きに取り、歩行時や着姿でチラリと見える色合いが装いのアクセントになる。羽二重やちりめんは素材名で、八掛に加工されることもあるが裾回しそのものを示す語ではない。したがって裾回しを表す正確な名称は『八掛』が正答となる。
Q9 : 和裁用のへらの主な素材として一般的なのはどれか。
へらは布を傷めずに折り線や合印を付けるためのマーキングツールで、滑りが良く適度な硬さを持つ素材が求められる。伝統的には水牛角や象牙が用いられ、現代ではプラスチックや合成樹脂が主流である。金属製は重さと固さで布を痛めやすく、ガラスや布では圧力不足で跡が付かない。したがって多くの仕立て職人が用いる一般的素材は樹脂や角類であり、選択肢1が正しい。
Q10 : 和裁で長着の裏に『肩当て』を付ける主な目的はどれか。
肩当ては長着の肩から背中心上部に縫い付ける当て布で、肩や背中は汗腺が多く汚れが付きやすいため表地が傷むのを防ぐのが最大の目的である。薄手の絹や木綿で作られ、外して洗濯・交換できるため本体を頻繁に解かずに済む利点がある。保温効果は副次的で裾さばきや重量調整とは直接関係しない。汗汚れを受け止めて本体を長持ちさせるという発想が和裁の合理性を示している。
まとめ
いかがでしたか? 今回は和裁クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は和裁クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。