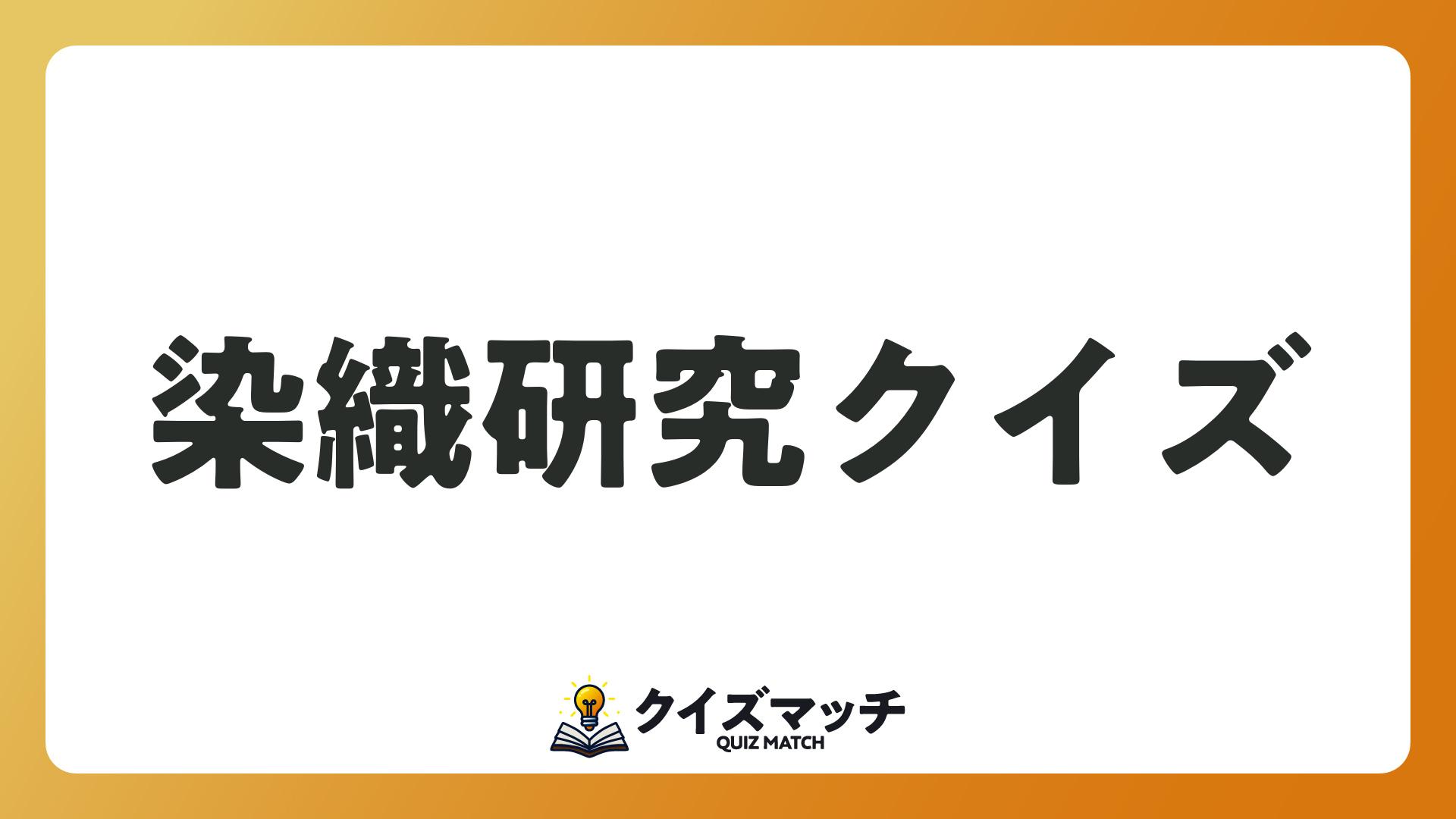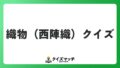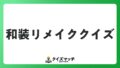染織研究に関する10問のクイズを掲載した本記事のリード文は以下の通りです。
天然染料や先染め織物など、染織の歴史と技術には奥深さがあります。本記事では、そうした染織の基礎知識に迫るクイズを10問お届けします。原料の特性から染色プロセス、織物構造まで、染織研究の様々な側面について、専門家ならではの視点で解説していきます。染色に関する科学的な仕組みや、日本の伝統技術の魅力を、クイズを通して探っていきましょう。染織への理解を深めていただければ幸いです。
Q1 : 経糸と緯糸を異色で染め分け、角度によって色が変わる効果を持つ先染め平織物は何と呼ばれるか。 経錦 紗綾形 玉虫織 絣
玉虫織(ショットシルク)は経糸と緯糸に補色関係など異なる色の先染め糸を用いて平織りすることで干渉ではなく視覚混色による色変化を生む技法である。光の反射方向と視線が変わると経糸または緯糸の色が優位に見えるため玉虫の羽のように色が移ろう。浮き織や綾織では組織効果が主で玉虫状の可変色は得にくく絣は染め分けによる模様であり角度依存の変色効果は小さい。
Q2 : 染色堅牢度試験のうち、水道水に含まれる塩素による変退色を評価するものはどれか。 摩擦堅牢度試験 酸性汗堅牢度試験 光堅牢度試験 遊離塩素耐久性試験
染色堅牢度試験は用途に合わせ複数あるが水道水中の遊離塩素は染料の酸化分解を招き色褪せの原因となる。JIS L 0848などで規定された遊離塩素耐久性試験では50ppmの塩素水溶液に試料を浸漬し退色階級で評価する。摩擦堅牢度や酸性汗堅牢度は物理摩擦や汗との反応を対象とし光堅牢度は紫外線による褪色を評価するもので塩素とは直接関係しない。
Q3 : 葛布(くずふ)の主原料として用いられる植物繊維はどれか。 クズ(Pueraria lobata) カヤツリグサ サトウキビ アサ
葛布は平安期から駿河や遠州で織られた涼感のある夏衣料で主原料はマメ科のクズの蔓。その靭皮から採取した繊維を苛性灰汁で軟化させ髄や木質を取り除き細糸に績み織機で平織りする。クズは蔓性で繊維長が短く扱いが難しいが光沢が高く吸湿性に優れる。カヤツリグサはい草畳表に用いられサトウキビはバガス繊維に用いられることはあるが葛布とは無関係。アサは麻布を構成する。
Q4 : ポリエステルを分散染料で高発色させるため、190℃前後の高温高圧が可能な代表的染色装置はどれか。 ジェット染色機 パッディングマシン 冷パッドバッチ装置 HTHPチューブラー染色機
ポリエステルは非極性でガラス転移温度が高く分散染料分子を吸収させるには130℃以上の高温か高圧が必要となる。HTHPチューブラー染色機(高温高圧染色機)は円筒状の密閉容器に織物をロードし飽和蒸気を循環させながら150〜180℃に加熱できるため短時間で均一に染まり昇華による固着不良も防止できる。ジェットやパッディングは常圧域が多く冷パッドバッチは室温長時間処理でポリエステルには適さない。
Q5 : 藍の染色において、還元作用により藍を水溶化させるために伝統的に用いられる発酵建ての原料として最も重要な糖分源はどれか。 ふすま(小麦の外皮) 木灰 生石灰 石灰窒素
藍染めは水に不溶のインディゴを可溶化させ繊維に浸透させたあと空気酸化で青色を発現させる還元染色である。日本の伝統的な発酵建てではスクモに木灰灰汁でアルカリ性を与え糖分源を加えて微生物を活性化しインディゴをロイコ体に還元する。糖分源として最も一般的なのが小麦の外皮であるふすま。アミラーゼで分解されたデンプンがブドウ糖となり電子を供給しpH緩衝にも寄与する。他の材料だけでは微生物の栄養が不足し建てが立たないことが多い。
Q6 : 絹フィブロインのβシート構造の規則的形成に最も寄与するアミノ酸はどれか。 セリン グリシン ロイシン チロシン
絹フィブロインの一次構造はグリシン‐アラニン‐グリシン‐セリンなどの繰返しが多く特にグリシンは分子量が小さく側鎖が水素1個しかないためポリペプチド鎖同士が密に重なり合うβシートを形成しやすい。この緻密な結晶部が絹特有の強度と光沢を生む。セリンも存在するが疎水性やサイズの点でグリシンほど規則的配列には寄与しない。ロイシンやチロシンは非結晶部に多くβシート安定化の主役ではない。
Q7 : インド更紗の木版捺染で、アリザリンと鮮紅色の錯体を作る目的で用いられる媒染金属イオンはどれか。 鉄 銅 アルミニウム クロム
インド更紗や日本の紅型に代表される植物染料アリザリンによる赤色染色では金属イオンとキレート錯体を作ることで色と堅牢度を高める。三価のアルミニウムはアリザリンの2つのヒドロキシ基と配位し鮮明な赤を出す媒染剤として古来からミョウバンが用いられてきた。鉄媒染は黒味を帯び銅やクロムは暗色になるため木版捺染での鮮紅色目的には適さない。
Q8 : 苧麻(ラミー)繊維の精練でペクチン質をもっとも効果的に除去できる条件はどれか。 弱酸性80℃処理 中性冷水浸漬 アルカリ性40℃処理 アルカリ性沸騰処理
苧麻はセルロース含有率が高いものの生皮にはペクチンやヘミセルロースが多く残っているため精練でこれらを除去しないと硬くて染色も不均一になる。ペクチンはアルカリに可溶で高温条件で分解が進むので炊き込みと呼ばれる苛性ソーダやソーダ灰を用いた沸騰処理が最も有効である。弱酸性や中性下では加水分解が進まず効果が低い。40℃程度ではアルカリでも不十分であるためアルカリ性沸騰が推奨される。
Q9 : 明治期に“ジャパンブルー”として世界に知られた天然青色染料はどれか。 インディゴ ラックダイ フクシン マリーゴールド
明治期に日本の輸出織物の主力となった藍染製品は欧米から『ジャパンブルー』と賞賛された。これはタデ科植物から得た天然インディゴを原料とする染色で徳島の阿波藍などが有名。ラックやマリーゴールドは赤や黄の染料で青色にはならずフクシンはアニリン系合成染料である。工業化以降も藍は伝統意匠と耐光性の高さから重要であり綿や麻の先染めにも広く使われ現在のデニム文化にも繋がっている。
Q10 : 草木染における『四三酸化鉄媒染』と俗称されるのはどの媒染法か。 酢酸アルミニウム媒染 酢酸鉄媒染 酒石酸媒染 重クロム酸カリ媒染
鉄媒染はタンニンを含む植物染料と結びついて濃灰色や黒味のある渋い色調を発現させ堅牢度も高い。酢酸鉄溶液を使う方法は溶解度が高く四三酸化鉄(Fe3O4)が最終的に繊維に析出するため『四三酸化鉄媒染』と呼ばれる。アルミ媒染は鮮やかな色を得る酒石酸も助媒染剤として使われる。クロム媒染は緑がかった暗色を与えるが六価クロムによる環境負荷が問題とされる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は染織研究クイズをお送りしました。
今回は染織研究クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!