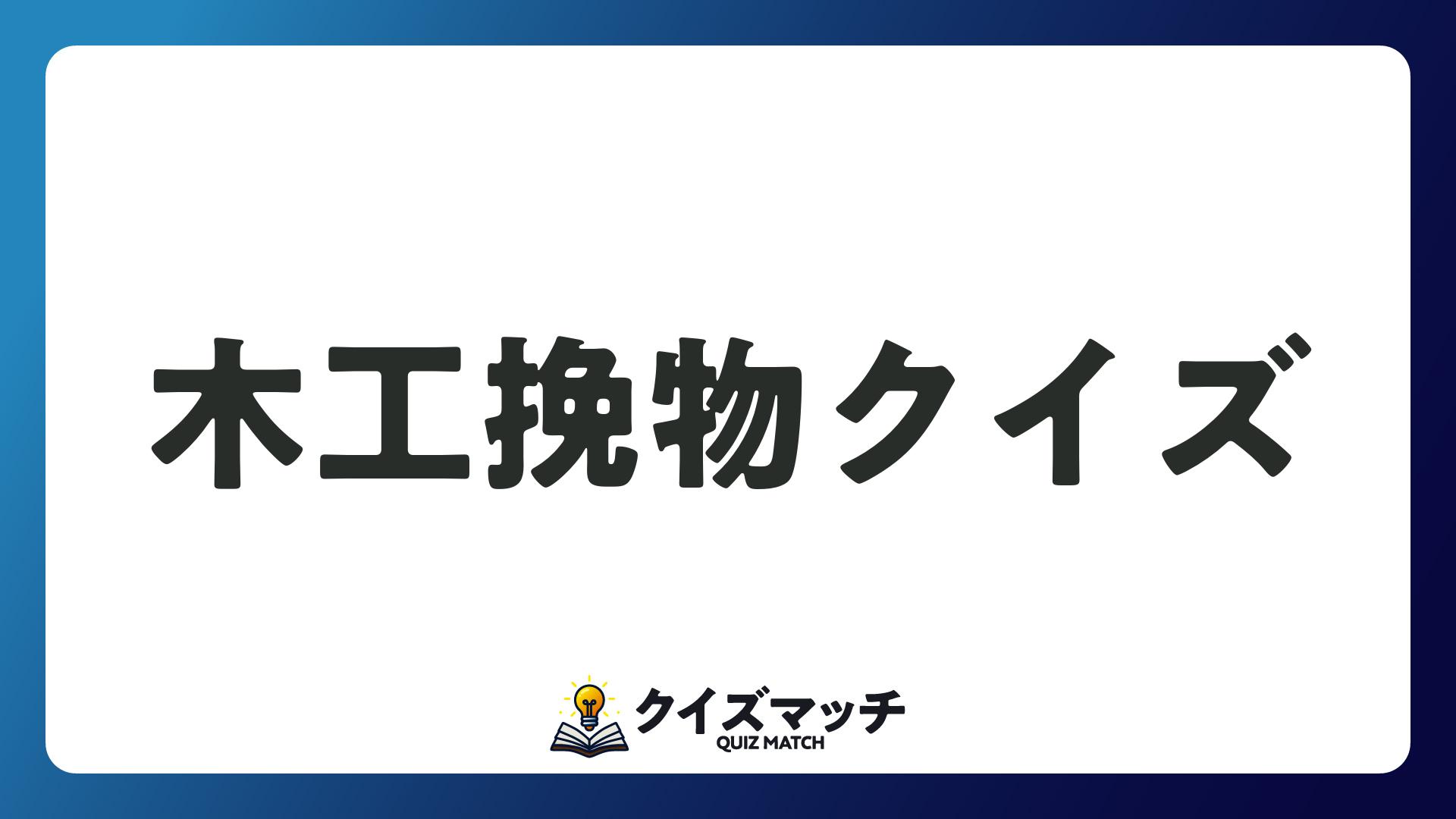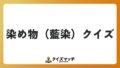木工旋盤は職人たちが様々な形のものを創り出す際に欠かせない道具です。この木工挽物クイズでは、回転する木材を巧みに操る技術や知識についてご紹介します。ボウルやスピンドル、各種仕上げ工程など、挽物の基本から応用までを10問に凝縮。木工旋盤の魅力を存分に味わっていただける内容となっています。挽物に詳しい方はもちろん、これから始めたい初心者の方にも、楽しみながら学べるクイズになっています。木工の奥深さを感じていただければと思います。
Q1 : ボウル成形で外周を先に整形し、その後内部をくり抜く工程が推奨される主な理由はどれか
外周を先に仕上げておけば、内部を削る際に工具がリムに当たって跳ねるリスクを低減できる。完成形のリファレンスラインが決まるため厚みを均一に保ちやすく、強度が十分残っている段階で外形を確定することで振動も抑制される。逆に内側を先に薄くすると外周部が弱くなり、チャック保持力低下や割れが発生しやすい。トルクやコストは主目的ではなく、審美性だけでは安全性を説明できない。
Q2 : チャックでボウルのテンオン(足部)を内側から押し広げて固定する方法の名称は何か
エキスパンジョンチャッキングはジョーを拡張方向に開き、ワーク内部に切った溝や下穴に押し当てて固定する方法である。外周全体に均一な圧力を掛けられるため、外面を仕上げた後でも痕跡が残りにくい。コンプレッションチャッキングは外側から締め付ける逆の方法、スレッドマウンティングはねじ切りで直接取り付ける方法、スクリューセンターチャッキングは一本ビスで引き寄せる方法であり、把持メカニズムが異なる。
Q3 : グリーンウッドをそのまま挽物加工すると乾燥後に起こる形状変化を一般に何と呼ぶか
生木は含水率が高く、削った後に乾燥が進むと繊維方向や年輪差によって収縮率が不均一となる。この結果、出来上がった作品は楕円化や傾き、ねじれを生じる。木工業界ではこの乾燥収縮による歪みをワープと総称する。キックバックは工具が跳ね返される現象、ランアウトはスピンドルの振れ、バインドは刃物が噛むことを指し、乾燥変形とは別問題である。ワープを見越して厚めに荒取りし、後日再旋盤する手法がよく採られる。
Q4 : スキューチゼルでビードを挽く際、特に引っ掛かりやすく危険とされる刃の部位はどこか
スキューチゼルのリーディングエッジ先端(尖端角)は木目に対して鋭角に当たるため、わずかな角度変化で食い込み大きな逆送りを招きやすい。ビード切削ではこの角をワークに触れさせないようにして、中央付近の切削部を用いベベルを常時当て続けることが安全作業の要点となる。シャンク背面は切削に関与せず、ベベル全体やフルート底部は支持面・切り屑排出面で危険度は低い。先端の扱いがスキュー操作の難易度を決定づける。
Q5 : サンディングを粗番手から細番手へ段階的に変える最大の目的はどれか
粗い番手は大きな傷を残すため、次に細かい番手でその傷を完全に消すというリレー式の工程を取らないと最終仕上げで微細な傷が残ってしまう。番手を飛ばしてしまうと深いスクラッチを消すのに長時間の研磨が必要となり、摩擦熱で樹脂分が溶けたりヤケができる恐れもある。傷跡を段階的に浅くしていくことが最も効率的かつ美観に優れた表面を得る方法である。熱を意図的に増やすわけでも、木目を潰すわけでもない点が重要。
Q6 : インデックス付きヘッドストックを利用すると容易にできる作業はどれか
インデックス機構はスピンドルを一定角度で機械的に固定できるため、ワークを静止させた状態で均等割りの線刻、フルート入れ、ドリル加工などが高精度に行える。例えば24分割リングを備えた場合は15度刻みでロックでき、歯車状の装飾や多角形の削り出しが容易になる。回転数制御は電子制御領域であり、刃物研磨や芯出しは別治具が必要でインデックスだけでは達成できない。
Q7 : 木工旋盤で回転方向を逆転させて切削や研磨を行う主なメリットはどれか
繊維の向きによっては通常回転だとアップカットになり、刃が逆目に食い込んでささくれやチップアウトを起こすことがある。回転を逆転させればダウンカット方向になり、繊維を押さえつけながら削れるため仕上げ面が滑らかになる。また、サンディング時に逆方向へ当てると前工程のサンディング痕が効率的に消える。チャックねじの締まりやモーター寿命、ベルト交換は直接関係がなく、逆転の主要目的は材面品質の向上と安全性の確保である。
Q8 : 木工旋盤で深いボウルやカップを荒削りする際に最も一般的に用いられる刃物はどれか
ボウルガウジはフルートが深く、切削抵抗を逃がしつつ大量の削り屑を排出できるため大きな窪みを短時間で形成できる。刃先角度をやや鈍角に設定することで長いベベルを確保し、ブレを抑えて安全に荒取りが行える。スキューチゼルは主にスピンドル外周の仕上げや平面切削、パーテイングツールは溝切りや切り落とし、スピンドルラフターナーは丸棒外径の荒削りに適し、深い凹部の大量除去には不向きであるため誤りとなる。
Q9 : センター間加工で尾押し台に取り付け、円錐先端が回転しながら被削材を支持する部品は何か
ライブセンターはベアリング内蔵で尾押し台側に取り付ける回転センターであり、ワークと同調して回転するため摩擦熱を最小限に抑えつつ確実に支持できる。ドライブセンターは主軸側で動力を伝える固定センター、フェイスプレートは板状治具で皿物用、チャコールはチャックの誤記でいずれも尾押し台支持部品ではない。生木や堅木でも焼き付きが起こりにくい点がライブセンターの最大の利点である。
Q10 : 安全回転数を目安にする経験則として広く知られ、直径とRPMの積を一定値に抑えるルールはどれか
木工旋盤ではワーク直径が大きいほど外周速度が上がり危険が増すため、直径(mm)×RPMを18000以下にするという経験則が用いられる。直径が300 mmなら最大回転数はおよそ60 RPM×100=18000→600 RPMが上限の目安になる。国や単位系により数値は6000(inch)などに置き換わるが、直径と回転数の積を制限する考え方は共通する。他の選択肢は業界に存在しないか、単位を誤った記述である。
まとめ
いかがでしたか? 今回は木工挽物クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は木工挽物クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。