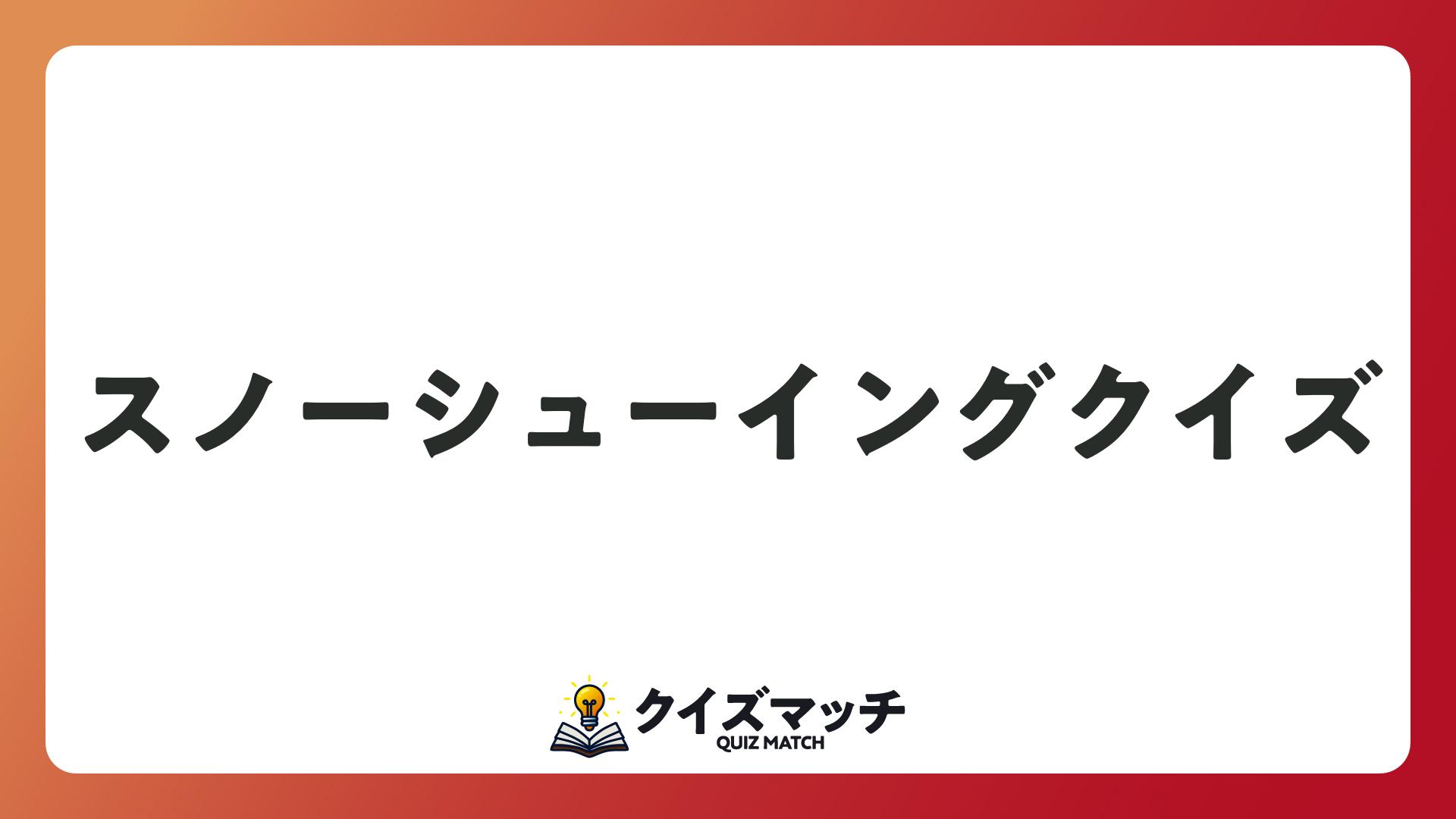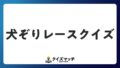スノーシューイングを思いっきり楽しもう!この記事では、雪上の冒険を盛り上げる10の興味深いクイズをご紹介します。雪の中を自由に歩き回るスノーシューの魅力と、その歴史、用具、競技情報など、多彩な知識を楽しみながら身につけていただけます。初心者からベテランまで、スノーシューの世界をさらに深く探検してみましょう。ご一緒に雪上の旅に出発しましょう!
Q1 : スノーシューのカタログでよく用いられる用語「フローテーション」が示す性能はどれか? 雪面に沈みにくい浮力性能 板の反発力 ビンディングの可動域 ポールの長さ調整幅
フローテーションとは浮力という意味で、雪面への圧力を分散し沈み込みを抑える性能を示す。デッキ面積が大きく軽量なほど体重が雪面に均一に伝わり、新雪でも足裏が深く埋まらず歩行効率が高い。反対に細身のレースモデルは軽快だがフローテーションが低く、パウダーが深い山域には向かない。サイズ選択や着脱式テイル追加で浮力を調整する考え方も含めて語られる。
Q2 : 汗冷えを防ぐためのレイヤリングで、スノーシュー行動時のベースレイヤーに最適とされる素材は? コットン100% メリノウール ポリエステルフリース ダウン
メリノウールは天然繊維ながら極細繊維で空気層を多く含み、発汗時は水分を繊維内部に保持して気化熱を遅らせるため汗冷えを最小限に抑えられる。さらに湿っても保温性が大きく低下せず、防臭性にも優れるので長時間の雪原行動に適する。コットンは濡れると乾きにくく体温を奪い、フリースやダウンは中間層・外層向けで肌面に直接着るにはオーバーヒートや汗戻りのリスクが高い。
Q3 : 1840年代に世界で初めてスノーシューを組織的なスポーツ競技として取り入れた国は? アメリカ合衆国 ノルウェー カナダ ロシア
カナダでは1840年にモントリオール・スノー・シュー・クラブが結成され、当時の英国駐屯兵やフランス系住民が伝統的道具を競技化した史料が残る。クラブは夜に松明を掲げて街道を行進するトーチライトランを開催し、これが近代スノーシュー・レースの起源と位置づけられている。アメリカでも19世紀半ばに広まったが、最初の組織化はカナダが先とされる。
Q4 : 国際的なスノーシュー大会を統括し競技ルールを策定している団体はどれか? ISMF FIS IAAF World Snowshoe Federation
World Snowshoe Federation(WSF)は2010年設立の国際競技連盟で、各国選手権の統括や世界選手権の開催、用具規格の標準化、ジュニア育成プログラムを担う。ISMFはスキーマウンテニアリング、FISはスキー競技、IAAFは陸上競技の統括団体でありスノーシューとは直接関係しない。WSFはIOC承認を目指しつつ環境保全と地域振興を掲げて活動している。
Q5 : トレッキングポールの先端に装着し、雪中で沈み込みを防ぐ円盤状のパーツ名は? バスケット キャップ ストラップ フィン
バスケットはポール先端の石突まわりに装着する円盤で、雪や泥に深く沈み込み過ぎるのを防ぐ。雪用は直径50〜100ミリまであり、広いほど支持面積が増えフローテーションが向上する。キャップは保護カバー、ストラップは手首固定、フィンは一部スキー用語。急傾斜でバスケットが支点となることでポールが杖として機能し、滑落停止や体重移動にも役立つ重要パーツである。
Q6 : 雪崩の危険があるエリアでスノーシュー行動を行う際、携行が推奨される基本的な雪崩安全装備3点セットはどれか? アイスアックス・ハーネス・クランポン プローブ・ビーコン・ショベル ヘルメット・ゴーグル・ゲイター テント・ストーブ・スリーピングマット
雪崩リスクのあるオープンバーンや樹林帯をスノーシューで行動する場合、ビーコン(送受信機)、プローブ(捜索用棒)、ショベル(掘削用)の三種は自己救助の基本セットとされる。ビーコンで埋没者の信号を捉え、プローブで正確な位置と深度を確認し、ショベルで迅速に掘り出すプロセスが確立している。他の装備だけでは埋没者救助は不可能で、グループ全員が携行・訓練するのが国際的なルールになっている。
Q7 : スノーシューで深雪を歩く際、左右の足を外側に開きハの字で進む基本的な歩行法は何と呼ばれるか? ダックウォーク シャッフルステップ グライドステップ トラバースステップ
ダックウォークはスノーシューの幅を活かしてつま先を外側に開き、左右のデッキがぶつからないように脚をハの字にして進む歩行法。深雪で交互に足をまっすぐ運ぶとフレームが重なって転びやすく、かつ沈降が大きくなる。ダックウォークなら着地面積が広がり浮力が増し、太腿への負担も分散される。急な登坂でも踏み込みやすく、初心者が最初に覚える基本ステップとされる。
Q8 : 伝統的な木製スノーシューのフレーム素材として最も一般的に用いられてきた北米産の木材は? ヒッコリー ホワイトアッシュ バンブー レッドシダー
ホワイトアッシュは北米東部に広く分布し、強靱で割れにくいわりに細く削ってもしなやかに撓るため、スノーシューのオーバル状フレームに最適とされてきた。19世紀にフランス系カナダ人や先住民が作った木枠スノーシューの多くがアッシュ材を蒸して曲げ、継ぎ目を革ひもで縛る構造を採用した。現代はアルミ合金が主流だが、クラシックモデルでは今もアッシュが好まれる。
Q9 : 現在レクリエーション用スノーシューで主流となっている、スノーボード由来の固定方式はどれか? 3ピンNNN ストラップ&バックル ラチェットバインディング ハイブリッドステップイン
ラチェットバインディングはスノーボード由来の金属バックルと樹脂ストラップを使い、ブーツを差し込んでレバーを倒すだけで素早く固定できるのが利点。雪や氷が付着してもギアが噛み合いやすく、グローブを外さず調整できるため冬山での操作性が高い。3ピンやNNNのような専用ブーツを必要とせず、ウィンターブーツや登山靴のまま装着できるのでレンタルやツアーで標準的に採用される。
Q10 : 急斜面をスノーシューで登る際、踵を高くしてふくらはぎの負担を減らすために起こして使うパーツは? テールクリート ポールバスケット フローテーションテイル ヒールリフター
ヒールリフターはテール側のデッキに折り畳まれた金属バーで、急斜面登行時に起こして踵を載せる。踵が浮くことで足首の角度が浅くなり、ふくらはぎの伸張を抑制して疲労を軽減できる。特に標高差が大きいバックカントリーでは同機能の有無が行動時間に直結すると言われる。テールクリートやフローテーションテイルは滑落防止や浮力向上のパーツで、ポールバスケットは別装備。
まとめ
いかがでしたか? 今回はスノーシューイングクイズをお送りしました。
今回はスノーシューイングクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!