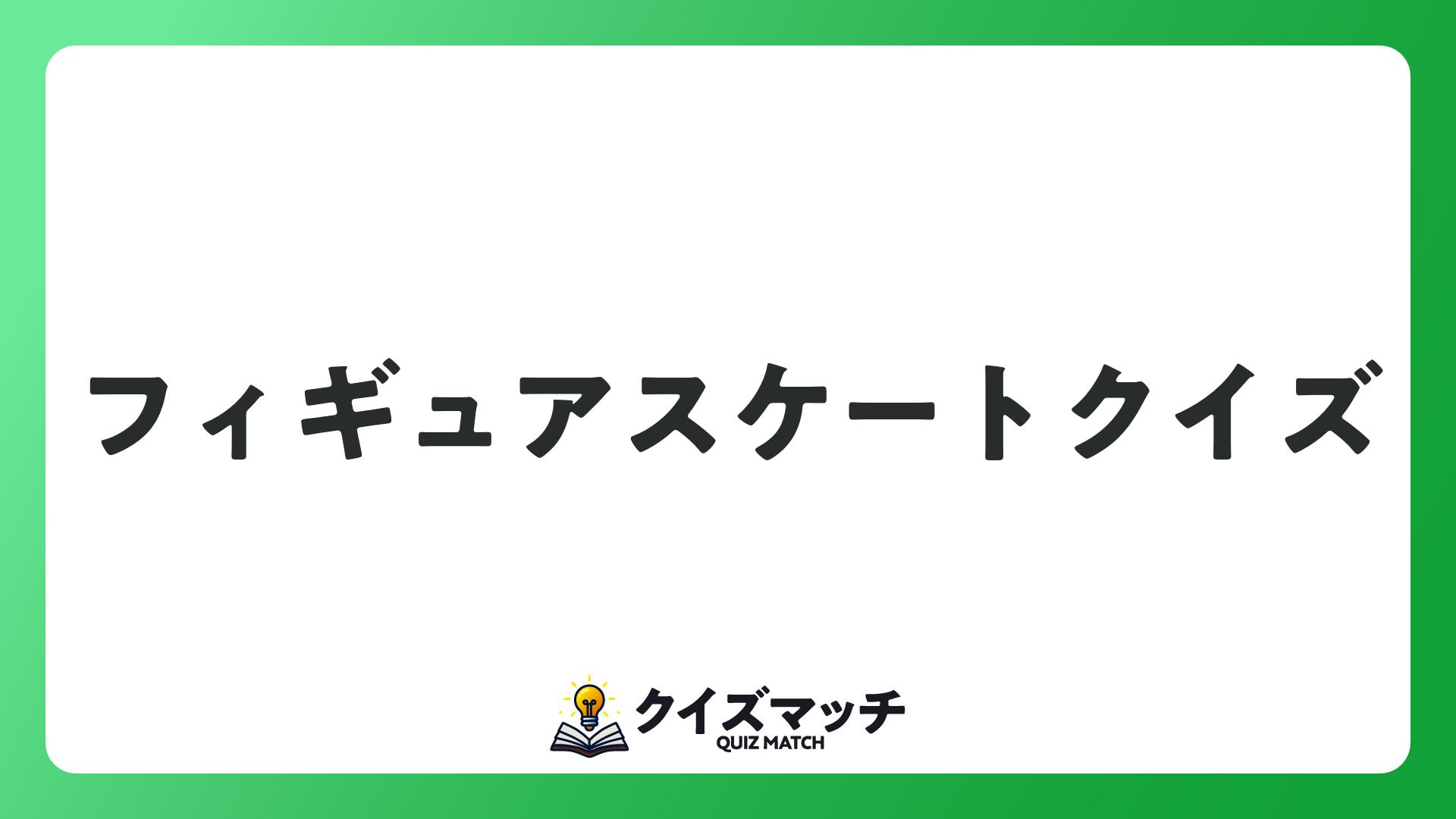フィギュアスケートは技術と芸術性が絶妙に融合した魅力的な競技です。今季も世界のトップスケーターたちが、華麗な演技で観客を魅了してきました。そこで、フィギュアスケートに詳しいあなたに、この競技の歴史や記録、選手たちの偉業について10問のクイズにチャレンジしていただきます。過去の五輪金メダリストから、4回転ジャンプの先駆者まで、フィギュアスケートの重要な出来事を振り返ることができるはずです。これを機に、フィギュアスケートの奥深さをさらに探究してみましょう。
Q1 : 2018年平昌オリンピックの女子シングルで金メダルを獲得したロシアの選手は誰? クセニア・ストルボワ ソフィア・サモドゥロワ アリーナ・ザギトワ カミラ・ワリエワ
アリーナ・ザギトワは平昌五輪のショートで自己ベスト82.92点を叩き出し、フリーでも終盤にジャンプ要素を集中させる戦略で合計239.57点を記録して金メダルを獲得した。当時15歳11か月での優勝は女子シングル史上2番目の若さ。後半ジャンプ配置ルールの改定が翌シーズンから行われる契機ともなり、ザギトワの戦略性と技術の高さが競技規則にまで影響を及ぼした。表現面では『ドン・キホーテ』の軽快な演技で観客を魅了し、ロシア女子の層の厚さを世界に示した大会となった。
Q2 : 国際スケート連盟(ISU)公認大会で史上初めて4回転ルッツを成功させた男子選手は誰? ネイサン・チェン ケヴィン・レイノルズ 羽生結弦 ブランドン・ムロズ
アメリカのブランドン・ムロズは2011年11月のISUグランプリシリーズ・中国杯のフリースケーティングでクリーンな4回転ルッツに成功し、ISU公認大会で史上初の快挙として国際連盟に正式認定された。4回転ルッツは踏み切りがトウ系ジャンプの中で最も難度が高く、現行ルールで基礎点11.5点を誇る。ムロズの成功はその後のネイサン・チェンや金博洋ら多回転時代の扉を開き、男子シングルにおけるジャンプ構成の上限を一段押し上げる象徴的出来事となった。
Q3 : ISUシニアグランプリシリーズ(グランプリファイナルを除く)の通常シーズンにおける大会数はいくつ? 5大会 6大会 7大会 8大会
シニアのISUグランプリシリーズは通常シーズンにアメリカ、カナダ、フランス、フィンランドまたは中国、ロシアまたはイギリス、日本の計6大会で構成される。それぞれの大会で選手は最大2戦に出場し成績に応じたポイントを獲得、上位6名(ペア・アイスダンスは6組)がグランプリファイナルへ進出するシステムになっている。シリーズは1995年に始まり、開催国は経済状況や国際情勢により変動するが、6大会制という枠組みは今日まで維持され、選手にとってシーズン前半の重要な指標となっている。
Q4 : 2014年ソチオリンピックの女子シングルで金メダルを獲得した選手は誰? キム・ヨナ アデリナ・ソトニコワ アリーナ・ザギトワ カロリナ・コストナー
ソチ五輪(2014年)の女子シングルでは、優勝候補と目された前回女王キム・ヨナをわずかに上回り、地元ロシア代表のアデリナ・ソトニコワが合計224.59点で歴史的な金メダルを獲得した。キム・ヨナが全体トップの演技構成点を得た一方、ソトニコワはトリプルループ‐トリプルトウループなど高難度ジャンプの出来栄え加点で技術点を伸ばして逆転。判定をめぐり論争も起こったが、採点ルールではジャンプの基礎点と出来栄えが勝負を分けた典型例として語られている。
Q5 : 女子選手として世界で初めて公式競技でトリプルアクセルを成功させたのは誰? トーニャ・ハーディング 荒川静香 伊藤みどり 浅田真央
伊藤みどりは1988年NHK杯でトリプルアクセルを女性として史上初めて成功させ、1992年アルベールビル五輪でも同ジャンプを決めて銀メダルを獲得した。トリプルアクセルは基礎点が8点を超える超高難度で、前向き踏み切り3回転半という構造上、空中姿勢と着氷バランスの双方が極めてシビアである。伊藤の快挙は女子フィギュアの技術革新を10年以上早め、後進の浅田真央やトゥルソワらの多回転時代の礎となった。
Q6 : 2022-23シーズンのシニア男子フリースケーティングの規定演技時間は? 3分30秒 4分30秒 5分00秒 4分00秒
2018-19シーズンからISUは競技時間短縮の方針を取り、男女ともフリースケーティングを30秒短い4分00秒(許容誤差±10秒)に統一した。これによりスタミナ配分やジャンプ配置の最適化が重要となり、選手たちは後半ボーナスを維持しつつ4分枠内に最大7本のジャンプ要素を詰め込む戦略を再構築した。特に4回転を複数本跳ぶトップ選手にとっては演技後半の体力との戦いがさらにシビアになり、音楽編集や振付密度の工夫が勝敗を左右する要素となっている。
Q7 : 日本人男子として初めてISUグランプリファイナルを制した選手は誰? 織田信成 高橋大輔 小塚崇彦 羽生結弦
2008-09シーズンのグランプリファイナル(韓国・高陽)で高橋大輔はショートプログラム1位、フリー1位の完勝を収め、日本男子として初めて同大会の頂点に立った。前年に右膝前十字靱帯断裂の大怪我を負いながら復帰後わずか1年での快挙であり、4回転フリップ挑戦と情感豊かなステップで高難度と芸術性を両立させた姿は国内外に大きなインパクトを残した。この偉業は後輩の羽生結弦、宇野昌磨らに続く日本男子黄金時代の幕開けを象徴する出来事として語られる。
Q8 : オリンピック競技でコンパルソリーフィギュアが最後に実施された大会はどれ? 1988年カルガリー 1984年サラエボ 1992年アルベールビル 1976年インスブルック
コンパルソリーフィギュア(規定演技)は氷上に描いた図形の正確さを競う歴史的種目だが、テレビ映えの乏しさや採点の透明性への疑問から1988年カルガリー大会を最後に廃止された。以降1990年世界選手権をもって完全に終了し、スケーターの練習時間はジャンプやスピンなどフリースケーティング重視へと移行した。カルガリーではブライアン・ボイタノやカタリナ・ヴィットらが規定・ショート・フリーの総合点で争い、コンパルソリーの配点が依然として勝敗を左右する最後の五輪となった。
Q9 : フィギュアスケートのジャンプ名『サルコウ』の由来となった人物は誰? ギリェルモ・サルコウ ガブリエル・サルコウ アンリ・サルコウ ウルリッヒ・サルコウ
サルコウジャンプは1909年世界選手権王者でスウェーデン出身のウルリッヒ・サルコウが考案し、自身の名を冠した。アウトエッジで後ろ向きに踏み切り、空中で1回以上回転して同じエッジで着氷するのが特徴で、現在のISUルールではトリプルで4.3点、クワッドで9.7点の基礎点が設定されている。20世紀初頭はまだシングル回転が主流だったため、この跳躍は革新的だった。サルコウは後にIOC委員も務め、技と組織運営の両面でフィギュア発展に大きく寄与した。
Q10 : フィギュアスケートの採点項目『TES』の正式名称は何? Technical Element Score Total Execution Score Technical Evaluation Scale Time Examination Standard
TESとはTechnical Element Scoreの略で、ジャンプ・スピン・ステップなど技術要素ごとの基礎点と出来栄え評価(GOE)を合算した数値である。演技構成点(PCS)と合計してプログラムスコアが算出されるが、特に高難度4回転やレベル4スピンで大きな加点を得た選手はTESが突出し順位を左右する。近年はGOEが±5段階に拡張され、基礎点の低いジャンプでも質が高ければ大きく得点を伸ばせるため、選手は難度と完成度のバランスを取った戦略が不可欠となっている。
まとめ
いかがでしたか? 今回はフィギュアスケートクイズをお送りしました。
今回はフィギュアスケートクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!