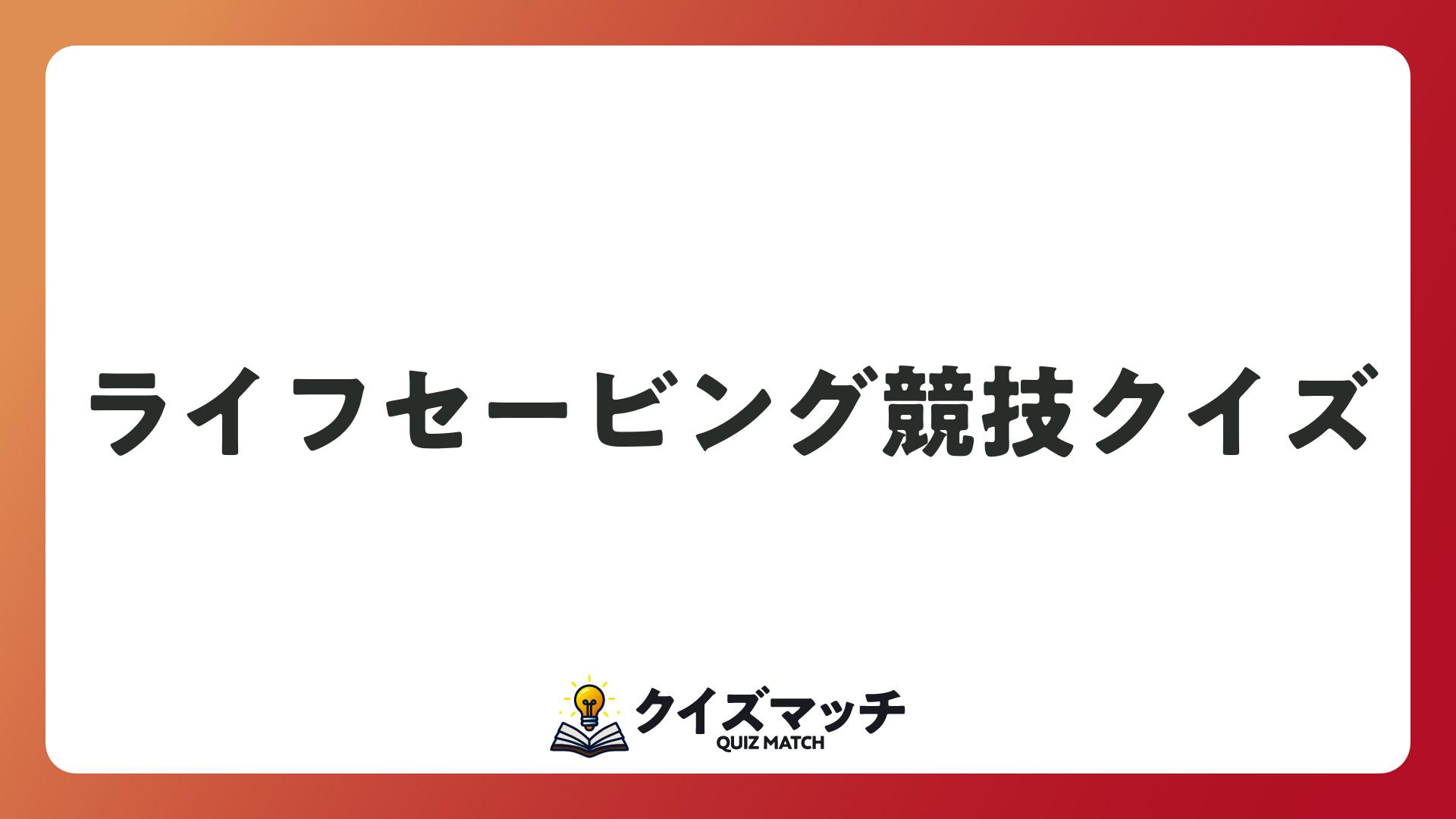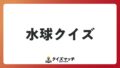ライフセービング競技に挑戦しよう!
Q1 : タプランリレー(Taplin Relay)に含まれない種目は次のうちどれか? ボード スイム サーフスキー ビーチスプリント
タプランリレーはオーシャンマン/オーシャンウーマンの団体版とも言える種目で、一般的にスイム、ボード、サーフスキー、そして最後にビーチラン(ランのみ)でゴールテープを切る4区間で争われる。したがって選択肢で唯一含まれないのは短距離単独種目であるビーチスプリントである。各区間の種目特性が大きく異なるため、チームは得意分野に応じたオーダー戦略を立てる必要がある。またタッチゾーンでのバトンタッチや波の選び方が勝敗を分けることも多く、総合力と戦術眼が両立して求められるリレー種目である。
Q2 : プール種目『100mマネキンキャリー with フィン』で選手が前半50mで使用する装備はどれか? フィンのみ パドル板 シュノーケルのみ フィンとシュノーケル
100mマネキンキャリー with フィンは、前半50mをフィンとシュノーケルを装着したまま高速で泳ぎ、折り返しで水底のマネキンをピックアップし、後半50mを肩に抱えてフィンキックで戻る種目である。シュノーケルを使うことで潜水せず呼吸を確保しながら前進でき、スピード維持と姿勢安定が図られる。ターン時の潜降・浮上動作をいかに素早く行うかがタイム短縮のカギで、フィンワーク、マネキンの抱え方、隊員の水中姿勢など総合的技術力が要求される。国際大会では1秒未満の差で順位が入れ替わることも珍しくないスリリングな競技である。
Q3 : ビーチスプリント競技の国際ルールで定められた距離は何メートルか? 70m 90m 100m 120m
ビーチスプリントは砂浜上の直線コースを全力疾走する陸上短距離系種目で、国際ライフセービング連盟のルールではスタートラインからフィニッシュラインまでの距離を90mと定めている。砂地は反発が少なく路面も不安定なため、陸上の100m走とは異なる筋力発揮とピッチのコントロールが求められる。転倒を避ける重心管理やサイドウインドへの対応も重要で、スタートダッシュと中盤以降の加速維持がタイムに直結する。また観客が近距離で観戦できるため、派手な競り合いが多くビーチ大会を盛り上げる中核種目となっている。
Q4 : ラインスロー(Line Throw)競技では要救助者役はプールサイドから何メートル沖に位置するか? 8m 10m 12.5m 15m
ラインスローはロープを用いた救助を競うプール種目で、要救助者役はスタート台から12.5m沖に配置されたルールブイに掴まって待機する。救助者は合図とともにロープを投げ、要救助者がロープ端を確保したのを確認して引き寄せ、双方がプール縁のタッチパネルに触れるまでの時間を計測する。距離が12.5mに設定されている理由は、25mプールのちょうど半分で視認性と難度のバランスが良く、実際の岸壁救助を想定した投擲技術が反映されやすいからである。正確なコントロールと素早いロープ回収が勝敗を左右する。
Q5 : インフレータブルレスキューボート(IRB)レースで1艇に乗艇するクルー人数は何人か? 2人 3人 4人 5人
IRBレースではゴム製の救助艇にドライバーとクルーの計2名が乗艇する。ドライバーは船尾でエンジンを操り、クルーは船首側でバランスを取りながら要救助者役のピックアップや旗タッチなどを行う。チームワークが悪いと波で艇が跳ね上がり転覆しやすいため、重量移動とスロットルワークを完全に連携させることが不可欠だ。競技では沖のターンブイを回り、要救助者を素早く救助してビーチに戻り、最後にボートを陸上へ押し上げてフィニッシュする高速種目で、波の読みとエンジン操作技術が大きく勝敗を分ける。
Q6 : SERC(Simulated Emergency Response Competition)での救助活動時間の制限は何分か? 1分 2分 2分30秒 3分
SERCは予め知らされない多傷病者シナリオに対し、4人1組のチームが臨機応変に対応するシミュレーション競技で、評価対象となる救助活動時間は2分と定められている。競技前に会場を見ずに30秒〜1分間のブリーフィング準備が与えられ、笛の合図でシナリオが開始、2分後の終了ホイッスルまでに安全確保・意識確認・通報・蘇生・外傷処置などを実施しなければならない。短い時間内に役割分担と優先順位の判断を行うため、知識だけでなくチームリーダーシップとコミュニケーションが高得点の鍵となる。2分を過ぎての処置は採点対象外となるため、タイムマネジメントが極めて重要である。
Q7 : サーフレース(Surf Race)で選手が往復するコースの総距離はおおよそ何メートルか? 200m 800m 400m 1500m
サーフレースはビーチからスタートし、沖合に設置されたターンブイを回って再びビーチへ戻る競技で、国際ライフセービング連盟(ILS)の競技規則ではコース長が約400mになるよう設定することが推奨されている。波や潮流によってロープの張り方が変わるため正確な距離は大会ごとに微調整されるが、概ね400m前後に統一されている。選手は短距離と長距離の中間的な負荷に対応する持久力に加え、波に乗る技術、ターンブイでのポジショニング、ビーチへのランニング導線など多彩な戦術を駆使して順位を争う。
Q8 : ビーチフラッグスで使用されるフラッグの本数はスタート時の選手数と比べてどのように設定されるか? 選手数と同じ 選手数マイナス1本 固定で5本 選手数の半分
ビーチフラッグスは砂浜にうつ伏せで並んだ選手が、合図とともに約20m先のフラッグを奪い合うトーナメント形式の競技である。スタート人数より1本少ないフラッグを設置するルールにより、必ず1名が脱落し、次ラウンドでは選手数とフラッグ数を再度「人数-1」に揃えていく。これを繰り返すことで勝者が決まるため、瞬発力だけでなく反応速度やスタート姿勢の最適化が重要になる。フラッグの本数を減らすことで常に競り合いが生じ、観客にもわかりやすいエキサイティングな展開が維持される点が魅力である。
Q9 : ボードレスキュー(Board Rescue)競技のチーム人数は何人か? 2人 3人 4人 6人
ボードレスキューは水面に待つ要救助者役のスイマーと、救助用レスキューボードに乗るレスキュアの計2人で構成される種目である。スイマーはスタートと同時に沖へ泳ぎ指定ブイで待機し、レスキュアはボードで漕いで接近、スイマーをボードに収容して共に戻る。素早い合流とボード上での体重移動、波を利用した滑走が勝敗を左右する。2人制であるためチームワークが結果に直結し、漕力と泳力のバランス、声掛けによる意思疎通など総合的な救助能力を試される点が競技の醍醐味となっている。
Q10 : レスキューチューブレスキュー(Rescue Tube Rescue)では1チームは通常何名で構成されるか? 2名 3名 4名 5名
レスキューチューブレスキューは4名1組で実施される。1人は沖合で要救助者役となって待機し、1人がレスキューチューブを装着して泳いで接近、残る2人は陸上からロープを巻き取りながら引き戻すアシストを担当する。泳者が要救助者をチューブで確保しサインを出すと、ビーチ上の2人が一気にロープを手繰り寄せて両者を引き上げ、最後に全員がフィニッシュラインを通過するとタイムが止まる。4名それぞれに明確な役割があり、泳力・力力・連携・コミュニケーションを総合的に試されるため、リレー的要素と本格的救助技術が融合した人気種目となっている。
まとめ
いかがでしたか? 今回はライフセービング競技クイズをお送りしました。
今回はライフセービング競技クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!