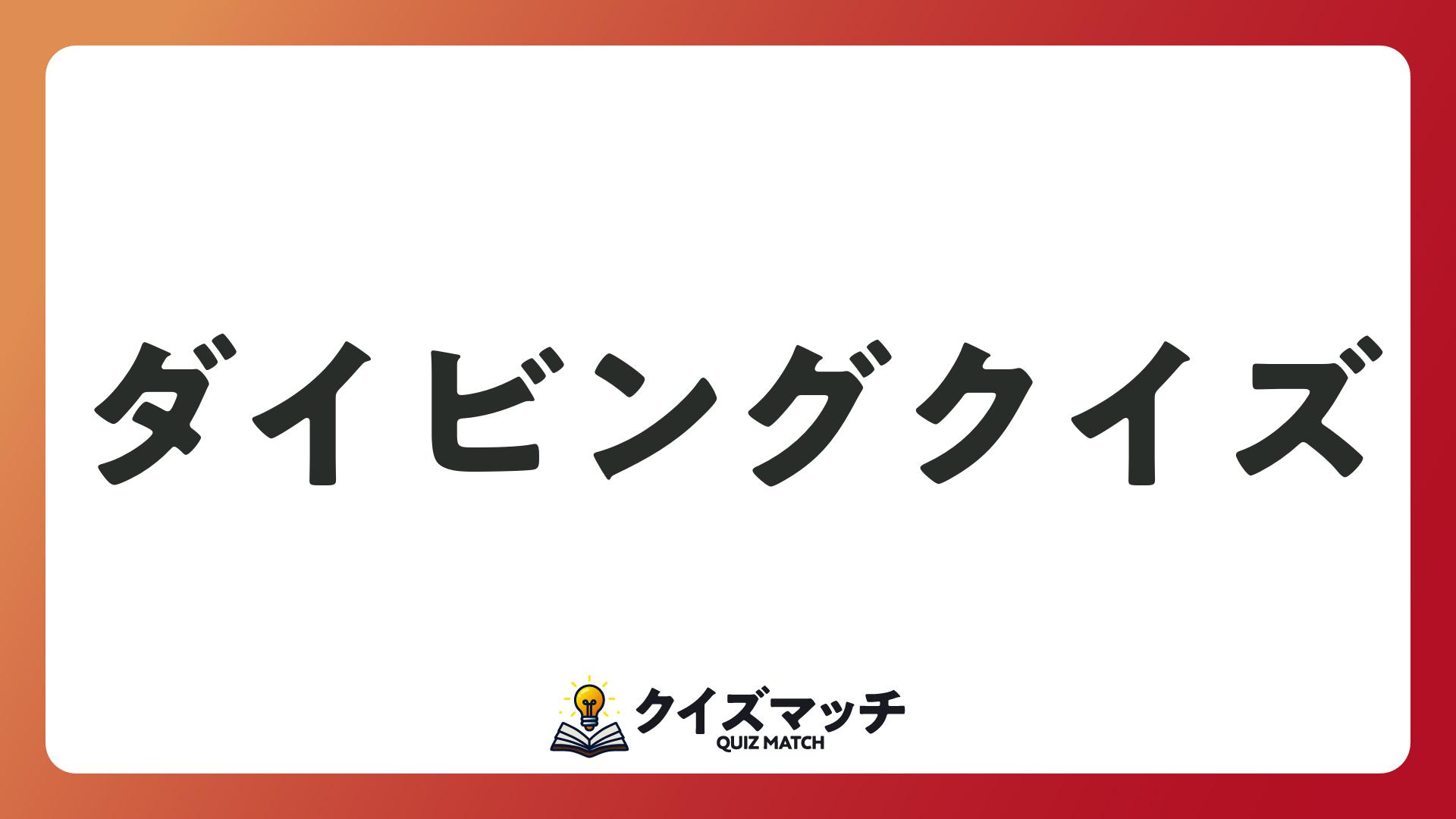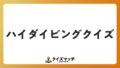ダイビングの基礎知識を問うクイズをお送りします。水中での物理法則や装備、安全対策について、初心者から上級者まで幅広く理解を深めることができる内容となっています。ダイビングの魅力と楽しさを感じながら、様々なテクニカルな側面にも注目していただければと思います。クイズを通して、ダイビングの知識と技術をさらに磨いていただければ幸いです。
Q1 : 代表的なアルミシリンダー(AL80)は残圧が減るにつれて水中でどのような挙動を示すか?
アルミ合金製のタンクは内部の空気質量が減ると全体の重さが軽くなり,水中における浮力が正の方向へ移動する。満タン時はわずかにマイナス浮力だが,残圧50気圧程度になるとプラス浮力になる個体もあり,適切にウェイトを設定していないと安全停止中に浮上してしまう恐れがある。スチールタンクは製造特性から最後までマイナス浮力を保ちやすいが,アルミタンクでは特にエア残量とトリムの変化を想定したウエイト計画が重要になる。
Q2 : 水中でレギュレーターがフリーフロー(連続排気)を起こした場合の初動として適切なのはどれか?
レギュレーターがフリーフローを生じても空気は常に供給されているため,外さずにくわえ続ければ呼吸は可能である。まずは排気ポートやダストキャップ付近を手で軽く抑える,スローヤークルを与えるなどして流量を抑え,姿勢を安定させてからゆっくり浮上または予備レギに切り替えるのが基本手順とされる。急に口から外すとパニックや水の誤飲を招きやすく,またBCDをいきなり排気すると制御不能な浮上につながる。水面やバディへの到達までのエア消費を最小限に抑えるためにも冷静な対処が重要である。
Q3 : レクリエーショナルダイビングで推奨される安全停止は一般的にどの深度で何分間行うとされているか?
無減圧潜水であっても最後に5メートル付近で3分間静止することで体内に溶け込んだ窒素を追加で排出する時間を確保できる。これは減圧症リスクを下げる最も簡単で効果的な予防策として世界中の指導団体が薦めている。ダイブコンピュータのアルゴリズムによっては義務ではなく推奨と表示される場合もあるが,多くのダイバーが毎回実施する習慣になっている。なお水面が荒れている場合はラインを持って停止すると姿勢を保ちやすい。
Q4 : 窒素酔い(窒素ナルコーシス)が顕著に現れ始めるとされるおおよその水深はどれか?
窒素は高圧下で麻酔作用を示すため水深が深くなるほど意識や判断力が鈍る。個人差はあるものの多くのダイバーが30メートル付近で手先の器用さ低下や計算ミスといった軽度の症状を感じ始めると報告している。浅い18メートル程度ではほとんど影響を受けないが,深度が40メートルを超えると泥酔状態に似た強い酩酊を起こす危険がある。ナルコーシスは浮上すると速やかに回復するが,発生中は自覚しにくいので計画深度を守りこまめに自己チェックすることが重要である。
Q5 : ダイバーが発症する減圧症(DCS)の直接的な原因として最も正しい説明はどれか?
呼吸中の窒素は圧力に応じて血液や組織に溶け込むが,浮上で圧力が下がると飽和しきれずに気泡となる。小さな気泡は肺で排出されるが,急浮上や長時間深い深度にいた場合は体内に多数の気泡が残存して関節痛,中枢神経障害,皮膚発疹など多彩な症状を起こす。これが減圧症の本質であり,ゆっくりとした浮上,減圧停止,十分な水分補給などはすべて窒素の気泡化を抑えるために行われる。酸欠や低体温は誘因になり得るが直接原因ではない。
Q6 : レクリエーショナルダイブコンピュータやテーブルに表示される『NDL』は何という語句の略称?
NDLは減圧停止を必要としない最大潜水可能時間を示す指標で,No Decompression Limitの頭文字を取ったもの。指定された深度でNDLを超えない範囲ならば,通常の浮上速度で水面まで安全に上がれると仮定されている。ダイブコンピュータは温度やプロファイルを解析してリアルタイムで残余NDLを計算し,値がゼロになると緊急減圧ステージが指示される。これを把握しておくことにより,安全マージンを保った潜水計画やエアマネジメントが可能になる。
Q7 : PADIオープンウォーターダイバーが講習直後に潜れる最大推奨水深は?
PADIオープンウォーターダイバー認定後のレクリエーショナルダイビングでは最大18メートルまでが推奨限界と定められている。これは水圧や窒素負荷,スキルレベルを考慮して安全係数を掛けた深度であり,多くの観光ダイビングの計画がこの範囲内で組まれる。さらにアドバンスド・オープンウォーターを取得すれば30メートルまで拡張される。初心者が不用意に18メートルを超える深度に到達すると、窒素酔いやエア消費の増大,緊急時の浮上距離増加などリスクが急増するため,経験を積むまでは規定を守ることが重要である。
Q8 : 水中で最初に視認しづらくなる色は一般的にどれか?
太陽光は波長によって吸収される速度が異なり,水深数メートルでも長波長の赤い光が大きく減衰する。したがって赤色の物体は10メートル付近で灰色や黒に見えるようになり,水中写真ではライトを当てないと赤の発色が得られない。青や緑の短波長は透過率が高く30メートル以上でも残るため,全体が青緑色の世界に見える。色の消失は深度感覚を惑わせたり血液の色を見えにくくしたりするので,ダイバーはライトやカラーチャートを活用して状況確認を行う。
Q9 : レクリエーショナルダイビングで高酸素ナイトロックスを使う場合,作業中に設定される最大許容酸素分圧(PO2)の一般的な上限値は?
酸素は分圧が高すぎると中枢神経障害や肺毒性を招くため,テクニカルではない通常のナイトロックス運用では1.4ataを上限に設定するのが国際的な標準となっている。例えばEAN36を吸う場合,1.4ataに達する深度は約28メートルであり,それを超えないようダイブコンピュータはMOD(最大作業深度)を計算して警告を出す。緊急時など短時間のコンティンジェンシーとして1.6ataまで許容する設定もあるが,長時間曝露は重大な痙攣リスクにつながるため計画段階で管理することが求められる。
Q10 : ダイビングにおいて「ボイルの法則」は空気などの気体が圧力とどの物理量の間で反比例するかを示したものか?
水深が2倍になると周囲圧力はおおよそ2気圧になり気体の体積は半分になるというように圧力と体積が反比例する関係を示すのがボイルの法則である。このためマスクや副鼻腔など体内外の空間は潜降に伴い縮み,圧平衡が取れないと痛みや損傷が起こる。浮上時は逆に膨張するので肺のオーバーエキスパンションを防ぐために呼気を続ける必要があるなど,ダイバーが安全に潜水するうえで最重要の物理法則とされる。
まとめ
いかがでしたか? 今回はダイビングクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はダイビングクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。