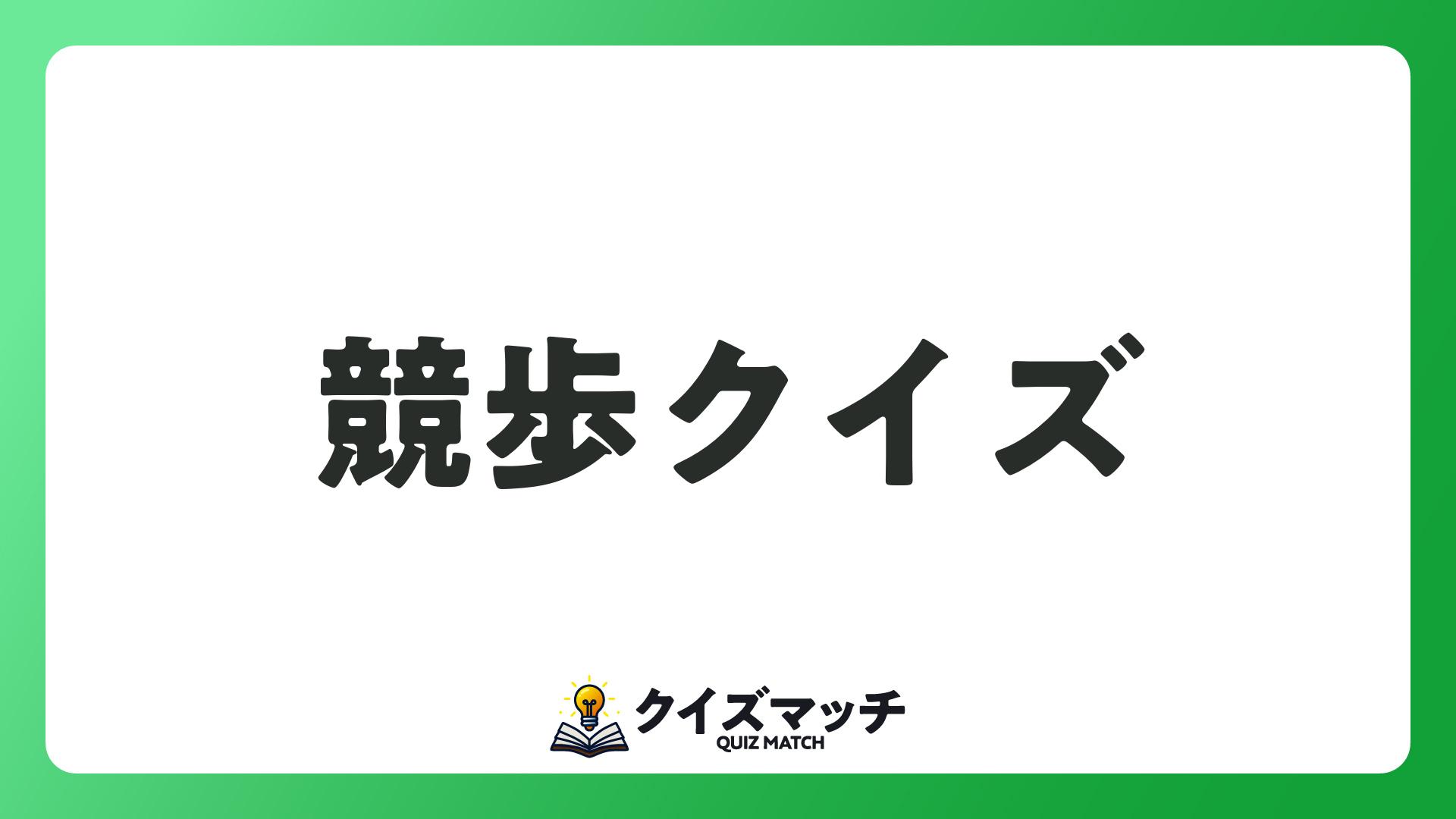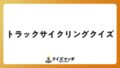競歩は、走りと歩行のルールを組み合わせた魅力的な競技です。この記事では、競歩のルールや歴史、有名選手など、競歩に関するさまざまな知識を深めるクイズを10問ご紹介します。競歩の基本的な仕組みから、最新の国際規則の変更点まで、競歩ファンもそうでない方も楽しめる内容となっています。競歩への理解を深めていただき、2023年のブダペスト世界陸上をはじめ、今後の競歩大会をより一層楽しんでいただければ幸いです。
Q1 : 東京2020オリンピックの女子20km競歩で日本選手の最上位となったのは誰?
藤井菜々子は高校時代から長距離で活躍し、実業団入り後に競歩へ専念。東京五輪では札幌に設定された14周コースを1時間31分53秒で完歩し、17位で日本勢最高となった。気温30度を超え体感湿度も高い中、多数の選手が後半に脱落するサバイバルレースとなったが、藤井はイーブンペースを守り着実に順位を上げた。入賞圏外とはいえ日本女子競歩が世界で戦う手応えを得たレースとして評価されている。
Q2 : 国際陸連(WA)が定める競歩用シューズ規定で、ソールの厚さ上限として正しい数値は?
厚底シューズの普及に伴い、競歩でも反発性素材の恩恵が議論となった。World Athleticsは公認記録の条件を統一するため、ロード種目のシューズ厚を40mm以下に制限し、競歩にも同条項を適用した。ソール内部にプレートを入れることは許可されるが、剛性が極端に高い場合は別途製品承認が必要となる。規定違反が発覚すると選手は失格・記録抹消だけでなくスポンサー契約にも影響するため、各国チームは計測ゲージを用いて事前確認を行っている。
Q3 : 競歩において膝を伸ばしていなければならない区間として正しいのは?
支持脚をまっすぐに伸ばして歩くことは競歩を走りと区別する決定的な条件で、国際規則の膝の伸展条項により体の垂直線を超えるまで膝が曲がると違反となる。接地前に曲げ伸ばしを行うと脚がバネのように使われ走行動作へ近づいてしまうため禁止されている。審判は選手の横方向から膝の角度を確認し、違反の疑いがあれば黄色パドルや赤カードで指摘する。
Q4 : 2021年東京オリンピックで実施された男子競歩最長距離種目はどれ?
東京2020大会では男子50km競歩が五輪史上最後の実施となった。早朝の札幌コースで行われ、猛暑の中でも多くの選手が完歩した。IOCとWAは競技時間が長く放送枠に収まりにくい50kmを廃止し、性別平等の観点から35km混合リレーへの変更を決定している。そのため東京で行われた50kmは歴史的なラストレースとなり、20kmより長い距離種目はこの大会限りで姿を消した。
Q5 : 2023年のブダペスト世界陸上・男子20km競歩で金メダルを獲得した選手は?
アルバロ・マルティンは2023年ブダペスト世界陸上で20km競歩を制し、自身初の世界タイトルを獲得した。終盤に強烈なロングスパートをかけ1時間17分32秒でゴール。日本の山西利和やスウェーデンのコケを突き放した。マルティンは35kmでも優勝し二冠を達成、スペイン競歩の黄金期再来を印象づけた。彼の安定したフォームはロス・オブ・コンタクトのリスクが少なく審判からの警告がゼロだった点も高く評価された。
Q6 : 2015年に石川県の大会で男子20km競歩の世界記録1時間16分36秒を樹立した日本人選手は?
鈴木雄介は2015年3月15日に石川県能美市で行われた全日本競歩20kmで1時間16分36秒の当時世界記録を樹立し、旧記録を大幅に更新した。平均ペースは1kmあたり3分49秒とハーフマラソン並みの高速。国内で誕生した世界記録は日本競歩界に大きな衝撃を与え、その後の強化策や若手育成の指標となった。鈴木はその後故障に苦しんだが、この記録は2021年まで世界トップとして君臨し続け、国内外にその名を刻んだ。
Q7 : 競歩で審判が黄色いパドルを選手に向けて掲げた場合、どのような扱いになる?
黄色パドルは公式には警告(Caution)と呼ばれ、審判が技術的な改善を求める合図である。まだレッドカードは提出されておらず、選手は失格にカウントされない段階でフォームを修正できる。パドルには<や~など記号が描かれ、何の違反が疑われているかが一目で分かる。トップ選手でも終盤に疲労で膝が曲がりやすいため、黄色パドルを受け取った瞬間にピッチと姿勢を立て直す能力が勝敗を左右する。
Q8 : 競歩の国際大会で導入が進むピットレーンペナルティ方式で、20km競歩シニアカテゴリーにおけるペナルティ時間は?
ピットレーンペナルティは2019年以降段階的に導入された新制度で、3枚目のレッドカードで即失格とする従来方式より観戦価値を高める狙いがある。シニア20kmでは2分間の停止が規定され、その間選手は設置されたレーン内で待機しなければならない。復帰後は位置を取り戻そうとオーバーペースに陥るリスクもあり、戦術が難しい。タイムペナルティ制はテレビ中継で視覚的に理解しやすく、若年層への競技普及にも寄与している。
Q9 : 競歩の発祥とされ、19世紀にプロ興行として発達した国はどこ?
イギリスの19世紀は鉄道網が発達する前で、徒歩による長距離移動が一般的だった。やがて歩行距離や時間を賭ける興行「ペデストリアニズム」がロンドンやマンチェスターで大流行し、高額賞金を目当てに専門選手が誕生した。歩行技術を公平に判定するルール作りが必要となり、審判制が確立されたのが近代競歩の出発点である。これが1908年五輪の正式種目採用へと繋がり、現在の競歩文化の原点とされる。
Q10 : 競歩の基本的なルールで、失格となる「ロス・オブ・コンタクト」とはどのような状態を指す?
競歩では規則3.1により常に地面との接触を保つことが要求されている。審判が肉眼で瞬間的に両足が浮いたと判断できるとロス・オブ・コンタクトとなり、まず赤カードが提出される。3人の審判から異なる赤カードが累積すると失格。スピードを上げるほど滞空時間が長くなりやすいためトップ選手ほどこの違反のリスクが高い。技術と体幹強化でピッチを維持し接地を確実にすることが鍵となる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は競歩クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は競歩クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。