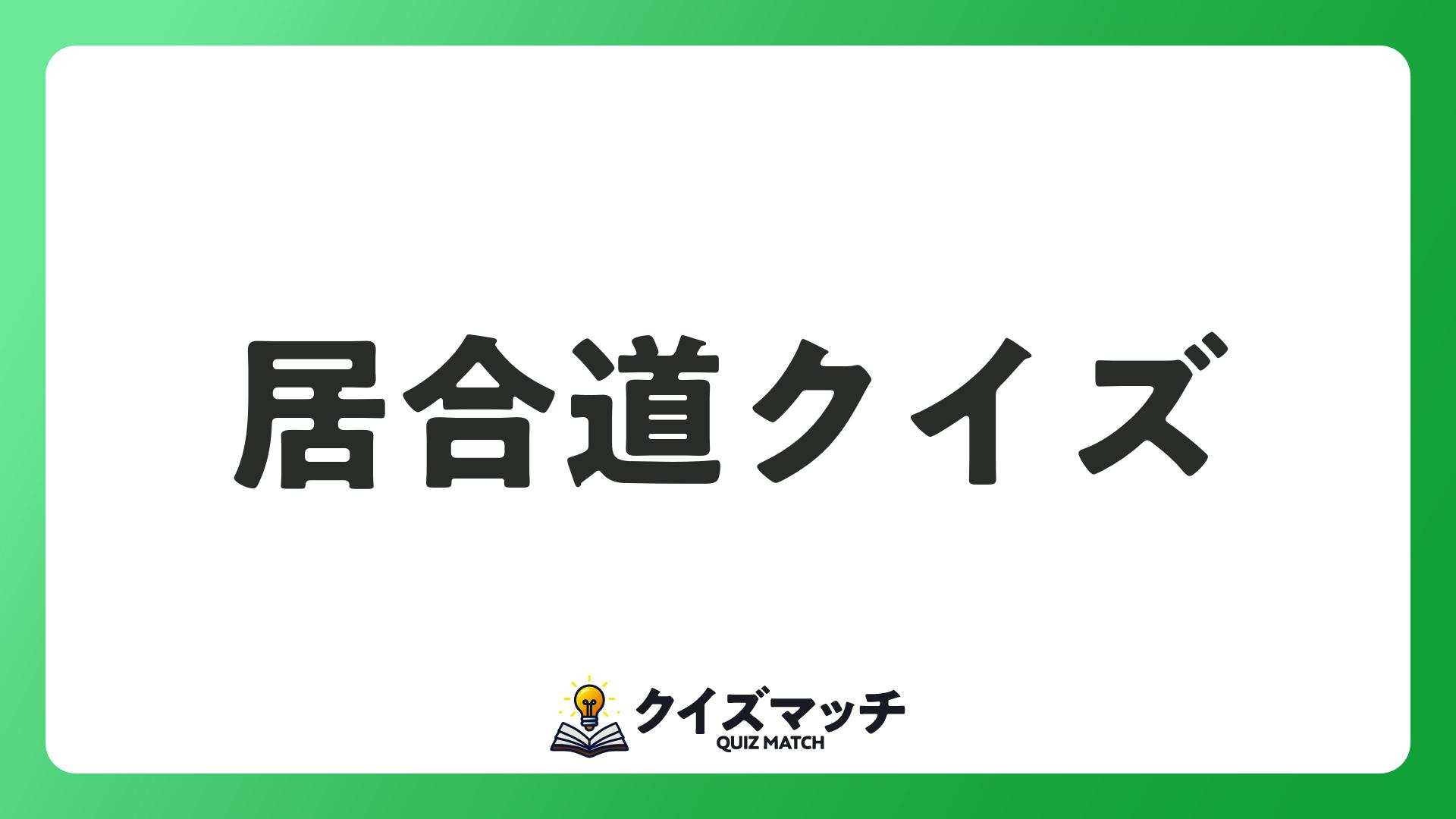居合道は、日本の伝統的な剣術の一つで、短刀や刀を鞘から抜いて即座に相手を斬る技術です。この分野には深い歴史と哲学があり、現代でも多くの熱心な実践者が存在しています。本記事では、居合道を学ぶ上で重要な基本知識を問うクイズを10問ご用意しました。居合道の歴史、技術、大会などについて理解を深めていただければ幸いです。居合道の奥深さと魅力を感じていただければ、さらなる探求の機会につながればと思います。
Q1 : 制定居合12本の中で、左腰側から刀を抜き相手の側面を想定して動く唯一の形はどれか?
制定居合第四本『左』は座位で右側に敵がいる状況を想定し、通常と反対側の左腰から刀を抜いて応じる特徴的な形である。抜刀方向が逆になるため鞘引きや体捌きに普段と違う注意が必要で、左右対称の身体操作が身に付いていないと安定しない。敵の動線を遮りながら間合を取り、最終的に斜め斬りで制する過程は居合道における柔軟な発想と姿勢保持力を養う教材となっている。審査では鞘の扱いと腰の切り替えが特に注視される。
Q2 : 全日本剣道連盟が主催し毎年秋に開催される居合道の全国大会は一般に何と呼ばれるか?
『全日本居合道大会』は全日本剣道連盟が昭和46年から開催している国内最高峰の居合競技会で、段位別・年齢別の部門が設けられ全国の有段者が技量を競う。会場は近年では愛知、東京、山梨など持ち回りで、例年10月頃に行われる。演武は制定居合と各自の所属流派の形を組み合わせて採点され、段位審査とは別に競技志向の評価が特徴。上位進出者は品位、間合の取り方、刀法の切れに加えて礼法の完成度まで総合的に審査される。
Q3 : 居合道で演武を終えた後、刀を鞘に収める所作を何と呼ぶか?
納刀は切リ終え血振りを行った後に刃を正確に鞘に戻す動作で、単に刀を収めるだけでなく心身を鎮め次への備えを示す重要な礼法である。刃線と鞘口を一致させる指先の繊細さ、左手の鞘引きと右手の送り込みの一致、さらに視線を敵から離さない『残心』が評価対象となる。動作中に刃が鞘に当たると減点の対象となるため、高段者ほど静謐かつ滑らかな納刀を追求する。日常の稽古でも最も反復回数が多いとされる核心動作である。
Q4 : 居合道の演武で最も一般的に用いられる開始および終了の礼法は何座礼か?
居合道では演武の開始と終了時に、正座姿勢から上体を倒す座礼が最も広く採用される。正座は刀を腰に帯びたままでも安定した姿勢を保てるうえ、鞘を跨がずに前礼が可能であるため礼法として合理的である。頭を下げる角度は約30度が目安とされ、背筋を伸ばし臀部を踵に乗せた姿勢を崩さないことが大切。審査員への敬意、場への敬虔、さらには自身の心を静める意味があり、礼法の正確さは技量と同等に評価されることが多い。
Q5 : 居合道で鞘から刀を抜いた直後に一拍子で斬撃を加える初動のことを何と呼ぶか?
抜き付けは刀の刃をわずかに鞘から滑らせた瞬間に敵の急所へ向けて切先を走らせる居合独特の動作で、ただ刀を鞘から出す抜刀とは異なり攻撃動作を兼ねている。腰の捻転や手の内、目付など各所が一致してこそ威力が生まれるため、審査では動きの速さよりも一拍子での合理性と姿勢の安定が重視される。多くの流派で基本中の基本とされ、上級者でも鍛錬を続ける要の技である。
Q6 : 全日本剣道連盟居合(制定居合)は全部で何本の形で構成されているか?
制定居合は1968年に当時の各流派の代表者が協議して制定した共通形で、1999年の改訂を経て現在は12本で構成されている。初学者が取り組みやすい基本技から高段者向けの複雑な技まで段階的に並び、各種大会や昇段審査ではこの12本の習熟度が重要な評価基準となる。数を正確に理解することは適切な稽古計画を立てる上でも不可欠であり、剣道連盟発行の教本でも12本が明記されている。
Q7 : 居合道の祖とされる流派「林崎夢想流」を開いた人物は誰か?
林崎甚助重信(はやしざき じんすけ しげのぶ)は16世紀後半に活躍した武芸者で、居合を体系化した最初期の人物として知られる。彼が編み出した『抜刀術』は後に夢想神伝流や無外流など多くの流派に影響を与え、江戸時代を通じて武士の必修科目とまで言われた。伝承によれば故郷の出羽国林崎明神への参籠中に着想を得たとされ、その功績から今日でも居合道の開祖として祭られている。
Q8 : 全日本剣道連盟居合の第一本目の形の名称は何か?
制定居合の第一本『前』は正座の姿勢から座った敵を想定し、正面にいる相手を抜刀から斬り下ろし、血振り、納刀までを一連で行う基本形である。名前のとおり真正面(前)との対峙を想定し、体幹の垂直保持、太刀筋の直線性、目付の安定など居合の基礎が凝縮されているため、昇段審査でも特に厳格に評価される。動き自体はシンプルだが、速さよりも呼吸の一致や緊張と弛緩のメリハリが問われ、上級者でも稽古の中心に据える形である。
Q9 : 真剣の代わりに亜鉛合金などで作られ、刃が付いていない稽古用の刀を一般に何と呼ぶか?
模擬刀は外観や重量バランスを真剣に近づけつつ切れ味を除いた安全性を確保した稽古刀で、居合道だけでなく舞台・撮影などにも用いられる。材質は亜鉛合金のほかジュラルミン、ステンレスなどがあり、鞘や柄巻、鍔も実刀と同様の仕様が選択できる。真剣より廉価で手入れも容易なため初心者が技術と礼法を学ぶ段階で多用されるが、重量や重心が若干異なるため、上達後は真剣稽古で感覚を調整することが推奨される。
Q10 : 無外流居合兵道を開いた人物は誰か?
無外流は江戸前期の剣客で禅僧でもあった辻月丹資茂(つじ げったん すけもち)が確立した流派で、剣より禅理を体現する『無外一以貫之』の精神を掲げる。抜き付けと斬り下ろしを一体化した直截な技法が特色で、後に居合や試合剣術として広く伝播した。辻月丹は諸国修行後、江戸幕府講武所でも教授したと伝わり、高弟によって西日本を中心に流派が発展。現在も各地の道場で無外流居合兵道として継承され、段位審査や全国大会が行われている。
まとめ
いかがでしたか? 今回は居合道クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は居合道クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。