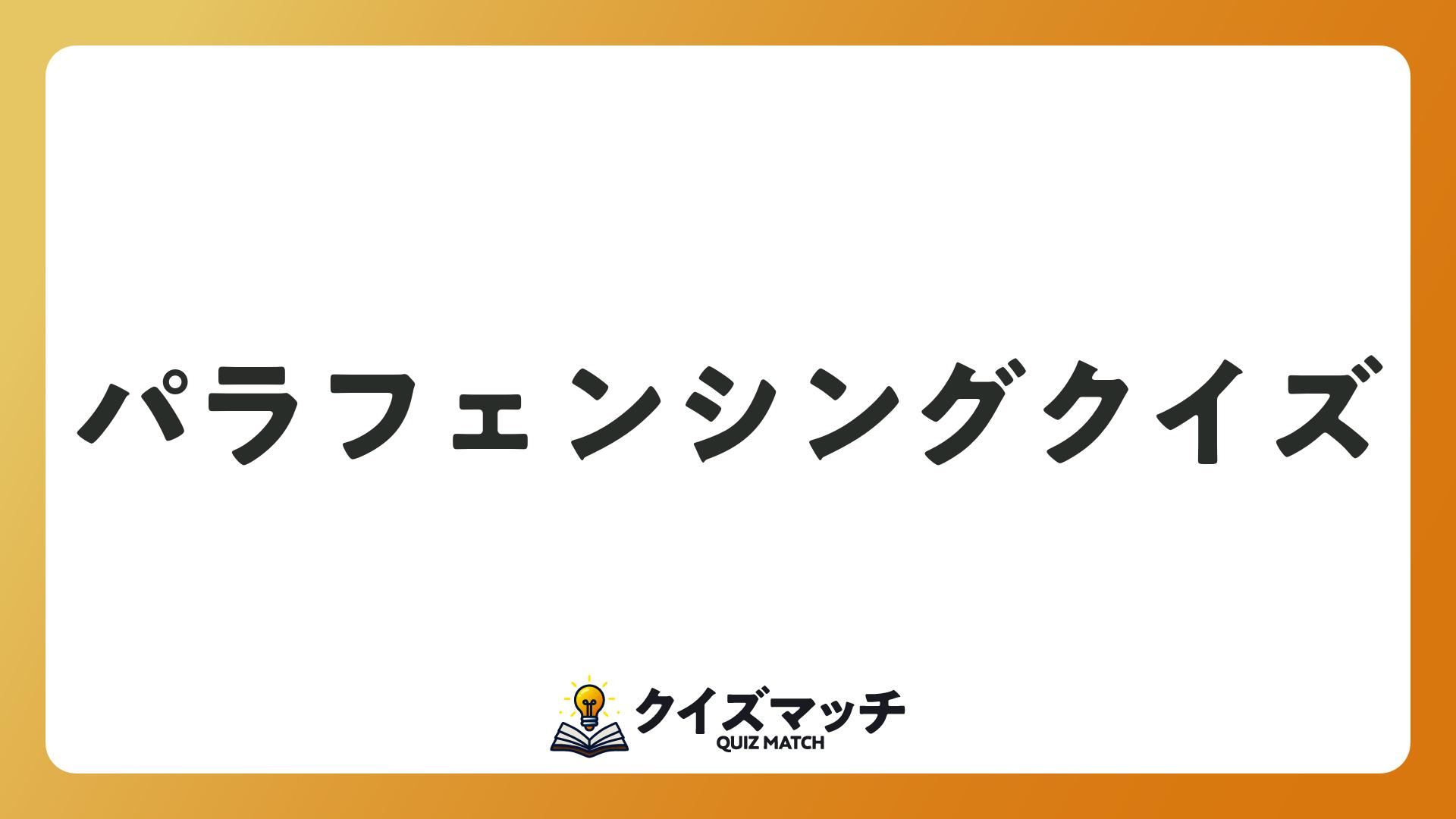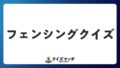パラリンピックでの車いすフェンシングの歴史は古く、1960年のローマ大会から正式競技として採用されてきました。車いすフェンシングは身体機能分類による公平性の確保や、オリンピックフェンシングとの共通ルールなど、障がい者スポーツの中でも特に制度化が進んでいる競技です。本記事では、そんな車いすフェンシングに関する10の興味深いクイズを紹介します。パラリンピックの黎明期から続く歴史や、ルール、競技運営の仕組みなど、車いすフェンシングの魅力を存分に味わえる内容となっています。フェンシングに詳しくない方でも楽しめるよう、わかりやすい解説とともにお届けしますので、ぜひお読みください。
Q1 : 車いすフェンシングで選手の車いすをピスト上に固定する標準的な方法はどれか?
座位の状態を安定させるため、車いすは床に置かれた頑丈な金属フレーム(フットプレート付きトラック)にクランプやボルトで固定される。これにより車輪が動かず、選手は上体のみで攻防する。同フレームには選手ごとのディスタンス調整機構も備わる。ベルトで審判台に縛る、スタッフが支える、吸盤で吸着といった方法は公式ルールでは認められていない。
Q2 : 車いすフェンシングとオリンピックフェンシングの共通点として正しいものはどれか?
車いすフェンシングは電気審判システムを用いる点でオリンピックフェンシングと共通している。フルーレとサーブルではランプで優先権が表示され、エペでは同時突きが点灯する。武器種はオリンピック同様3種で、攻撃権の概念も同一である。したがって、有効面や判定装置の構成は基本的に共通であり、システムを共有できる。脚部が常に有効面になる等の特殊性は存在しない。
Q3 : 車いすフェンシングのフルーレ種目で有効面とされる部位はどこか?
フルーレは“胴体を突く”競技という原則が車いすフェンシングでも守られ、両肩から股関節までを含む胴体部分のみが有効面である。腕、頭、脚に当たってもランプは点灯するが得点にはならない。視覚上の識別のため胴体部分には導電性ジャケット(ラメ)が装着され、電気的に有効面を区別する。攻撃権の優先判定もフルーレ独自のまま採用されており、範囲規定は国際ルール共通だ。
Q4 : 車いすフェンシングで試合開始前に行われる「ディスタンス設定」の正しい説明はどれか?
固定された車いす間の距離は、両選手が腕を最大限に伸ばした状態で互いの剣先が相手の有効面に“わずかに届く”長さに設定する。審判はまず剣をクロスし選手に腕を伸ばさせ、短い方の選手が届く位置を基準にフレームのクランプを締める。これにより両者に同等の間合いが保証される。遠過ぎれば試合が始まらず、近過ぎれば一瞬で突きが決まるため、この事前設定が競技の公平性を左右する。
Q5 : 国際パラリンピック委員会が認定する車いすフェンシングの国際統括団体はどれか?
IWAS(International Wheelchair & Amputee Sports Federation)は歴史的にストーク・マンデビル競技大会を引き継いだ団体で、車いすフェンシング部門を“IWAS Wheelchair Fencing”という名称で運営している。競技規則策定や世界ランキング管理、パラリンピックへの競技代表推薦なども同部門が担当する。IPCの競技コードでは各競技ごとに国際連盟を指定しており、車いすフェンシングの場合はIWAS Wheelchair Fencingが正式な統括団体となる。
Q6 : 2024年現在、パラリンピックで実施される車いすフェンシングの武器種数はいくつか?
パラリンピックではオリンピックと同じくフルーレ、エペ、サーブルの3種目が実施される。各武器は男女別の個人戦に加え、国・大会によってチーム種目も行われる。かつてはサーブルが実施されない時期もあったが、2004年アテネ大会以降は3種そろって行われており、2024年パリ大会でも同じ構成が予定されている。したがって現在パラリンピックで採用される武器種は3である。
Q7 : 車いすフェンシングが初めてパラリンピックの正式競技として採用された大会はどれか?
1960年のローマ大会は、ストーク・マンデビル競技大会が発展した第1回パラリンピックであり、アーチェリーや卓球と並んで車いすフェンシングが正式競技に加わった。以後、車いすフェンシングは連続して採用され、障がい者スポーツの中でも歴史が長い競技となっている。この事実は国際パラリンピック運動の黎明期から同競技が存在したことを示しており、東京1964大会が最初という誤解も多いが正しくはローマである。
Q8 : 車いすフェンシングの身体機能分類で「カテゴリーA」の選手の特徴として正しいものはどれか?
身体機能分類は選手の公平性を保つための基礎で、カテゴリーAは体幹と剣を持つ腕の機能が良好な選手が入る。これにより上体を左右や前後に大きく傾けて攻防を行える。一方、体幹保持が難しい者はカテゴリーB、四肢重度障がいはカテゴリーCと区分され、Cはパラリンピックでは実施されない。したがって、上体の可動域が広いことがAの特徴となる。
Q9 : 車いすフェンシングの個人予選プール戦で採用される試合形式として正しいものはどれか?
車いすフェンシングの個人戦は予選プールと決勝トーナメントで試合形式が異なる。予選では短時間で多くの対戦をこなすため、5本先取または3分1ピリオドで勝敗を決める方式が採られる。3分以内に5本入らなければ時間切れ時の優勢判定となる。決勝トーナメントに進むと15本/3分×3ピリオド方式となるため混同しやすいが、プール戦は5本制が正しい。
Q10 : 車いすフェンシングのチームリレー戦で勝利ラインとなる総得点(タッチ)はいくつか?
チームマッチは3人対3人のリレー形式で行われ、各選手が交代しながら5本刻みで累計得点を45本まで積み上げる。すなわち第1リレーは5本、第2は10本…と進み、最終第9リレーで45本に到達した側が勝利する。これはオリンピックフェンシングと同じ形式で、45という数字が公式ルールに明記されている。30や40では不十分、50では長すぎるため誤りとなる。
まとめ
いかがでしたか? 今回はパラフェンシングクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はパラフェンシングクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。