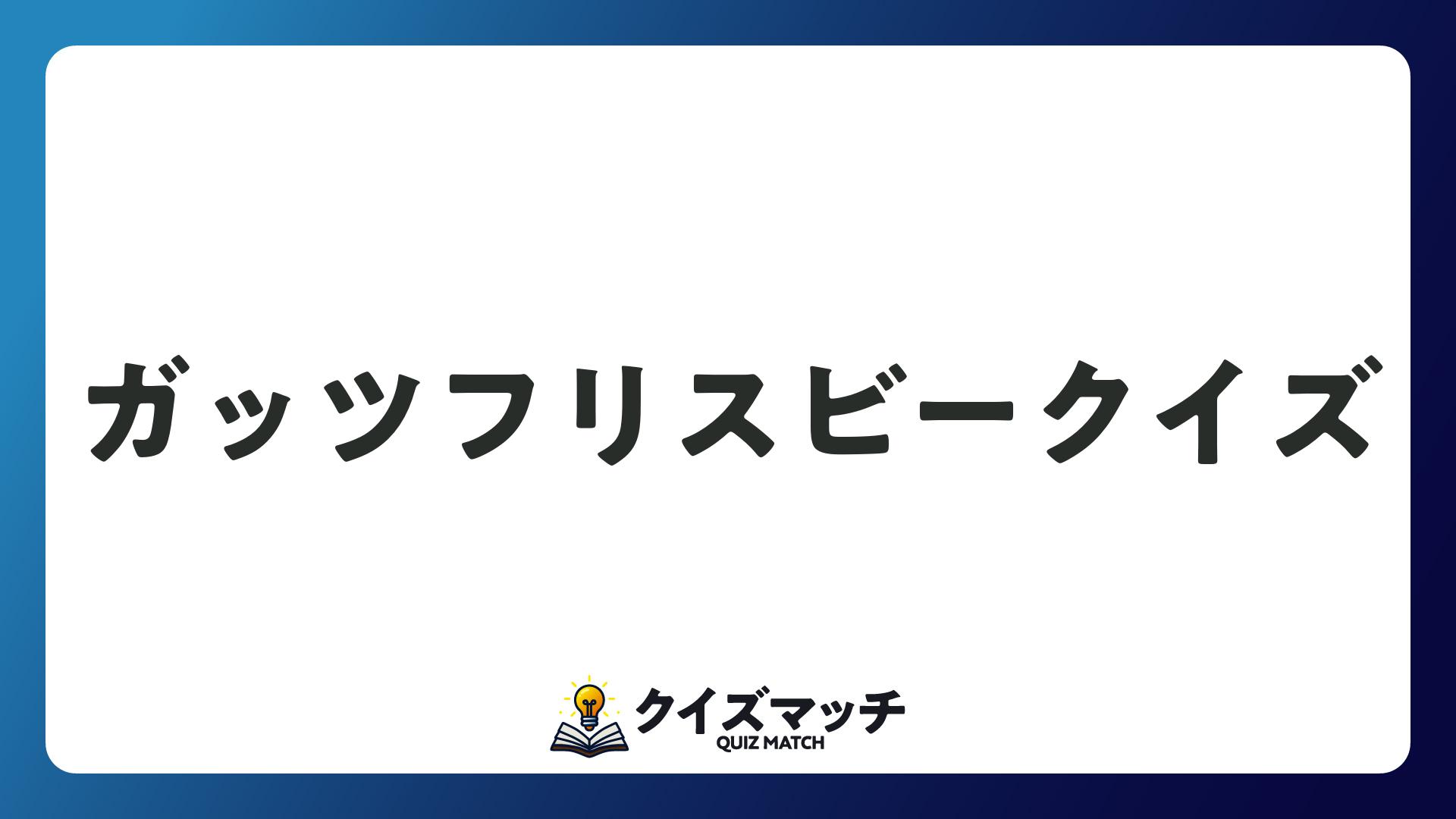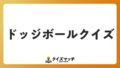フライングディスク競技の中でも高度な技術と迫力を誇るガッツフリスビー。両チームの攻防が激しく入り乱れる中で、選手は瞬時の判断と上質なキャッチテクニックを駆使する。国際競技規則で定められた14メートルの投擲距離、5人制の編成、21点先取2点差制など、ゲームルールとスピーディな攻防が生み出す魅力的な展開を、この10問のクイズを通じて紹介していきます。フリスビーの真髄を味わえる競技、ガッツフリスビーの奥深さに迫ります。
Q1 : 世界選手権で公式ディスクとして採用される「ライトフライトプロ110」の重量はおよそ何グラム? 110g 150g 175g 85g
ガッツ用ディスクとして最も普及しているのがWham-O社のライトフライトプロ110で、その名の通り重量はおよそ110グラムである。175グラムのアルティメットディスクより65グラム軽く、エッジが薄いため空気抵抗が少なく高速化が可能。その一方で風に流されやすく、スロー角度やリリースポイントを細かく調整しなければストライクゾーンを外しやすい。軽量化とスピード、扱いやすさのバランスを取った結果が110グラムという設定になっている。国内メーカーも同規格のディスクを製造しているが、重量は必ず110±2グラムの範囲に収めることが大会レギュレーションで求められる。
Q2 : スローが相手ラインまで届かず地面に触れた場合、ルール上どう扱われる? 攻撃側の得点 受け側の得点 やり直し(リスロー) 投擲失敗として得点なしで攻守交替
スローが相手ラインを越えずに地面に触れるとグラウンダーと宣告され、その投擲は無効となる。得点は入らず、ディスクは自動的に受け手側へ移り次のラリーが開始される。攻撃側は安全に強打を放つためにも最低14メートルを確実に越えるコントロールが求められ、失敗すると攻守が交替してリズムを手放すことになる。このルールが投擲精度の重要性と試合のテンポを同時に担保している。ゆえにトッププレーヤーは風向きや高度、ディスクの角度を常に意識し、確実に相手ラインを越える攻撃的かつ安定したスローを磨いている。
Q3 : ガッツフリスビーが米国ミシガン州で誕生したのはおおよそ何年代? 1950年代 1960年代 1970年代 1980年代
歴史資料によるとガッツは1958年、アメリカ合衆国ミシガン州イーグルハーバーでヘイリー家の兄弟が余興としてパイ皿を投げ合ったことから誕生した。それが1950年代末に近隣のビーチフェスティバルへ広まり、1960年代には国際トーナメントへ発展した。したがって競技が生まれた年代を問われた場合は1950年代と答えるのが正解である。このオリジンストーリーは世界大会の開会式でも語られる定番ネタであり、選手にとっても競技文化を共有する象徴的エピソードとなっている。
Q4 : ディスクが通過すべきスコアリングゾーンの横幅は最端の選手から外側にディスク直径何個分までと定義されている? 0.5個分 1個分 2個分 3個分
スコアリングゾーンは受け手が横一列に並んだラインを基準に、最外側のプレーヤーの両側へディスク直径1枚分(約27センチ)を加えた範囲と定義される。このゾーンを通過した場合にのみキャッチの成否が判定され、外れたスローは無効となる。1枚という設定は攻撃側に狙い所の余白を与えつつ、防御側の壁を大きく外す安全策を抑制するための絶妙な幅として国際大会でも長年踏襲されている。ゾーン幅の厳密化により審判は投擲ライン延長線上に立ち、一瞬でインかアウトかを判定できるよう研修を受ける体制も整備されている。
Q5 : 受け手がディスクを正規キャッチした後、次のスローを行うのはどのチーム? 元の攻撃側チーム キャッチを成功させたチーム 点差で負けているチーム じゃんけんで決めたチーム
ガッツではキャッチが成功した時点で守備と攻撃が即座に交替するため、ディスクを手にしたチームが次のスローを行う。これによってラリーの主導権をキャッチ技術で奪い合うダイナミックな展開が生まれる。逆にキャッチミスで得点が入った場合は得点した側が続投し、勢いを維持できる。こうしたルールがガッツのスピード感と戦略性の両立を支えている。攻守が目まぐるしく入れ替わることで試合の流れが遮断されず、観客もリズムを保って観戦できる点が他のディスク競技と異なる魅力と評価されている。
Q6 : ガッツフリスビーで、両チームのライン間の正式な距離は何メートルと規定されている? 10m 14m 20m 30m
国際競技規則(WFDF Guts Official Rules)では、エンドラインと呼ばれる各チームが一列に並ぶラインの間隔を14メートルと定めている。14メートルは投擲の威力と受け手の安全とのバランスを取るために試行錯誤で決まった距離で、長すぎれば攻撃側の得点機会が激減し、短すぎれば守備側が容易にキャッチでき試合が単調になる。現在では世界大会から学校体育の授業までこの距離が共通基準として使われている。競技者は練習中でも14メートルを測って感覚を養うことが推奨されており、初心者向けクリニックでも最初にメジャーで距離を設定するのが通例である。
Q7 : ガッツフリスビーで公式ルール上、1チームがフィールドに立てる最大人数は? 5人 7人 4人 6人
ガッツは1対1から5対5までプレーできるが、公式大会では最大5人が横一線に並ぶ形式が採用される。5人いればプレーヤー間の隙間がほどよく狭くなり、正確なコースを突かなければディスクが通過しないため攻撃に高度な技術が要求される。一方で極端に狭すぎないため受け手もダイビングキャッチやポジションチェンジで対応でき、スリリングな攻防が生まれる。6人以上になるとゾーン幅が消滅し競技性が損なわれるため認められていない。したがってチーム編成では5人を軸に交替要員を含むロースターを組むのが世界標準とされている。
Q8 : ガッツフリスビーを世界的に統括し、ルール制定や世界選手権を主催している団体はどれ? ITF FIFA WFDF IAAF
ガッツを含むフライングディスク競技全般を統括するのはWFDF(World Flying Disc Federation)であり、ルール策定、審判養成、世界ランキング管理、国際大会の主催を行っている。WFDFはIOC公認団体でもあり、ワールドゲームズの競技採用に向け各国連盟と連携して普及活動を行う。ITFはテニス、FIFAはサッカー、IAAF(現World Athletics)は陸上競技の国際連盟で、ガッツの競技運営には関与していない点が区別のポイント。近年はWFDFが作成したルールブックの日本語版も公開され、国内大会でも原文と同じ番号体系でルールが引用されるよう統一が進んでいる。
Q9 : ガッツで受け手が行うキャッチの条件として正しいものはどれ? 両手で同時につかむ 足で押さえてもよい 片手でつかみ身体で挟んでもよい 片手のみで身体を使わずにつかむ
ガッツの受け手は、片手のみを使いディスクを体やもう一方の手で挟まずにクリーンキャッチすることが義務づけられている。ディスクがいったん胸や腕に当たってから握り直したり、両手で同時につかんだりするとフォールトとなりスロー側に得点が入る。高速回転するディスクを片手で確実につかむには反射神経だけでなくエッジの柔らかい部分を瞬時に見極める経験が必要で、ここにガッツ特有のスリルと職人芸がある。一流選手は勢いを弱めるクッションキャッチやディスクを滑らせて回転を殺すテクニックを駆使しながらも片手規定を完遂するため、観客からはしばしば大きな歓声が上がる。
Q10 : 国際ルールで、ゲームは先に何点を取ったチームが2点差をつけて勝利となる? 11点 15点 21点 25点
国際ルールでは試合は21点先取2点差制で行われる。21点に到達しても1点差の場合はゲームが続き、22-20や24-22のように2点差になった時点で勝者が決定する。これにより終盤の緊張感が増し、リードしていても油断できない構造になっている。得点は一度に1点ずつしか入らないため最大で理論上無限にデュースが続く可能性もあり、集中力と持久力が試される。このため試合の山場は20点前後で訪れることが多く、観戦者は一投ごとに歓声とため息を繰り返す極めて劇的な終盤となる。
まとめ
いかがでしたか? 今回はガッツフリスビークイズをお送りしました。
今回はガッツフリスビークイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!