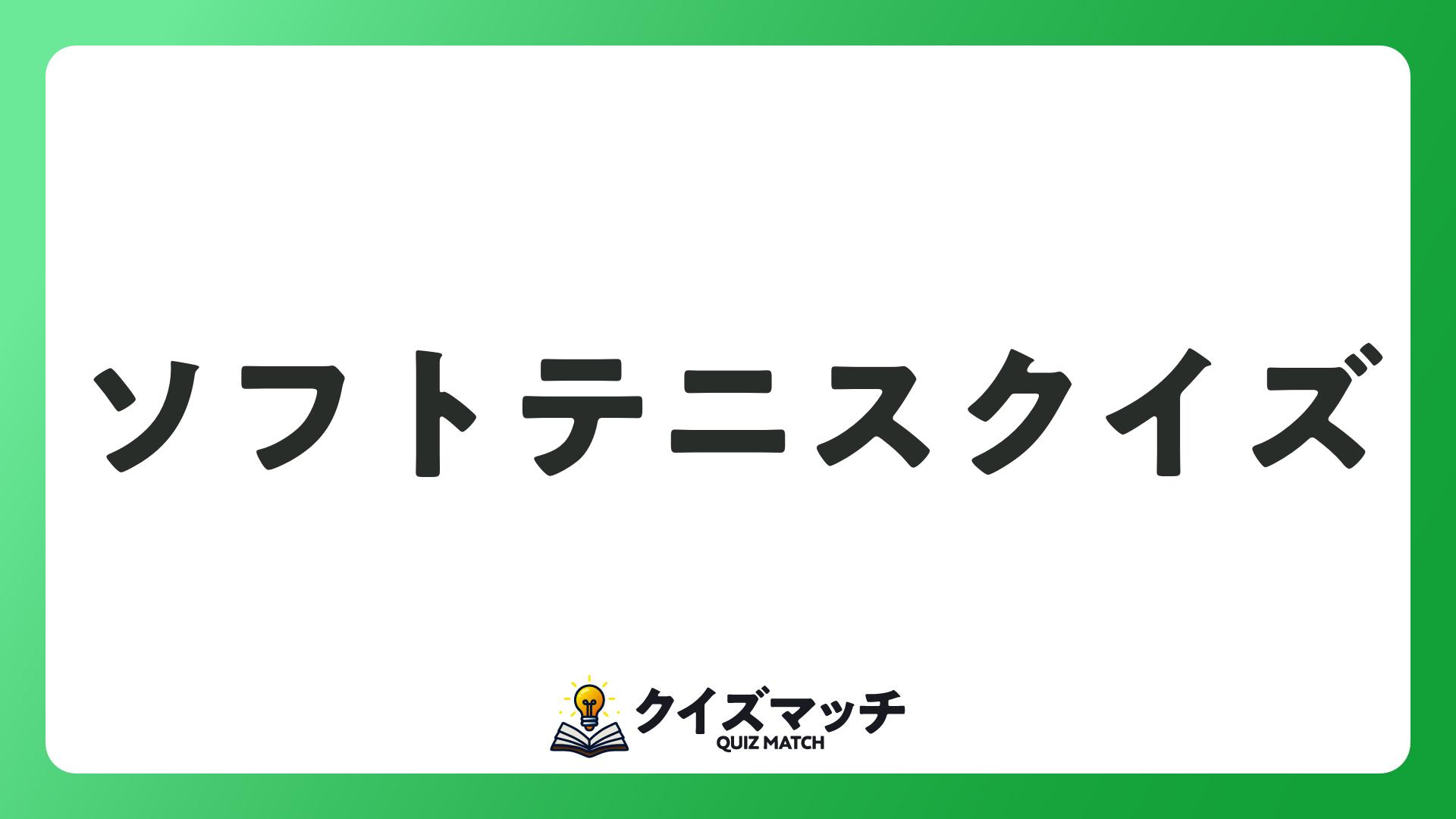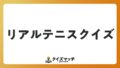ソフトテニスはコートサイズや用具、ルールなど、硬式テニスとは大きく異なる特徴を持つスポーツです。この記事では、そんなソフトテニスに関する10の基本的な知識を問うクイズをお届けします。国際大会の公認球の色や得点計算、ダブルスの戦術、用具規格など、ソフトテニスのより深い理解につながる内容を厳選しました。ソフトテニスファンはもちろん、これから始める方にも、このクイズを通じてスポーツの魅力を感じていただければ幸いです。
Q1 : 世界ソフトテニス選手権(ワールドチャンピオンシップ)は原則として何年ごとに開催されるか。
世界ソフトテニス選手権は1975年の第1回大会以来、原則4年ごとに開催されている。4年周期は各国連盟が代表強化計画や国内選考を組み立てやすい期間とされ、ハイレベルな国際舞台を維持する上で合理的と評価されている。大会開催地はアジアを中心にヨーロッパや南米にも拡大しており、4年ごとのサイクルがルール改正や用具規格の見直しの節目としても機能している。オリンピック競技でない種目の中では稀有な安定運営が続いている。
Q2 : サービスがネットに触れてインされた場合に宣告される『レット』の回数制限について正しいものはどれか。
ソフトテニスのサービスがネットに触れて相手サービスコート内に落ちた場合はレットとなり、サーバーは無罰で打ち直しができる。ルール上このレットサーブには回数制限がなく、1ポイント中に何度続いても許容される。連続してレットが起こると集中力の維持やタイミングの調整が難しくなるため、ベテランはフォーム確認や呼吸法でリズムを崩さない工夫を行う。制限があるという誤解は硬式テニスと混同したものに過ぎない。
Q3 : 日本女子が金メダルを獲得した2018年アジア競技大会ソフトテニス競技の開催地はどこか。
2018年アジア競技大会はインドネシアのジャカルタとパレンバンを共同開催都市として実施され、ソフトテニスはジャカルタのテニスセンターで行われた。日本女子代表は決勝で韓国を破り団体金メダルを獲得し、高温多湿の過酷な環境と短い準備期間を克服した粘り強い戦いぶりが注目された。北京、仁川、広州はいずれも他年の多種目大会開催地で、本問題の年には該当しない。
Q4 : 日本最高峰の大会『天皇賜杯・皇后賜杯全日本選手権』で争われる種目はどれか。
天皇賜杯・皇后賜杯全日本ソフトテニス選手権は毎年秋に開催され、男子ダブルスと女子ダブルスの2部門のみで日本一を決定する。シングルスや団体戦のタイトルは別大会で争われるため、この大会ではペアの連係や陣形の完成度が勝敗を左右する。昭和初期から続く長い歴史と皇室から賜杯が授与される格式の高さゆえに、多くのトップ選手が年間最大の目標として位置付けている権威ある大会である。
Q5 : 日本ソフトテニス連盟の規定で、公認球の重量として正しい範囲はどれか。
公認ソフトテニスボールの重量は30〜31グラムと定められており、この軽さがゴム製ボール特有の柔らかな打感とコントロール性を支えている。28〜29グラムでは空気抵抗や風の影響を受けやすく規定のバウンド性能を満たしにくい。32グラム以上では反発が強すぎラケットや身体への負担が増えるため、国際基準でも同一範囲が採用されている。統一された用具規格が世界中の大会で公平性を保つ基盤となっている。
Q6 : ソフトテニスコート端に立つネットポストの高さとして正しい値はどれか。
ネットポストはダブルスサイドライン外側に設置され、その上端の高さは地面から120センチ(1.20メートル)と規定されている。中央部はストラップで105センチに下がり、端部を120センチに保つことで適切なテンションと弓状のネット形状が確保される。110センチや115センチでは中心部が低くなりすぎ、125センチでは高すぎてボールが当たりやすくなるためルールに抵触する。ポストの高さは見落とされがちだが、競技の公平性を担保する重要な数値である。
Q7 : 公式試合開始前にエンドとサービス権を決定する方法として規則で採用されているのはどれか。
ソフトテニスの競技規則では、試合開始前にラケットを回転させて表裏を当てるラケットトスでエンドおよびサービスの選択権を決める。勝者はサーブかリターン、または好きなエンドを選択し、敗者が残りを選ぶことで公正さを担保する。じゃんけんやくじ引きは練習試合で行われることがあるが公式大会では認められていない。ラリーを行って決める方式もローカルルールに過ぎず、国際大会では適用されない。
Q8 : ソフトテニス用ストリングで一般的に最も多く使用される太さ(ゲージ)として適切なのはどれか。
ソフトテニス用ガットは打球時の食いつきと耐久性のバランスをとるため、1.25〜1.30ミリ前後の細さが標準的とされる。細めのゲージはボールを掴む感覚が強くスピン性能に優れる一方で、太くなるにつれ反発は増えるがコントロール性と回転量が落ちる。メーカー各社は1.25・1.27・1.30ミリを主力に製品展開しており、トップ選手からジュニアまで広く採用されている。1.45ミリ以上は高い耐久性と引き換えに操作性が低下するため選択肢としては少数派である。
Q9 : 現在、国際ソフトテニス連盟(ISTF)の主催大会で主に使用される公認球の色はどれか。
ソフトテニスの公式球は以前はアイボリー色のみだったが、視認性向上のため2000年代以降に黄色が追加承認された。国際大会では屋内外問わず黄色の方が選手と観客から見やすいという理由で標準として用いられており、現在は白球が選ばれるケースはほとんどない。規則上は白と黄色の両方が認可されているが、問題ではより一般的な使用状況を問うている。
Q10 : ダブルスで広く用いられる、前衛がネット近く、後衛がベースライン付近という配置の陣形は何と呼ばれるか。
雁行陣は後衛がベースライン付近でストロークを担当し、前衛がネット際でボレーやスマッシュを狙う伝統的な日本発祥のダブルス陣形で、左右から見た配置が雁の隊列に似ていることから命名された。並行陣は二人とも前に出る速攻型、スタガードは前後が頻繁に入れ替わる可変型、チャージは短時間でネットに詰めてプレッシャーをかける戦法と、それぞれ役割が異なる。
まとめ
いかがでしたか? 今回はソフトテニスクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はソフトテニスクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。