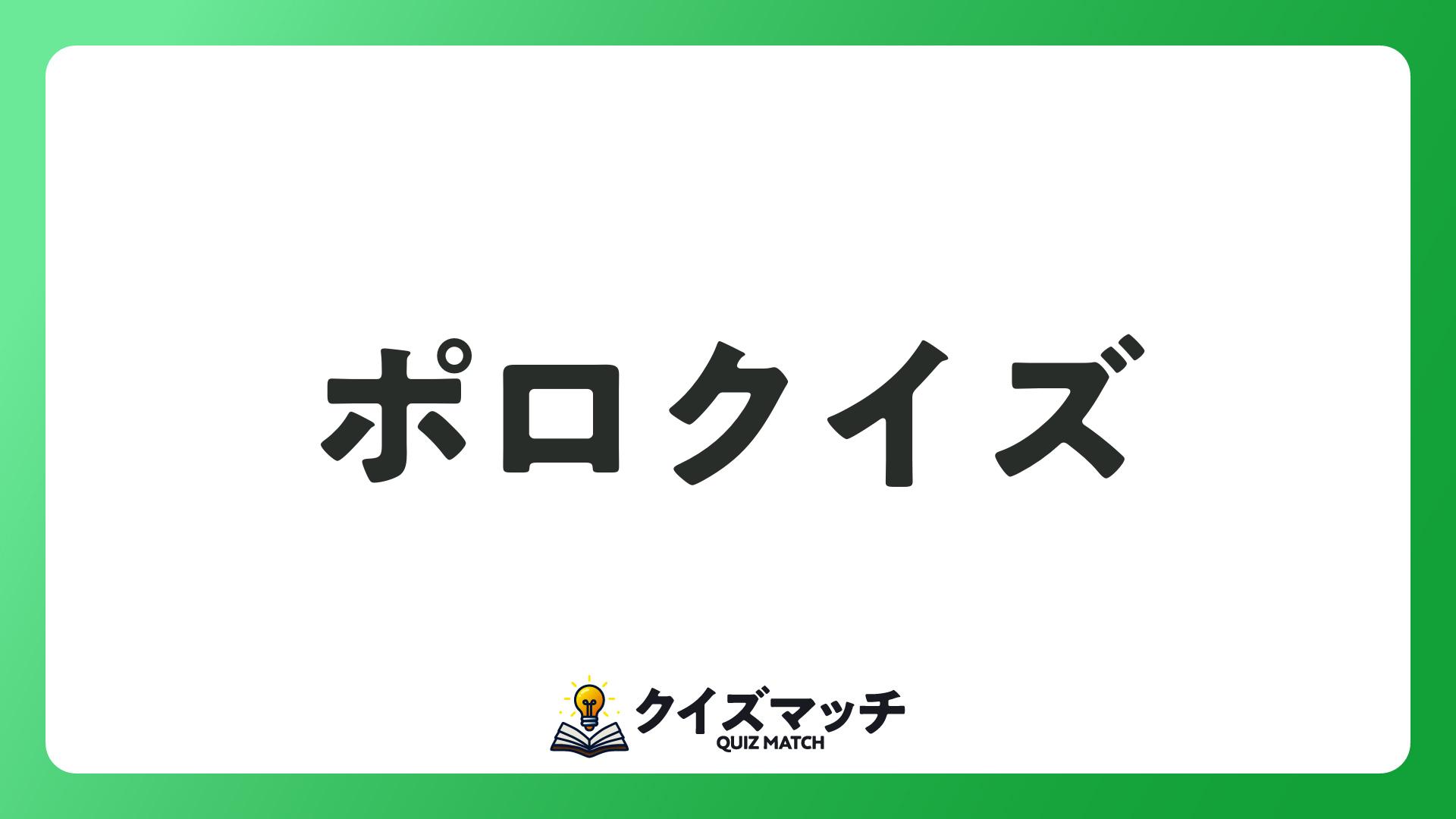近年、日本人の間でもブームになっているポロクイズ。南米の国家事情やノーベル賞経済学賞の歴史、輪島塗やフェルマーの最終定理など、意外と知らないことが多い地理・科学・文化の雑学問題が満載。日常の何気ない会話からテレビ番組の出題まで、状況に応じて巧みに使いこなせるこのジャンルの知識は、教養と機転を備えた教養人を目指す上で欠かせません。是非この10問をチャレンジして、ポロクイズ通への一歩を踏み出しましょう。
Q1 : ノーベル経済学賞(正式名称は経済学賞)を設立した機関はどれか
ノーベル賞のうち経済学賞だけはアルフレッド・ノーベルの遺言に含まれておらず、1968年にスウェーデン国立銀行が創立300周年を記念して基金を拠出し、王立科学アカデミーの管理下で授与が始まった。平和賞がノルウェー、医学・生理学賞がカロリンスカ研究所の推薦で行われるのと混同されやすい。名称も「アルフレッド・ノーベル記念経済学スウェーデン国立銀行賞」と独特で、授与主体の違いが試験で問われることがある。
Q2 : 2011年に世界自然遺産に登録された小笠原諸島は行政区分上どの都道府県に属するか
小笠原諸島は東京から南へ約1000kmの太平洋上に点在する島嶼群で、行政上は東京都小笠原村に属する。火山活動で形成された島々には独自の生態系が残り、固有種の多様性が評価されて2011年にユネスコ世界自然遺産に登録された。沖縄や鹿児島と混同されがちだが、江戸幕府が領有を宣言し戦後米国統治を経て1968年に返還された経緯から東京都が管轄している。船でしか行けない離島ながら都道府県別統計にも東京都として計上される。
Q3 : 宇宙マイクロ波背景放射を偶然観測しビッグバン理論の有力証拠を得たペンジアスとウィルソンが使用していたホーンアンテナを所有していたのはどの研究所か
1964年、アメリカ・ニュージャージー州ホルムデルにあるベル研究所のホーンアンテナを用いて通信衛星の雑音研究を行っていたアーノ・ペンジアスとロバート・ウィルソンは、方向を変えても消えない3K程度の微弱マイクロ波を検出した。解析の結果、それは宇宙誕生直後の残光とされる宇宙マイクロ波背景放射であると判明し、ビッグバン理論の決定的証拠となった。IBMやロッキードではなく通信技術の最先端を担ったベル研究所だからこその発見であった。
Q4 : アメリカ50州のうち唯一州議会が一院制なのはどの州か
合衆国各州は州憲法に基づく立法機関を持つが、1937年の憲法改正以降ネブラスカ州は上院・下院を統合した一院制を採用している。かつては他州でも一院制改革が議論されたが実現せず、現在も49州は上院(Senate)と下院(House)から構成される二院制である。ネブラスカ州議会は無党派選挙や非公開の議長選挙など独自色が強く、コスト削減と法案審議の効率化を目的としたモデルとして政治学の教材で取り上げられる。
Q5 : 1994年に完全な証明が発表され長年の数学的未解決問題に終止符を打った「フェルマーの最終定理」を証明した人物は誰か
フェルマーの最終定理は17世紀の数学者ピエール・ド・フェルマーが命題として残したもので、nが3以上の整数のときx^n + y^n = z^n を満たす自然数解は存在しないという内容である。1994年、英国の数学者アンドリュー・ワイルズがモジュラー形式と楕円曲線の谷山‐志村予想を用いる斬新な手法で証明に成功し、翌年修正論文を発表して完全に確定した。共同研究者リチャード・テイラーの助力もあったが、主要な証明者はワイルズであり、彼は2016年にアーベル賞を受賞した。
Q6 : 本部がスイス・ジュネーブに置かれている国連専門機関はどれか
世界保健機関(WHO)は1948年設立の国連専門機関で、感染症対策や医薬品規格策定など国際保健の中心機関として活動している。本部はスイス西部の都市ジュネーブにあり、多数の国際機関が集まるジュネーブ国際機関地区の象徴的存在である。IMFはワシントンD.C.、FAOはローマ、UNESCOはパリに本部があり混同しやすい。所在地はニュース記事や国家試験で頻出のポイントとなるため押さえておきたい。
Q7 : 通算在任日数が最長となった日本の内閣総理大臣は誰か
日本の首相在任日数ランキングは2020年9月の辞任時点で安倍晋三が通算3188日(第一次政権を含む)で歴代最長となっている。これまでの首位は1964〜72年に政権を担った佐藤栄作(2798日)、続いて吉田茂(2616日)であったが、安倍政権の長期化により記録が更新された。初代首相の伊藤博文は通算2720日で4位。政治史では頻出の数字で、憲政史上の流れを把握するうえで重要な基礎知識となる。
Q8 : 憲法上の首都はスクレだが行政・立法機能がラパスに置かれている南米の国はどこか
ボリビアは1825年の独立当初からスクレを首都として定めているが、標高が高いスクレでは統治が難しいとの事情から、19世紀末に実務機関がより人口の多いラパスへ移された。以来、憲法上の首都と事実上の首都が分かれる「二都制」となり、国会や大統領府はラパスに、最高裁判所のみがスクレに残るという独特の体制が続く。この例は南米では極めて珍しく、地理や政治の授業で頻繁に取り上げられる。
Q9 : 元素周期表で原子番号79にあたる元素はどれか
原子番号は陽子数を表す。79番の元素は貴金属の代表である金で、その化学記号はAu、ラテン語のAurumに由来する。銀は47番、銅は29番、プラチナは78番といずれも金と同じく遷移金属だが番号が異なる。金は展延性が高く酸化されにくい性質から、古代文明以来通貨や装飾品に幅広く用いられ、現代の電子部品や医療機器にも欠かせない。周期表の暗記では区切りの良い番号として頻出する。
Q10 : 伝統工芸品「輪島塗」の主な産地として知られる都道府県はどこか
輪島塗は国の重要無形文化財に指定されている漆器で、能登半島北端に位置する石川県輪島市で発展した。木地に布着せや下地塗りを何度も重ね、漆と輪島地の粉を用いて強靱な塗膜を形成するのが特徴で、過酷な使用にも耐える実用性と華やかな蒔絵装飾を両立させている。同じ北陸地方には福井の越前漆器や富山の庄川挽物があるが、製法や地理が異なる。地理と文化財の双方で頻出する知識である。
まとめ
いかがでしたか? 今回はポロクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はポロクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。