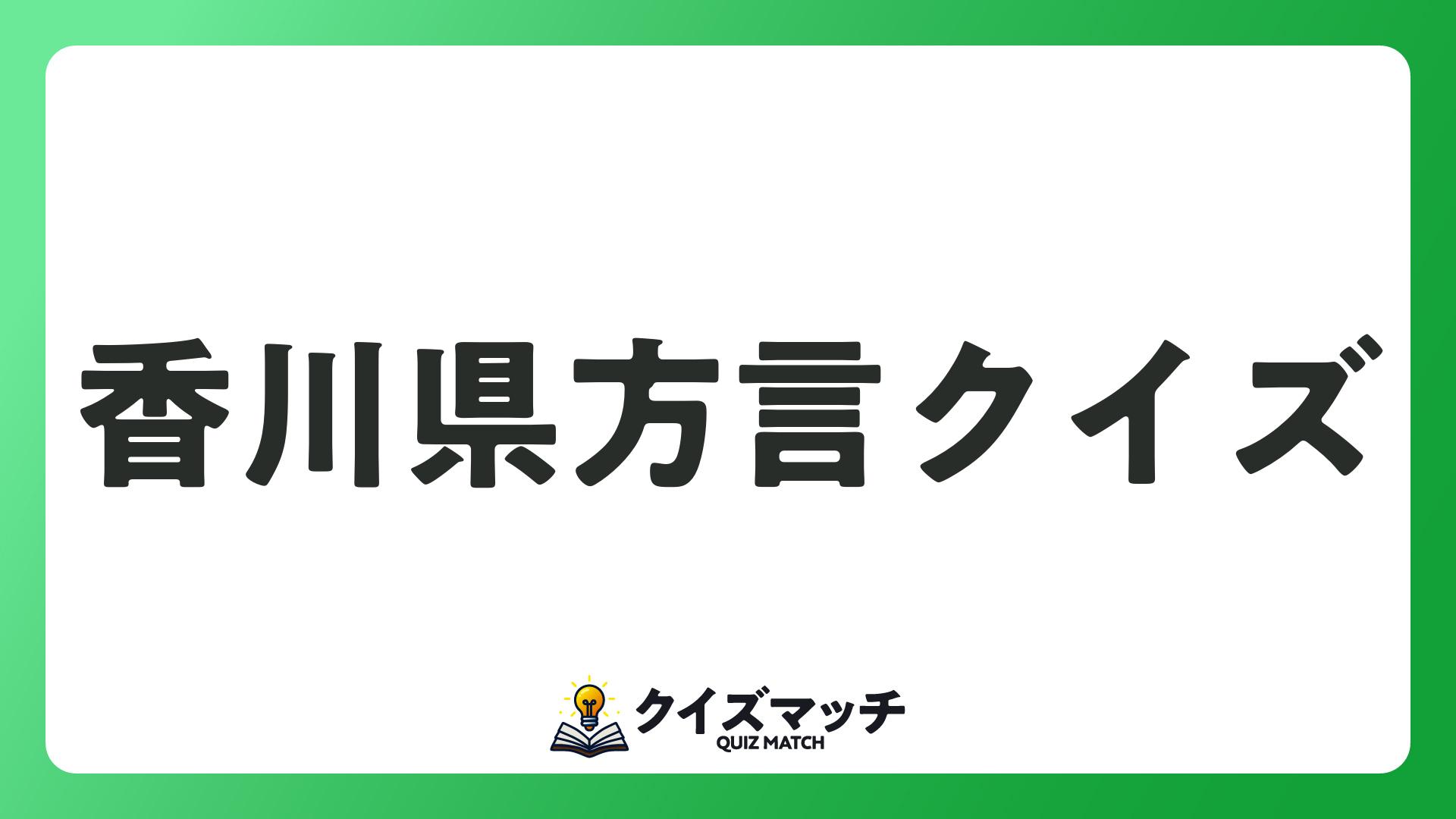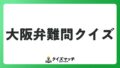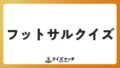香川の方言を知って、地域の魅力を発見しましょう。
この記事では、香川弁のクイズを通して、その特徴と使い方を楽しく学べます。方言には地域性や歴史が刻まれ、日本の言語文化の多様性を示しています。「おいでる」「ようけ」「じょんならん」など、香川ならではの表現に注目。標準語との違いを確認しながら、香川の人々の生活に寄り添う言葉の使い方を理解していきます。方言を知ることで、地域の個性や人々の感性に触れることができるはずです。この機会に、香川の魅力的な方言を探検してみましょう。
Q1 : 香川の嘆きの言葉「じょんならんわ」の「じょんならん」とは何を意味する?
「じょんならん」は「どうにもならん」が変化したとされ、状況や物事が手に負えず打つ手がない様子を示す。例「この汚れはじょんならん」「あの機械はじょんならんで修理も無理」。諦めや嘆きを含む否定的表現で、ポジティブな「元気がある」「儲かる」とは真逆。香川では日常的に聞くが、意味を取り違えると励ましのつもりが失礼になる場合もあるため注意が必要である。
Q2 : 方言動詞「もんてくる」は標準語で何と言う動き?
「もんてくる」は「戻って」を表す「もんて」に方向を示す「くる」が付いた香川の複合動詞で、標準語の「戻ってくる」に相当する。例「学校からもんてきた」「傘を取りにもんてくる」。物や人が元の場所に帰る動きを示し、“捨ててくる”のような逆方向や動作停止の意味は含まれない。四国の方言連続の一環で徳島・高知にも類似形があり、地域を跨いで理解される便利な語である。
Q3 : うどんが「しわい」と言われたとき、どんな状態と考えられる?
「しわい」は語源が「しぶい」「しわくて硬い」などとされ、香川では主に食べ物や物質が硬く噛み切りにくい状態を形容する。「この肉しわいなあ」「クッキーがしわいけん気をつけて」のように歯応えが強すぎて食べにくいニュアンスを帯びる。疲れるの意味で使う地域もあるが、香川では硬さが中心。軟らかい・甘い・小さいといった性質を示す語ではないため注意が必要である。
Q4 : 香川で「さいさい来る客やなあ」と言うときの「さいさい」の意味は?
「さいさい」は漢字で「再々」と書き、標準語の「たびたび」「しばしば」に当たる回数副詞。香川では来訪や故障など頻発する事柄を示す際に「さいさい壊れる」「さいさい電話する」などと用いる。速度を示す「ゆっくり」や確実性の「しっかり」とは異なり、同じ動作が短い間隔で繰り返されることに焦点がある。標準語では古風な語感のため方言として耳に残りやすい点が特徴である。
Q5 : 香川弁で「おとろしい旨いうどんやな」と言われたときの「おとろしい」は?
「おとろしい」は本来の「恐ろしい」から意味が転じ、香川では程度副詞的に「すごく」「非常に」を示す。良い事柄にも悪い事柄にも使え、「おとろしい速さ」「おとろしい量」のようにインパクトの強さを表す。恐怖を感じる標準語のニュアンスは薄く、単に程度の高さを強く示す点がポイント。恐ろしいと混同すると文脈が狂いやすいため、方言特有のポジティブ転化を理解しておくと会話が円滑になる。
Q6 : 香川県で量を表す「ようけ」は標準語でどの意味と等しい?
「ようけ」は「余計」が転訛した語で、数量や量が多いことを示す。「ようけ取れた」「人がようけおる」のように日常会話で頻出し、標準語の「たくさん」「多くの」と同義。比較の強調「ようけに~」で「より一層」の意味も持つ。対義は「ちょっと」「少し」で、速度や重さとは無関係。読みだけ追うと「余計=不要」と誤解されやすいが、香川ではポジティブに「豊富」を表す点が大きな特徴である。
Q7 : 香川の方言「おいでる」は標準語でどんな意味?
「おいでる」は動詞「おる(居る)」に進行や状態を示す接尾語「でる」が付いた形で、香川では単に「存在している」ことを指す。標準語の「いる」と同義で、「猫がおいでる」「まだ皆おいでる?」のように使われ、人や物の所在を表すだけで来訪や起立の意味は含まれない。語感から「来ている」と誤解されやすいが方言では誤用となる。年配だけでなく若者も用い、徳島など周辺県でも通じる広がりを持つ点も覚えておきたい。
Q8 : 香川でよく聞く「おえん」は、どういう意味の否定表現?
「おえん」は「終えん(終えられない)」が縮まったとも言われ、香川では「できない」「無理だ」「だめだ」という可能の否定を示す言葉として定着している。例「今日は忙しゅうて手伝いがおえん」「そんな重い荷物、一人じゃおえんで」。能力不足や状況的困難を示し、疲労を訴える語ではない。中国・四国地方で広く分布するが、香川では日常頻度が高いので意味を取り違えないことが重要である。
Q9 : 「まけまけちゃ詰めて乗ってや」と言われたときの「まけまけちゃ」の意味は?
「まけまけちゃ」は狭い空間や容器に物や人をぎゅうぎゅう押し込む様子を表す語で、香川では乗り物や弁当箱などに対して使うことが多い。「電車がまけまけちゃで動けん」「ご飯をまけまけちゃ入れて」など窮屈さを強調する。語源は「巻け巻け」など諸説あるが、いずれにしても空間的余裕の無さを示す。急ぐ、静かにするといった意味は含まれず、ゆったりとは正反対のニュアンスとなる点が特徴である。
Q10 : 香川県で相手を評して「へらこい奴やな」と言うと、どんな意味?
「へらこい」は香川を含む西日本に分布する形容詞で、「こすい」「ずる賢い」「抜け目ない」といった否定的評価を表す。笑顔の「へらへら」とは無関係で、人を出し抜こうとする狡猾さを非難する際に使われる。例「へらこい真似するな」「あいつはへらこいけん信用できん」。大人しいや優しいなど肯定的意味合いはなく、また単に粗暴・ひどいというより策略的で計算高い状態を指す点が語感のポイントである。
まとめ
いかがでしたか? 今回は香川県方言クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は香川県方言クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。