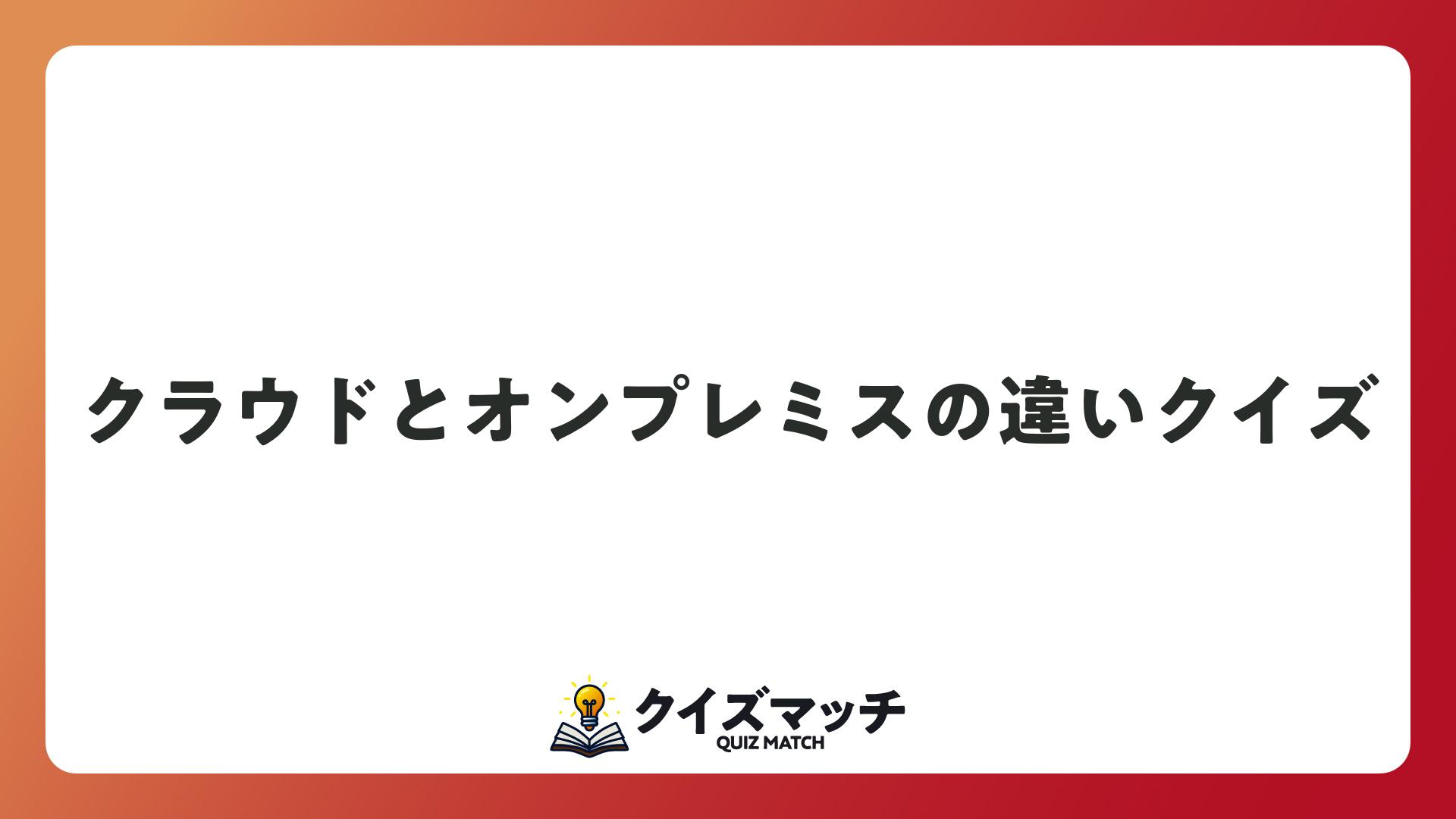クラウドサービスの活用が広がる中、オンプレミスとクラウドの違いを理解することが重要になっています。本記事では、クラウドとオンプレミスの主な相違点について、10問のクイズを通じて解説します。初期投資、スケーリング、可用性SLA、データ管理、セキュリティパッチ適用、災害復旧、リードタイム、レイテンシ、ハードウェアカスタマイズ、課金モデルなど、クラウドとオンプレミスの特性をクイズ形式で比較していきます。クラウドとオンプレミスの使い分けを検討する上で、この記事が参考になれば幸いです。
Q1 : GPUを独自ファームウェアで書き換えて使うなど、特殊ハードウェアをフルカスタマイズしたい場合に適しやすい選択肢はどれか?
オンプレミスでは筐体やボードを完全に自己管理できるため、PCIeカードの入れ替えやファームウェアのカスタムビルド、独自ドライバの適用などハードウェア層まで自由度が高い。クラウドではGPUインスタンスが用意されていても、ベンダが許可したファームウェアやドライババージョンのみ利用可能で、低レイヤーへのアクセス権はセキュリティ上制限されている。研究開発でニッチなASICを使う場合やリアルタイム処理でカーネルを改造する場合にはオンプレミスが推奨されることが多い。
Q2 : クラウドとオンプレミスにおける課金モデルの違いとして最も適切なのはどれか?
パブリッククラウドではCPU時間、転送量、ストレージ使用ギガバイトなど利用指標があらかじめ設定されており、実使用量に応じて月末に課金される従量課金もしくはサブスクリプションモデルが中心である。オンプレミスは機器を購入・リースした時点で支払を確定させる買い切り(CAPEX)が一般的で、稼働率が低くても費用は変わらない。この差によりクラウドは需要変動に合わせてコストを追随させる運用が容易であり、オンプレは固定費として残るため長期利用と高い稼働率でコストメリットを発揮する。
Q3 : クラウドでは初期投資が少ないと言われるが、その主な理由として正しいものはどれか?
クラウドサービスではサーバやネットワーク機器をサービス事業者が所有しており、利用者は必要な期間・量だけをサービスとして借りる形になる。そのため自社でサーバラックやUPSを購入するような多額の資本的支出(CAPEX)が発生せず、月次や秒単位などの利用量に応じた運用費(OPEX)として処理できる。オンプレミスでは導入時に購入費用が発生し減価償却を行うが、クラウドではこれが不要なため初期投資が少なく済むという特徴が生まれる。
Q4 : オンプレミスと比較したクラウドの水平スケーリングに関する説明として最も適切なのはどれか?
クラウド基盤は仮想化と自動プロビジョニングが標準化されており、管理者はWebポータルやCLI、REST APIなどから起動台数やスペックを指定するだけでリソースを数分、場合によっては秒単位で追加可能である。オンプレミス環境では新サーバの選定、発注、配送、ラック設置、配線、OSインストールなど複数工程が必要となり数週間から数カ月を要する場合もある。したがって水平スケーリングの俊敏性はクラウドが圧倒的に高いと言える。
Q5 : 可用性SLAの提供主体に関する次の記述のうち、クラウドとオンプレミスの比較として正しいものはどれか?
AWS、Azure、Google Cloudなどのパブリッククラウドでは、EC2やStorageなど各サービスごとに月間稼働率を示したSLA(Service Level Agreement)が公開されており、下回った場合はサービスクレジットが支払われる。一方オンプレミスでは機器もネットワークも自社保有であり、稼働率を外部に保証する主体が存在しないため、部品や冗長構成を自社で手配しなければならない。したがって可用性を保証する主体がクラウドではベンダ、オンプレでは利用企業自身となる点が大きな違いである。
Q6 : データを自社指定の特定国・地域内に必ず保管したい場合、一般的に最も自由度が高いのはどの形態か?
パブリッククラウドでもリージョンを選択することで地理的制約をある程度満たせるが、クラウドベンダはデータ複製ポリシーを内包しており裏側で別国リージョンにメタデータが置かれる可能性や、契約上ベンダによる物理的管理が避けられない。一方オンプレミスで自前の施設を所有する場合、サーバ筐体からバックアップ媒体、アクセス権管理までを企業が決定できるため、指定国境内での保存と処理を完全にコントロール可能である。規制産業や機微情報ではこうしたフルコントロールが求められるケースが多い。
Q7 : OSやミドルウェアのセキュリティパッチ適用責任について正しい記述はどれか?
IaaS型クラウドでは仮想マシン以上のレイヤー、すなわちゲストOSやアプリケーションは利用者責任領域に含まれる。オンプレミスも同様にOSやDBのパッチは自社で検証し計画停止のうえ適用する必要がある。クラウド側が管理するのはハイパーバイザや物理ホストまでで、それより上位はShared Responsibility Modelの顧客側責任に該当する。したがってオンプレとIaaSクラウドでは利用者が能動的にパッチ運用を担う点で共通している。
Q8 : クラウドとオンプレミスの災害復旧(ディザスタリカバリ)体制構築に関する説明で正しいものはどれか?
パブリッククラウドでは物理的に離れたリージョンを選び、RPOやRTOの要件に応じてスナップショット複製やデータベースのマルチリージョン配置といった機能をマネージドサービスとして提供しているため、追加ハードウェアを買うことなく数クリックで遠隔地バックアップが可能になる。一方オンプレミスで同等のDRサイトを構築するには、別都市にデータセンターを確保し機器を二重に購入、回線も冗長化するなど多額の費用と長期プロジェクトが必要となる。ゆえにクラウドは低コストかつ迅速にDRを実現しやすいといえる。
Q9 : 新規業務システムを稼働させるまでのリードタイムに関する説明として最も正しいものはどれか?
クラウドサービスは仮想ネットワークやデータベースをテンプレート化しているため、プログラムコードやIaCを用いれば数時間から数日でテスト環境、本番環境を並行で構築できる事例が多い。オンプレでは機器調達、工事、監査、システムインテグレーションを含めると平均して数カ月を要し、スケジュール遅延も頻発する。そのため新規サービスの市場投入スピードを重視するスタートアップやDX施策ではクラウドが選択されることが多い。
Q10 : ネットワークレイテンシの予測性という観点でクラウドとオンプレミスを比較した場合、一般的に優位とされるのはどちらの特徴か?
オンプレミス環境ではサーバ間通信を同一ラックやキャンパスLAN内に閉じることができ、ネットワーク機器も専用で占有できるため遅延と帯域の揺らぎを細かく測定しながら設計可能である。パブリッククラウドではデータセンター内部は高速だが、利用者拠点からクラウドまではインターネットVPNや専用線で接続するため経路混雑やベンダメンテに伴う揺らぎが避けられない。特にミリ秒単位の遅延が業務影響となるリアルタイム制御系ではオンプレの物理的近接性が強みとなる。