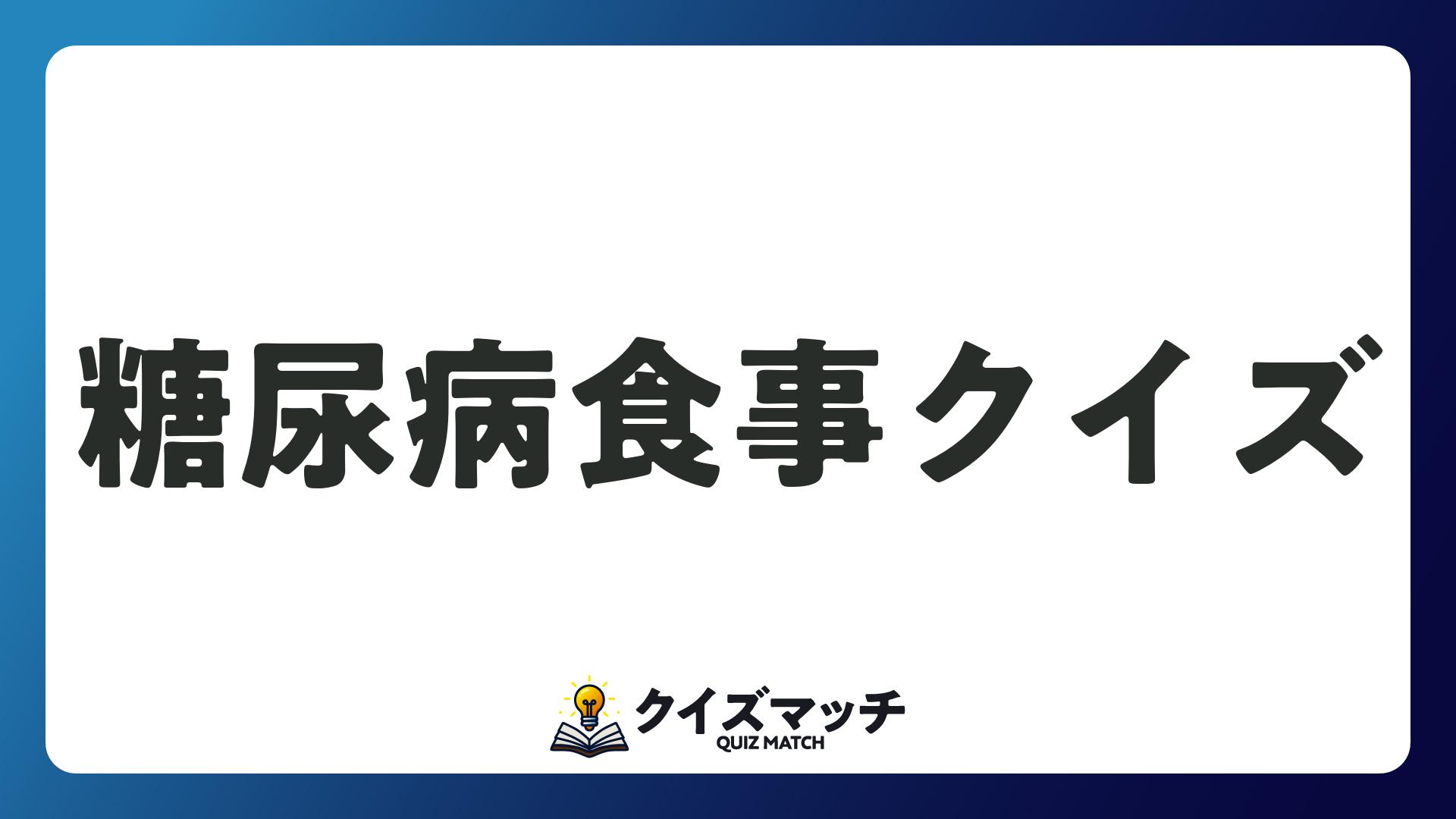糖尿病の食事療法において、主食の選択は血糖コントロールの重要なカギを握ります。食物繊維や消化吸収速度の観点から、玄米や雑穀類が最も推奨されますが、その他にも、低GI値の食品選択、適量のたんぱく質・脂質摂取、間食のコツ、飲酒時の注意点など、さまざまな工夫が必要です。次の10問の糖尿病食事クイズを通して、効果的な食事療法のポイントを確認しましょう。正解を見つけて、自身の食生活の改善につなげていきましょう。
Q1 : 糖尿病食のエネルギー配分として一般的に推奨されている三大栄養素の割合に最も近いものはどれでしょう?
エネルギー配分について日本糖尿病学会は炭水化物50〜60%、たんぱく質20%以下、脂質20〜30%を目安とする。炭水化物を過度に制限するとエネルギー不足やケトン増加、リバウンド的過食の懸念があり、脂質過多は動脈硬化を進行させる。選択肢3の炭水化物50%、たんぱく質20%、脂質30%はこの範囲に収まり、バランスと持続可能性を兼ね備えている。その他の配分は炭水化物が少なすぎたり、たんぱく質が不足したり、脂質が過剰で推奨基準から外れる。
Q2 : 食後高血糖を抑えるために推奨される『食事の順序』として適切なのはどれでしょう?
食物繊維が豊富な野菜を最初に食べると、胃から腸への移動速度が遅くなり糖質の吸収がゆるやかになる。次に肉や魚、大豆などのたんぱく質を摂ることでインクレチン分泌が促進され追加インスリン分泌がスムーズになる。最後に炭水化物であるご飯や麺を食べると、血糖のピークが下がり食後高血糖を抑制できる。逆に炭水化物や甘味を先に摂ると急激な血糖上昇を招く。丼物のような混食も同様によろしくないため、推奨順序は野菜→たんぱく質→炭水化物となる。
Q3 : エネルギーゼロや糖質ゼロをうたう清涼飲料水に使用される人工甘味料について、現在のエビデンスで正しいとされる説明はどれでしょう?
人工甘味料(アスパルテーム、スクラロース、アセスルファムKなど)は糖質を含まないため血糖値を直接上げないが、動物実験や観察研究では腸内細菌叢の変化や甘味受容体の刺激による食欲増進の可能性が報告されている。現行のADI(一日許容摂取量)内での利用は安全とされるが、長期大量摂取の心血管や代謝への影響については結論が出ておらず、WHOも適度な利用にとどめるよう勧告している。したがって完全に安全とは言い切れず、節度ある利用が望ましい。
Q4 : 外食時に糖尿病患者が比較的安心して選べる和定食の例として、最も適切なのはどれでしょう?
刺身定食は主菜が高たんぱく低脂質の魚であり、調理過程に揚げ油や衣を用いない。ご飯を小盛りにすることで炭水化物量を調整でき、味噌汁や小鉢で野菜や海藻を追加すれば食物繊維とミネラルを補える。とんかつ定食は揚げ油と衣により脂質とエネルギーが高く、ラーメン+チャーハンやカレー+ナンは炭水化物と塩分が過剰。外食では主食量の調整と揚げ物を避け、野菜を増やした定食スタイルが望ましく、刺身定食はバランスが取りやすい。
Q5 : 糖尿病の食事療法では、主食を選ぶ際に血糖上昇を緩やかにする食物繊維を多く含むものが推奨されます。次のうち最も適しているのはどれでしょう?
玄米は外皮や胚芽が残っているため食物繊維、ビタミンB群、ミネラルが豊富で消化吸収がゆっくり進む。血糖値の上昇が緩やかになりインスリン分泌負荷を軽減できる。精白米や小麦粉主体のパン、うどんは精製度が高く、同じ炭水化物量でもGI値が高く血糖が急上昇しやすい。噛む回数が増えることも満腹感の維持に寄与するため、主食に選ぶなら玄米が最も望ましい。
Q6 : 食品の血糖指数(GI値)は糖尿病管理で重要です。一般にGI値が低い食品は血糖を急上昇させにくいとされます。次の中で相対的にGI値が最も低いのはどれでしょう?
さつまいもは澱粉にレジスタントスターチや食物繊維が多く、加熱後も糖の吸収がゆるやかになるためGI値は55前後と中等度から低めに分類される。じゃがいもは調理法によってはGI値が80を超え、白パンやコーンフレークは精製小麦やトウモロコシを高温加工しているため消化が極めて速く90以上になることが多い。よって同量の糖質でもさつまいもは血糖上昇を抑えやすい。
Q7 : 糖尿病患者がたんぱく質源として摂取する場合、飽和脂肪酸や塩分の摂取過多になりにくい食品を選ぶことが重要です。次のうち最も望ましい選択肢はどれでしょう?
大豆製品は植物性たんぱく質が豊富で、飽和脂肪酸量が少なくコレステロールを含まない。さらに食物繊維やイソフラボンも含み、血糖値上昇やインスリン抵抗性改善に寄与する報告もある。一方、ベーコンやソーセージなど加工肉は塩分・飽和脂肪酸・亜硝酸塩が多く心血管リスクを高める。鶏もも肉も皮付きのままだと脂質が増える。たんぱく質補給としては大豆製品が最もバランスが良い。
Q8 : アルコール摂取は血糖管理に影響を及ぼします。糖尿病患者が飲酒する場合、特に注意したい飲み方として正しいものはどれでしょう?
アルコールは肝臓での糖新生を抑制し、インスリンや経口薬を使用している場合は低血糖を招く恐れがある。空腹時や大量飲酒、脱水状態はその危険性をさらに高め、血圧上昇や中性脂肪の増加も引き起こしやすい。推奨されるのはビールなら中瓶1本、日本酒1合、ワインならグラス約2杯程度を目安に、必ず食事(特に炭水化物とたんぱく質)を一緒に取りながら時間をかけてゆっくり飲む方法である。これにより低血糖や急激な血糖変動を防ぎやすい。
Q9 : 果物はビタミンや食物繊維が豊富ですが、果糖による血糖上昇も考慮が必要です。日本糖尿病学会が1日あたりの果物摂取目安として推奨する量に最も近い組み合わせはどれでしょう?
日本糖尿病学会は果物を1日可食部100g程度(エネルギー約80kcal)までとし、血糖自己測定で影響を確認しつつ分割して摂ることを推奨している。みかん1個はおよそ100gで80kcal前後のため基準に合致する。バナナ3本やぶどう1房は糖質量が過多になりやすく、りんご半分とキウイの合計150gも目安を超える場合が多い。果物はビタミンやカリウム補給に有用だが、量を守り間食として分けて摂取することが重要である。
Q10 : 血糖コントロールを考えた間食選びとして最も適切なのはどれでしょう?
無糖ヨーグルトは乳糖由来の緩やかな糖質とたんぱく質、カルシウムが摂取でき、血糖上昇が緩やか。ナッツは不飽和脂肪酸と食物繊維が豊富で腹持ちを高め、GI値も低い。組み合わせることで総糖質を抑えながら満足感が得られる。一方、ポテトチップスや菓子パン、チョコバーは精製炭水化物と飽和脂肪酸、塩分や添加糖が多く血糖を急上昇させ、摂取カロリー過多や体重増加を招きやすい。したがって最適なのは無糖ヨーグルトとナッツの組み合わせである。
まとめ
いかがでしたか? 今回は糖尿病 食事クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は糖尿病 食事クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。