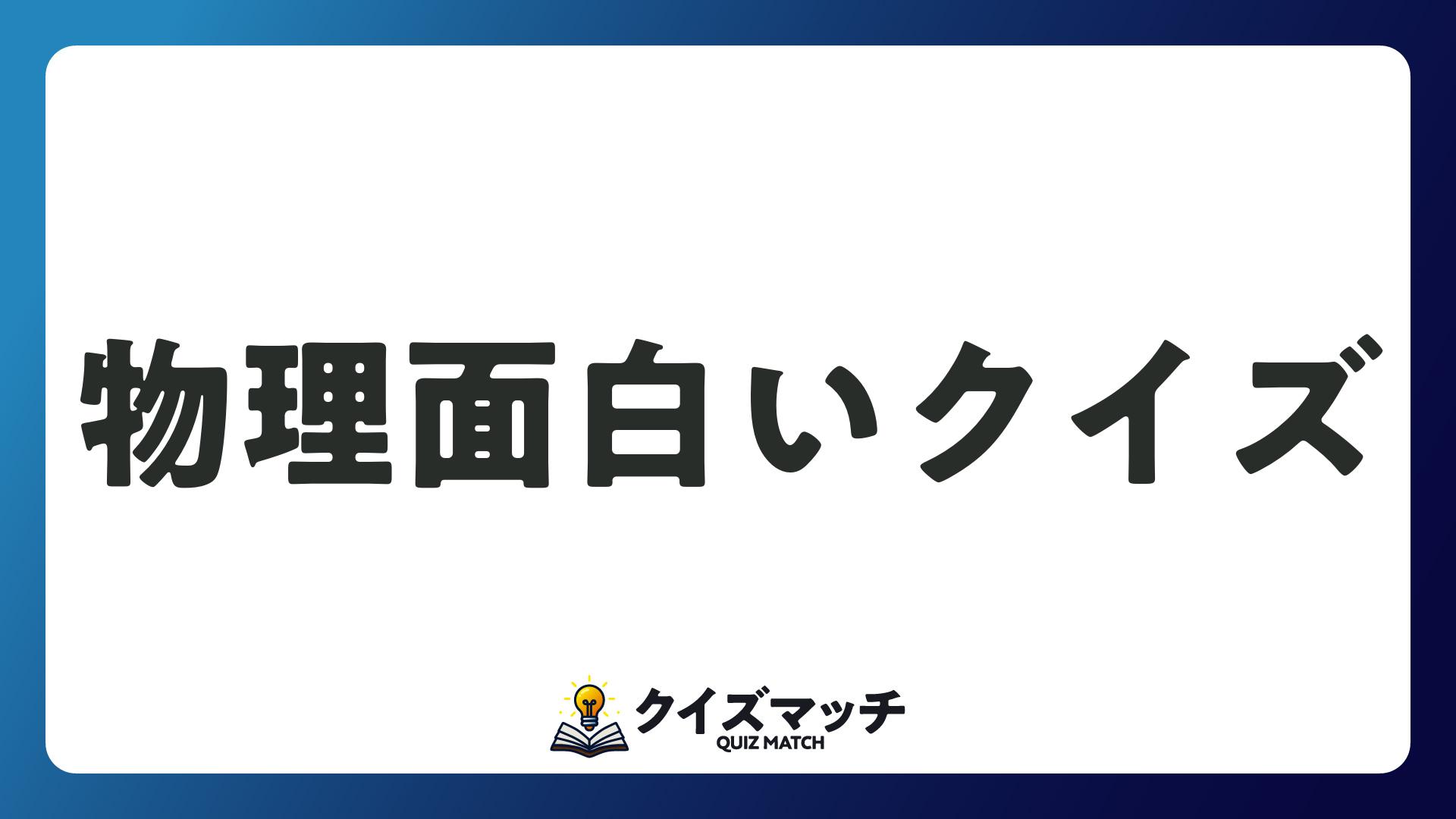物理の知識が試されるクイズを集めました。空気の散乱や素粒子の性質、音速、電磁誘導、星の瞬き、脱出速度、絶対温度、反粒子など、様々な分野から10問をご用意しました。これらのクイズを解くことで、物理学の基礎から応用までの理解を深めていただけると思います。物理が面白く感じられる一助となれば幸いです。ぜひお楽しみください。
Q1 : 夜空で恒星が瞬いて見える主な理由として正しいものはどれか? ドップラー効果による周波数変化 地球大気の屈折むら(シンチレーション) 重力レンズによる光路の曲がり 恒星からの黒体放射の強弱変化
地球を取り巻く大気は温度や密度が時間・空間的に揺らいでおり、その結果屈折率が局所的に変動する。星光は大気を通過するときランダムに屈折し、像の位置と明るさが短時間で変化するため、肉眼には瞬いて見える。この現象はシンチレーションと呼ばれ点光源ほど顕著になる。面積をもって見える惑星は像が平均化されるのでほとんど瞬かない。ドップラー効果や重力レンズ、黒体放射の時間変動は瞬きの主要因ではない。
Q2 : 地表から抵抗を無視して打ち出すとき、地球の引力圏を脱出するために必要な速度に最も近いものはどれか? 7.9 km/s 9.8 km/s 11.2 km/s 15.0 km/s
脱出速度は万有引力による位置エネルギーと運動エネルギーが等しくなる条件 1/2 m v^2 = GMm / r から求められ、v = √(2GM/r)。地球質量5.97×10^24 kg、半径6.37×10^6 m、万有引力定数6.67×10^-11 N·m^2/kg^2 を代入すると約11.2 km/sとなる。7.9 km/sは低軌道へ投入する第一宇宙速度、9.8 km/sは地表重力加速度を数値化したもので、15 km/sは火星脱出に近い値で地球では過大である。
Q3 : 熱力学で定義される絶対零度の温度はケルビン温度目盛りでいくつか? -273 K -459 K 100 K 0 K
ケルビン温度は熱運動エネルギーを直接指標化した絶対温度で、1 K は水の三重点の1/273.16と定義される。分子運動が理論的に最も小さくなる極限状態が絶対零度で、このとき温度は 0 K である。摂氏では -273.15 ℃、華氏では -459.67 °F に相当し、負のケルビン温度は存在しない。100 K は液体窒素が沸騰する程度の低温であり、-273 K や -459 K といった表記は単位と数字を混同した誤りである。
Q4 : 反粒子が自身と同一であるとされる粒子を次の中から選べ。 光子 電子 陽子 中性子
光子は電荷ゼロ、質量ゼロのゲージボソンであり、場の量子論では自身のアンチパーティクルと区別がない。メジャーナ状態とも呼ばれ、粒子・反粒子の概念が重なる。電子や陽子にはそれぞれ電荷が逆符号の陽電子や反陽子が存在し、同一ではない。中性子は電荷ゼロだが内部のクォーク構成が異なる反中性子が区別される。従って自分自身が反粒子と一致するのは選択肢中では光子だけである。
Q5 : プリズムを通過した白色光が色ごとに分かれて現れる現象は何と呼ばれるか? 干渉 回折 反射 分散
透明媒質の屈折率は波長によって変わる。白色光がプリズムに入射すると波長が短い青紫は屈折率が大きく大きく曲がり、赤は小さく曲がるため光路が開き色帯が生じる。この波長依存屈折を色の分散と呼び、分光器や虹の物理にも共通する原理である。干渉は複数波の重ね合わせ、回折は波が障害物の後ろに回り込む効果、単純な反射は同一波長のまま方向が変わるだけでスペクトルは生まれない。
Q6 : 空が晴れている昼間に人間の目に青色が多く届く主な理由は次のうちどれか? レイリー散乱 ミー散乱 オゾン層の吸収 海面の反射
太陽光は可視域の全波長を含むが、気体分子によるレイリー散乱の強度は波長の4乗に反比例するため、短波長ほど大きく散乱される。青や紫が特に散乱され空を満たすが、人の目は紫より青に感度が高いため青く感じる。一方ミー散乱は粒径が大きいエアロゾルで波長依存性が弱く白色霞になる現象であり、オゾン吸収や海面反射は空の色に主役としては寄与しない。
Q7 : β崩壊の際に働き、中性子が陽子や電子に変換されるのを仲介する基本相互作用はどれか? 重力相互作用 弱い力(弱い相互作用) 電磁相互作用 強い力(強い相互作用)
β崩壊ではWボソンを交換する弱い相互作用が働き、クォークの種類が変化して中性子が陽子に変わり、同時に電子と反ニュートリノが放出される。電磁力は荷電粒子間のクーロン相互作用、強い力はクォークを束縛し原子核を保つ働き、重力は巨視的質量間で主に作用するが原子核スケールでは極めて弱い。従ってβ崩壊の根本原因は弱い相互作用である。
Q8 : 次の素粒子のうちスピンが整数でフェルミオンではなく、ボース統計に従う粒子はどれか? 電子 陽子 光子 中性子
粒子は半整数スピンをもつフェルミオンと整数スピンをもつボソンに大別される。電子・陽子・中性子はいずれもスピン1/2でパウリの排他原理に従うフェルミオンであるのに対し、光子はスピン1をもつ質量ゼロのゲージボソンで、同じ量子状態に多数が存在できる。レーザー光がコヒーレントに強度を増幅できるのも光子がボソンだからである。
Q9 : おおよそ摂氏20度の乾燥空気中での音速に最も近い値はどれか? 150 m/s 230 m/s 299 m/s 340 m/s
音速は気体の温度と音波の伝播媒体となる分子の比熱比に依存し、理想気体では v = √(γRT/M) で与えられる。空気(γ≈1.4, M≈0.029 kg/mol)を摂氏20度(絶対温度293K)とすると計算値は約343 m/sになる。測定でも海面気圧下でおおむね340 m/s前後と一致する。150 m/sや230 m/sは極低温ガスや液体中の値に近く、299 m/sは0℃付近の空気の音速に相当する。
Q10 : 誘導起電力の大きさが磁束の時間変化率に比例し、向きが磁束変化を打ち消す方向に生じるという法則はどれか? ファラデーの電磁誘導の法則 ガウスの法則 アンペールの法則 クーロンの法則
コイルを貫く磁束を変化させると起電力が生じる現象はファラデーの電磁誘導の法則で記述され、E = −dΦ/dt が成り立つ。負号はレンツの法則を示し、誘導電流が磁束変化に抗う向きを取ることを示す。ガウスの法則は電場の発散と電荷量の関係、アンペールの法則は磁場の回転と電流の関係、クーロンの法則は静電気力の大きさと距離の二乗逆比例を与えるもので、誘導起電力そのものを述べてはいない。
まとめ
いかがでしたか? 今回は物理 面白いクイズをお送りしました。
今回は物理 面白いクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!