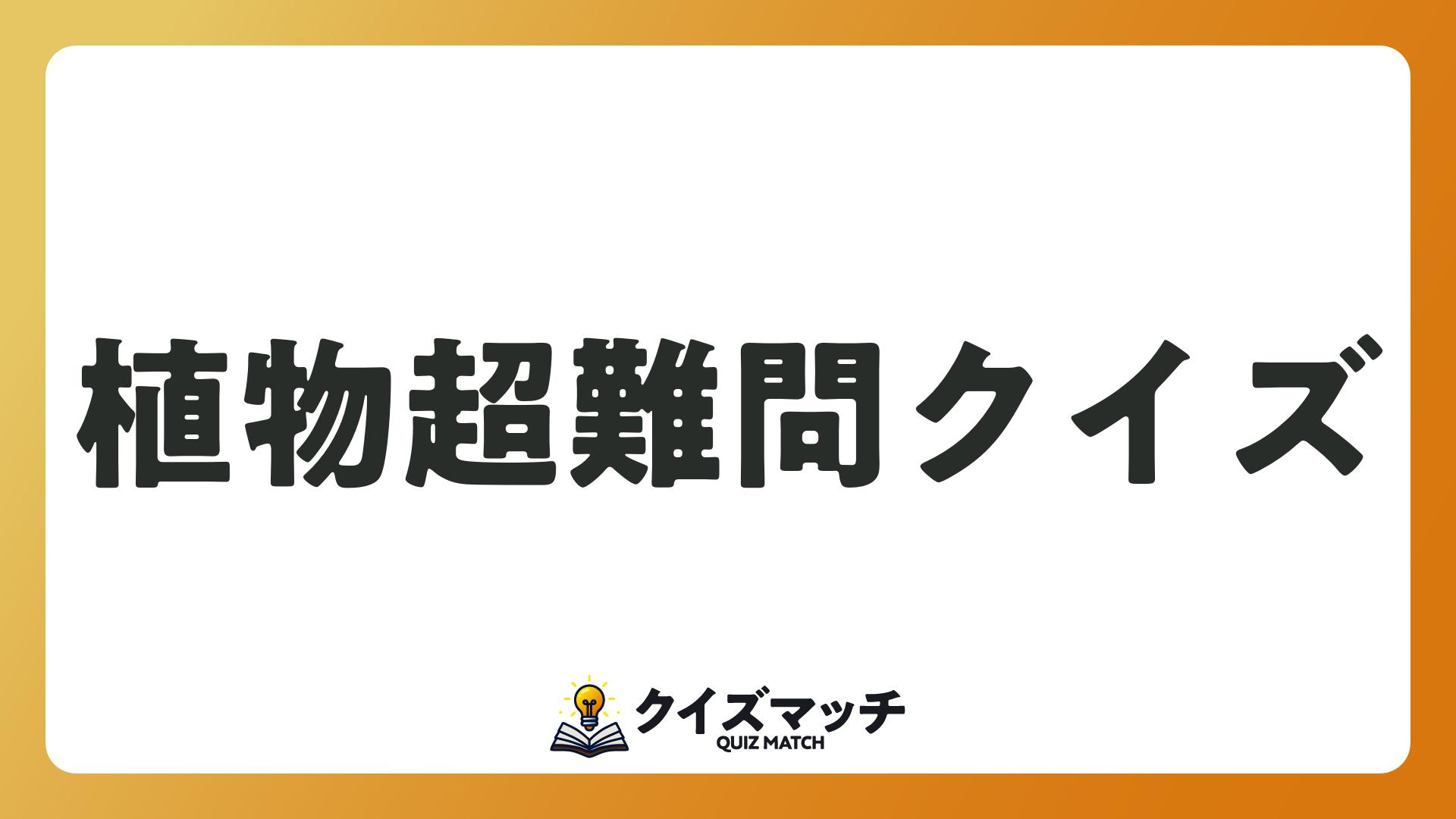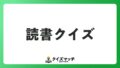「植物超難問クイズ」にご挑戦ください。植物の形態や系統、生理・生態的特性など、専門知識が問われる10問の厳選クイズをご用意しました。花の時計盤状の形態から名付けられたトケイソウ属、世界一の高さを誇るセコイアの愛称、CAM型光合成の代表的モデル植物など、植物に精通した方でも知識の及ばない難問が満載です。植物に造詣の深い方はもちろん、植物への関心が強い方も奮ってご参加ください。この機会に植物の不思議な世界を深く探究してみてはいかがでしょうか。
Q1 : ソメイヨシノ(Prunus × yedoensis)はエドヒガンともう一種のサクラの交配で生じたとされるが、そのもう一種とはどれか?
分子系統解析やマイクロサテライトDNAの比較により、ソメイヨシノはエドヒガン系統の花粉親と伊豆諸島原産のオオシマザクラ系統の種子親が江戸時代後期に人為的に交配されて生まれた単一クローンと考えられる。オオシマザクラ由来の大輪・芳香性と、エドヒガン由来の早咲き性が組み合わさり、全国に接ぎ木で広まった。ヤマザクラやカスミザクラは近縁でも遺伝子寄与が確認されず、チョウジザクラは系統的に遠い。従って正解はオオシマザクラである。
Q2 : 世界最大級の花序を形成し開花時には腐臭を放つショクダイオオコンニャク(Amorphophallus titanum)が属する科はどれか?
ショクダイオオコンニャクはスマトラ島固有の球茎植物で、開花時には高さ3mを超える肉穂花序を形成し、腐肉臭で送粉昆虫を誘引する。仏炎苞や肉穂花序、地下にデンプン質の球茎を持つ特徴はサトイモ科の典型的形質であり、ミズバショウやカラーと同じ仲間に当たる。ヤマイモ科やユリ科の花は6枚の花被片を持つ真正単子葉で構造が異なり、双子葉のシソ科とは系統が大きく離れる。したがって正解はサトイモ科である。
Q3 : 西洋ワサビを原料とする薬味「ホースラディッシュ」の学名として正しいものはどれか?
ホースラディッシュはヨーロッパ原産の多年草でアブラナ科。辛味成分イソチオシアネートを豊富に含み、ローストビーフなどの薬味に用いられる。正式な学名はArmoracia rusticanaで、Wasabia japonicaは日本ワサビ、Raphanus sativusはダイコン、Cochlearia officinalisはクレソンの仲間と別種。根形態や染色体数、花色なども異なるため、正解はArmoracia rusticanaとなる。
Q4 : 食虫植物ウツボカズラ属(Nepenthes)が分類される科はどれか?
ウツボカズラ属は東南アジアを中心に約170種が分布し、ツル性で先端が袋状の捕虫葉を形成する独特の形態を持つ。形態・花序構造・DNA解析の結果、属のみでウツボカズラ科を構成する単型科とされ、北米のサラセニア科、モウセンゴケのドロセラ科、タヌキモ科とは系統的に遠縁で捕虫器は収斂進化の産物である。よって分類上の正解はウツボカズラ科(Nepenthaceae)である。
Q5 : 裸子植物イチョウ(Ginkgo biloba)の木部で見られず、被子植物では一般的に存在する細胞要素はどれか?
裸子植物の木部は主に仮導管で水を運び、被子植物に特徴的な導管要素(道管)は基本的に欠く。イチョウも例外ではなく、木質部は仮導管と木部柔細胞で構成され、導管要素がないため水の輸送効率は被子植物より低いとされる。篩細胞は師部側の要素で裸子植物に存在し、木部繊維は支持組織として発達するが、道管は系統的に出現しなかった。古生代に分岐した系統を示す特徴であり、正解は導管要素である。
Q6 : 植物ホルモンの中で細胞伸長を促進し、頂芽優勢や光屈性の制御に関与するインドール酢酸(IAA)はどのホルモン群に分類されるか?
IAAはインドール環と酢酸骨格を持つ最初に発見された植物ホルモンで、酸成長仮説により細胞壁を可塑化し伸長を促す作用が代表的。頂芽優勢、重力屈性、側根形成など多くの発生過程に関わる。オーキシン類にはIAAのほかIBAや合成オーキシンNAAなどが含まれ、ジベレリンやサイトカイニン、アブシシン酸とは生合成経路も作用も異なる。したがってIAAはオーキシン群に分類される。
Q7 : 世界で最も高い木として公式に記録される高さ115m超のセコイア(Sequoia sempervirens)の巨木に付けられた愛称はどれか?
2006年にカリフォルニア州レッドウッド国立・州立公園で発見されたコーストレッドウッドの個体は115.92mと測定され、現存する世界一の樹高を誇る。発見者はギリシア神話の天空神にちなみ「ハイペリオン」と命名。同公園には高さ記録を過去に持ったストラトスフィア・ジャイアントや、兄弟木のヘリオスもあるが、巨幹体積世界一で有名なジェネラル・シャーマンは別種ジャイアントセコイアである。従って正解はハイペリオン。
Q8 : 乾燥環境に適応し夜間に気孔を開けてCO₂を一時固定する「CAM型」光合成のモデル植物として古くから研究されてきたベンケイソウ科の観葉植物はどれか?
CAM型光合成では夜間にPEPカルボキシラーゼでCO₂をリンゴ酸などに固定し、昼間に再放出してカルビン回路に供給することで水損失を抑える。カランコエ・ブロスフェルディアナは葉が肉厚で栽培も容易なため1960年代からCAM研究の標準材料となり、日長依存的な花成やストレス応答遺伝子の解析にも用いられる。アロエやサンセベリアもCAMを行うが科や系統が異なり、エケベリアはモデルとして一般的でない。従って正解はカランコエである。
Q9 : 日本の暖地に自生し樹高が数メートルに達する木生シダヘゴ(Cyathea lepifera)はどの科に分類されるか?
ヘゴは屋久島以南の亜熱帯林に生育し、葉柄基部が幹に残って層を成すことで樹木状の外観を示す木生シダである。胞子嚢群は杯形の包膜で覆われ、維管束構造や鱗片の形態からヒカゲヘゴなどとともにヘゴ科に分類される。リュウビンタイ科も大型だが木生化せず、コバノイシカグマ科やダチョウシダ科は草本性。DNA系統解析でもCyatheaceaeの単系統性が支持されるため、正解はヘゴ科である。
Q10 : 花の形が時計の文字盤を思わせることから和名が付いたトケイソウ属(Passiflora)を含む植物の科はどれか?
トケイソウ属は熱帯から亜熱帯に約500種が知られるつる植物で、花の副花冠が時計の針のように見えることが名前の由来。APG体系では単型のトケイソウ科に置かれ、ムラサキ科やナデシコ科などとは果実構造と花の形態が大きく異なる。食用のパッションフルーツ(P. edulis)や観賞用園芸品種も多く、薬用研究も進む。従って正解はトケイソウ科である。
まとめ
いかがでしたか? 今回は植物超難問クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は植物超難問クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。