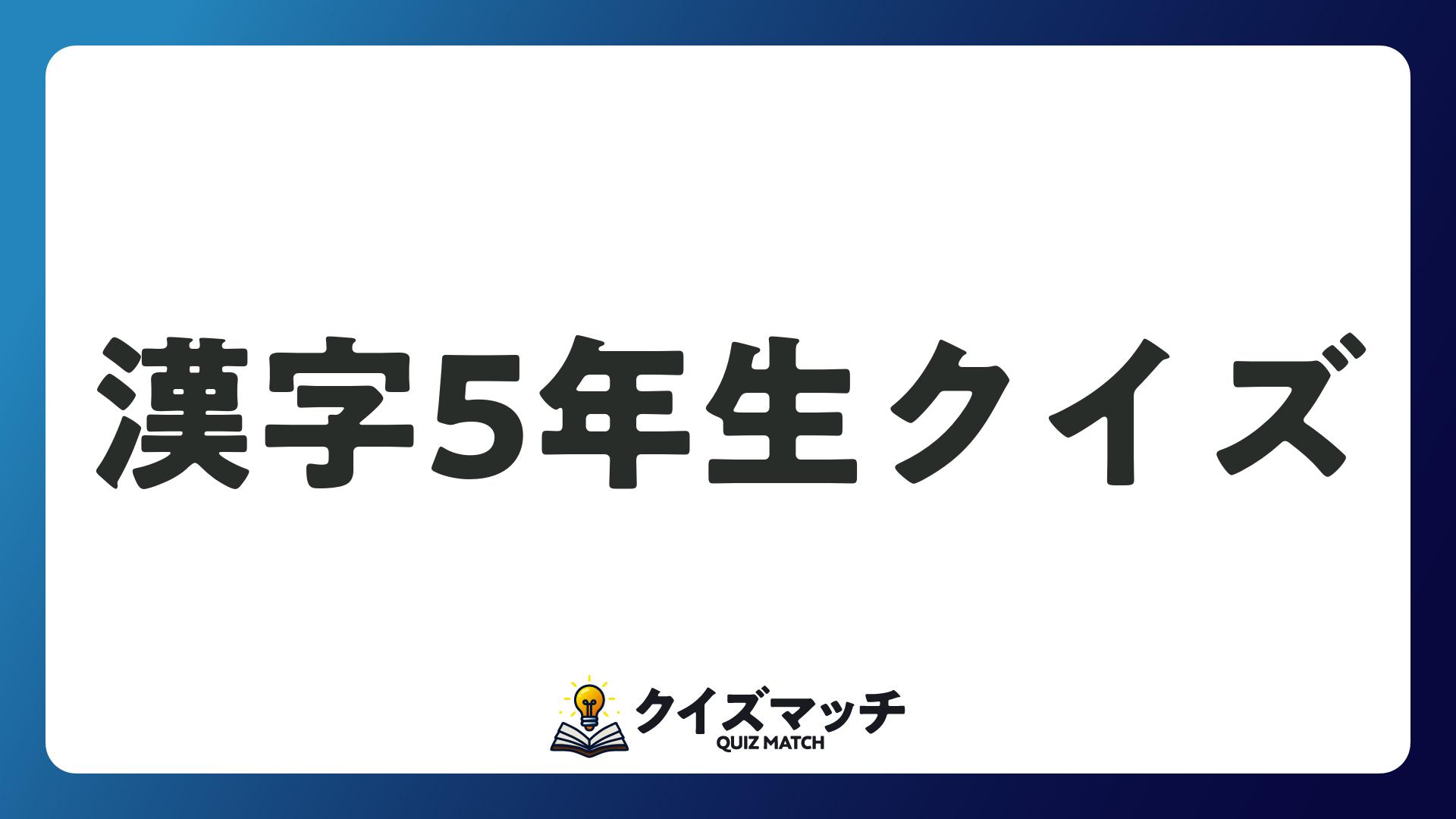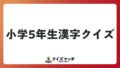小学5年生を対象に、「漢字クイズ」をお届けします。漢字の成り立ちや音読み、熟語の使い分けなど、学習の振り返りに最適な10問を厳選しました。間違えやすい箇所にも光を当て、確実な理解につなげていきます。漢字力は国語の基礎ともいえる重要なスキル。この機会に、自分の弱点を発見し、着実にレベルアップを目指しましょう。楽しみながら漢字の奥深さに迫る、充実のクイズ企画をお楽しみください。
Q1 : 『軽』の反対語として最も適切な漢字はどれ?
「軽」は重さや責任が少ないことを示す漢字で、その対義語は量や重要さが大きいことを表す「重」です。「弱」は強さの反対、「厚」は薄さの反対、「大」は小ささの反対で意味領域が一致しません。語彙学習では対義語は意味の軸が揃っていなければ成立しない点を確認する必要があります。五年生で習う「軽視―重視」「軽量―重量」などの熟語を比べれば、軽と重がペアであることがよくわかります。
Q2 : 次の文の空欄に入るもっとも適切な熟語はどれ?『夏休みに祖母の家に_____する。』
「訪問」は相手の家や施設をたずねる行為を表す熟語で、文脈の「祖母の家に行く」という内容に合致します。「寄付」は金品を差し出す行為、「登校」は学校へ行くこと、「放棄」は権利などを捨てることで、いずれも状況に適しません。五年生では『訪』の音読みホウと訓読みたずねる、『問』のモンを組み合わせた熟語として訪問を学びます。適切な熟語を選ぶ力は文章読解の基礎となります。
Q3 : 次のうち『縮』を正しく用いた熟語はどれ?
「縮」は『ちぢむ・ちぢめる』の意味から派生し、規模を小さくすることを示す語義を持っています。実際の日本語では『縮小』『短縮』『圧縮』などの形で使われます。問題の選択肢のうち辞書に載るのは『縮小』だけで、「縮農」「縮布」「縮業」は造語で存在しません。正しい熟語を覚えることで文脈に合わせた語句選択が出来るようになり、誤用を防げます。
Q4 : 『障害』の『障』の音読みはどれ?
「障」は阜(こざとへん)に音を示す「章」を加えた形声文字で、『ショウ』という音読みが基本です。「障害」「故障」「防障」などの熟語はすべてショウと読みます。ジョウ・ゴウ・ソウという読みは存在せず、読み誤ると意味が伝わりません。小学校では訓読みが無い漢字として扱われ、音読みを確実に覚える必要があります。熟語で反復学習すると定着が速く、試験でも役立ちます。
Q5 : 『沿』という漢字の意味として最も近いものはどれ?
「沿」はさんずい偏に「㕣」を組み合わせた形声文字で、水のほとりに沿って動く様子から『そばを伝って進む』『流れに従う』という意味を持ちます。代表的な熟語には『沿岸』『沿線』『沿道』があり、いずれも川や海、線路や道路などのすぐそばの地域を指します。選択肢のうち「そば」が最も意味が近く、外側・向かい・間は方向や位置の概念が異なるため適切ではありません。
Q6 : 『郷土』の『郷』の音読みとして正しいものはどれ?
「郷」は『ふるさと』を意味し、音読みは『キョウ』、訓読みは『さと』です。五年生の国語では郷土料理や郷土芸能などの語が頻出し、いずれもキョウと読みます。『故郷』『郷愁』などの熟語も同じ読みです。漢字には複数の読みがあるため、語によって使い分ける意識が必要になります。音読みキョウを確実に覚えておくと文章読解や漢字テストで迷いません。
Q7 : 『我』を使った正しい熟語はどれ?
『我慢』は自分の感情や欲求を抑えて耐えることを表す五年生の熟語です。『我』はわれ、『慢』はおごる・ゆるむという意味から転じて自制する意を含みます。一方、我級・我安・我礼は実際には存在しない造語で、辞書や教科書には掲載されていません。正しい熟語を識別する力は語彙力向上に不可欠で、文章を書いたり読んだりする際の表現の幅を大きく広げます。
Q8 : 「拡」という漢字の音読みとして正しいものはどれ?
「拡」は扌(てへん)に「広」を加えた形声文字で、手を使って広げる動作を表すことから「ひろげる」意味が生まれました。音を示す部分の「広」に由来する音読みが「カク」で、小学校5年生で習います。日常語では「拡大」「拡散」「拡充」「拡張」などすべて「カク」と読み、訓読みの「ひろがる・ひろげる」が使われる例は限られます。辞書でも音読みは一つだけなので迷わず選べます。
Q9 : 『磁石』の『磁』の部首は何?
「磁」は意味を表す左側が「石」で、音を示す右側が「辞」に由来する形声文字です。部首は漢字辞典で分類の基準となる意味側の部分が採用されるため、この字の部首は金偏ではなく『石』になります。古代中国で磁石が石の一種と考えられた歴史的背景も理由です。部首を誤って覚えると索引で探せなくなるため、石部の字として確実に身につけることが重要です。
Q10 : 『憲法』の『憲』の総画数は次のうちどれ?
「憲」は宀の3画、真中の一・儿など5画、外側の見が7画、下の心が1画で合計16画になります。漢検や教科書の画数表でも16画と定められており、15画や17画と数えるのは点やはねを一つ少なく数えたり、多く数えたりした誤りです。正しい画数は筆順を正確に書いて確認すると自然に確定するので、まず書き順を覚えることが大切です。
まとめ
いかがでしたか? 今回は漢字 5年生クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は漢字 5年生クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。