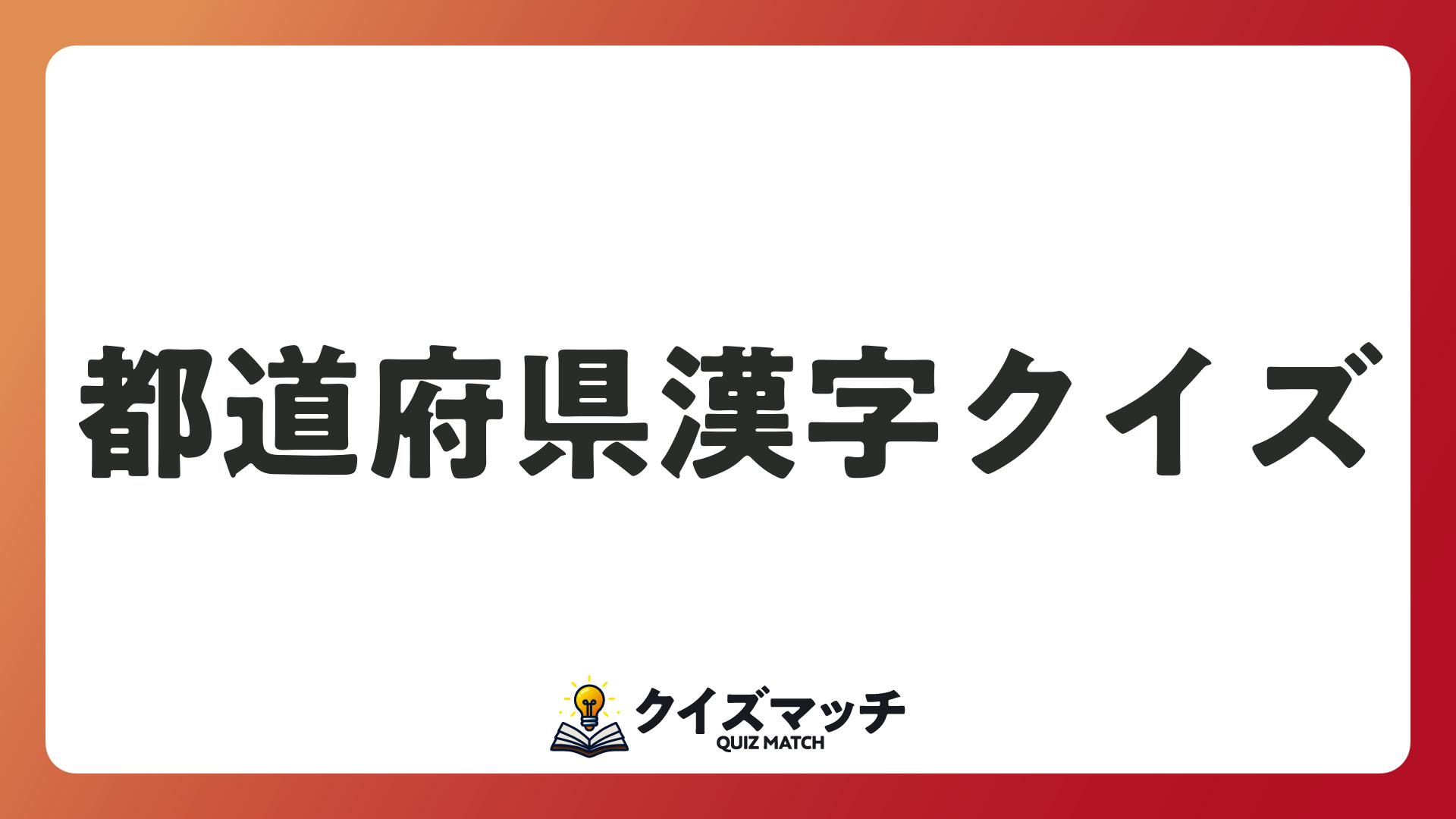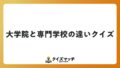47都道府県の名称に隠された漢字の謎に迫る!都道府県漢字クイズ
都道府県の正式名称に使われている漢字は、地域の歴史や地理的特徴をしっかりと反映しています。ところが、これらの漢字は一見してはわかりにくく、見間違えやすい文字も少なくありません。この記事では、そんな都道府県漢字の謎に挑戦する10問のクイズを用意しました。地名の由来や文字の成り立ちを学びながら、あなたの漢字力を試してみてください。都道府県の魅力的な一面が、きっと新たに見えてくるはずです。
Q1 : 次の漢字『徳』が県名に入るのはどの都道府県?
『徳』は道徳や恩恵を意味する漢字で、都道府県名では徳島県だけが採用しています。江戸期に蜂須賀氏が築いた徳島城下の呼称がそのまま県名となり、吉野川流域の肥沃な土地がもたらす恵みを『徳』の字に託したともいわれます。山口・宮城・佐賀には『徳』は入らないものの、宮城の『城』など似た部首を含む文字が並ぶため早読みは禁物です。阿波踊りやすだちなど県の文化を思い浮かべると漢字も合わせて覚えやすくなります。
Q2 : 次の漢字『奈』が県名に入るのはどの都道府県?
『奈』は古語に由来する字で、神奈川県の二字目にも見られますが、県名がこの字で始まるのは奈良県のみです。古代首都・平城京を抱える地域で、『平らな地=なら』が転じて『奈良』の漢字表記が定着したとされます。長野・滋賀・富山には『奈』は含まれず、とくに長野県は読みが似ているため誤答が多いポイントです。東大寺や吉野の桜、法隆寺など歴史資産と結びつけて覚えると印象が強まります。
Q3 : 次の漢字『佐』が県名に入るのはどの都道府県?
『佐』は『たすける』『補佐』の意を持つ漢字で、県名に用いられるのは佐賀県のみです。地名の由来には砂洲を意味する『沙佐』が転訛した説や、神功皇后を祀る『佐潟』にちなむ説があり、いずれも古代の自然地形や信仰と関連します。大阪・岩手・高知には『佐』は含まれませんが、高知の旧名『土佐』や大阪の『佐』を含む地名との混同が生じやすい点に注意が必要です。佐賀県は県庁所在地と県名が一致する数少ない県でもあり、吉野ヶ里遺跡や有明海苔などと併せて覚えると効果的です。
Q4 : 次の漢字『熊』が県名に入るのはどの都道府県?
『熊』は動物のクマを表すだけでなく『力強い』『大きい』という意味合いを持つ漢字で、都道府県名では熊本県のみが使用しています。由来としては古代南九州にいたとされる『熊襲』の名を受け継いだ説や、火山灰が堆積した暗い谷を『隈=くま』と呼んだ説などがあり、いずれも地勢や歴史が反映されています。宮崎・広島・千葉の県名に『熊』は含まれず、同じ音の『隈』『粂』などと書き違えやすい点に注意。熊本城、阿蘇山、馬刺しなどイメージと結びつけると記憶が深まります。
Q5 : 次の漢字『阜』が県名に使われているのはどの都道府県?
『阜』は「おか」「山のふもと」といった意味をもつ難読漢字で、47都道府県のなかで正式名称に用いられているのは岐阜県のみです。地名は戦国時代に織田信長がそれまでの稲葉山を改め、中国の周の発祥地とされる岐山と、天下泰平を願う故事『太平阜財』にちなみ命名した説が有力です。福岡・熊本・香川には似た形の『阝』偏を含む字が見られるものの、『阜』そのものは含まれず、字形が似る『附』『部』などと混同しやすいため注意が必要です。
Q6 : 次の漢字『栃』が県名に入るのはどの都道府県?
『栃』はトチノキを指す漢字で、常用漢字外のため新聞や地図では平仮名の『とち』で表記されることもあります。都道府県名に『栃』が含まれるのは栃木県だけで、『木』は旧国名下野の別称『下毛野』に由来するともいわれます。福島・高知・愛媛には『栃』は登場しませんが、木偏の似た漢字が多いため早とちりしがちです。日光東照宮、宇都宮餃子、那須高原など県を象徴する名物と一緒に覚えると印象に残ります。
Q7 : 次の漢字『埼』が県名に入るのはどの都道府県?
『埼』は突き出した陸地、岬を意味する字で、県名では埼玉県のみに使われていますが、市町村や駅名では全国に点在するため混同されやすい文字です。埼玉の地名は古墳時代の『幸魂(さきたま)』を祀る地に由来する説や、荒川の河岸段丘の突端を示した説など諸説ありますが、いずれも『埼』の字義と深く結びついています。山形・長崎・大分の県名には『埼』は含まれず、似た音の『崎』『岬』との誤記にも注意が必要です。
Q8 : 次の漢字『滋』が県名に入るのはどの都道府県?
『滋』は『うるおう』『しげる』を意味し、豊かな水や養分を連想させる漢字です。47都道府県でこの字が現れるのは滋賀県のみで、古代律令制の滋賀郡の名を引き継いで明治期に県名となりました。琵琶湖を有する土地柄と字義が一致する点も興味深いところです。島根・佐賀・岡山には『滋』は含まれませんが、佐賀には同じ『賀』が入るため見間違えやすいのが落とし穴。水が『滋する』イメージで覚えると記憶に残ります。
Q9 : 次の漢字『縄』が県名に入るのはどの都道府県?
『縄』は綱や連なるものを示す漢字で、県名に現れるのは沖縄県だけです。明治初期、琉球処分により『琉球藩』から県へ改編された際、島々が外洋に連なる姿を表す『縄』と、海の沖を表す『沖』を組み合わせ『沖縄』と定めました。北海道・石川・山梨には『縄』は使われず、似た糸偏の漢字との取り違えが起こりがちです。離島が数珠つなぎに並ぶ地理的特徴と絡めて覚えれば、文字のイメージが腑に落ちやすくなります。
Q10 : 次の漢字『静』が県名に入るのはどの都道府県?
『静』は『しずか』『おさまる』を表す字で、県名では静岡県のみに登場します。明治時代、駿河国と遠江国を合わせた新県名を定める際、駿府城北西の『静岡山』にちなんで名付けられました。福岡・群馬・三重には『静』の字は含まれませんが、福岡と静岡はいずれも二字目が『岡』のため字面が似ており混同しやすいのが注意点。富士山、お茶、駿河湾の桜えびなど土地のイメージと結びつけると記憶が定着します。
まとめ
いかがでしたか? 今回は都道府県漢字クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は都道府県漢字クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。