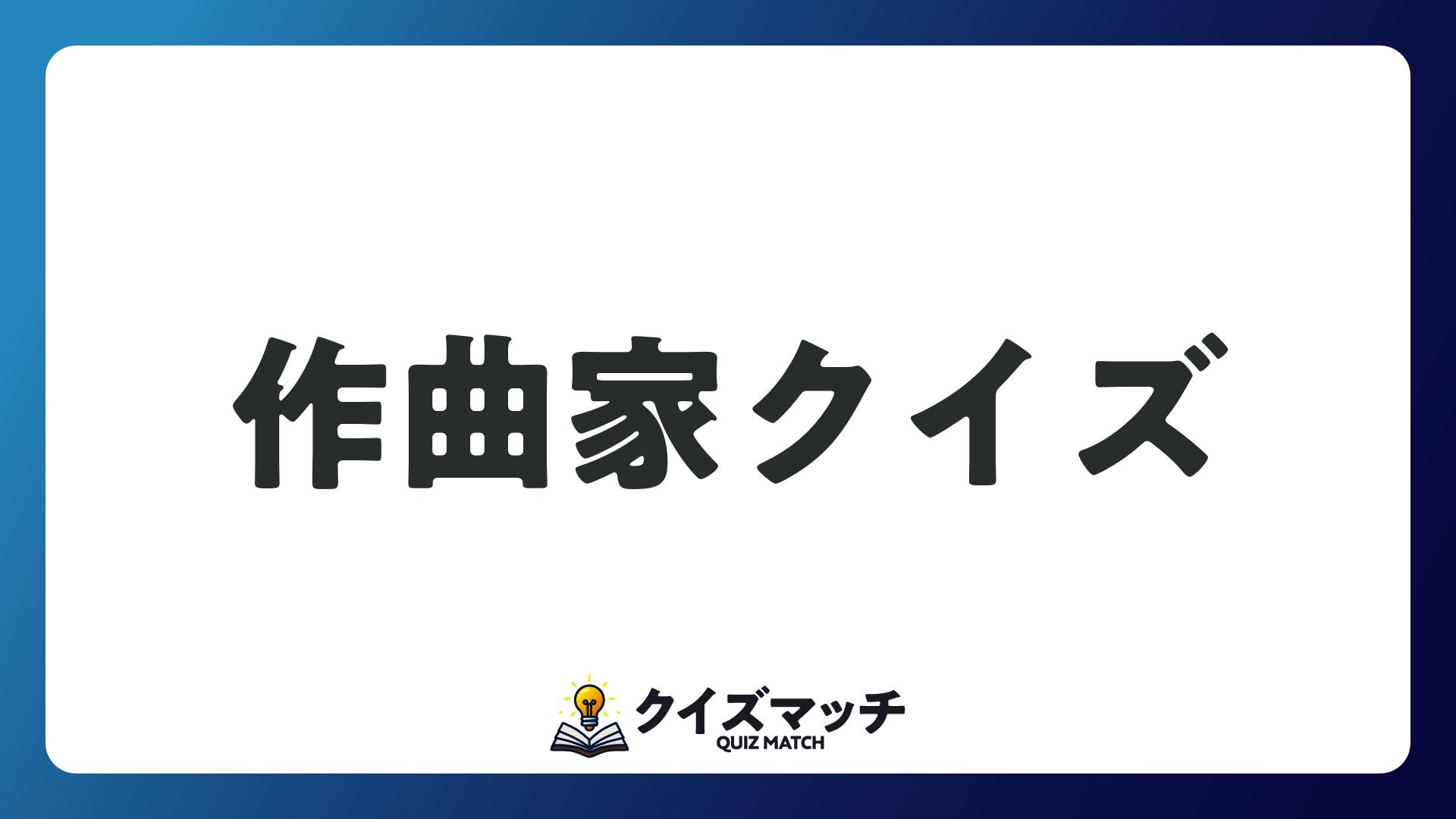作曲家の知識を試すクイズ10問をお届けします。クラシック音楽ファンには定番の作品から、20世紀の革新的な作品まで、作曲家の生涯や代表作について掘り下げていきます。ベートーヴェンのオペラ、ムソルグスキーの管弦楽組曲、シェーンベルクの十二音技法など、クラシック音楽の歴史を彩った名作について、皆さんの理解を深めていただければ幸いです。音楽の背景にある逸話や作品の特徴にも注目しながら、作曲家の個性と業績を振り返っていきましょう。
Q1 : 自らの失恋体験を投影したとされる『幻想交響曲』の作曲家は?
ベルリオーズは女優ハリエット・スミソンへの激しい恋愛感情を題材に1830年、『幻想交響曲』を完成させました。恋人を象徴する旋律“イデー・フィクス”が全楽章に姿を変えて現れる物語的構成、巨大な管弦楽編成、革新的なオーケストレーションは当時としては破格で、標題音楽の代表例とされています。第4・5楽章ではギロチンの処刑や魔女の夜宴など幻想的場面が描かれ、ロマン派芸術の想像力を拡大しました。本作はリストやワーグナーへ影響を与え、後の交響曲に劇的要素を導入する先駆となりました。
Q2 : 組曲『展覧会の絵』を作曲したロシアの作曲家は誰?
『展覧会の絵』は画家ハルトマンの遺作展を見た感想を音楽にしたピアノ組曲で、作曲者ムソルグスキーはロシア五人組の一員。絵の間を歩く様子を表すプロムナードが各曲をつなぎ、管弦楽版へはラヴェル編曲が特に有名です。原曲は奇抜な和声とリズムを持ち、ロシア民俗的な語法を取り入れており、西欧中心だった当時の音楽界に強烈な個性を示しました。ムソルグスキーの早世により出版は遅れましたが、今日ではピアノ・オーケストラ双方で定番レパートリーとなっています。
Q3 : 十二音技法(セリー技法)を確立した作曲家は誰?
シェーンベルクは後期ロマン派的な巨大作品から出発しましたが、20世紀初頭に無調へ移行し、1920年代に十二音技法を体系化しました。12音を重複なく並べた音列を転回・逆行などで変形して用いることで調性に依存しない作品構造を可能にし、弟子のベルクやウェーベルンとともに新ウィーン楽派を形成しました。この技法は戦後の総音列主義や現代音楽にも強い影響を及ぼし、20世紀音楽史を語るうえで欠かせない転換点となっています。
Q4 : 同じリズムとオーケストレーションが続く革新的な管弦楽曲『ボレロ』の作曲者は誰?
ラヴェルの『ボレロ』は1928年にバレエのために書かれた一楽章作品で、16小節の旋律とオスティナートのリズムを終始繰り返しながら編成とダイナミクスだけを増強する斬新な構成が特徴です。スネアドラムの一定リズムの上に管楽器が次々と加わり、最後に全奏で爆発的クライマックスに達します。作曲時間は比較的短かったものの、単純さと高揚感の融合が世界的成功を収め、オーケストレーションの教科書的作品として引用されることも多い名曲です。
Q5 : 謎の主題をもとに友人たちを描いた変奏曲『エニグマ変奏曲』を書いたイギリスの作曲家は?
エルガーは地方音楽家から身を起こし、1899年に『エニグマ変奏曲』で一躍国際的作曲家に仲間入りしました。14の変奏は家族や友人の肖像を音楽で描写し、冒頭主題の背後に引用されない謎の旋律が潜むと示唆したことから“エニグマ”と呼ばれます。この作品によりイギリス音楽復興の旗手と目され、のちの『威風堂々』『チェロ協奏曲』などへ続く道を開きました。豊かな和声とブラスの厚みを生かしたオーケストレーションが魅力で、現在も英国管弦楽曲の代表格として演奏されています。
Q6 : アメリカ滞在中の経験を生かし『新世界より』交響曲を作曲したチェコの作曲家は?
ドヴォルザークは1892年からニューヨークの国民音楽院院長を務め、アメリカ黒人霊歌やネイティブ・アメリカンの旋律に着目しました。その経験を基に1893年、交響曲第9番『新世界より』を完成。第2楽章のイングリッシュホルンの旋律は後に歌曲『家路』として親しまれ、全曲は民族色豊かなリズムとチェコ的抒情が融合した傑作として世界中で演奏されています。帰国後の1895年にプラハで指揮した際も大成功を収め、以後ドヴォルザークの名は国際的に不動のものとなりました。
Q7 : バレエ『春の祭典』を作曲し、20世紀音楽に衝撃を与えた作曲家は誰?
ストラヴィンスキーが1913年にパリで初演した『春の祭典』は、複雑なリズム、不協和音の重層、原始的エネルギーによって観客に衝撃を与え、会場は騒乱状態となりました。プリミティブなロシアの春の祭礼を描いた音楽は従来のバレエ観を覆し、20世紀音楽の方向性を一変させました。ストラヴィンスキーはその後も『火の鳥』『ペトルーシュカ』など多彩な作品を手がけ、新古典主義へ転向するなど常に革新を追求。『春の祭典』はリズムとオーケストレーションの可能性を拓いた歴史的里程標と評価されています。
Q8 : 静かなピアノ小品『ジムノペディ』で知られるフランスの作曲家は?
サティはパリのキャバレーで伴奏をしながら独自の作風を固め、1888年頃に『ジムノペディ』三曲を作曲しました。淡く浮遊する和声と単純なリズム、静かな旋律は当時の濃厚なロマン派様式と一線を画し、ドビュッシーによる管弦楽編曲で広く知られるようになりました。サティの風刺的タイトルや簡潔な書法は後のミニマル音楽、環境音楽の先駆とも評されます。彼の実験精神は若いフランス六人組やジョン・ケージにも影響を与え、20世紀音楽の多様性を刺激しました。
Q9 : オペラ『カルメン』を作曲したのは誰?
ビゼーの『カルメン』は1875年パリ・オペラ=コミック座で初演されましたが、奔放な主人公像と悲劇的結末が保守的な観客に敬遠され、作曲者はその3か月後に失意のまま他界しました。しかしその後国外上演で絶賛され、スペイン風の旋律やハバネラ、闘牛士の歌などキャッチーなナンバーが人気を博し、現在では世界で最も上演されるフランス語オペラとなりました。ビゼーのオーケストレーションや舞台効果は後世のプッチーニらに影響を与え、音楽劇のリアリズムの先駆と位置づけられています。
Q10 : ベートーヴェンが生涯で完成させた唯一のオペラはどれ?
ベートーヴェンは交響曲や室内楽では多数の傑作を残しましたが、舞台作品には苦戦し、何度も改訂を重ねた末に『フィデリオ』だけを完成させました。初演は1805年のウィーン宮廷劇場。自由と夫婦愛をテーマにしたドイツ語オペラで、序曲が4種類存在することでも有名です。ベートーヴェンは劇音楽『エグモント』なども書きましたが、歌劇としての完成作はこれだけで、当初の題名は『レオノーレ』。改訂を経て現在の三幕版に落ち着き、ドイツ・オペラの草分けと評価されています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は作曲家クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は作曲家クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。