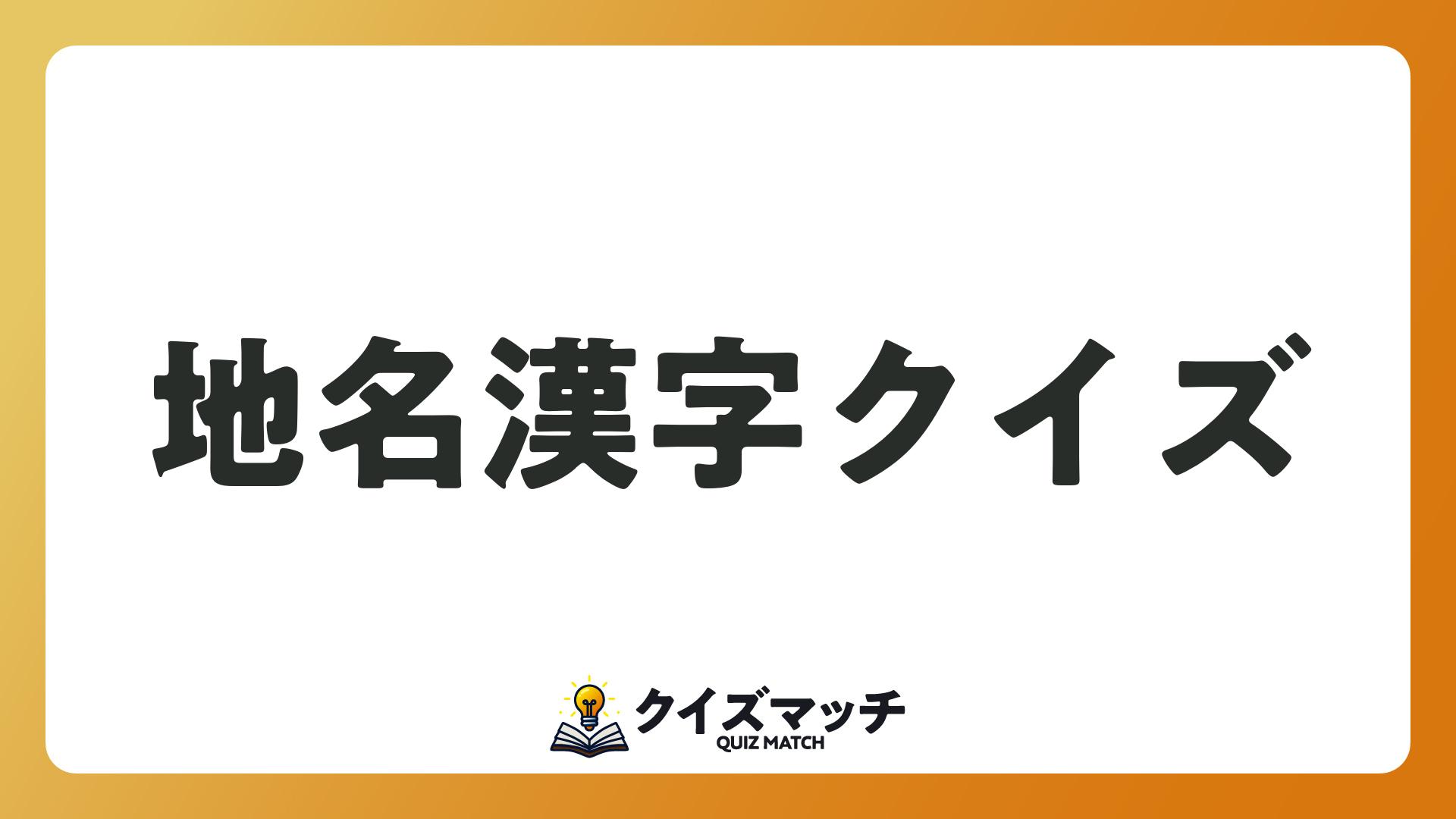地名クイズ、一体どれだけ難しいのでしょうか。この記事では、日本各地の読みにくい地名を10問集めてみました。地名の由来や歴史、特産品などにも注目しながら、一見わかりそうで意外と読めない地名の正しい読み方を確認していきましょう。地名に秘められた物語に迫りながら、地理やカルチャーの知識も深められるはずです。ご家族やお友達と一緒に挑戦して、あなたの地名クイズ力を試してみてはいかがでしょうか。
Q1 : 地名「府中町」はなんと読む?
説明: 広島県安芸郡府中町の読みは「ふちゅうちょう」。東京都府中市や広島県府中市と混同されるが、ここは県庁所在地広島市に隣接する町で、人口約5万人と町としては全国でも上位の規模を誇る。奈良時代に国府が置かれたことから「府中」の字が用いられたが、広島県内に同名の市があるため住所表記の際には郡名を付して区別する必要がある。町内にはマツダ本社工場があり、自動車産業の拠点として経済力が高い。読み自体は平易だが「ちょう」か「まち」かで迷う人が多い点が落とし穴である。
Q2 : 地名「行田市」はなんと読む?
説明: 埼玉県北部の行田市は埼玉古墳群や足袋の町として知られ、読みは「ぎょうだ」。古文書には「行田郷」と書かれ、行田の「行」は「巡る」「往く」を示し、忍城下に物資が行き交った歴史が語源とされる。県名の由来となった「埼玉(さきたま)」古墳群を抱え、映画『のぼうの城』の舞台になった忍城が残ることから観光資源も豊富。足袋産業の隆盛で「行田足袋」は全国に名を轟かせた。読みは「こうだ」「ゆきた」と誤読されることが多く、特に県外の人が戸惑いやすい地名である。
Q3 : 地名「雲南市」はなんと読む?
説明: 島根県中南部の雲南市は2004年に6町村が合併して誕生した市で、読みは「うんなん」。中国の雲南省と同じ字を用いるため話題になるが、出雲国南部に位置する「雲南地方」から命名された。国譲り神話が伝わる斐伊川流域を含み、ヤマタノオロチ退治の舞台とも言われるなど神話色が濃い地域だ。奥出雲そばや酒造りなど食文化も豊かで、たたら製鉄の歴史を残す菅谷たたら山内は産業遺産として注目される。県外では「うんあん」「くもみなみ」と誤読されがちだが、正しくは「うんなん」である。
Q4 : 地名「東彼杵郡」はなんと読む?
説明: 長崎県中央部の東彼杵郡は「ひがしそのぎぐん」と読む。彼杵は古代からの郡名で「そのぎ」と音読みし、東西に分かれた際に方位を冠したため現在の形となった。郡内には川棚町、波佐見町、東彼杵町が属し、有田焼と並ぶ波佐見焼や茶所として知られるそのぎ茶が特産。大村湾に面し、長崎新幹線の新駅建設でも注目を集める。読みにくさの原因は「彼」を「かれ」と読む通常訓と、「杵」を「きね」と読む訓の組み合わせが想起されるためで、「そのぎ」という歴史的音を知らないと誤読しやすい。
Q5 : 地名「鹿角市」はなんと読む?
説明: 秋田県北東部に位置する鹿角市の読みは「かづの」。古くは「鹿角郡(かづのこおり)」と呼ばれ、アイヌ語源とされる「カツヌ」が転訛したとも言われる。十和田八幡平国立公園の玄関口で、史跡尾去沢鉱山や大日堂舞楽など歴史文化資産が豊富。古文書では「鹿角(かづの)」と振り仮名が付されるものが多いが、現代人は字面から「しかつの」「ろくかく」と誤読しがちである。米代川が市内を貫き、稲作やホップ栽培が盛んで、近年はクラフトビールでも知名度が上昇している。
Q6 : 地名「神栖市」はなんと読む?
説明: 茨城県東南部に位置する神栖市の読みは「かみす」。2005年に神栖町と波崎町が合併して誕生した比較的新しい市で、鹿島臨海工業地帯の一翼を担う重化学工業の集積地として発展してきた。地名は古代の鹿島神宮の神領「神州(かみす)」が語源とされ、神の栖む地というイメージから当て字が用いられたという説もある。港湾施設が整備されているため外国人技能実習生が多く、多文化共生が進む街でもある。読みは「しんし」「じんす」と誤読されがちで、郵便物の誤配も起こるほど難読の部類に入る。
Q7 : 地名「不破郡」はなんと読む?
説明: 岐阜県西部に位置する不破郡は関ケ原町と垂井町などで構成される行政区域で、読みは古代の官職名「不破(ふわ)の関」に由来する「ふわ」。歴史的には壬申の乱や関ケ原の戦いの舞台になった要衝で、山陽と東山道を結ぶ交通の要であったことから地名が残った。現在もJR東海道本線や名神高速道路が通過し、東西交通の結節点として知られている。郡は平成の大合併で唯一残った郡部で、読みを間違えやすい。
Q8 : 地名「読谷村」はなんと読む?
説明: 沖縄県中部に位置する読谷村は世界遺産座喜味城跡や残波岬で知られる観光地で、読みは「よみたん」。琉球方言では「ユンタ」と発音されることもあり、漢字表記とのギャップから本土の人は「よみたに」と読み違えがちである。地名は古くは山田・都屋など各字の集合体を表す行政単位「与美端」が転じたとされ、戦後の米軍統治時代を経て現在の形に落ち着いた。村としては人口が日本一多く、文化と自然が調和する活気ある地域である。
Q9 : 地名「香美市」はなんと読む?
説明: 高知県東部の香美市は平成の大合併で土佐山田町、香北町、物部村が合併して誕生した市で、読みはシンプルに「かみ」。高知県内には香南市(こうなんし)もあるため混同されやすく、かがみ、こうみと誤読しがちである。古来この地域は香木を産したことから「香」字が付き、中央部の物部川流域に位置するため「美しい香りの川沿い」という意味合いもあると言われる。龍河洞やアンパンマンミュージアムなど観光資源が豊富で、土佐弁と温かな人柄が魅力の地方都市である。
Q10 : 地名「廿日市市」はなんと読む?
説明: 広島県西部に位置する廿日市市の読みは「はつかいち」。廿は二十を表す古字で、江戸期に毎月二十日に市が立ったことが名称の由来とされる。初見で「にじゅうにちいち」と読んでしまう人も多いが、口語では「二十日(はつか)」と読むため「はつかいち」が正解。市内には世界遺産厳島神社のある宮島が含まれ、牡蠣やもみじ饅頭など広島を代表する特産を育む。平成の合併で佐伯郡の町村を編入し、瀬戸内の海と中国山地の山並みを併せ持つ風光明媚な自治体として発展している。
まとめ
いかがでしたか? 今回は地名漢字クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は地名漢字クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。