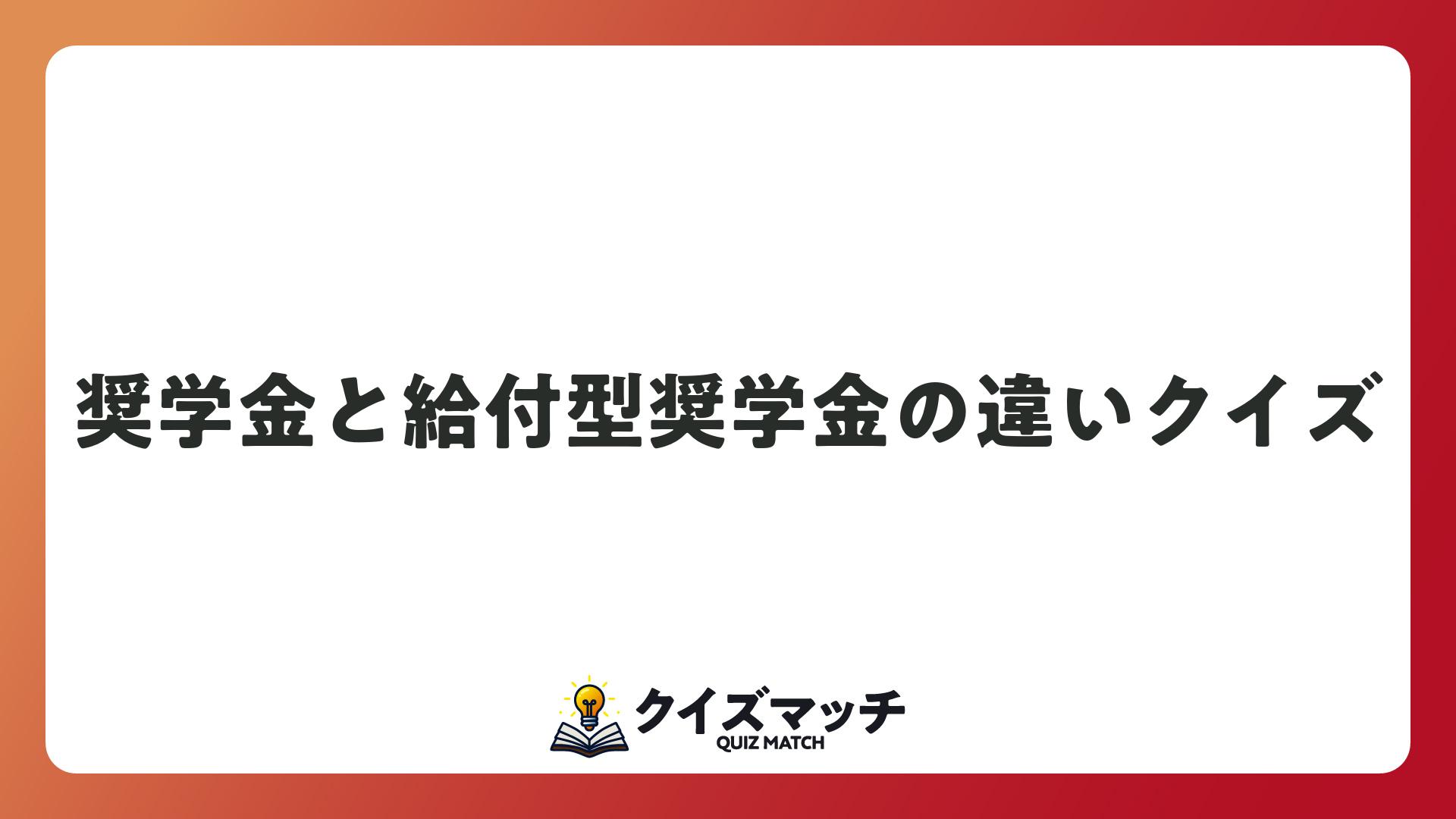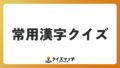日本学生支援機構の第一種奨学金と給付型奨学金には、返済義務の有無を始めとする決定的な違いがあります。この返済の有無が、卒業後の家計設計、ローン審査、進路選択にまで大きな影響を及ぼします。また、貸与型の第二種奨学金には利息も発生するなど、奨学金の種類によって特性が大きく異なります。本記事では、奨学金と給付型奨学金の違いに関する10問のクイズを通して、学生が奨学金を適切に選択・活用する上で重要なポイントを確認していきます。
Q1 : 地方自治体が設ける返済免除付奨学金と典型的な給付型奨学金の大きな相違点は何か
地方自治体の返済免除付奨学金は、多くの場合卒業後に一定期間その自治体で勤務することを条件に返済が免除される貸与型制度です。典型的な給付型奨学金は勤務義務がなく無条件で返済不要なため、卒業後の勤務条件の有無が両者の根本的な違いとなります。勤務が果たせなければ免除されず返済義務が残るため、将来の勤務地やキャリアプランに合わせて慎重に制度を選ぶ必要があります。
Q2 : JASSO給付型奨学金の支給額を決定する際に主に考慮されるのは
JASSO給付型奨学金は、自宅生か自宅外生かという通学形態と世帯所得の水準を組み合わせて支給月額を設定しています。経済的困窮度を客観的に測定し、最も必要性の高い学生へ適切な金額を配分することが狙いです。部活動実績や面接点は選考の一要素になる場合がありますが、支給額そのものの増減には直接関与しません。結果として、同じ大学でも家庭状況の違いにより月額3万円から7.5万円程度まで差が生じる仕組みになっています。
Q3 : 給付型奨学金と貸与型奨学金は併用可能な場合もあるが、併用判断の最終的な決定権を持つ主体はどこか
奨学金の併給可否は、各制度を管轄する運営機関が規程に基づき審査し決定します。学生本人や学校長が独断で併用を決められるわけではなく、兼給申請書や収入証明を提出して重複受給の妥当性がチェックされます。運営機関には日本学生支援機構のほか大学独自基金や地方公共団体などがあり、制度間で情報連携も行われます。虚偽申告や無許可併用が発覚すると返還請求や支給停止の厳しい処分を受けるため、規程に従った正式手続きが不可欠です。
Q4 : 日本学生支援機構の第一種奨学金と給付型奨学金の決定的な違いは何か
第一種奨学金は国から借りる貸与型のため卒業後に毎月の返済義務が生じます。一方、給付型奨学金は返済不要で、支援された金額は学生の負担になりません。この返済義務の有無が最大の相違点であり、卒業後の家計設計、ローン審査、進路選択にまで影響します。返済を要するか否かは、奨学金選択時に最優先で確認すべきポイントだとされています。
Q5 : 貸与型奨学金の中でも第二種は給付型と異なり何が発生する可能性があるか
日本学生支援機構の第二種奨学金は貸与型であり、民間金融機関並みの上限年3%の利率で利息が発生します。利息は在学中は元本に繰り入れられ、卒業後に支払う返済額に加算される仕組みです。一方、給付型奨学金には返済義務がそもそも存在しないため利息概念はありません。利息負担の有無は総返済額を大きく左右し、将来の生活設計にも影響するため、第二種と給付型を比較するときの重要な判断材料となります。
Q6 : 給付型奨学金を継続受給するために毎年大学が学生の何を確認する基準が設けられているか
給付型奨学金は支給決定後も自動継続ではなく、大学が定めるGPAや取得単位数などの学業成績基準を毎年、あるいは学期ごとに満たしているかが審査されます。基準を下回れば支給停止や廃止になる可能性があるため、受給者は学修に真摯に向き合う必要があります。年齢や通学距離は補足情報にとどまり、継続判定の中心はあくまで学業成績です。この仕組みにより、支援の趣旨である「学ぶ意欲のある学生の支援」が担保されています。
Q7 : 同じ学内で貸与型奨学金と給付型奨学金を同時に受給する際、最も注意すべき点はどれか
奨学金制度ごとに併給可否や上限額が規定されており、禁止条項に抵触すると返還請求や支給停止など重大なペナルティを受けることがあります。そのため、複数制度を組み合わせる場合は、必ず併用が許可されているかを募集要項や実施要領で確認し、大学や運営機関に事前相談することが欠かせません。振込口座やメールアドレスの誤記は修正可能ですが、制度違反は後から取り返しがつかず、学生生活全体に影響を及ぼすリスクがあります。
Q8 : 日本の所得税法上、給付型奨学金が原則として非課税となる理由として正しいものはどれか
所得税法第9条1項15号により、学資に充てることを目的とした給付金は非課税とされています。給付型奨学金は教育機会均等を図る社会政策的性格が強く、課税すると支援の趣旨が損なわれるため非課税扱いとなります。未成年かどうか、支給額の大小などは非課税判定の直接要因ではありません。非課税であることで受給者は生活費や教材費に全額充当でき、確定申告も不要ですが、営利目的で流用すると課税対象となる可能性がある点には留意が必要です。
Q9 : 奨学金を貸与型で借りた場合、返済が厳しくなったときに利用できる代表的な救済制度はどれか
貸与型奨学金には、失業や収入減などで返済が困難になった場合に備えた減額返還制度があります。一定期間、月々の返済額を1/2または1/3に引き下げることで家計の急変に対応できる仕組みです。利用には収入基準や申請手続きが必要で、返済そのものを打ち切るわけではありません。給付型奨学金は返済義務自体がないため減額制度を利用する必要がありませんが、貸与型を選ぶ学生はリスク管理として制度内容を事前に把握しておくことが重要です。
Q10 : 貸与型奨学金で必要になることが多い保証制度に関して、給付型奨学金では通常どう扱われるか
貸与型奨学金では返済不能時に備えて連帯保証人や機関保証料が求められるのが一般的です。しかし給付型奨学金は返済義務がないため、債務履行を担保する保証そのものが不要です。保証料が発生しないぶん家計負担が軽くなるほか、親族に保証を依頼する心理的負担も生じません。この違いは奨学金を選ぶ際の比較ポイントであり、特に保証人を立てにくい家庭にとって給付型のメリットは大きいといえます。
まとめ
いかがでしたか? 今回は奨学金と給付型奨学金の違いクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は奨学金と給付型奨学金の違いクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。