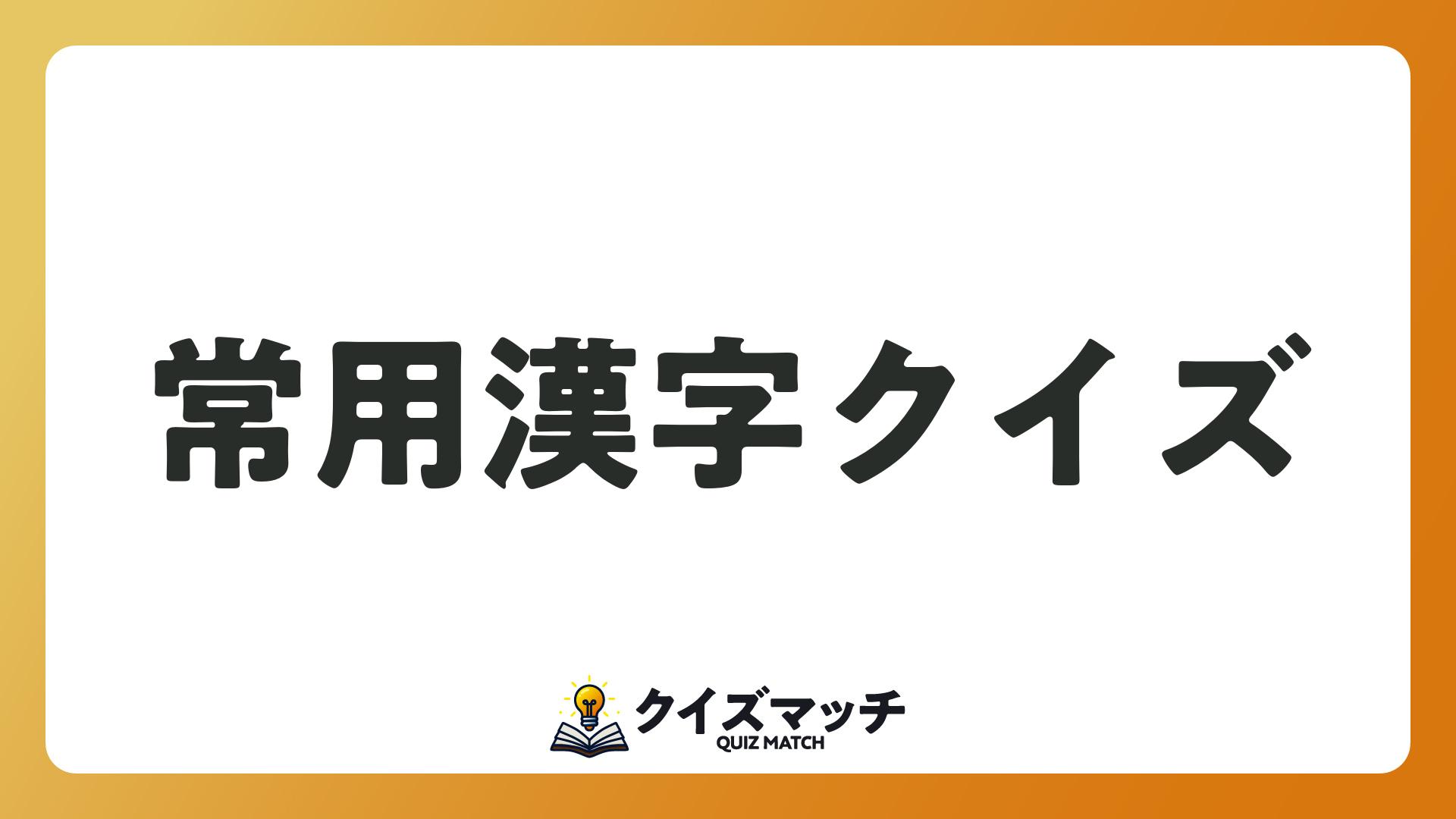常用漢字クイズ – 漢字の深層に迫る10問
日本語の基礎を支える常用漢字には、奥深い歴史と知識が隠されています。この10問のクイズでは、よく使われる漢字の読み方、部首、成り立ちなどに迫っていきます。漢字の背景にある意味や変遷を理解することで、語彙力の向上や漢検対策にもつながるはずです。漢字を深く掘り下げて楽しみながら、あなたの国語力を磨いてみましょう。
Q1 : 常用漢字「遡る」の正しい読み方はどれ?
「遡る」は水流を逆行することから転じて時間や原因を逆方向にたどる意味で使われる。熟字訓で読みは「さかのぼる」。文字単体の音読みは「ソ」だが、日常語としては訓読みが圧倒的に多い。選択肢1「のぼせる」は頭に血が上る意で漢字「上せる」を当てるのが一般的、2「なぞる」は「なぞる」という別動詞、3「さかさる」は存在しない造語でいずれも誤り。熟字訓は形声や偏旁の読みからは推測しにくいため、語彙として覚えることが必要である。
Q2 : 「貢献」の「献」の画数は次のうちどれ?
『献』は部首を「犬」に持つ形声文字で、旧字は「獻」と書く。康煕字典体では手や皿を並べた複雑な構形だが、常用漢字版では略されて総画は13画となる。具体的には「犬」4画、「臤」部分が9画の合計である。選択肢2の11画は略し過ぎ、3の14画・4の15画は旧字に近い数え方を混同した誤り。正しい画数を把握しておくと書写試験や公用文作成で減点を防げる。また部首索引から調べる際にも画数情報は不可欠となる。
Q3 : 常用漢字「寛」を含む熟語として正しいものはどれ?
「寛」は「ひろ-い」「ゆる-やか」など心身のゆとりを表す文字で、宀の下に「寬」の略体を配する。正しい熟語は「寛容」で、相手を受け入れて厳しくとがめない心の広さを意味する。選択肢1の「寛朗」は実際には用例のない誤字熟語で、「寛闊」や「朗らか」を混同したもの、3の「寛靄」は漢語として成立せず、4「寛慎」は「寛厚」と「謹慎」を混ぜた誤答。熟語は辞書や法令用語に掲載されているかで真偽を確認できるため、なるべく実例と併せて覚えると効果的である。
Q4 : 『頒布』の「頒」の音読みとして正しいものはどれ?
「頒」は頭部を表す「頁」に「分」が重なった字形で、「分かち与える」「配る」の意味を持つ。常用漢字表では音読み「ハン」のみが掲げられており、「頒布(はんぷ)」は「広く配り届ける」ことを示す。選択肢1「わん」は訓読みの存在しない音、2「ばん」は濁音化してしまった誤り、4「ほん」は「本」に引きずられた誤答。なお訓読み「わか-つ」は歴史的にはあったが常用では採用されていない。公文書などでは「配布」より意味が狭いことにも注意したい。
Q5 : 『沸騰』の『沸』に含まれる部首はどれ?
『沸』はさんずい偏に「弗」を組み合わせた形声文字で、液体が熱せられて盛んに泡立つ様を表す。部首は水に関する漢字をまとめる「水(さんずい)」であり、辞書では第三水部に分類される。選択肢1の「火」は意味上熱と関係するため紛らわしいが部首ではない。2「土」は形が似た横棒と縦棒で惑わされやすい例、3「欠」は「弗」に欠けた部分が似ているだけで誤り。部首を知ることで字源や漢字検索が効率化し、漢文や古典の学習でも役立つ。
Q6 : 常用漢字『繕』の音読みとして正しいものはどれ?
『繕』は糸編に「善」を組み合わせた形声文字で、「つくろ-う」「修繕」など補修や整える意を示す。音読みは「セン」で、これは声符「善」の音を受け継いだもの。選択肢1の「ゼン」は同じ音でも訓読み「つくろう」の語との混同から生じやすい誤答。3「テン」は漢音変化の推測違い、4「セイ」は「精」「誠」など異字の音読み。音読みを把握しておくと「補繕」「修繕費」などの熟語を目にした際に読解スピードが上がり、漢検対策にも有効である。
Q7 : 『顧みる』という言葉の読みとして正しいものはどれ?
『顧みる』は過去の出来事や自らの行為を振り返る動詞で、正しい読みは「かえりみる」。漢字『顧』は「雇」の声符を含む形声で音読みは「コ」、訓読みは「かえりみる」「かえりみ」。選択肢1「こたえる」は「応える」、2「おもんじる」は「重んじる」、4「おもう」は「思う」であり、いずれも用字が異なる。似た動詞に「省みる」があり混同しやすいがこちらは「反省」の意味が強い。語義と読みを正確に押さえることで文章表現の幅が広がる。
Q8 : 常用漢字「漸」を用いた言葉「漸く」の正しい読みはどれ?
「漸く」は「ようやく」と仮名書きされることも多いが、漢字で書けば「漸く」となる。「漸」は「次第に」や「だんだん」といった漸進的な変化を示す漢字で、音読みは「ゼン」、訓読みは「ようやく」。「ようやく到着した」のように用いられる。選択肢2の「しだいに」は意味的に近いが読みではなく副詞表現であるため誤り。選択肢3「なめらか」、4「すすむ」はいずれも読みでも意味でも対応しない。漢字の意味と訓読みを結び付けて覚えると定着しやすい。
Q9 : 常用漢字「稚」の部首はどれ?
「稚」は「幼稚」「稚魚」などで使われる漢字で、「いとけない」「わかい」を表す。構成を見ると左側に「禾」(のぎへん)が付き、右側に「隹」が組み合わさっている。「禾」は稲など穀物の穂を描いた偏であり、植物に関係する漢字に多用される。したがって部首分類上は「禾」が正しく、選択肢1の「子」は右下の部分に似ているが部首ではない。「米」や「竹」も画的に近く見えるが部首表では異なる区分になる。部首を覚えると辞書引きが格段に速くなるので重要である。
Q10 : 常用漢字「顕」の音読みとして正しいものはどれ?
「顕」は「顕微鏡」「顕著」「顕在化」など科学やビジネスで頻出する漢字で、「あらわ-れる」「はっきりした」の意を持つ。音読みは慣用音を含めて「ケン」のみで、「ゲン」は同じ「現」や「玄」など別字の読みである。「けい」「がん」はいずれも存在しない読みで誤答。漢字は声符部分「顯」の音を受け継ぎ、語頭子音がカ行に変化して「ケン」となった歴史を持つ。音読みを押さえておくと熟語の意味推測や読解速度が向上するため、確実に覚えておきたい。
まとめ
いかがでしたか? 今回は常用漢字クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は常用漢字クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。