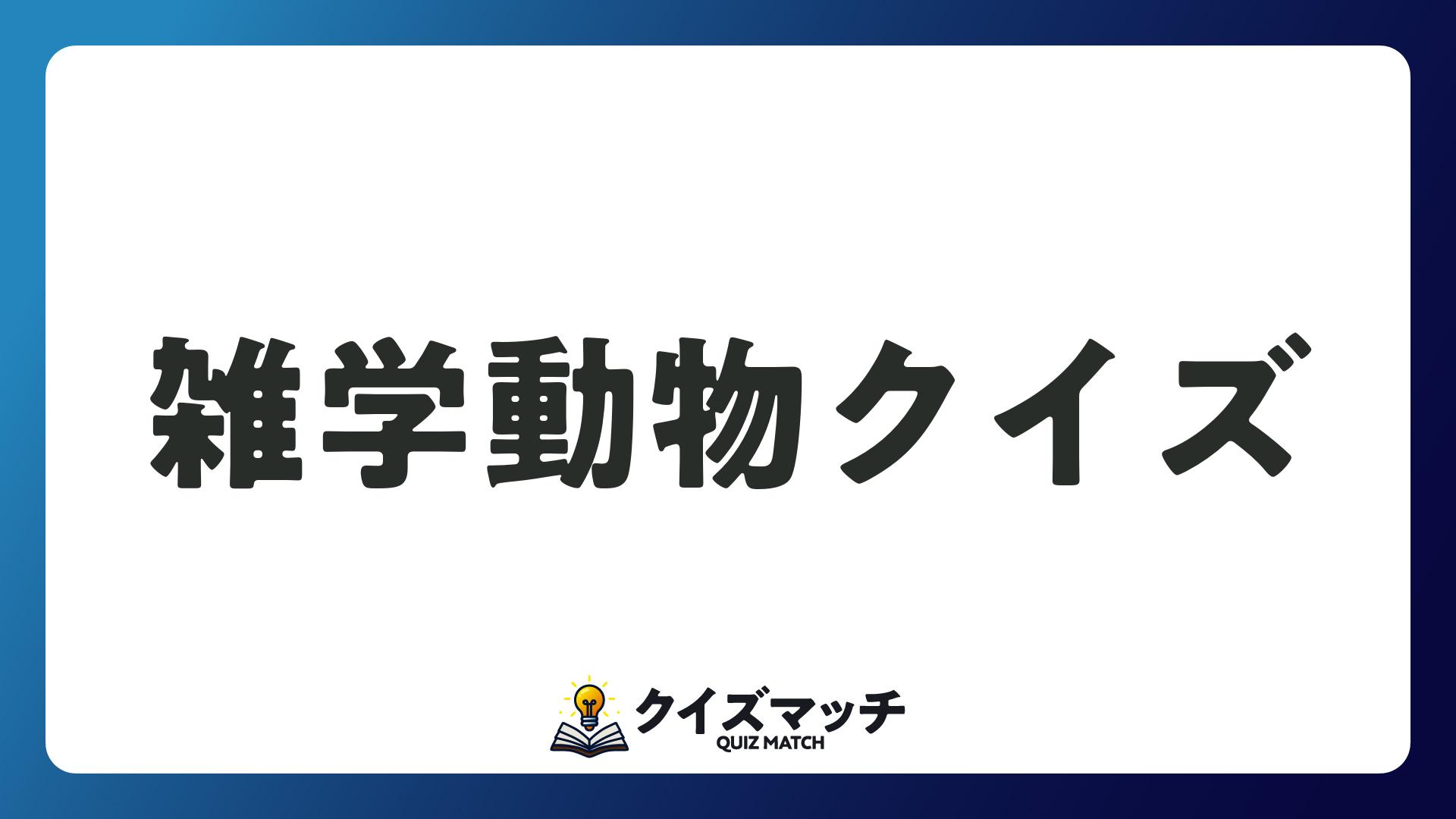動物の持つ驚くべき特徴を知ろう!動物クイズで楽しく学ぼう
ヒトとよく間違えられるコアラの指紋や、世界最大の両生類チュウゴクオオサンショウウオ、後ろ向きに飛べるハチドリ、毒を持つカモノハシのオス…動物にはさまざまな驚きの特徴がありますが、一体どんなものなのでしょうか? このクイズで動物の不思議な能力や習性を楽しく学んでいきましょう。動物好きはもちろん、知的好奇心のある方も必見の内容です。動物の世界をもっと知りたくなるはずです。
Q1 : ペンギンの中で最も体高が高い種はどれでしょう?
コウテイペンギンは成鳥で体高約120センチ、体重30キログラムを超える個体もいる現生ペンギン最大種です。南極の厳寒期に繁殖し、オスが氷上で約65日間卵を抱く間絶食することで知られます。ジェンツーやマゼランは80〜90センチ程度、ヒゲペンギンはさらに小型で、いずれもコウテイほどの体格はありません。巨体は寒冷地での体熱保持に有利で、厚い脂肪層と相まって長時間の潜水を可能にします。
Q2 : ゾウの妊娠期間はおよそどれくらいでしょう?
アフリカゾウ、アジアゾウともに妊娠期間は平均22か月前後で哺乳類最長とされています。長い妊娠期間は大きな脳と体を十分に発達させ、生まれた子象がすぐに歩行して群れに同行できるようにするためです。10か月は人間程度、18か月はサイなど一部の草食獣、36か月という例は哺乳類には存在しません。長い妊娠は母体への負担が大きい反面、子孫の生存率を高める戦略となっています。
Q3 : ネコが喉を鳴らすゴロゴロ音は骨折の治癒を促進する振動域と重なるとされますが、その主な周波数帯はおよそ何Hzでしょう?
ネコのゴロゴロ音は25〜150Hzの広い周波数帯を持ちますが、この範囲は獣医療研究で骨折や筋肉損傷の回復を促す低周波振動治療と重なることが分かっています。飼い猫が安静時やストレス時に喉を鳴らす行動は自己治癒や群れへの安心シグナルという説があり、野生の大型ネコ科より広い周波数幅で振動を発する点が特徴です。5〜15Hzでは低過ぎ、120〜180Hzは上限のみ一致、20〜40Hzでは帯域が狭すぎます。
Q4 : タコの血液が青いのは、酸素を運搬する色素にどの金属イオンが含まれているためでしょう?
タコやイカなど軟体動物の血液は銅を含むヘモシアニンが酸素を運搬するため酸化すると青色を呈します。哺乳類のヘモグロビンは鉄を含み赤く見えるのと対照的です。海水温や低酸素環境での溶存酸素輸送効率を高めるため、銅イオンを中心とするヘモシアニンは低温でも粘度を保ちつつ酸素親和性を維持します。マンガンやコバルトは酸素運搬色素として生体内で使われる例がほぼなく、色彩も異なります。
Q5 : ミツバチが8の字ダンスで太陽の方角を知る際、特に重要な感覚器官はどれでしょう?
ミツバチが行う8の字ダンスは、食物源までの距離をダンスの往復時間、方角をダンスの中央線が示す角度で仲間に伝える高度な情報伝達手段です。これを解読するには太陽の位置を正確に知る必要があり、ミツバチは複眼に備わる紫外線感受細胞で雲に覆われた日でも散乱紫外光から太陽の方位を検出します。触角は嗅覚や接触感覚中心、中脚の振動受容は巣板伝搬用、口吻の味覚は採餌確認用です。
Q6 : コアラには人間とほぼ見分けがつかないある特徴があります。それは何でしょう?
コアラの指紋は渦状や輪状のパターンが人間の指紋とほぼ同じで、従来の指紋鑑定で区別するのが極めて困難とされています。サル以外で精巧な指紋を持つ例は稀で、研究者は滑りやすいユーカリの葉をしっかり握る必要から進化したと推測しています。オーストラリアの現場では実際にコアラの指紋が混入し鑑識が混乱した事例も報告されており、生態学と犯罪学の両面で興味深い題材となっています。
Q7 : 世界最大の両生類とされる種はどれでしょう?
チュウゴクオオサンショウウオは全長1.8メートルに達する記録がある世界最大級の両生類で、中国の山間部の冷たい渓流に生息します。絶滅危惧種に指定され、食用や薬用目的の乱獲で個体数が激減しました。肺呼吸も可能ですが、主に皮膚呼吸に依存し、夜行性で魚や甲殻類を捕食します。日本のオオサンショウウオは近縁種ですが、平均サイズはこれより小さく、最大でも1.5メートル程度です。
Q8 : ハチドリが飛行中にできる珍しい動きはどれでしょう?
ハチドリは鳥類の中で唯一、ホバリングだけでなく後ろ向きに飛行できる能力を持ちます。翼の関節が球状で柔軟に回転し、8の字を描く独特の羽ばたきにより、前後左右へ瞬時に方向転換できます。毎秒50〜80回もの高速羽ばたきと高い代謝率に支えられ、花の蜜を効率的に吸うために停空飛翔と後退飛行を組み合わせることが可能です。滑空や水面走行は行いません。
Q9 : 哺乳類で唯一、毒を持つオスがいることで知られる動物はどれでしょう?
カモノハシのオスは後脚の足首に毒腺と繋がる蹴爪を持ち、繁殖期になると強い痛みを伴う毒を分泌します。哺乳類で機能的な毒を持つ例は極めて稀で、ハリモグラは同様の蹴爪が退化しているため毒を注入できません。毒はタンパク質由来で、ヒトが刺された場合は激痛と腫れが数週間続くと報告されています。捕食や防御ではなく、主にオス同士の闘争で使用されると考えられています。
Q10 : キリンの首の骨(頸椎)の数はいくつでしょう?
キリンの首は非常に長いものの、頸椎の数はヒトや大半の哺乳類と同じ7個です。それぞれの椎骨が約30センチ以上と大きく伸長しているため全長が長く見えます。もし頸椎の数が増えると神経や血管の分岐に負担がかかり奇形のリスクが高まるため、数を変えずに骨を伸ばす進化的制約が働いたと考えられています。これにより高い木の葉を食べる生態に適応しました。
まとめ
いかがでしたか? 今回は雑学 動物クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は雑学 動物クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。