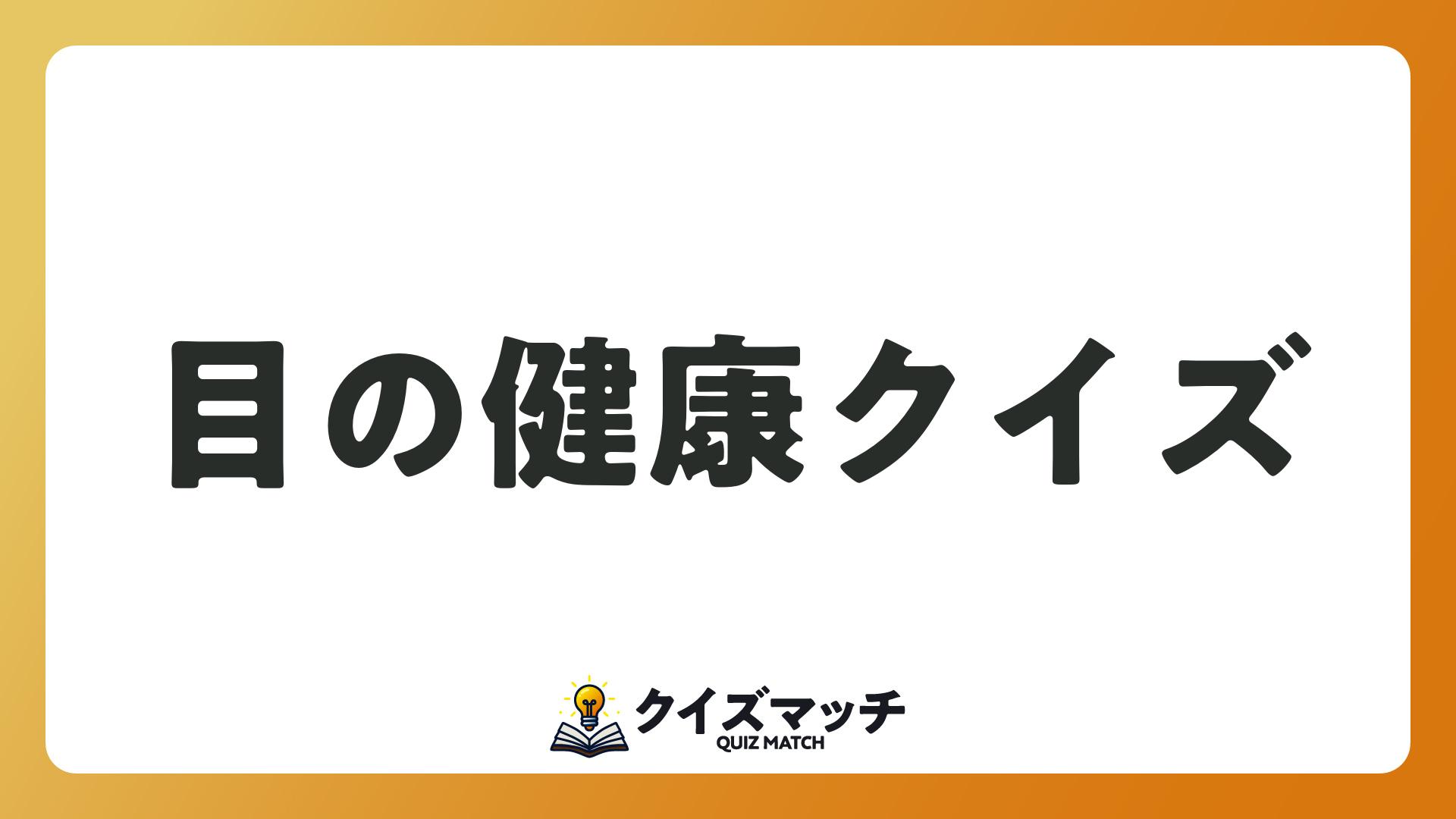目の健康にはさまざまな要因が関わっています。パソコン使用やコンタクトレンズ装用など、日々の生活習慣がその健康状態に大きな影響を及ぼします。この記事では、眼の構造や機能、代表的な眼疾患、そして適切な予防対策について、10問のクイズを通して解説していきます。目の健康について正しい知識を身につけ、快適な視生活を送るためのヒントが見つかるはずです。
Q1 : 高眼圧症のスクリーニングに使われる非接触トノメータの測定原理はどれか
非接触トノメータは短時間の空気パフを角膜中央に吹き付け、角膜が扁平化する瞬間の反射光を光学センサーで捉えて眼内圧を算出する装置である。空気圧が角膜を変形させる力と眼内圧との釣合いから圧を推定する。角膜に接触しないため角膜損傷や感染リスクが少なく、麻酔点眼も不要でスクリーニングに広く用いられる。電気刺激や超音波干渉は用いない。
Q2 : 紫外線から目を守るためのサングラス選びで最も重要なのはどれか
紫外線は角膜や水晶体だけでなく網膜にも障害を与えるため、サングラスは紫外線透過率で選ぶことが重要。レンズの色が濃くてもUVカット加工がなければ瞳孔が開いた状態で紫外線がより多く入る可能性がある。JIS規格ではUVカット率99%以上のものを選べば波長400nm付近までほぼ遮断でき、白内障、翼状片、加齢黄斑変性などの予防に役立つ。フレーム素材やテンプル幅は副次的要素にすぎない。
Q3 : 緑内障の診断で最も重要とされる検査はどれか
緑内障は視神経乳頭の変化と視野欠損が特徴の慢性疾患で、早期には自覚症状に乏しい。眼圧測定だけでは正常眼圧緑内障を見逃すことがあるため、病態を反映する視野検査が診断と経過観察の中核検査とされる。静的量的視野検査(ハンフリー)では閾値を定量評価でき、進行パターン解析で治療効果判定も可能。視力検査や角膜形状解析は補助情報にとどまる。
Q4 : 加齢黄斑変性のリスク因子として最も関連が低いものはどれか
加齢黄斑変性は黄斑部の萎縮や脈絡膜新生血管で中心視力低下を起こす疾患で、加齢、喫煙、家族歴、白人の人種が主要リスク因子として確立している。一方、高度近視は網脈絡膜萎縮や後部ぶどう腫に伴う近視性黄斑変性の原因になるが、加齢黄斑変性と病態が異なり疫学的関連は比較的低い。禁煙と抗酸化サプリメント摂取、定期検査が予防と早期発見に重要。
Q5 : ビタミンA欠乏で最も早期にみられる眼症状はどれか
ビタミンAは網膜の羅ドプシン合成に不可欠で、欠乏するとまず杆体機能が障害され暗所視力が低下し夜盲症になる。進行すると結膜ビトー斑や角膜乾燥、最終的には角膜軟化症へ至るが、初期症状は夜間の見えづらさである。白内障や眼圧上昇、ぶどう膜炎はビタミンA欠乏と直接関係しない。途上国の小児で失明原因となるが、先進国でも低栄養や脂肪吸収不全で発生する。
Q6 : 使い捨てソフトコンタクトレンズの日常的な取り扱いで正しいものはどれか
ソフトコンタクトレンズは水分を多く含み細菌が増殖しやすいため、装着操作前の石鹸による手洗いが最も基本的かつ重要な衛生手段になる。水道水にはアカントアメーバなどが含まれる可能性がありレンズのすすぎに用いるべきではない。装用したまま寝ると低酸素や微生物角膜炎のリスクが大幅に上がり禁止。使用期限を超えたレンズは物性劣化や汚染の危険が高く破棄する必要がある。
Q7 : 涙液の三層構造でマイボーム腺が主に分泌する層はどれか
涙液は角膜表面から脂質層・水層・ムチン層の三層に区分され、最外層である脂質層をまぶた縁のマイボーム腺が分泌する。脂質層は水層の蒸発を抑え表面張力を下げて涙液の均一な広がりを維持する役割がある。マイボーム腺機能不全では脂質層が減少し蒸発亢進型ドライアイを引き起こす。ムチン層は杯細胞、水層は涙腺が主に担う。電解質層という独立した層は定義されていない。
Q8 : 眼底検査で黄斑部の中心に位置する陥凹部の名称はどれか
網膜黄斑部の中央にある直径約1.5mmの陥凹は中心窩と呼ばれ、錐体細胞が最密集し最も高い視力を担う領域である。眼底検査では周囲より暗赤色で反射が強く見える。乳頭は視神経頭部、血管弓は網膜動静脈の走行で中心窩とは位置も機能も異なる。加齢黄斑変性や黄斑円孔は中心窩が障害されるため著しい視力低下や変視症を来す。検査には光干渉断層計が有用。
Q9 : 視力1.0はランドルト環視力表でどの大きさの切れ目を識別できる能力を示すか
国際視力表では視力1.0は最小可視細分角1分(1/60度)を識別できる能力を指す。ランドルト環なら環の全直径は5分角で切れ目の幅および太さが1分角になる。視力が0.5なら識別角は2分、2.0なら0.5分に相当する。5分角や10分角を要する場合は視力が低いことを意味する。視力は角膜・水晶体の屈折や網膜・視神経機能の総合指標で、数値だけで眼疾患の有無は判定できない。
Q10 : パソコン作業時の眼精疲労を減らす「20-20-20ルール」では、20分ごとにどの程度離れた場所を見ると推奨されているか
20-20-20ルールは米国眼科学会などが推奨する休憩法で、20分ごとに20フィート(約6メートル)離れた物を20秒間見るというもの。遠くを見ることで毛様体筋が弛緩し、一点凝視で緊張した調節機能が回復しやすい。20センチや20インチでは近すぎて調節が休まらず、20メートルと限定する根拠もない。デジタル機器使用によるドライアイや近見過多の予防に有効とされる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は目の健康クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は目の健康クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。