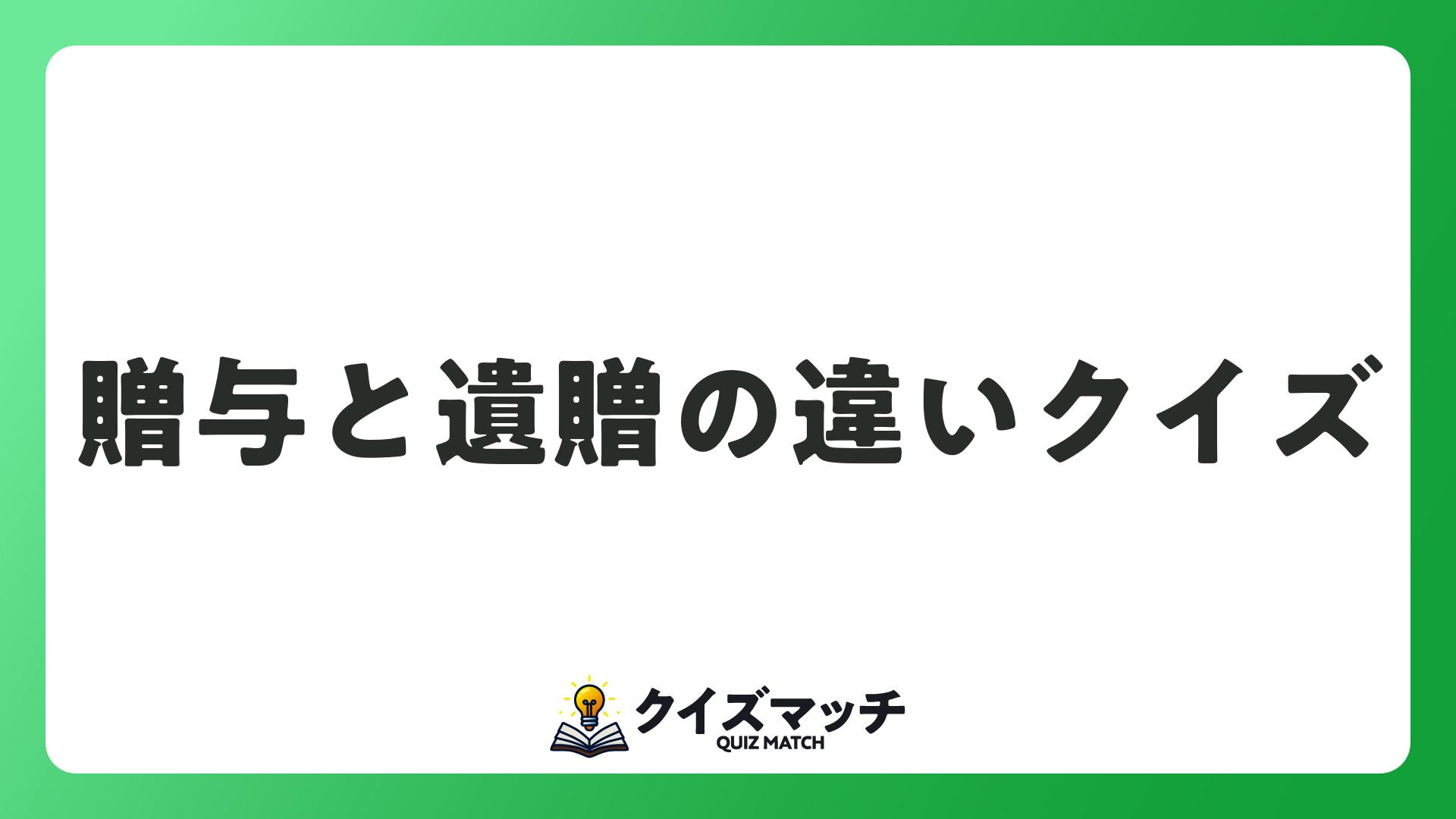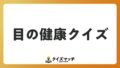贈与と遺贈は民法上の重要な概念ですが、その違いを正確に理解することは意外に難しいものです。本記事では、10問のクイズを通じて、この2つの制度の違いをわかりやすく解説していきます。贈与契約の成立要件、遺贈の放棄期限、債務の承継関係など、暮らしに密接にかかわる基本知識を確認できるでしょう。贈与と遺贈の違いを体系的に整理し、自身の理解度をチェックする良い機会となれば幸いです。
Q1 : 遺言者が一方的に撤回できるが贈与者は撤回できないケースとして適切なものはどれか?
遺贈は遺言による単独行為であり、遺言者は民法1021条によっていつでも自由に撤回することができる。一方、生前贈与は契約であり、書面を備えた贈与が履行済みの場合などは原則として一方的に撤回することはできない。選択肢のうち『包括遺贈』は遺贈の一種であるため、遺言者がいつでも撤回可能である。負担付贈与や書面による贈与などは撤回自由が制限されており、死因贈与契約も双方契約なので同意なく一方的撤回はできない。
Q2 : 死因贈与契約と遺贈を比較したときの法的性質に関する説明で正しいものはどれか?
死因贈与は贈与者の死亡を停止条件として効力が生じる契約であるため、締結時には贈与者と受贈者双方の意思表示が必要となる。これに対し、遺贈は遺言者が単独で行う遺言によって成立し、受遺者の承認は効力発生の要件ではない。従って『死因贈与は契約で合意が必要、遺贈は単独行為』という説明が正しい。他の選択肢は遺贈を契約と誤解したり、両方とも単独行為とするなど民法の基本構造を取り違えている。
Q3 : 不動産の贈与と遺贈における所有権取得時期の原則として正しいものはどれか?
不動産の所有権は対抗要件として登記が必要だが、物権変動がいつ生じるかについては行為類型で異なる。贈与の場合、当事者の意思表示と登記の具備をもって初めて第三者に対抗できるため、登記完了時点で所有権取得と見るのが原則である。一方、遺贈は被相続人の死亡と同時に受遺者に権利が帰属する(民法985条)ので、登記は対抗要件に過ぎず、取得時期は死亡時と評価される。よって選択肢4が正しく、他の選択肢は時期を混同している。
Q4 : 遺贈を受けた受遺者が放棄できる期間について最も正しいものはどれか?
受遺者が遺贈を放棄するには特別の期間制限は設けられておらず、民法986条により、受遺者が承認をするまではいつでも放棄できる。相続放棄と混同しやすいが、相続放棄は相続開始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所へ申述する必要がある。一方、遺贈の放棄は遺言執行者などに対して意思表示をすれば足り、家庭裁判所を経る手続きも不要である点で大きく異なる。
Q5 : 包括遺贈が贈与と大きく異なる点として正しいものはどれか?
包括遺贈は民法964条により、受遺者が相続人と同じ割合で遺産全体を承継するものとされる。そのため、プラスの財産だけでなく被相続人が負っていた債務も同率で承継しなければならない。これは純粋に利益のみを取得する贈与とは本質的に異なるポイントであり、債務については相続人と同様に責任を負う。負担の承継がないという選択肢や一部のみ負担するという選択肢はいずれも法律に根拠がない。
Q6 : 民法550条が規定する書面によらない贈与契約の効力に関する説明として正しいものはどれか?
贈与契約は原則として書面でなくても有効に成立するが、民法550条は『書面によらない贈与は履行が終わるまで各当事者が撤回できる』と規定している。したがって、書面を作成しない場合は引渡しや登記が完了するまでは贈与者も受贈者も自由に契約を取り消すことができる。無効になるわけでも直ちに履行義務が生じるわけでもない点に注意が必要で、遺贈の撤回自由とは制度趣旨が異なる。
Q7 : 負担付贈与と負担付遺贈に共通して法律上必要とされる受贈者・受遺者側の行為はどれか?
負担付贈与と負担付遺贈はいずれも受贈者・受遺者が一定の義務を負う点で共通しており、民法554条・988条は『受諾(承認)』を法律上の要件としている。受諾があることで初めて負担義務が確定し、受諾前に受贈者・受遺者が死亡すれば負担も消滅する。相続放棄や登記の手続きは状況によって必要になることがあるが、法律上必須なのはまず承認である。公正証書の作成は証拠保全にすぎず、成立要件ではない。
Q8 : 贈与税と相続税(遺贈に課税される税)の基礎控除額の比較で正しいものはどれか?
贈与税の年間基礎控除は110万円しかないのに対し、相続税(遺贈を含む)の基礎控除は3000万円+600万円×法定相続人と法定上大幅に高く設定されている。これは生前贈与による租税回避を防ぐ趣旨で、贈与税の課税ベースを厚くし、死後にまとめて課税する相続税には広い非課税枠を設けるという政策的バランスがある。したがって、『相続税の方が基礎控除が高い』という選択肢が正しく、その他は事実に反するか制度を誤解した説明である。
Q9 : 未成年者が受ける贈与および遺贈の承認・放棄に関し、民法の規定に照らして正しいものはどれか?
民法5条1項ただし書は、未成年者でも『単に権利を得、又は義務を免れる行為』については法定代理人の同意なしに単独で行えると定めている。負担のない贈与や遺贈の受諾は純粋利益行為に該当するため、未成年者でも単独で有効に承認できる。一方、負担が付されている場合や放棄などは利益のみとは言えないため、必ず法定代理人の同意が必要になる。よって負担の有無で要件が変わるという選択肢が正解であり、その他の選択肢はいずれかの要件を誤っている。
Q10 : 贈与契約が民法上成立するタイミングとして正しいものはどれか?
民法549条は贈与を諾成契約と定め、書面の有無にかかわらず、当事者双方の意思表示が合致した瞬間に契約が成立すると明示している。目的物の引渡しや登記はあくまで履行又は対抗要件にすぎず、成立要件ではない。また贈与は生前行為なので死亡時点を待たずに効力が発生する。書面を公証人が作成するかどうかは証拠力には影響するが成立時期を左右しない。
まとめ
いかがでしたか? 今回は贈与と遺贈の違いクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は贈与と遺贈の違いクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。