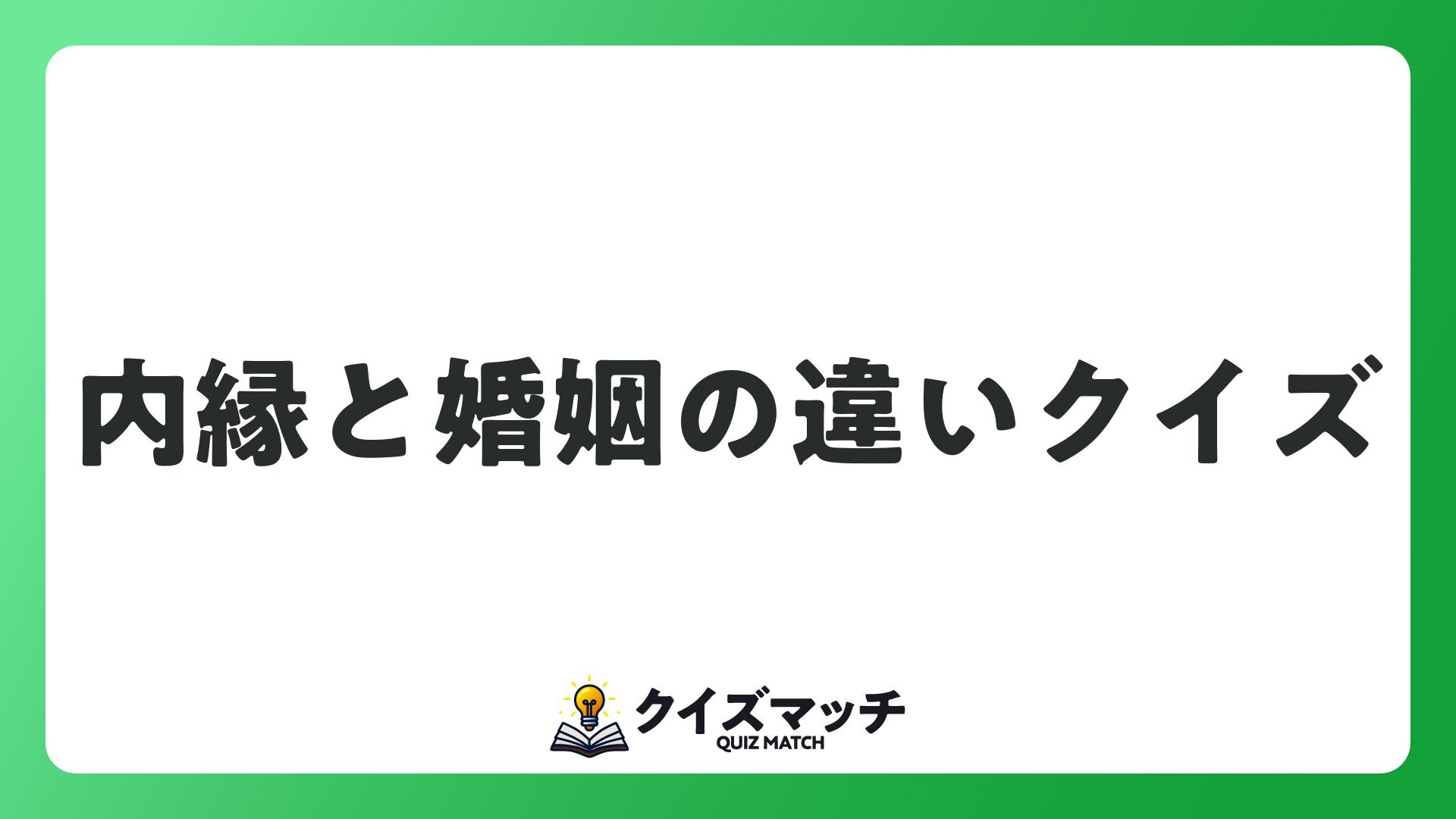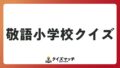内縁と婚姻の違いを問う10問のクイズを用意しました。内縁関係とは、法律上の婚姻関係にはないものの、事実上夫婦と同様の関係にある男女のことを指します。戸籍上の取り扱いや法的効果の違いから、内縁と婚姻には大きな差異がありますが、実際の生活上の取り扱いでは両者に曖昧な部分も見られます。このクイズを通して、内縁と婚姻の微妙な違いを理解していただけると幸いです。
Q1 : 次のうち、内縁の配偶者でも一定の条件を満たせば受給できる可能性がある公的給付はどれか?
労働者災害補償保険法施行規則8条は、死亡した労働者と『事実上婚姻関係と同様の事情にあった者』で死亡当時1年以上同居していた場合などを遺族補償年金・一時金の受給対象としている。内縁配偶者は生活の維持や扶養実態などを証明することで法律婚の配偶者と同等の給付を受けられる。一方、所得税の配偶者控除や相続税の配偶者軽減、国民年金の遺族基礎年金は戸籍上の婚姻を要件としており、内縁配偶者には適用されない。こうした制度の差異は税・社会保障分野での内縁と婚姻の扱いのギャップを端的に示している。
Q2 : いわゆる重婚的内縁に関する判例の考え方として正しいものはどれか?
最高裁昭和54年10月4日判決などは、重婚状態であっても後婚側の内縁が善意無過失で形成された場合には保護に値するとして、民法768条の類推適用により財産分与を認め、不法行為に基づく慰謝料請求も肯定した。これを『重婚的内縁』と呼び、生活共同体としての実態を重視する立場を示している。刑法184条の重婚罪は二重に法律婚を行った場合に限られ、内縁関係だけでは成立しない。したがって重婚的内縁でも一定の権利救済が図られるが、法律婚の配偶者の地位を凌駕するわけではなく、利害調整は個別具体的に行われる。
Q3 : 住民票の『続柄』欄において、内縁配偶者を記載する際の運用として正しいものはどれか?
住民基本台帳事務処理要領は、事実婚であることが客観的資料によって確認できる場合、『未届の妻』や『内縁の夫』といった続柄表記を許容している。これは戸籍上の身分関係ではないことを示しつつも、社会生活上の便宜を図る趣旨で、健康保険の被扶養者申請や会社の福利厚生手続における「事実婚証明」として広く利用される。一方、戸籍の続柄は法律婚を前提に構成されているため、同じ『妻』『夫』という表記を行うことはできない。住民票での続柄記載は内縁の実態を公的に裏付ける資料となるが、相続や税制など戸籍を要件とする制度までは代替できない点に注意が必要である。
Q4 : 内縁配偶者に関する年金制度の取り扱いとして正しいものはどれか?
厚生年金保険法施行令3条は、被保険者と『事実上婚姻関係と同様の事情にあった者』を遺族厚生年金の受給資格者に含めている。日本年金機構は同居の住民票、公共料金名義、賃貸契約、互いの扶養実態など複数資料を総合的に審査し、1年以上の共同生活と婚姻意思があると認めれば法律婚の配偶者と同等の年金を支給する。一方、遺族基礎年金は戸籍上の配偶者であることを前提としており、内縁では対象外であるため、年金制度内でも差異が残る。税法の配偶者控除や相続税の配偶者軽減も婚姻届を要件としており、事実婚で自動的に権利が発生するわけではない点に注意すべきである。
Q5 : 内縁関係にある男女が同じ姓を名乗る場合に関して正しいものはどれか?
内縁は婚姻届を提出していないため戸籍上は別氏のままであり、民法750条の氏の同一義務も適用されない。そのため役所に改姓を届けることはできないが、社会生活上の便宜として銀行口座、クレジットカード、名刺などでパートナーと同じ姓を「通称」として使用することは慣行上許容される。公文書での通称使用には住民票の備考欄に通称登録を行う方法があり、内縁関係を証明する書類を添付すれば職務上の支障なく利用できる。ただし法律上の改姓とは異なり、戸籍・旅券・不動産登記など公的身分行為では原則として本姓を用いなければならない点に注意が必要である。
Q6 : 法律上の配偶者が存在しないまま内縁パートナーが死亡した場合、遺言がないときの内縁配偶者の相続に関する説明として正しいものはどれか?
民法は相続人となる配偶者を戸籍上の婚姻関係がある者に限定しており、内縁配偶者には相続権も遺留分も発生しない。ただし民法958条の3は被相続人と特別の縁故があった者に対し、家庭裁判所の審判で相続財産の全部または一部を与える制度を設けている。内縁配偶者は被相続人と長年同居し生計を共にしていた事実を立証すれば「特別縁故者」に該当する可能性があり、財産取得の道が残されている。また生前に遺言で遺贈することは自由であり、遺言書を作成しておけば内縁配偶者に確実に財産を残すことができるため、事前の対策が重要となる。
Q7 : 健康保険(協会けんぽ等)の被扶養者認定において、内縁の配偶者の取り扱いとして正しいものはどれか?
健康保険法および同施行規則は、被扶養者に該当する者として「被保険者と事実上婚姻関係と同様の事情にある者」を明記している。したがって内縁の配偶者も同一世帯で生活を維持し、婚姻意思が継続していることを証明できれば被扶養者として認定され、保険料負担なしに医療給付を受けられる。申請時には住民票、公共料金領収書、双方の身分証など複数の資料を提出して審査を受ける。一方、所得税の配偶者控除は戸籍上の婚姻を要件とするため、同じ「配偶者」でも税制と医療保険で取り扱いが異なる点が典型的な差異となる。
Q8 : 内縁関係を解消するときに必要な手続として最も適切なものはどれか?
内縁は戸籍上の婚姻という身分行為が成立していないため、離婚届などの公法上の手続は不要である。当事者が共同生活を終了する意思を表明すれば契約関係としての内縁は解消される。ただし内縁にも民法上の準婚的保護が及んでおり、解消に伴う財産分与や慰謝料、未成年子の監護などを巡る紛争が生じることがある。その場合は家庭裁判所に民事調停や訴訟を提起して解決を図るのが通常である。協議内容を公正証書にまとめておくと強制執行が容易になるなど、後日のトラブル防止に資する。
Q9 : 婚姻届を提出することで初めて生じ、内縁では得られない法律効果として正しいものはどれか?
民法890条は戸籍上の配偶者を常に第一順位の相続人と定め、同900条で法定相続分を明確にしている。これらの効果は婚姻届により法律婚が成立した場合にのみ発生し、内縁関係のままではどれほど長期間同居していても相続権が認められない。また夫婦財産制が即時に共有へ移行するわけではなく、婚姻前の個別債務が当然に連帯化することもない。相続権は配偶者に与えられる最大級の法的保護であり、戸籍上の婚姻を欠く限り遺言や生前贈与で補う必要がある点が内縁と婚姻の大きな境目になる。
Q10 : 内縁カップルに生まれた子どもの法律上の地位について正しい説明はどれか?
民法772条は嫡出推定を婚姻成立を前提に規定しており、内縁には及ばない。そのため内縁カップルの子は出生時点で母のみと親子関係があり、母の戸籍に非嫡出子として記載される。父親が任意認知(民法781条)または裁判認知を行えば父子関係が成立し、扶養義務・相続権は嫡出子と同等になるものの、戸籍上の「嫡出子」へ転化するわけではない。2013年の改正で相続分の差別は撤廃されているが、婚姻外出生である事実は記録に残る。なお出生届自体は通常どおり提出する必要があり、提出しないと戸籍・住民票が作成されない。