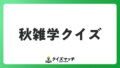親権と監護権の違いを正しく理解することは、離婚や子の養育に関する法的ルールを把握する上で重要です。本記事では、10問のクイズを通して、親権と監護権の具体的な内容や相違点について学ぶことができます。親権者と監護権者の権限、子の氏の変更手続、親権の制限など、様々な場面における両者の役割を確認できるでしょう。親子関係法に精通するために、この機会に親権と監護権の違いを確実に身につけましょう。
Q1 : 民法上、監護権の根拠規定とされる条文はどれか。
民法766条1項本文は、父母が離婚する際に子の監護をどのように定めるかを協議で決め、その内容を家庭裁判所が判断することを規定している。これが親権と切り離した「監護権」を法律上明示的に認める根拠条文とされる。820条は親権の一般条項、840条は扶養義務に関する規定である。したがって監護権の法的根拠は766条1項本文にあると理解されている。離婚後に親権者と監護権者を分ける実務はこの条文を基礎に展開している。
Q2 : 養育費を請求する権限の基礎となるのは次のうちどれか。
養育費は子と同居し日常生活を保護する者が、子の利益のために他方親に対し請求する金銭で、その根拠は身上監護としての監護権にあるとされる。監護権者は子の生活維持の費用を調達する必要があるため、調停・審判で養育費請求の当事者適格を認められる。財産管理権は子自身の財産を扱う権限であり、養育費の請求権とは直接結び付かない。後見権は未成年後見制度の話で本件とは異なり、扶養義務は親同士の負担根拠だが実際に権利行使するのは監護権者である。
Q3 : 監護権を持たないが親権を持つ父が別居中の子の転校届を学校に提出した。この行為の有効性はどれか。
転校や就学義務に関わる届出は子の就学先や教育方針を決定する重要な法律行為であり、民法821条の「子を代理する権限」に当たる。そのため財産管理権ではなく親権者の法定代理権が根拠となる。監護権は日常生活上の事務処理を担うのみで、学校選択まで単独で決定する権限はないとする実務が一般的である。よって監護権を持たない父でも親権者であれば転校届は有効に成立する。ただし子の利益に反する場合には家庭裁判所が監護権者変更や親権行使の制限を命じ得る点は注意が必要である。
Q4 : 監護権者が持たない権限は次のうちどれか。
監護権は日常生活上の世話、教育、居所の指定など身上面の権限に限られるため、子の財産処分や法律行為の代理は含まれない。子名義の不動産を売却する行為は民法824条に基づく財産管理権の範疇であり、親権者でなければ行えず、さらに家庭裁判所の許可が必要となる場合もある。一方、食事や健康管理、生活費の支出、居所決定は身上監護の典型例であり、監護権者が単独で行える。したがって監護権者が持たない権限は子名義の不動産売却である。
Q5 : 母が親権者、父が監護権者となった離婚ケースで、子の氏を変更するために通常必要となる手続はどれか。
父母が離婚し親権が母に帰属すると、子の氏(姓)は原則として母の氏に変更できるが、市区町村への届け出だけでは足りず、民法791条に基づき家庭裁判所の許可を得た上で「子の氏の変更許可申立て」を行う必要がある。監護権者である父は身上監護を行うが、氏や戸籍に関わる法律上の地位は親権者の管理事項とされる。特別養子縁組や住民票の職権訂正は氏変更の一般手段ではなく、市町村長への不服申立ても根拠がない。したがって正解は家庭裁判所の許可による子の氏の変更届である。
Q6 : 親権の一部制限や喪失を命じる権限を有する機関はどれか。
親権の行使が子の利益を著しく害するときは、民法834条・835条により家庭裁判所が親権者に対し親権喪失または停止(制限)を命ずることができる。行政機関である法務局や市町村役場、弁護士会にはそのような司法判断権限はない。家庭裁判所は家事審判法(家事事件手続法)に基づき、親権者の交代、停止、喪失、監護者指定など子の保護に関する広範な審判を行う唯一の機関である。子の利益最優先の観点から、親権の制限は慎重に審理され、監護権の付与先も併せて判断される。
Q7 : 未成年の子がアルバイト契約を結ぶ際、原則として同意を与えることができる立場は誰か。
未成年者が労働契約を締結するには、民法5条1項により法定代理人の同意が必要で、この法定代理人は親権者(または未成年後見人)が務める。監護権者は身上監護中心で財産管理・代理権を有しないため、単独では労働契約への同意権を持たない。学校長の許可は校則上必要な場合があるが法的に代理権はなく、後見監督人は未成年後見人を監督する立場で日常の代理権はない。したがってアルバイト契約への同意を出せるのは親権者である。
Q8 : 監護権のみを有する父が子のパスポート申請書に署名したが発給されなかった。最も適切な理由はどれか。
旅券法では未成年者のパスポート申請には親権者の同意書または署名が必要とされており、監護権しか持たない親には法定代理権がないため単独署名では要件を満たさない。監護権者は居所や日常生活を管理できるが、子に代わる法律行為の代理権は有さず、外国渡航という重大な法律行為に関する申請は親権者の権限となる。未成年でも親権者の同意があれば旅券取得は可能であり、居所指定権の有無は旅券法の同意要件とは別問題である。したがって発給されない理由は親権者の同意欠如である。
Q9 : 次のうち、親権者の同意がなくても監護権者が単独で行える行為はどれか。
監護権者は子の日常の身上監護を担い、健康管理は最重要義務に含まれる。医師の診療行為や緊急の治療に関する同意は子の生命身体の保護に直結するため、判例・実務上、監護権者が単独で行えると解される。一方、自動車売却や遺産分割参加は財産管理権に属し親権者の代理権が必要となる。高校転校は学籍の大きな変更であり、戸籍・氏と同様に親権者の法定代理権による手続が通常求められる。よって監護権者が単独で行えるのは診療同意である。
Q10 : 親権は大きく2つに分けられるが、その正しい組み合わせはどれか。
親権は民法820条以下で規定され、内容は①子の財産を管理し代理行為を行う財産管理権、②子の居所指定・教育・懲戒など身分関係を守る身上監護権に大別される。この2権能を総称して親権と呼ぶ。監護権は身上監護権の中核部分を指すが、離婚時にはこれだけを分離して他方親に付与することがある。扶養権や教育権は学説上の言葉で民法上の分類ではなく、後見権や代理権は親権とは別制度である。したがって正しい組み合わせは財産管理権と身上監護権である。
まとめ
いかがでしたか? 今回は親権と監護権の違いクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は親権と監護権の違いクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。