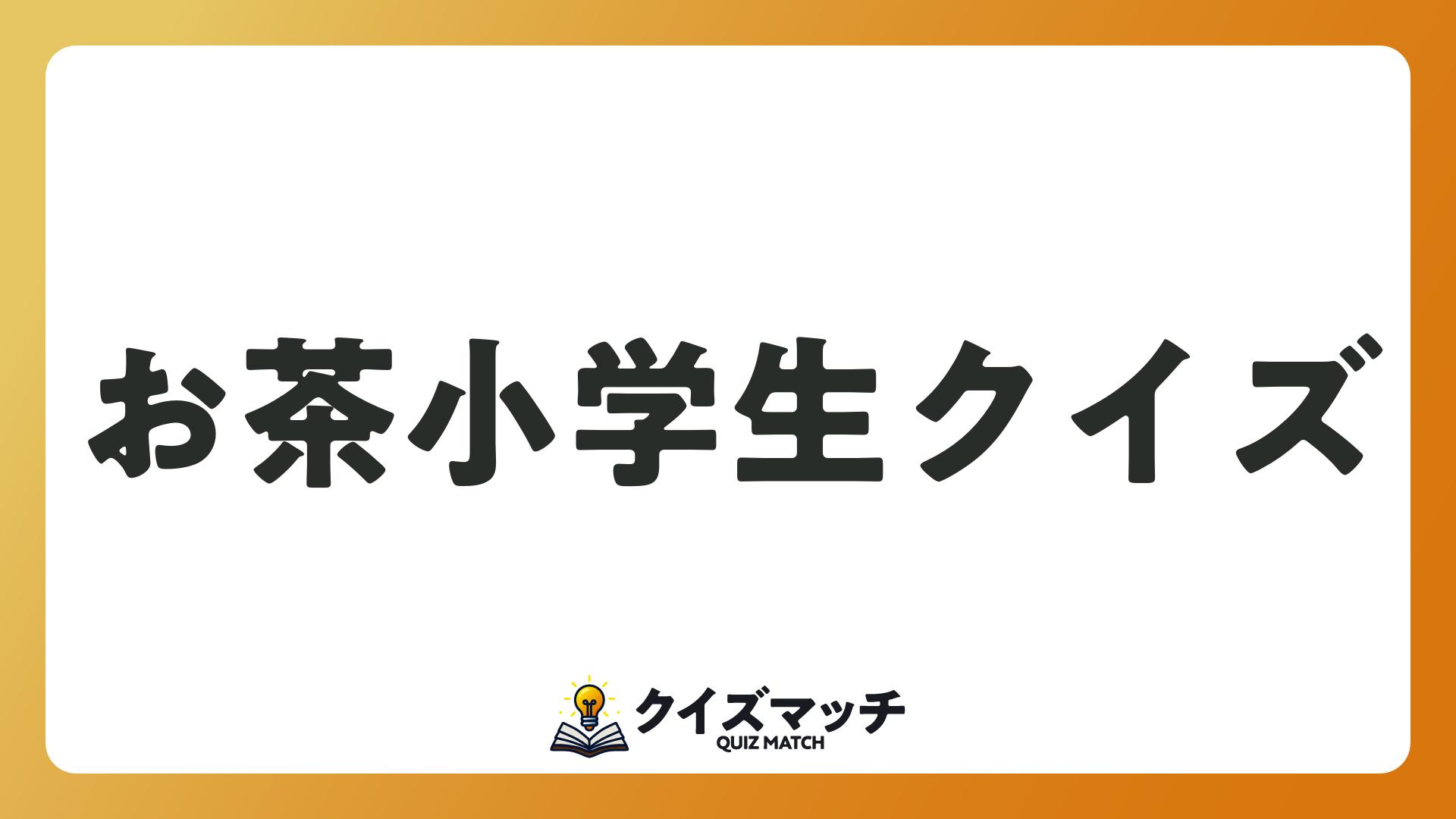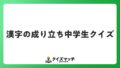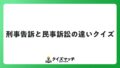小学生のみなさん、日本茶に詳しくなりませんか?お茶には歴史や文化、健康効果など、知れば知るほど面白い魅力がたくさんあります。この記事では、お茶の基礎知識から最新情報まで、楽しみながら学べるクイズを10問ご用意しました。茶道の道具、産地や製法の違い、カフェイン含有量など、意外な事実が満載です。お茶についての理解を深めて、もっと日本の伝統文化を好きになってくださいね。さあ、クイズにチャレンジしましょう!
Q1 : 抹茶を泡立てるために用いる竹製の道具はどれ?
茶筅は竹を細かく割き、先端を房状に削って作った茶道具で、抹茶と湯を素早く混ぜ空気を含ませることできめ細かな泡を立てる役割を持つ。節を抜いた淡竹を使い、一本一本を手作業で削るため奈良県生駒市高山地区など専門の職人が受け継ぐ伝統工芸品となっている。使用後は湯を通して粉を落とし、立て掛けて乾かすことで穂先の変形やカビを防ぐ。茶筅の穂の数は64本や100本など種類があり、薄茶用と濃茶用で形も異なる。茶道の稽古では「茶筅通し」という手前で穂先を柔らかくしてから点前を始める。
Q2 : 日本の緑茶は酸化発酵を行わないが、この特徴を表す分類はどれ?
茶の分類は茶葉を摘んだ後どれだけ酸化酵素の働きを止めるかによって決まる。日本の緑茶は摘み取ってすぐ高温の蒸気で加熱して酸化酵素を失活させるため、細胞内のポリフェノールが酸化せず鮮やかな緑色と爽やかな香りを保つ。このように発酵を行わない茶は「不発酵茶」と呼ばれ、主に中国緑茶や日本緑茶が属する。ウーロン茶は半発酵茶、紅茶は完全発酵茶、プーアル茶は後発酵茶と分類される。酸化度合いの違いは香味だけでなくカフェイン抽出量や保存性にも影響する。
Q3 : 茶摘みで実際に採取されるのはチャノキのどの部分?
チャノキの芽は日ごとに成長するが、一芯二葉または一芯三葉と呼ばれる若い葉と芯芽の部分が最も柔らかく香味成分が多いため茶摘みの対象となる。硬くなった古葉や茎は繊維質が増え苦渋味が強く抽出されにくい。春先の一番茶は新芽が密集しており、旨味成分のテアニンやビタミンCが豊富で品質も高い。根は水分と養分の吸収、樹皮や花は基本的に茶製造には使われないが、花は地域によって観賞用や蜂蜜源に利用されることがある。茶摘みでは指先を使って芽をはさみ、関節を折るようにして素早く折り取る独特の手技が伝えられている。
Q4 : 約50〜60℃の低めのお湯でじっくり淹れるのが勧められる茶は?
玉露は被覆栽培でテアニンが豊富なため繊細な甘味と旨味を引き出すには約50〜60℃の湯で2分ほどゆっくり抽出するのがよい。高温湯を用いるとカテキンとカフェインが過剰に溶け出し渋苦味が際立ってしまう。一方焙煎して香ばしさを楽しむほうじ茶や番茶は90℃以上でも問題ない。麦茶は湯で煮出すか水出し。温度を変えることで同じ茶でも味のバランスが大きく変化するため、玉露は「湯冷まし」を使うなど温度管理が茶の評価に直結する。
Q5 : 緑茶に豊富で抗酸化作用を持ち、レモンにも多いことで知られるビタミンは?
緑茶にはレモンの約数分の一から同等量のビタミンCが含まれ、カテキンとともに抗酸化作用を発揮して体内の活性酸素を抑制する。熱に弱いイメージがあるが茶葉を蒸して乾燥する工程で比較的安定し、また抽出時にポリフェノールが保護するため80℃程度の湯でもそれほど壊れないとされる。ビタミンAやDは脂溶性で茶にはほとんど含まれず、B12は主に動物性食品に多い。風味と栄養の両面から、朝の一杯の緑茶は風邪予防や美肌維持に役立つとされ、小学生にも親しみやすい健康飲料である。
Q6 : 宇治茶の産地として最も有名な都道府県は?
宇治茶は京都府宇治市を中心とした地域で生産された茶の総称で、日本三大銘茶の一つに数えられる。室町時代に足利将軍家が宇治の茶園を保護し、高品質の抹茶が作られたことから名声が高まった。現在も宇治川沿いの霧深い気候と良質な土壌、職人の被覆や揉捻の技術が合わさり、玉露や抹茶、煎茶など多彩な製法で香り高い茶が生み出されている。京都府外で栽培された茶葉でも宇治の工場で仕上げ加工をすれば宇治茶と名乗れるなど、ブランド管理も行われている。
Q7 : 日光を遮って育てることで旨味を強くした高級緑茶は?
玉露は茶摘みの約20日前からよしずや覆いを掛け、日光を遮って育てる被覆栽培によって作られる高級緑茶である。日光を遮ることで光合成が抑えられ、旨味成分テアニンがカテキンへ変化しにくくなるため、甘味とコクが際立つ。若芽だけを手摘みし、蒸し、揉み、乾燥を経て針のように整形した茶葉が特長。低温のお湯でゆっくり淹れると、透明でとろみのある滋味深い茶が抽出される。日本では山口県の上関茶や京都の宇治田原、福岡の八女などが名産地として知られている。
Q8 : 次のうちチャノキではなく大麦を煎じて作るため、カフェインを含まない飲み物は?
麦茶は大麦の実を焙煎し、煮出しまたは水出しして作る飲料で、チャノキ由来のいわゆる茶ではない。茶のカフェインは植物アルカロイドの一種で、チャノキに特有だが大麦には含まれないため、麦茶は就寝前や幼児でも安心して飲めるノンカフェイン飲料として夏を中心に親しまれている。香ばしい風味は焙煎過程で糖質がメイラード反応を起こし生成されたピラジン類による。古くは平安時代の宮中で「むぎがゆ」と共に飲まれていた記録があり、江戸時代には「むぎ湯」として町中に売り歩く商売もあった。近年はティーバッグ化やペットボトル飲料化により通年流通している。
Q9 : 最もカフェイン量が多いと言われる日本茶はどれ?
玉露は被覆栽培で育ち新芽の細胞分裂が盛んなためカフェイン合成量が多く、さらに茶葉を薄い低温湯で抽出する際もカフェインがしっかり溶け出す。ほうじ茶や玄米茶は葉が成熟してから作られたり焙煎したりすることでカフェインが少なく、麦茶はそもそもチャノキではないので含まない。玉露一杯に含まれるカフェインは同量の煎茶の約1.5倍ともいわれ、覚醒効果が高いので飲み過ぎには注意が必要だが、テアニンとの相乗効果で穏やかな持続性があるとされる。
Q10 : 茶道の「薄茶」を点てるときに使われる主な茶はどれ?
抹茶は碾茶という茶葉を石臼で微粉末にしたもので、茶碗に入れた粉に70〜80℃程度の湯を注ぎ、茶筅で泡立てて飲む。葉を丸ごと摂取するためカテキンやテアニンなどの成分を無駄なく取り入れられる。室町時代の侘び茶の成立以降、茶道では薄茶や濃茶として供され、茶碗や棗などの道具、客人への礼法と一体になった文化を形成している。現在も初釜や学校教育の茶道体験などで広く用いられ、日本の伝統文化を象徴する存在である。
まとめ
いかがでしたか? 今回はお茶小学生クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はお茶小学生クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。