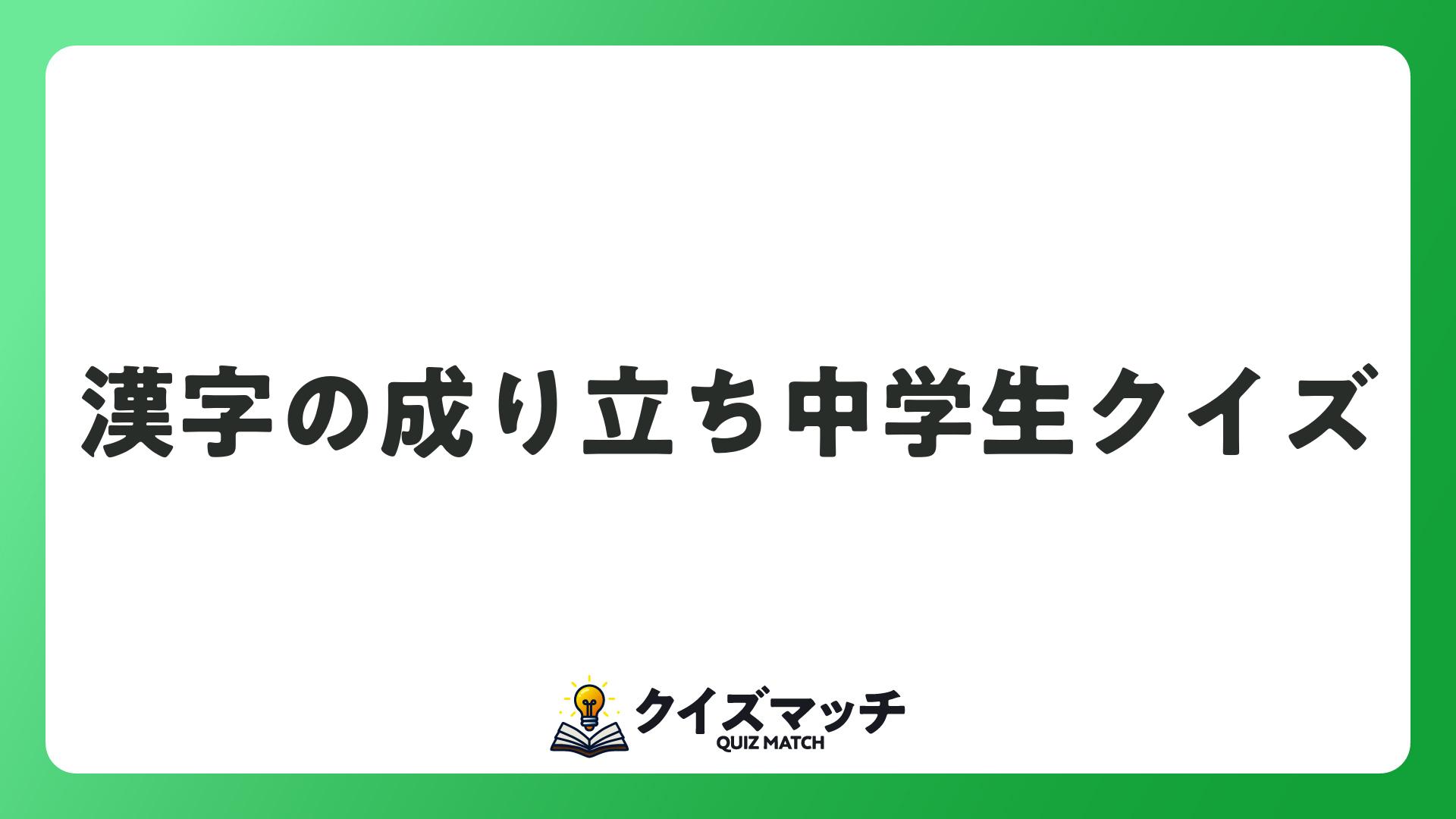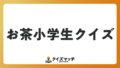漢字の成り立ちを知ろう!中学生クイズに挑戦しよう
漢字は単なる文字の集まりではありません。実は、その成り立ちには深い歴史や工夫が隠されているのです。今回のクイズでは、漢字の6つの造字法をはじめとする、漢字の成り立ちについて学んでいきます。漢字の成り立ちを理解することで、単なる覚え方ではなく、漢字の意味や成り立ちを体系的に捉えることができるはずです。中学生の皆さん、漢字の深い世界に迫っていきましょう。
Q1 : 既存の同音字を借りて全く別の意味を表す造字原理を何というか。
仮借(かしゃ)とは、当時まだ文字が無かった語を表記するために、発音が似た既存の漢字を『借りて』用いる方法で、六書の一つ。例えば『来』は本来『麦が実る』意味の象形文字だったが、後に『くる』の読みを表すために流用され、元の意味は『麦』の新字『麦』に譲った。同様に『我』『以』『南』なども仮借の例である。仮借は音を優先し意味を後付けする点で形声と混同されやすいが、仮借では字形の中に意味を示す意符が存在しない。古代中国語表記の柔軟さと、多義的な字が生まれる仕組みを理解するうえで重要な概念である。
Q2 : さんずい+工から成る「江」は、六書のどの種類か。
「江」は水を示すさんずい偏が意味を担当し、右側の『工』が『こう』という音を示すことで、全体で『大きな川』を意味する字になった。意味を担う意符と音を担う音符を組み合わせる造字法は形声文字と呼ばれ、全漢字の七〜八割を占める最も多いタイプである。形声は意味と発音の両方を一度に示すことができるため、新語が増えた戦国時代以降に大量に作られた。「江」はその代表的な初期例で、『工』が音を提供する一方、意味は左側の水部が明確に示している。
Q3 : 水平線の上に短い線を置いた「上」という漢字はどの造字法か。
「上」は甲骨文では地面を示す長い横線の上に短い縦棒を突き出す形で刻まれており、『基準線より上方』という抽象的な位置関係を記号的に表した。物の形そのものではなく、線と点で方位や数量など概念を指し示す造字法を指事文字という。指事には『下』『本』『一』『二』などが含まれ、日常で使う基本概念を簡素な記号で示すのが特徴。象形や会意と違い、絵としての連想が難しい分、意味を理解するには基準線が何かを意識する必要がある。
Q4 : 次のうち、もともと「垂れ下がった稲穂」の形を象った象形文字はどれか。
『禾』は甲骨文では根元から伸びる茎と、上部に垂れた穂を細かい点で表した図で、収穫期の稲を真横から見た姿をそのまま描いている。古代中国では穀物は生活の中心であり、稲や麦を表す漢字が早い段階で作られた。禾はのちに部首として『秋』『税』『季』など穀物に関係する字に使われ、原義である稲・穀物を連想させる役割を果たす。一方、刀・目・言はいずれも器物や身体部位、発話を示す象形・象徴で、稲穂とは無関係である。
Q5 : 『日』と『月』を並べた『明』は六書で何に分類されるか。
『明』は、昼を照らす太陽『日』と夜を照らす月『月』という二つの光源を組み合わせ、『あかるい』という共通の性質を示した会意文字である。最古の甲骨文では左右に配置された日と月がそれぞれ大きく刻まれ、二つの要素が同じ重みで意味を担うことが視覚的に分かる。形声文字と誤解されがちだが、本来『月』は音符ではなく意味符である点が会意の決定的根拠。のちに『明らか』『説明』など抽象的な概念にも転用され、会意文字が意味拡張の土台になり得る好例といえる。
Q6 : 甲骨を割って得られる亀裂を描いた『兆』は、六書でどの造字法にあたるか。
『兆』は亀甲獣骨占いで生じた亀裂を線で表し、ひび割れが未来の前兆を示すことから『きざし』の意味になった。字形は裂け目をそのまま模した抽象的な絵であり、具体物の外形を写し取って作られる象形文字の一種である。古代人にとって占いの結果を記録することは政治と宗教に直結し、兆の字は殷周期の甲骨文に頻出する。その後、『兆候』『億兆』など数量や比喩を示す語にも派生し、象形文字が時代とともに意味を拡張する過程をよく示している。
Q7 : 『借』は人偏と『昔』から成り、他人から物をかりる意味を表す。六書では何文字か。
『借』は左側の亻(人偏)が『人間の行為』を示す意符、右側の『昔』が『しゃく』という音を示す音符として機能し、両者が結合して『かりる』という動作を表す形声文字である。古代の形声文字は『意符+音符』の配置が一定せず、金文では右が音符、左が意符という例が多い。借では『昔』自体に『かりる』の意味はなく、専ら発音を提供している点が会意文字との違い。音符の語頭子音が似通う字を組み合わせることで、新たな概念でも発音を類推できるようにした古人の工夫がうかがえる。
Q8 : 人偏と『言』で構成される『信』は本来どの造字法で作られたか。
『信』は左側の人偏が『人』、右側の『言』が『ことば』を意味し、『人の言葉はまことだ=まかせる・信用する』という概念を表す会意文字である。甲骨文や金文の字形を見ると、人物を正面から描いた図の横に口を強調した形が配されており、音符としての機能はほぼ確認されない。のちに発音が似る『伸』『紳』などが『申』を音符とする形声文字として増えたが、信の字は意味合成が先で音は後付けだったと考えられる。結果として『信頼』『通信』など現代語にも連なる中心概念が生まれた。
Q9 : 「山」という漢字の成り立ちとして正しいものはどれか。
「山」は甲骨文の段階から三つの峰が連なる稜線をそのまま描いた絵を基にして作られた。古代人は実際の対象を写し取ることで意味を示し、音は後から当てはめた。こうした造字法は六書で象形文字と呼ばれ、川・月・鳥など自然物や生き物の名称を中心に用いられた。象形は『姿を描く』という単純な方法ゆえに、最も古く基本的な造字原理と位置づけられ、多くの中学生が最初に学ぶ成り立ちの代表例である。
Q10 : 「休」は人と木を組み合わせて作られた漢字である。この字を六書の分類で表すと何に当たるか。
「休」は、左側の亻(人偏)が『人が立つ姿』、右側の木が『樹木』を示し、『人が木に寄りかかってひと休みする』という状況を二つの図形要素で同時に表現している。このように、複数の部品の意味を組み合わせて新しい概念を示す造字法を会意文字という。会意は『体』『明』『森』など、部品の意味が合わさって全体の意味が生じる文字に多用される。なお、形声との違いは、右側が音符ではなく意味素である点で、休の場合は『木=きゅう』という読みを示す目的ではない。
まとめ
いかがでしたか? 今回は漢字の成り立ち 中学生クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は漢字の成り立ち 中学生クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。