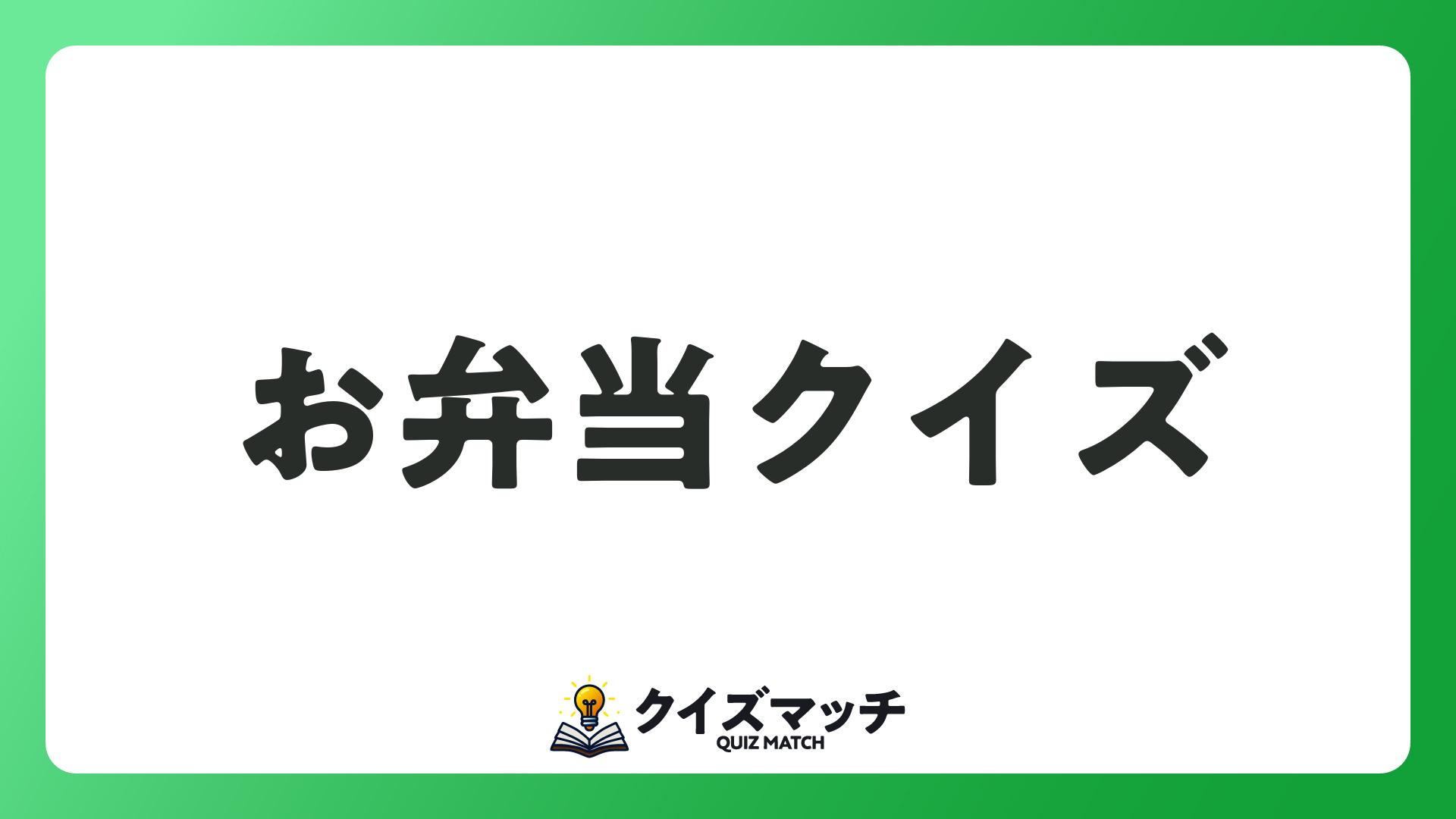お弁当ってみんなが大好きですよね。毎日の楽しみになっていることでしょう。でも、お弁当にはそれぞれ歴史や秘話が隠されているんです。今回のクイズでは、そんなお弁当の知られざる一面を探っていきましょう。幕の内弁当の由来や、日本初の駅弁の舞台となった駅、のり弁のアクセントになる揚げ物のこと…etc. お弁当にまつわる様々な雑学が満載です。ぜひ、クイズに挑戦して、お弁当の深いところにも注目してみてくださいね。
Q1 : 自然解凍OKの冷凍おかずを弁当に入れる際、安全とされる中心温度に達する推奨時間は?
自然解凍OKの冷凍おかずは、製造時に加熱殺菌と急速凍結を行い、解凍途中で危険温度帯に長時間留まらないよう設計されている。多くのメーカーは室温約20℃で1.5〜2時間で中心温度が0〜5℃となり、昼食時までに食べ頃の状態になることを想定している。30分では凍結が残り、4時間以上常温に置くと細菌増殖の恐れがあるため、弁当箱に詰めてから2時間以内の解凍が推奨される。
Q2 : のり弁当の定番として入ることが多い揚げ物は次のうちどれ?
のり弁は白飯にかつお節としょうゆをまぶし、その上に海苔を敷き、さらに揚げ物を載せる庶民的弁当で、1970年代の持ち帰り弁当店の普及とともに定番化した。揚げ物には安価で淡白なタラやホキなど白身魚のフライを用い、ソースが染みても衣がはがれにくい利点がある。鮭なども入る場合はあるが、白身魚フライが「のり弁の顔」として最も一般的である。
Q3 : 弁当の食中毒を防ぐために注意すべき危険温度帯として厚生労働省が示す範囲は?
細菌が最も増殖しやすい温度帯を危険温度帯と呼び、厚生労働省の大量調理施設衛生管理マニュアルでは約20〜50℃を該当範囲として警告している。弁当は調理後できるだけ早く粗熱を取り、10℃以下または65℃以上で保管すればリスクを大幅に下げられる。夏場に常温放置すると短時間で20℃を超え、黄色ブドウ球菌などが急増するため特に注意が必要である。
Q4 : キャラ弁でピンク色を出すためによく用いられる天然素材は?
キャラ弁は彩りが命で、赤系の発色にはビーツ、紅麹、梅肉などが重宝される。ビーツに含まれる天然色素ベタシアニンは熱に比較的強く、ゆで汁やパウダーを少量混ぜるだけでご飯や薄焼き卵を鮮やかなピンクに染められる。竹炭は黒、ほうれん草は緑、ウコンは黄色を出す素材なので、ピンク色を目的とする場合には適さず、ビーツが代表格となる。
Q5 : 駅弁「峠の釜めし」を製造・販売している企業はどこ?
峠の釜めしは1958年に群馬県横川駅で荻野屋(現おぎのや)が発売した陶器の釜入り駅弁で、具材とご飯を一度に温かく提供できる工夫が評判を呼び国民的ヒットとなった。栗、鶏肉、筍、牛蒡、椎茸、グリーンピース、杏など彩り豊かな具材と、秘伝のだしで炊き上げたコシヒカリを詰め、食べ終わった釜は土鍋として再利用できる点も土産需要につながった。
Q6 : ハワイで定着している弁当スタイルで、定番の主食とされるものは?
ハワイでは日系移民の影響で弁当文化が定着し、現地ではBentoやspam musubiとして親しまれている。特にスパムむすびは、缶詰ハムのスパムを甘辛タレで焼き、ご飯に乗せて海苔で巻いた携帯食で、第二次大戦中に軍の配給品として流入したスパムを有効活用したのが始まりとされる。今やコンビニやプレートランチ店でも定番で、弁当文化の象徴的存在となった。
Q7 : アルミ製弁当箱の特徴として誤っているものはどれ?
アルミ製弁当箱は熱伝導率が高く冷ましやすい、変質やにおい移りが少ない、オーブントースターで再加熱できるなど調理・衛生面の利点がある。しかし金属なので電子レンジのマイクロ波を反射し火花放電を起こす危険があるため使用禁止とされる。レンジ対応を求める場合はポリプロピレンや樹脂製を選ぶ必要があり、この点が唯一の大きな弱点と言える。
Q8 : 江戸時代に行楽のお供として普及した籠入りの箱型弁当は何と呼ばれる?
行楽弁当は遊山や花見など屋外娯楽の広まりとともに発展し、特に江戸の庶民が桜の下で味わった花見弁当は、重箱や籠に色とりどりの料理を詰めて春の訪れを祝う習慣として定着した。重詰にすることで料理が崩れにくく、複数人で取り分けることができる。俳句や浮世絵にも花見弁当の描写が多く、行楽弁当の象徴として現在も料亭やデパ地下で販売されている。
Q9 : 幕の内弁当の名前の由来として最も支持される説は次のうちどれ?
幕の内弁当は江戸時代、芝居見物の際に幕間で腹を満たす酒肴として売られたのが始まりとされる。「幕の内」とは舞台の幕の内側でなく、芝居の幕と幕の間に食べたことを指すという説が広く知られ、学術的・資料的にも最も有力とされている。他説もあるが裏付けが乏しい。
Q10 : 駅弁の元祖とされ、日本初の駅弁が売られた駅はどこ?
1885年(明治18年)日本鉄道宇都宮駅で旅館白木屋が販売した握り飯とたくあんが駅弁第1号とされる。当時の汽車は車内販売がなく、乗客は停車中に食事を調達する必要があった。宇都宮は東北線の要衝で客も多く、冷めても食べやすい握り飯を笹の葉で包んだ弁当が好評を博した。諸説はあるが業界団体もこの説を採用している。
まとめ
いかがでしたか? 今回はお弁当クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はお弁当クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。