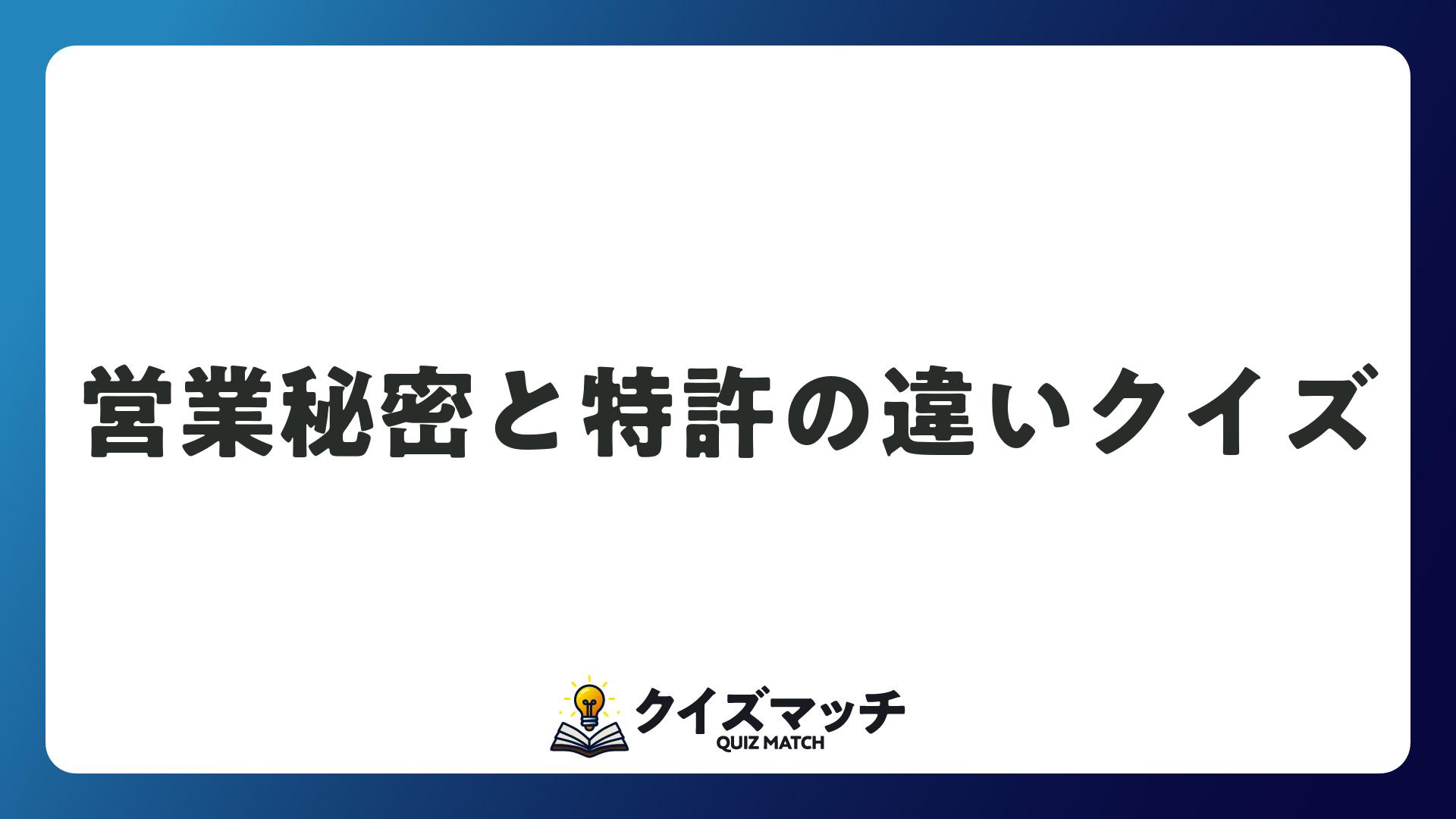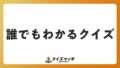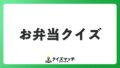営業秘密と特許は、企業における知的財産を保護する重要な制度ですが、その違いは微妙です。この記事では、営業秘密と特許の違いに関するクイズを通じて、両者の特徴や使い分けのポイントを掘り下げて解説します。営業秘密は非公開性と社内管理を前提とした制度ですが、特許は一定期間の独占権を代償に公開を求める制度です。これらの違いが企業の競争力や製品開発戦略に大きな影響を及ぼします。本クイズでは、両者の要件、期間、救済手段などの相違点を深く理解することができます。知的財産の活用を検討する際の重要な判断材料となるはずです。
Q1 : 特許出願を行わずに発明をウェブサイトで事前公開した場合、通常どのような結果になるか?
特許法29条は『出願前に公知となった発明は新規性を欠く』と定めており、ウェブで公開すると自己開示であっても原則として特許取得は不可能になります(6か月の例外は限定的)。公開情報は非公知性を失うため営業秘密としても保護の対象外です。よって事前公開は特許と営業秘密の両面で致命的ダメージを与える可能性があります。研究成果の公開前には出願や秘密保持措置を講じることが極めて重要です。
Q2 : 企業が営業秘密を実務上保護するために最も一般的に採用する方法はどれか?
営業秘密は登録制度ではなく、秘密管理性を自社で確保することが要件です。そのため企業は秘密保持契約(NDA)の締結、権限設定、入退室管理、情報の暗号化、教育など多層的な内部統制を行います。特許庁やWIPOへの出願は公開につながり営業秘密保護と矛盾しますし、官報掲載は情報を公知化してしまいます。したがって契約と技術的・組織的管理措置こそが営業秘密維持の核心となり、特許制度とは根本的に異なります。
Q3 : 日本では産業上利用可能性の観点から特許の客体とならないが、営業秘密として保持することは可能な技術分野はどれか?
特許法32条の解釈により人体に対する外科的手術など医療行為は『産業上利用可能性』を欠くとされ特許対象外です。しかし手術手技の詳細を機密として管理すれば営業秘密として保護可能です。製造プロセスや化学物質は特許でも守れますし、ビジネス方法も技術的手段を伴えば審査対象になり得ます。よって医療手術方法は『特許不可だが秘密管理で守れる』典型例となり、営業秘密の柔軟性を示しています。
Q4 : 公開タイミングに関する次の記述のうち、正しいものはどれか?
特許法64条は『特許出願は出願の日から1年6月を経過した後、特許庁長官はこれを公開する』と規定し、18か月で公開公報が発行されます。一方、営業秘密はそもそも行政機関への提出を必要としないため公開の仕組みがなく、公開すると保護が消滅します。特許が公開を制度の前提とし、営業秘密が非公開を前提とするという対照は、両制度の選択を検討する際の重要な判断材料になります。
Q5 : どの状況が営業秘密よりも特許による保護を選択すべき典型的ケースと評価されるか?
製品に組み込まれた技術が分解や試験で簡単に把握できる場合、秘密管理をしても競合が模倣するリスクが高く、営業秘密としての実効性は低下します。そのような技術は公開されても排他権が得られる特許の方が効果的です。逆に逆解析が困難な技術、社内のみで用いられるプロセス、顧客リストのような情報は秘密保持が適しています。可視性や模倣の容易性は、特許か営業秘密かを判断する重要なファクターです。
Q6 : 営業秘密の保有者が学会発表で誤って情報を公表してしまった場合、直ちに発生する法的リスクとして最も正しいものは?
営業秘密は公知となると不正競争防止法上の保護対象から外れます。学会や展示会で誤って内容を開示すれば非公知性が消滅し、侵害訴訟で営業秘密として主張できなくなります。特許についても、出願前の自己開示は原則新規性喪失となり権利取得が困難です(6か月の救済も限定的)。つまり、うっかり公開は営業秘密にも特許にも甚大なダメージを与えるため、情報公開前の出願手続や秘密保持措置の徹底が不可欠です。
Q7 : 営業秘密として保護を受けるために不公知性、秘密管理性、有用性の3要件が必要とされます。次のうち、この3要件に含まれないものはどれ?
営業秘密は、不正競争防止法2条6項で①秘密管理性(管理された情報であること)、②非公知性(公知でないこと)、③事業活動に有用であることという三要件が必要です。特許で要求される「新規性」は営業秘密の要件ではありませんが、特許では絶対的に必要です。さらに、営業秘密は不正競争行為に対して差止めや損害賠償の救済が用意されていますが、国から付与される権利ではなく登録も審査も不要です。したがって自社による厳格な管理努力が不可欠になる点が特許との大きな違いです。
Q8 : 公開を前提に独占排他権を与える制度はどれか?
特許制度は発明を公開する代わりに20年間の排他的権利を付与する公開代償型の制度です。出願書類は原則18か月で公開され誰でも閲覧可能になりますが、その公開と引き換えに権利者は製造・販売を独占できます。営業秘密は非公開を維持することでしか保護されず、公的登録は存在しません。ノウハウライセンス契約や秘密保持契約は私法上の契約であり、国家が排他権を付与するものではありません。したがって公開を前提とするのは特許のみです。
Q9 : 日本の特許権の存続期間として正しいものは?
特許法67条1項は特許権の存続期間を『出願の日から20年をもって終了する』と規定しています。医薬品などは最大5年の期間延長が認められますが、基本は20年です。他方、営業秘密には期間の上限がなく、秘密が保持される限り理論上は半永久的に保護が続きます。つまり特許は公開を代償に期間限定の独占を得る制度であるのに対し、営業秘密は非公開と管理を条件に期間制限なく競争優位を維持できる点が大きな相違点となります。
Q10 : 次のうち、特許権侵害では利用できても営業秘密侵害では制度が用意されていない救済手段はどれか?
特許権者は関税法に基づき税関に侵害物品の輸入差止を申し立てることができます。これにより海外からの模倣品流入を水際で阻止でき、権利行使の実効性が高まります。一方、営業秘密については不正競争防止法に民事差止や損害賠償、刑事罰はありますが、現行法には税関での輸入差止制度が整備されていません。したがって海外からの流入対策は特許で強力に機能する一方、営業秘密では別途契約や技術的管理で対処せざるを得ないという違いがあります。
まとめ
いかがでしたか? 今回は営業秘密と特許の違いクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は営業秘密と特許の違いクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。