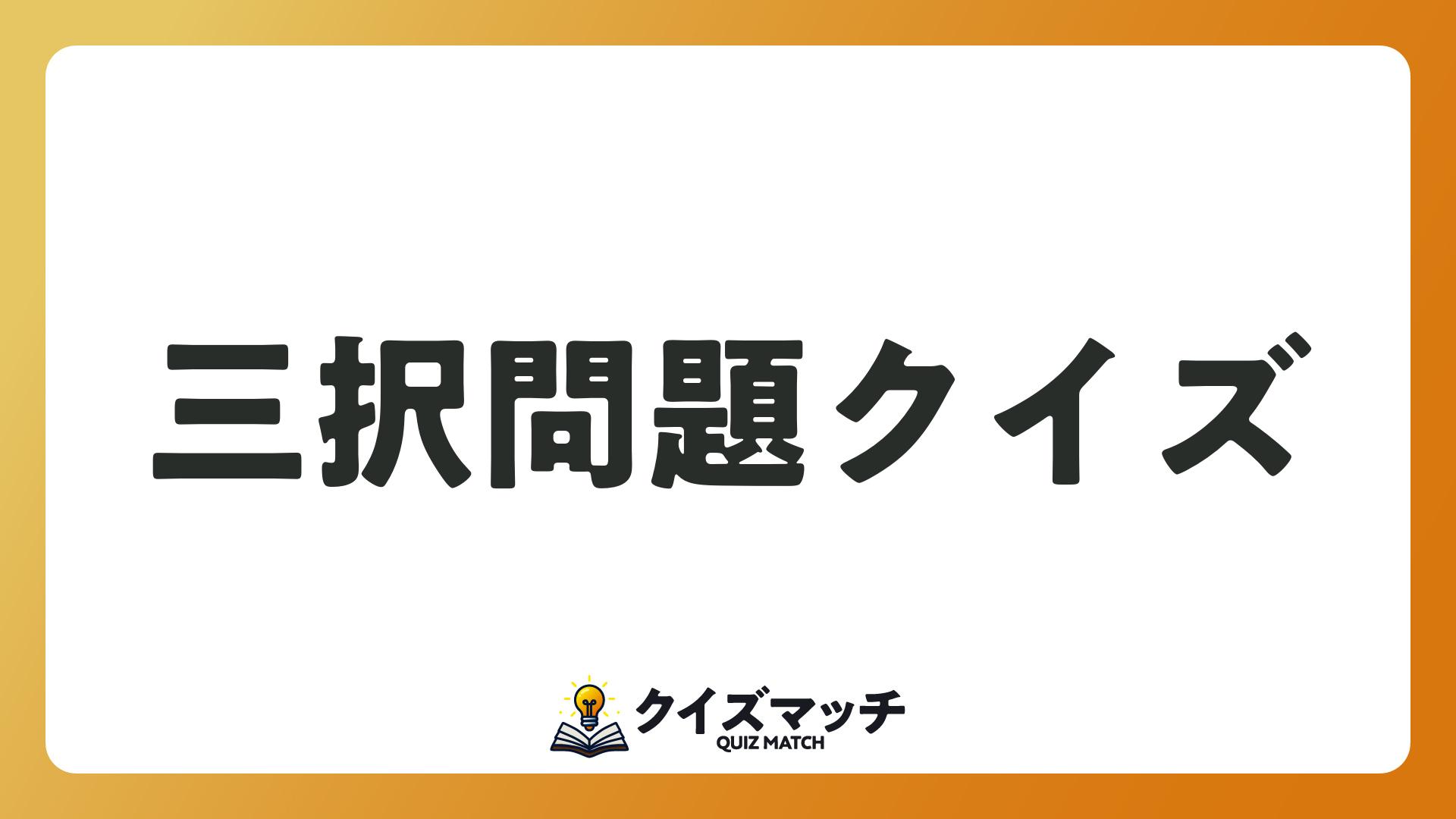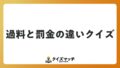近代社会の礎を築いたフランス革命、DNAやRNAの塩基の違い、光の性質、ギリシャ神話の女神たち、経済学の需要弾力性、ベートーヴェンの交響曲の代表作、世界三大瀑布、ノーベル賞の二冠達成者、囲碁のコミ制度など、枚挙にいとまのない知的好奇心を掻き立てる三択クイズを集めました。歴史、科学、文化の広範囲にわたる雑学の中から、思わず「ああ、そうだったのか」と唸らされるはずの問題が10問用意されています。思わぬ落とし穴にご注意ください。知識の幅を広げ、頭の体操をしていただければ幸いです。
Q1 : 次の人物のうち、異なる分野でノーベル賞を2度受賞した科学者は誰?
マリー・キュリーは1903年に放射能の研究で物理学賞を夫ピエール・キュリー、アンリ・ベクレルと共同受賞し、1911年にはラジウムとポロニウムの化学的性質の解明で化学賞を単独受賞した。異なる分野で二度受賞した初めての人物である。ワトソンはDNA二重らせん構造解明で生理学医学賞を一度、ファインマンとディラックはそれぞれ量子電磁力学や量子力学の功績で物理学賞を一度ずつ受賞したにすぎないため、本問の正答はマリー・キュリーとなる。彼女の業績は医学や原子力の発展にも大きな影響を与えた。
Q2 : 囲碁において白番が後手の不利を補うために与えられるコミは、現在主流の日本ルールでは何目半?
囲碁では黒が先手で有利になるため、白番にハンディキャップとしてコミが与えられる。日本棋院や主要国際棋戦では1991年以降6目半が標準となり、終局後に白に6.5ポイント加算して勝敗を決める。小数点以下の半目は引き分けを防ぐ目的で導入される。かつては5目半や4目半などが用いられた時期があり、中国ルールでは7目半が主流だが、現在の日本ルールでは6目半が一般的であるため正解となる。コミの変遷を知ると囲碁史やルール差の理解が深まる。
Q3 : 同じ分子式を持ちながら原子の結合順序や空間配置が異なる化合物同士の関係を示す用語は?
異性体は同一の分子式であっても原子の結合順序や三次元配置が異なるため、化学的・物理的性質が大きく変わる化合物群を指す。構造異性体は結合の並び方が違い、立体異性体にはシス・トランス、光学異性体などがあり、医薬品の選択的作用や材料の特性にも大きく影響する。同素体は元素単体での結晶構造の違い、同位体は中性子数の違いによる核種の区別、異方体は光学や結晶学の性質を表す用語であり本問の概念とは異なる。従って正解は異性体である。
Q4 : DNAの4種類の塩基のうち、DNAには含まれずRNAにのみ現れるものはどれ?
DNAを構成する塩基はアデニン、チミン、グアニン、シトシンの4種で、チミンの代わりにRNAではウラシルが用いられる。したがってDNAにはウラシルは本来含まれない。化学的にはウラシルはメチル基の有無でチミンと区別され、DNA損傷検出や転写の鋳型識別に重要な役割を果たす。選択肢のアデニン、シトシン、グアニンはプリンあるいはピリミジン塩基としてDNAとRNAの双方に存在するため誤答となる。
Q5 : 可視光の中で波長が最も短くエネルギーが最も高い色はどれ?
光は波長が短いほど周波数が高くエネルギーも大きくなる。可視光では長波長側から赤、橙、黄、緑、青、藍、紫と続き、紫がほぼ可視域の短波長端に位置する。紫外線に近接しているため、物質に与える刺激やフォトン1個当たりのエネルギーが大きく、蛍光や光化学反応を引き起こしやすい。逆に赤は波長が最長でエネルギーが低い。選択肢の中では紫が最も波長が短くエネルギーが高いため正解となる。
Q6 : ギリシャ神話で、太陽の光を司る神アポロンの母とされる女神は誰?
ギリシャ神話ではアポロンと双子の女神アルテミスを産んだ母親はレトである。ゼウスとの間に子を宿した彼女は正妻ヘラの怒りを買い、出産場所を探して長い放浪を強いられた。最終的にエーゲ海の浮島デロスで双子を生み、島は固定され聖地となった。アテナは知恵と戦略の女神、ヘラはゼウスの正妻で結婚の神、アフロディテは愛と美の女神であり、いずれもアポロンの母ではない。レトの逸話はギリシャ神話の迫害と救済を象徴し、アポロン信仰の起源を語る重要なエピソードである。
Q7 : 経済学で「需要の価格弾力性」が1より大きいときの需要の性質を表す言葉は?
需要の価格弾力性は価格が1%変化したときに需要量が何%変化するかを示す指標で、絶対値が1より大きい場合は需要量の変化率が価格変化率を上回る。これを弾力的需要と呼ぶ。例えば贅沢品や代替品が多い財では価格が下がると需要が大きく増え、価格が上がれば急激に減るため弾力的需要となりやすい。逆に1より小さい場合は非弾力的、ちょうど1の場合は単位弾力的と呼ばれ、ギッフェン需要は特殊な例で価格と需要が同方向に動く現象である。したがって1より大きい場合は弾力的需要が正答となる。
Q8 : ベートーヴェンの交響曲で『運命』の愛称で親しまれているのは第何番?
交響曲第5番ハ短調作品67は冒頭のタタタターンという4音動機で広く知られ、日本では『運命』の愛称で呼ばれる。1808年のウィーン初演以来、ベートーヴェンの革新的な構造と動機労作の象徴とされ、ロマン派への橋渡しとなった。第3番は『英雄』、第7番はリズムの盛り上がりが特徴でワーグナーが舞踏の神化と称賛、第9番は合唱付き『歓喜の歌』である。ゆえに『運命』を示すのは第5番であり、時代背景や作曲家の苦悩を想起させる代表作として位置付けられる。
Q9 : 世界三大瀑布の一つでブラジルとアルゼンチンの国境に位置する滝はどれ?
世界三大瀑布は北米のナイアガラ、アフリカのビクトリア、南米のイグアスを指す。イグアスの滝はアルゼンチンとブラジルの国境を流れるイグアス川が240以上の支流に分かれ落下する巨大な連瀑布で、最大落差は約80m、幅は2.7kmにも達する。轟音と水煙を上げる主瀑はガルガンタ・デル・ディアブロ(悪魔の喉笛)と呼ばれ、双方の国立公園はユネスコ世界遺産に登録された。ナイアガラとビクトリアは別大陸、エンジェルフォールはベネズエラの世界最高落差の単独滝であるため本問の正解ではない。
Q10 : フランス革命が始まった年は?
フランス革命は旧体制を覆し近代市民社会へと移行する契機となった世界史の大事件で、1789年7月14日のバスティーユ襲撃が象徴的な開幕として語られる。啓蒙思想や財政難、第三身分の不満が重なって蜂起が広がり、人権宣言の採択、王政の崩壊、ナポレオンの台頭へと続く激動の端緒となった。この年を覚えておくと近代史の年号の基準点を作れる。1812年はナポレオンのロシア遠征、1848年は欧州革命、1917年はロシア革命の年でありいずれもフランス革命そのものではない。
まとめ
いかがでしたか? 今回は三択問題クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は三択問題クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。