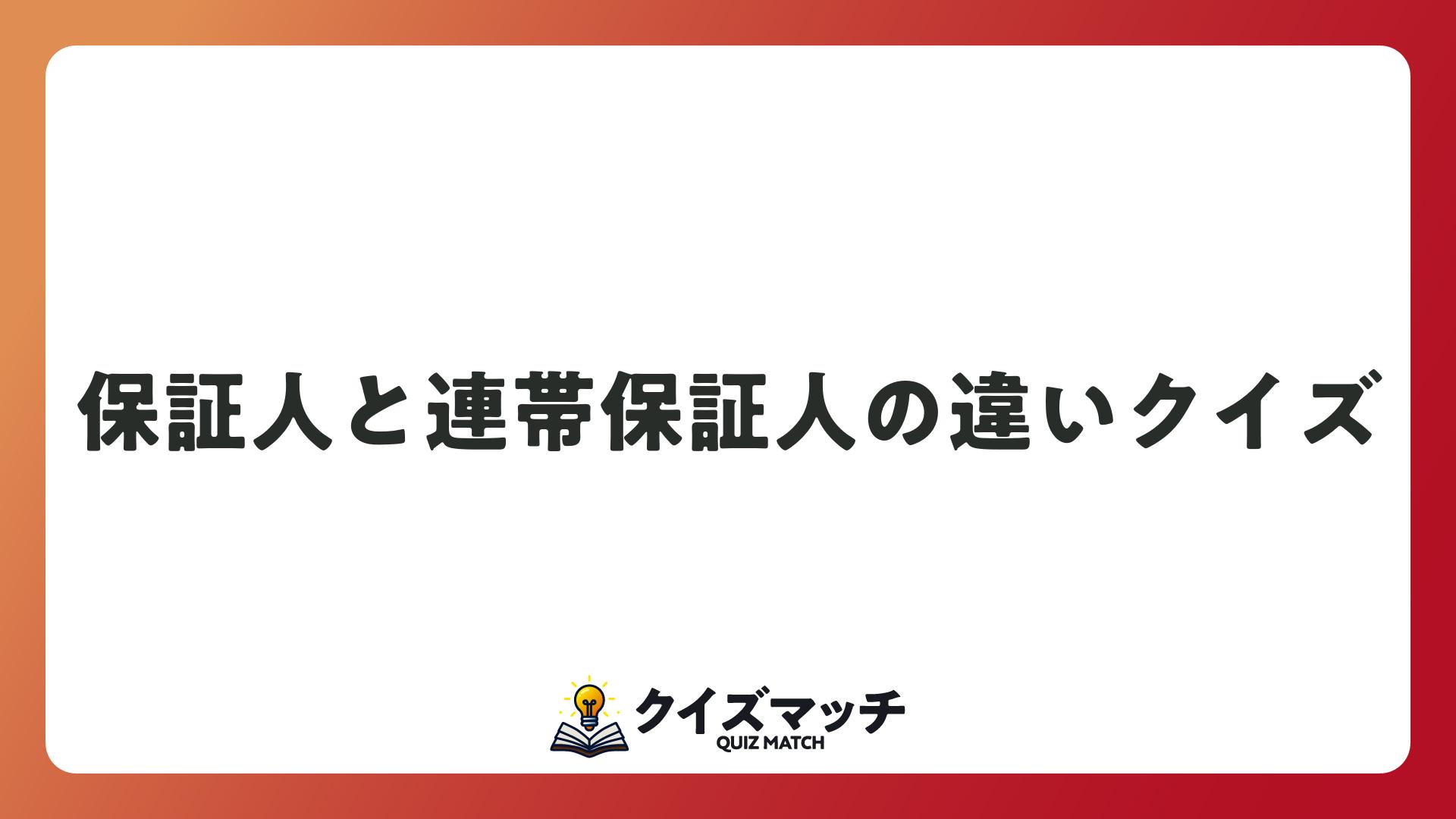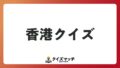金銭を借りる際、保証人や連帯保証人を立てることは一般的ですが、その違いをよく理解していないと、予期せぬリスクを引き受けてしまうことがあります。本記事では、保証人と連帯保証人の違いに関する10問のクイズを通して、それぞれの特徴や法的責任の差異を詳しく解説します。例えば、連帯保証人には認められない抗弁権や、弁済後の求償権の違いなど、保証形態によって大きな法的効果の差異が生じることを確認できます。保証契約を検討する際は、このクイズで自分のレベルを確認し、リスクを正しく理解しましょう。
Q1 : 次のうち連帯保証人でも行使できる権利はどれか。
相殺の抗弁権は主債務と反対債権との相殺を主張して債務を消滅させる権利で、連帯保証人にも保証人にも認められている。これに対し催告の抗弁、検索の抗弁、分別の利益は通常の保証人にのみ認められ、連帯保証人には認められない。つまり連帯保証人は弁済の場面で主債務者とほぼ同一の防御方法しか持たず、債権者に対する立場が極めて弱い点が特徴である。
Q2 : 個人が保証契約を締結する際、書面に必ず明示しなければ契約が無効となる事項はどれか。
2020年施行の改正民法465条の2により、個人が保証契約を締結する場合には「極度額」を書面または電磁的記録に明示することが義務付けられた。極度額とは保証人が負う債務の上限額を示すもので、これが記載されていないと契約は無効になる。保証期間や返済計画自体の記載は義務ではないし、契約書に「連帯保証を拒否できる」旨を入れても法律上の効力は限定的である。極度額を明示することで保証人の無限責任を防ぐのが改正の狙いである。
Q3 : 検索の抗弁権が認められない場合として正しいものはどれか。
検索の抗弁権は保証人が債権者に対して「主債務者に執行してもなお弁済が得られないときでなければ自分に請求するな」と主張できる権利で、民法453条に定められている。しかし連帯保証の場合は民法454条で明文により排除されているため、連帯保証契約が存在するだけでこの抗弁権は行使できなくなる。主債務者の破産などは検索抗弁が否定される別のケースだが、連帯保証という契約形態そのものが権利を奪う点が保証人との大きな差である。
Q4 : 保証人が弁済した後の求償に関する説明として正しいものはどれか。
保証人が債務を弁済した場合、民法459条2項により主債務者に対して求償権を取得し、弁済した全額を請求することが原則である。ただし複数の保証人が存在すれば、各保証人の負担部分(法定部分または約定割合)に応じて調整される。一方連帯保証人が全額弁済した場合も主債務者に全額求償できるが、他の連帯保証人がいればその持分に応じて負担分を請求することになる。負担割合の理解は、弁済後の資金回収計画に直結する。
Q5 : 主債務が時効消滅した場合の保証人・連帯保証人の責任について正しい結論はどれか。
主債務が消滅時効にかかった場合でも、保証債務は附従性のため一緒に消滅するわけではなく、保証人・連帯保証人が自ら時効を援用しなければ責任を免れない(民法145条)。援用権自体は両者に認められているので、連帯保証人も主債務者と同様に時効を主張できる。しかし援用しなければ支払義務を負い続ける点が落とし穴である。保証人・連帯保証人は債権者からの催告に接したら、まず残存期間や中断事由を確認し、時効援用の可能性を検討する必要がある。
Q6 : 消費貸借契約締結前に口頭で保証の承諾をした場合の効力について正しいものはどれか。
改正民法465条の6では、個人が保証契約を締結する場合、書面または電磁的記録によらなければ無効と定められている。法人はこの制限を受けないため、事前に口頭で承諾した保証契約でも有効となる。したがって、消費貸借契約前に口頭で個人が保証人や連帯保証人になると約束しても法的効力は生じない。契約の成立要件を満たさなければ債権者は個人保証人に請求できず、保証人側は不用意な「一言」で責任を負うリスクを回避できる。
Q7 : 債権者の情報提供義務に関する説明として正しいものはどれか。
改正民法458条の2により、保証人または連帯保証人が債務残高や履行状況を質問したとき、債権者は遅滞なく書面または電磁的記録で回答する義務を負う。この情報提供義務は両者に等しく認められており、いずれか一方だけに限定されない。債権者が正確な情報を示さなかった場合には損害賠償責任を負う可能性もある。保証人等がリスクを把握しやすくすることで、過大な保証契約の締結を抑制し、適切な債務管理を促すのが制度趣旨である。
Q8 : 連帯保証人には認められず保証人のみに認められる抗弁権はどれか。
保証人には民法452条で催告の抗弁権が認められており、債権者に対し「まず主債務者に請求してほしい」と主張できる。一方、連帯保証人は民法454条で「連帯保証人は催告又は検索の抗弁を主張できない」と定められているため、この権利を持たない。その結果、連帯保証人は主債務者への請求が先になされなくても債権者から直ちに履行を求められる。違いを理解しないと負担の重さを誤認しやすいので注意が必要である。
Q9 : 連帯保証人が請求を受けた場合の責任範囲について正しいものはどれか。
連帯保証人は主債務者と「連帯して」債務を負うため、民法436条・454条により債権者は主債務者に先立って連帯保証人に全額の履行を請求し、直ちに強制執行することもできる。普通の保証人なら催告・検索の抗弁権があるので、まず主債務者の資力調査や請求を求めることができるが、連帯保証人にはそれがない。したがって連帯保証契約に署名すると、実質的には自分の借金と同じリスクを抱えることになる。
Q10 : 『分別の利益』の説明として正しいものを選べ。
分別の利益は、多数の保証人がいる場合に債権者が各保証人に対して負担部分のみ請求すべきとする制度で、民法459条に規定される。通常の保証人はこの利益を主張できるため、他の保証人と均等に負担を分けることが可能である。しかし連帯保証人は「全額について連帯して責任を負う」ことを約束しているため、この利益が否定される。したがって連帯保証人一人だけが全額を弁済させられる危険がある。
まとめ
いかがでしたか? 今回は保証人と連帯保証人の違いクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は保証人と連帯保証人の違いクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。