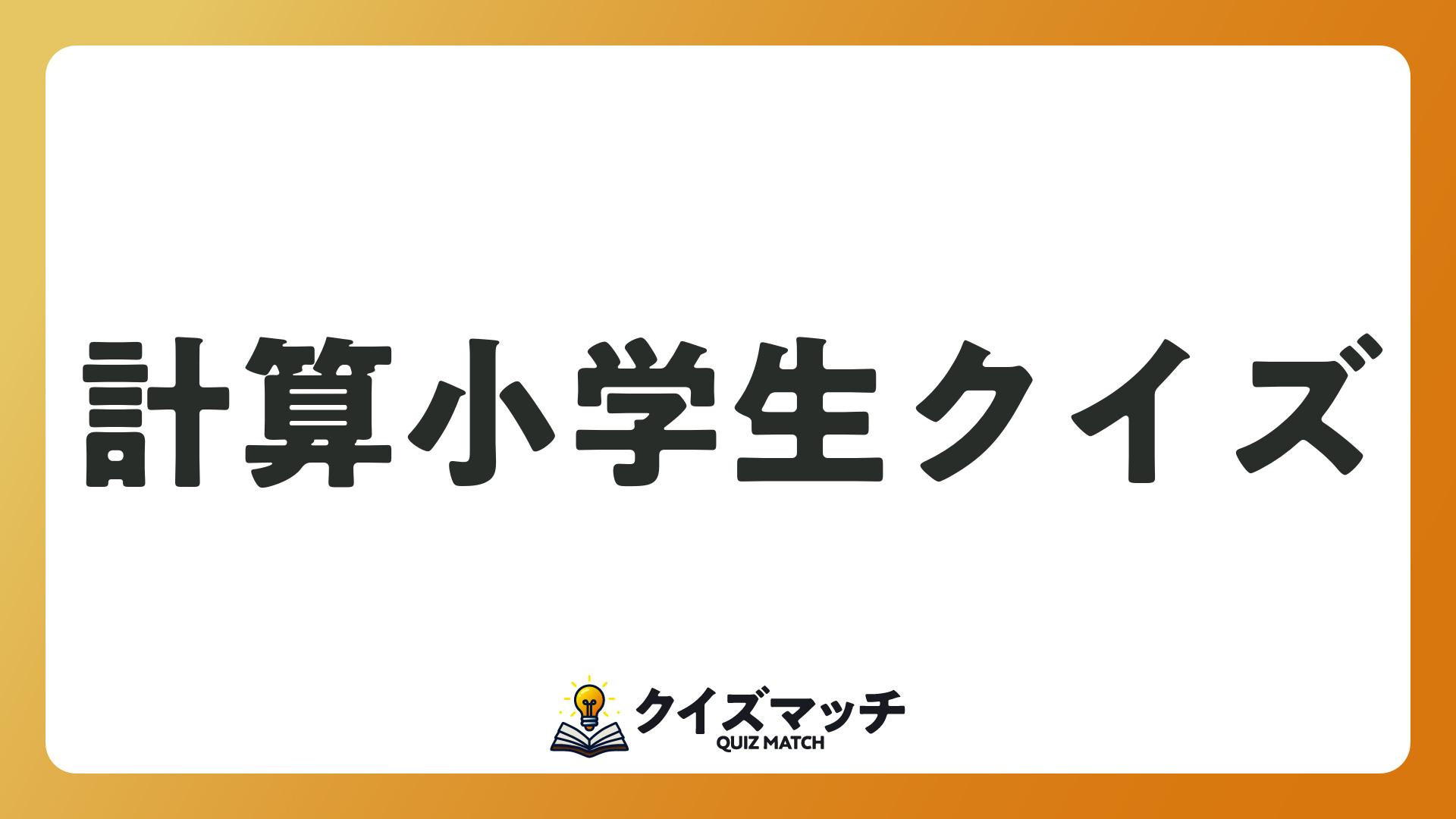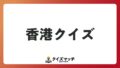小学生のみなさん、楽しい小学生クイズがいよいよスタートです! これからあなたたちの算数力を試す10問のクイズに挑戦してもらいます。計算問題や図形、割合など、小学校で学習した内容がしっかりと身についているかをチェックしましょう。楽しみながら、自分の弱点を発見し、今後の学習につなげていきましょう。解答のヒントもありますので、落ち着いて冷静に考えてみてくださいね。準備はいいですか? それでは、クイズスタート!
Q1 : 5冊で350円のノートを同じ値段で8冊買うといくら?
まず1冊の値段を求めるため350円÷5冊=70円とする。次に8冊×70円で560円が答え。比例を使う場合には5冊:350円=8冊:□円と式を立て350×8÷5=560としても同じになる。単価を出さずに350×8をして2800円にしてから5で割り忘れる、あるいは掛け算と割り算の順序を混同して550円や540円を選ぶミスが多い。買い物の実生活でも使える計算なので、場面をイメージして理解すると定着しやすい。
Q2 : 900から256と139の合計を引くといくつ?
まず256+139=395を求め、900−395を計算する。百の位からの筆算では0−5ができないため10を借り、一の位10−5=5、十の位9−9=0、百の位8−3=5で505となる。395を400−5と見て900−400=500、そこに5を足して505と工夫してもよい。繰り下がりを忘れて495や515にしてしまうミスが多いので、最後に505+395が900に戻るかどうか検算する癖をつけると確実に正答できる。
Q3 : 縦18cm横12cmの長方形の周りの長さ(周囲)は?
長方形の周囲は(縦+横)×2で求められる。18+12=30、さらに2倍して60cmが答えとなる。別の方法として18+18+12+12と4辺をすべて足しても60になる。30で止めてしまったり、縦横を掛けた面積216cm²と混同して54や72を選ぶミスが起こりがち。公式を覚えるだけでなく、実際に紙に図を書き4辺を数えると理解が深まる。単位を忘れず書くことも小テストで減点されないコツである。
Q4 : 45を6でわるといくつ?(小数第一位まで求めよ)
45÷6は両方を3で割って15÷2とすると計算が楽で、15÷2=7.5が得られる。筆算では6が45に7回入り余り3、余りを10にして小数点を立て、30÷6=5となり7.5で割り切れる。余りをそのままにして7とする、あるいは途中で近い近似値を選んで7.2や7.3にするのは典型的な誤り。分数に直せば7と3/6=7.5であることも確認できる。割り算の途中経過を丁寧に書くと正解に到達しやすい。
Q5 : 次のうち9で割り切れる数はどれ?
9の倍数判定は各位の数字の和が9の倍数になるか確認する方法が便利で、126では1+2+6=9だから条件を満たす。実際に筆算すると126÷9=14で余り0となり割り切れるとわかる。128は1+2+8=11、122は1+2+2=5、124は1+2+4=7でいずれも9の倍数ではなく、割っても余りが出る。大きな数でも同じ判定が使えるため、テストや暗算で時間を節約できる重要なテクニックである。
Q6 : 32の3/4はいくつ?
3/4倍は4で割って3を掛ける順番か、逆の順番で計算できる。32÷4=8、8×3=24で答えは24。最初に3/4を0.75として乗算しても24になる。割合の計算を足し算と混同し20や26を選ぶ間違いが多いので注意。分母と分子を約分してから計算しても良いが、手順をうっかり変えると誤差が生まれる。答えが元の数より小さくなることをイメージすると、増減の方向を早期に確認できる。
Q7 : 8×8−5×5の値はいくつ?
式には掛け算と引き算が混在しており、計算の順序で掛け算を先に済ませる必要がある。まず8×8=64、次に5×5=25を求め、64−25=39が答えとなる。もし先に8−5=3としてしまうと3×5で15など全く違う値が出るので注意。引き算では64から20を引いて44、さらに5を引くと39と分解すると暗算が速い。49や59、69は途中で数を取り違えたり繰り下がりを忘れた場合に生じやすい誤答である。
Q8 : 72÷9と14÷2の結果をたして得られる数は?
まずそれぞれの割り算を行う。72÷9は9×8=72より8、14÷2は2×7=14より7である。次に8+7=15を計算して答えを求める。はじめに72+14で86を出してから9や2で割るなど順序を誤ると正しい結果にはならない。分配法則を誤用して72÷(9+2)とするミスもありがち。個別の計算結果を紙に書き出してから足し算する手順を守れば、見落としや計算違いを防げる。
Q9 : 278+456の計算で正しい答えは?
278と456をたすときは、まず一の位の8+6=14で4を書き10をくり上げる。十の位は7+5=12にくり上がりの1を足して13となるので3を書き再び1くり上げ。百の位は2+4=6にさらに1を足して7となるから734になる。くり上がりをメモし忘れると724や744などの誤答になりやすい。計算後に734−456を行い278に戻るか検算すれば安心。位をそろえて筆算を書く習慣が正確さを高める。
Q10 : 63×7の答えとして正しいものは?
63は60と3に分けると計算が簡単で、60×7=420、3×7=21、足して441になる。筆算では7×3=21で1を書き2をくり上げ、7×6=42に2を足して44と書き441とする。くり上げの2を書き忘れると421や431、余計に足すと451になるなど典型的なミスが起きやすい。掛け算の答えが9の倍数になるかどうかでも誤りをチェックできるので、暗算後に簡単な倍数判定をすると精度が上がる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は計算 小学生クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は計算 小学生クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。