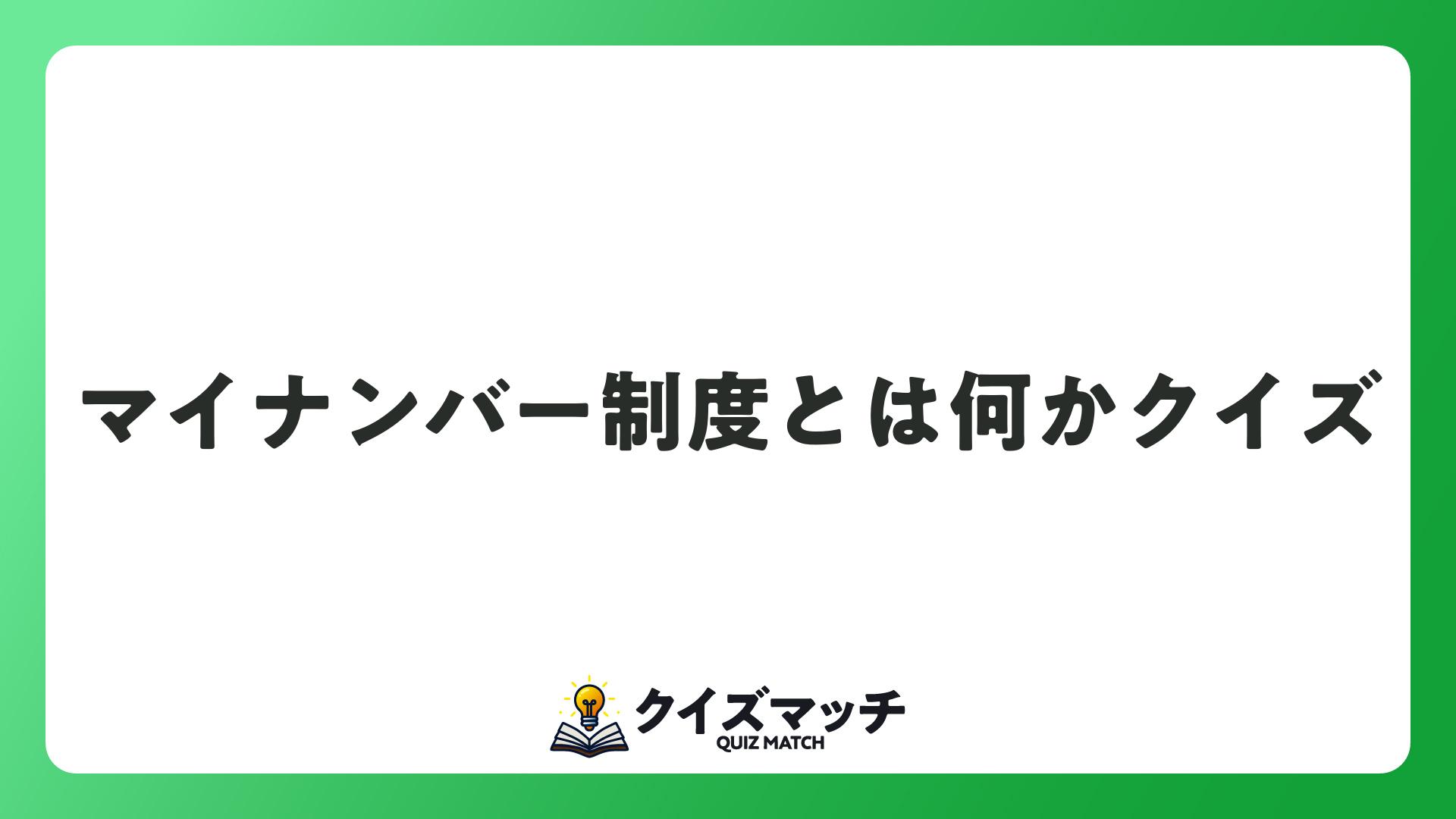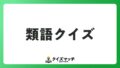マイナンバー制度は、国民一人ひとりに割り当てられる12桁の個人番号で、税・社会保障・災害対策の3分野での行政事務効率化を目的に2016年から本格運用が始まりました。このクイズでは、マイナンバーの仕組みや活用、個人情報保護などについて基本的な知識を問います。マイナンバー制度の現状と課題について、この10問を通して理解を深めていただければと思います。
Q1 : マイナポータルに関する説明として正しいものはどれか?
マイナポータルはデジタル庁が運営するウェブサービスで、利用者はマイナンバーカードとパスワードを使いログインし、行政機関が保有する本人の特定個人情報の閲覧、児童手当など各種給付のオンライン申請、情報提供等記録の確認が可能である。さらに医療費通知や年金記録なども閲覧でき、民間サービス連携も進んでいる。銀行サービスや職員向けサイトではなく、流出監視を有料で行うサービスでもない。
Q2 : 転職などで雇用先が変わる際、企業が従業員からマイナンバーを再取得する主な理由は何か?
会社は所得税源泉徴収、住民税の特別徴収、健康保険・厚生年金・雇用保険の資格取得届など、多数の法定調書を作成・提出する義務がある。番号法によりこれらの書類には従業員のマイナンバーを記載しなければならないため、採用時に本人確認と同時に番号の提供を求める。社員証や社内SNSといった任意目的で番号を使うことは原則禁止されており、福利厚生アンケートへ転用するのも番号法の目的外利用に該当し違法となる。
Q3 : マイナンバー制度が実際に行政手続で運用を開始したのは西暦何年からか?
マイナンバー制度は2013年に番号法が成立し、その後自治体・国税庁・年金機構などでシステム整備が行われた。2015年10月に通知カードが発送され番号自体は知らされ始めたが、税・社会保障・災害対策の各事務で番号を実際に記載し利用するのは2016年1月からと法律で定められている。したがって制度が本格稼働した年は2016年であり、2015年は導入準備段階、2018年はマイナポータル機能拡充などの後期フェーズである。
Q4 : 個人に付与されるマイナンバーの桁数は次のうちどれか?
マイナンバーは住民票を有するすべての人に一意に割り当てられる番号で、桁数は法律で12桁と厳格に規定されている。先頭から11桁目までは乱数等で構成され、最後の1桁はチェックデジットとして誤入力を検出するアルゴリズムが組み込まれている。12桁という長さは番号の重複を防ぎつつデータベース管理を容易にする目的で設計されており、10桁や16桁のバリエーションは存在しない。
Q5 : マイナンバー制度が当初想定している主な利用分野として正しい組み合わせはどれか?
番号法の第9条では、マイナンバーの利用範囲を社会保障、税、災害対策の三分野に限定している。社会保障では年金や雇用保険、税では確定申告や源泉徴収、災害対策では被災者支援金の迅速給付などで番号を用いる。医療や防衛、外交などは法改正が無い限り直接利用できず、金融や教育分野も現行法では対象外である。この限定的運用によってプライバシー侵害のリスクを抑えつつ行政効率を高める狙いがある。
Q6 : マイナンバーカードのICチップに物理的に記録されていない情報はどれか?
マイナンバーカードのICチップには、券面情報(氏名、住所、生年月日、性別、マイナンバー)と電子証明書、公的個人認証利用者証明用データが格納されている。また2021年以降は健康保険証利用に必要な符号も格納されるが、診療明細やレセプト内容そのものはカード内には入らない。レセプト情報は医療機関や支払基金が管理するデータベースにあり、カードはアクセスキーに過ぎないため、チップ内には保持されていない。
Q7 : 民間企業が従業員や取引先のマイナンバーを取得・利用できるのはどのようなケースに限定されているか?
番号法はマイナンバーの収集・保管・利用を厳しく制限し、民間事業者が取り扱えるのは源泉徴収票作成、健康保険・厚生年金・雇用保険などの社会保険手続、報酬支払調書作成といった法令で義務付けられた事務に限られる。マーケティングや社内IDなど任意用途は本人同意があっても許されず、違反すると行政指導や罰則の対象となる。こうした限定利用により目的外使用と漏えいリスクを最小化する設計となっている。
Q8 : 紙製の『通知カード』が新規発行を終了したのは何年5月か?
通知カードはマイナンバーを住民に知らせるために2015年から郵送されていたが、マイナンバーカード普及促進と個人情報保護強化を目的に2020年5月で新規発行が終了した。以後は出生や転入で番号を付番された場合、住民には個人番号通知書(番号のみを記載し写真なし)が交付される仕組みに切り替わった。既存の通知カードは記載事項が最新であれば引き続き本人確認書類として利用可能だが、住所変更などで記載が異なると失効扱いとなる。
Q9 : 次のうち、現行法上マイナンバーの利用対象に含まれていないものはどれか?
パスポートの発給業務は外務省管轄の旅券法に基づき行われ、番号法上の利用事務ではないためマイナンバーは求められない。一方、年末調整や雇用保険資格取得届は税・社会保障分野に該当し番号記載が義務化されている。災害時の被災者支援金請求も災害対策分野として番号利用が想定されており、自治体が迅速に被災状況と給付履歴を照合できる。したがってパスポート申請のみが利用対象外である。
Q10 : マイナンバーを含む特定個人情報の監督を行う独立組織はどれか?
個人情報保護委員会は内閣府の外局として設置された三条委員会で、マイナンバーを含む特定個人情報の取り扱いを監督する権限を持つ。行政機関や地方公共団体だけでなく民間事業者も監視対象で、立入検査、勧告、命令、罰則適用の権限がある。番号法に違反した漏えい事案が生じた場合には報告徴求や是正命令を行い、国民のプライバシー権を保護する役割を担う。他の選択肢はマイナンバー専管の監督機関ではない。
まとめ
いかがでしたか? 今回はマイナンバー制度とは何かクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回はマイナンバー制度とは何かクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。