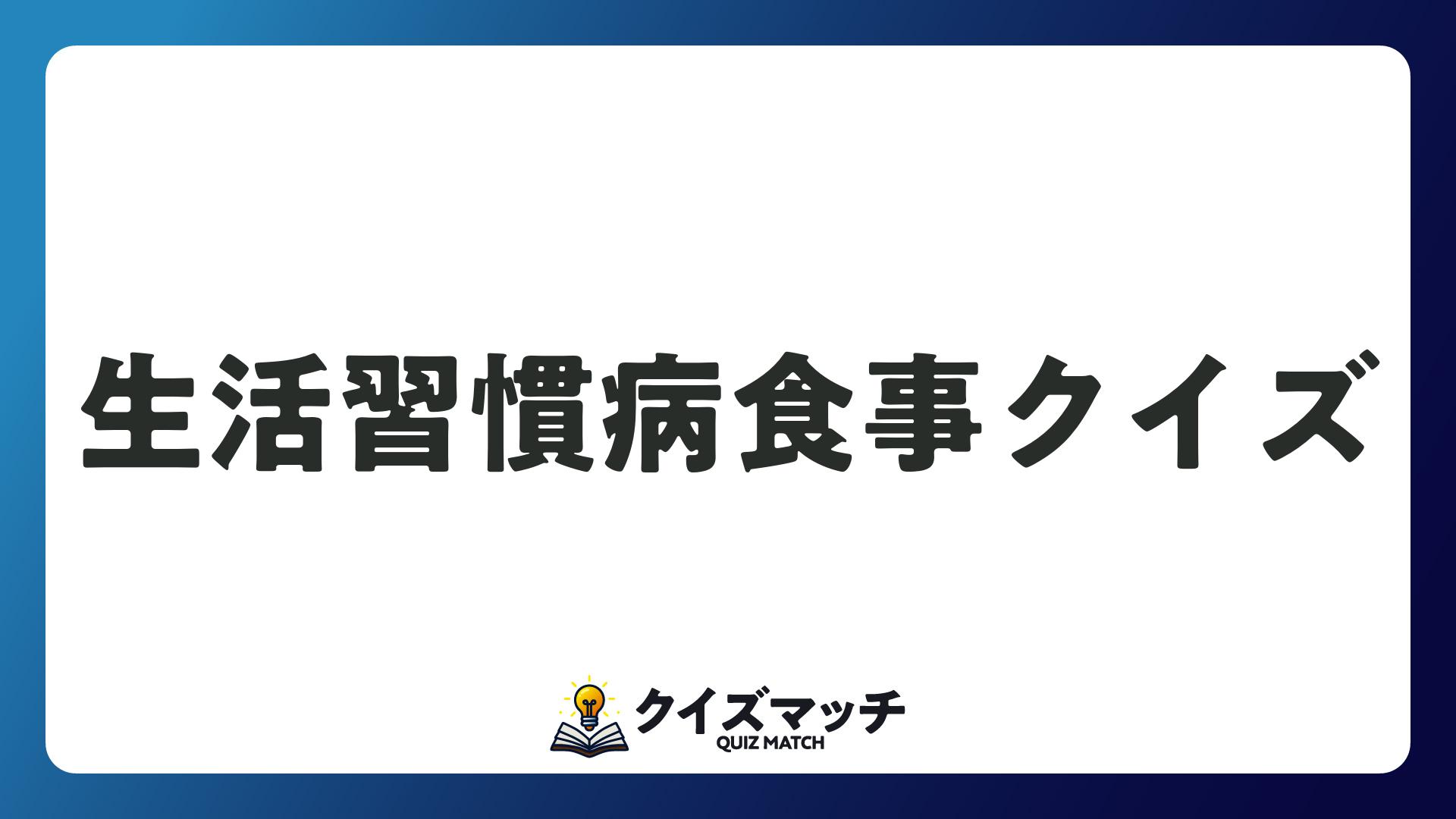生活習慣病の予防には食事が重要な役割を果たします。今回は、食事と生活習慣病をテーマにしたクイズをお届けします。日本人の食事摂取基準や動脈硬化、糖尿病、高尿酸血症など、生活習慣病の発症に深く関わる食事の知識を問います。ご自身の食生活を振り返りながら、健康的な食事のポイントを再確認してみてください。10問のクイズを通して、生活習慣病予防のための食事のヒントが見つかるはずです。
Q1 : 厚生労働省の食事バランスガイドが示す1日あたりの野菜摂取目標量はおよそ何gか?
「健康日本21」や食事バランスガイドでは、野菜類を1日350g以上摂取することを国民に推奨している。緑黄色野菜120g、淡色野菜230g程度を目安にすると、ビタミン、ミネラル、食物繊維、抗酸化物質がバランスよく確保でき、高血圧や脂質異常症、がんなど多くの生活習慣病リスクが低下する。生野菜だけでなく、蒸す、煮るなど調理法を変えて体積を減らすと達成しやすい。
Q2 : 動脈硬化予防の食事で推奨される飽和脂肪酸エネルギー比率の上限は総エネルギーの何%未満か?
動脈硬化の進展には血中LDLコレステロールが深く関与しており、飽和脂肪酸の摂取割合を減らすことが有効とされる。日本動脈硬化学会や米国心臓協会は飽和脂肪酸を総エネルギーの7%未満に抑える目標を示している。例えば2000kcalの食事なら飽和脂肪酸は約15g以下となる。脂身肉やバターを控え、魚、豆、オリーブ油へ置き換えることで、HDLを保ちつつLDLと総コレステロールを低下させ心筋梗塞リスクが下がる。
Q3 : 日本人食事摂取基準(2020年版)では、高血圧予防のため成人男性の食塩摂取量を1日あたり何g未満に抑えることが推奨されている?
日本人の平均食塩摂取量は約10g前後とされており、高血圧患者は依然多い。食塩は血液量を増加させ血管壁に負担をかけるため、厚生労働省は男性7.5g未満、女性6.5g未満を目標に掲げている。加工食品、外食、漬物、汁物などを見直し、香辛料やだしで減塩することが生活習慣病の一次予防に非常に重要とされる。
Q4 : 日本人男性のメタボリックシンドローム判定に用いられる腹囲基準値は何cm以上か?
ウエスト周囲径は内臓脂肪の蓄積を簡易的に推定でき、メタボリックシンドローム診断では必須項目となる。日本人男性では85cm、女性では90cmが基準で、これを超えると高血圧・脂質異常・高血糖が複合して発症しやすいと報告されている。腹囲を減らすには運動習慣とともに、甘い飲料や脂質の多い食事を控え、野菜・魚中心のエネルギー制限が推奨される。
Q5 : 炭水化物を過剰摂取した場合、特にリスクが高まる生活習慣病はどれか?
過剰な糖質摂取で一番問題になるのは血糖とインスリンの急上昇で、これが長期に続くと膵臓β細胞が疲弊し、インスリン抵抗性も高まる。その結果代表的に発症するのが2型糖尿病である。骨粗鬆症や痛風も食事由来の疾患だが、直接の主因は糖質ではなくカルシウム不足やプリン体過多である。COPDは肺の病気で糖質とは別系統。主食量の見直しや食物繊維追加が有効策となる。
Q6 : LDLコレステロールを低下させる働きがあるとされる脂肪酸はどれ?
脂質は種類によって血中コレステロールへの影響が異なる。飽和脂肪酸やトランス脂肪酸はLDLを上げ動脈硬化を促進するが、オメガ3系脂肪酸は逆にLDLを下げ、HDLをわずかに増やし、血小板凝集抑制や炎症抑制作用も示す。青魚や亜麻仁油、えごま油に豊富で、週2回以上の魚食や植物油への置換が推奨される。オメガ6系も必要だが摂りすぎは望ましくないためバランスが重要とされる。
Q7 : 食後血糖の急上昇を抑えるとされる「食べる順番」の組み合わせとして適切なのはどれ?
食後高血糖は動脈硬化のリスクを高め、糖尿病の発症・進展に関わる。最初に食物繊維を多く含む野菜を食べると胃内での糖吸収が緩やかになり、主菜のたんぱく質・脂質がさらに胃排出を遅らせるため、最後に主食を取る順序が最も血糖上昇を抑える。逆に白飯を真っ先に食べると血糖スパイクが起こりやすい。咀嚼回数を増やす、食べる速度を落とす工夫と併用するとより効果的である。
Q8 : WHO等が示す節度ある飲酒の上限として、男性の1日純アルコール量目安は何gか?
アルコールは適量であっても血圧を上げる作用があるため、日本高血圧学会やWHOは純アルコール20g/日以内を節度ある飲酒量の上限として示している。20gはビール中瓶1本、日本酒1合、ワイン2杯程度に相当する。40gを超えると収縮期血圧が平均5〜6mmHg上昇するという疫学データがあり、高血圧薬の効果を相殺する場合もある。休肝日を設け、糖質オフの酒や水割りを選ぶ工夫も重要である。
Q9 : 低GI食品の例として最も適切なものはどれ?
GI値は食品を食べた後の血糖上昇速度を示す指標で、55以下が低GIとされる。そばは主にでんぷんだが、ポリフェノールのルチンや食物繊維が豊富で消化吸収が緩やかなためGIは50前後と低い。白米や食パンは70〜90、うどんも65程度と比較的高GIで血糖が急上昇しやすい。低GI食品を選ぶことでインスリン分泌負荷を減らし、2型糖尿病や肥満のリスクを低減できる。食物繊維の併用調理がさらに効果を高める。
Q10 : プリン体が比較的少なく、高尿酸血症予防に推奨される食品はどれ?
痛風の原因になる高尿酸血症は、体内のプリン体代謝が産生する尿酸の過剰と排泄低下が重なることで起こる。レバーやかつお節、ビールはプリン体含有量が多く、過剰摂取で血中尿酸値が上がる。一方牛乳やヨーグルトなどの乳製品はプリン体が少ないうえ、カゼインホスホペプチドが尿酸排泄を促すとの報告もある。適切な水分摂取、果糖飲料の制限、体重管理を行うと予防効果がより高まる。
まとめ
いかがでしたか? 今回は生活習慣病 食事クイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は生活習慣病 食事クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。