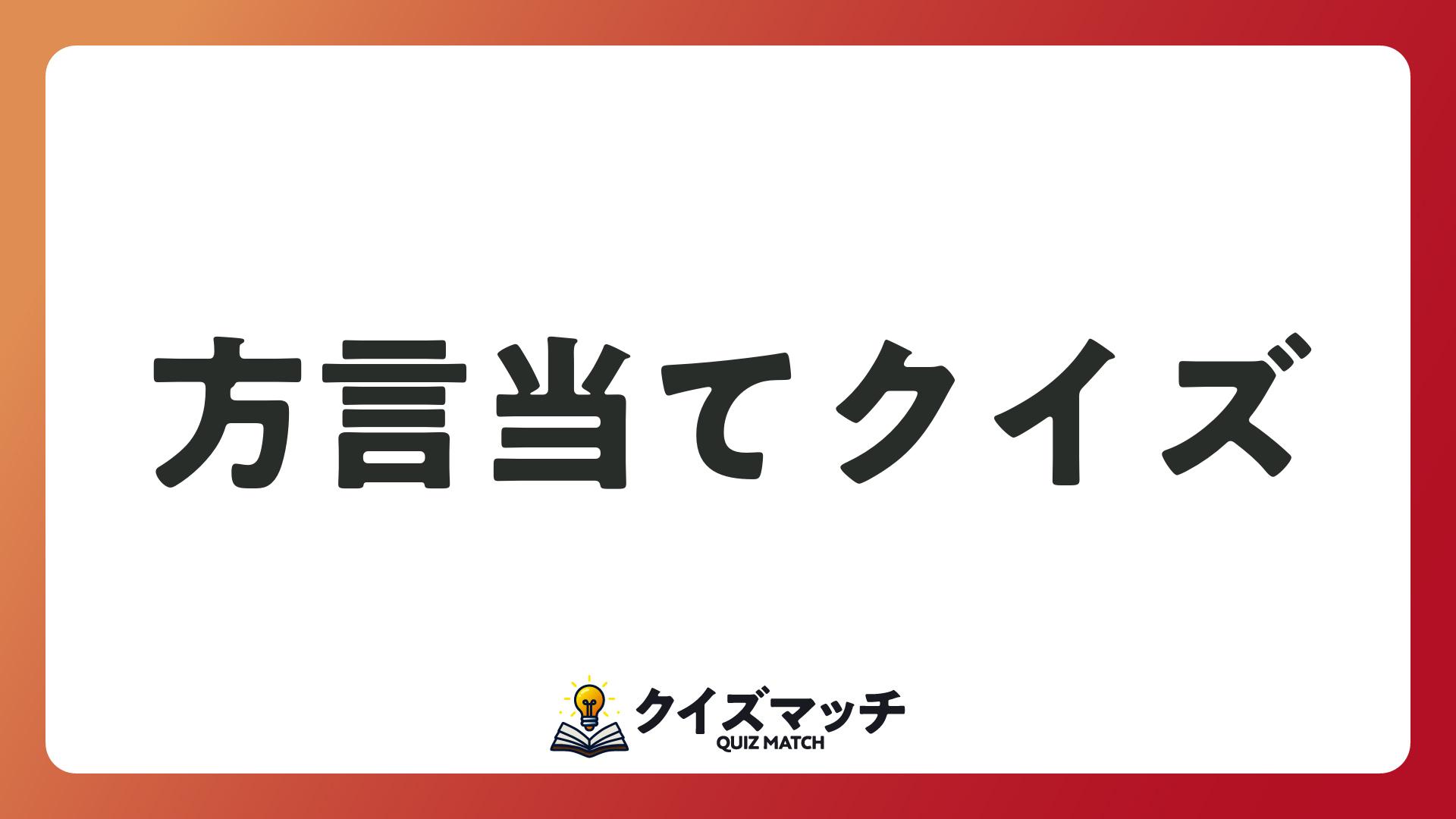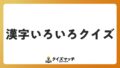方言が織りなす地域のおもしろさ。忘れられがちな方言にスポットライトを当てる「方言当てクイズ」をお届けします。首都圏の人には聞き慣れない表現も、各地の生活習慣や気質を反映した個性豊かな言葉ばかり。県民性や歴史を感じ取れる貴重な言語遺産を、クイズを通して楽しく学んでいきましょう。首都圏と地方の”言葉の壁”を越えて、お互いの地域文化に触れる良い機会になれば幸いです。
Q1 : 東北や北海道で聞く「しゃっこい」という言葉の意味として正しいものはどれ?
「しゃっこい」は東北北部と北海道で用いられる形容詞で、標準語の「冷たい」と同義。井戸水や雪に触れて「手がしゃっこい」と言うのが典型例で、氷菓やビールなどを褒めるときにも「しゃっこいからうまい」と使う。音変化で関東の年配が使う「ひゃっこい」と同根とされ、寒冷地の生活文化を背景に定着した。冬の厳しさを肌で感じる地域ならではの語で、他地方の人にも語感で意味が伝わりやすく観光PRにも活用される。方言菓子「しゃっこいサブレ」など商品名にも登場し、方言そのものがブランド価値になっている。
Q2 : 名古屋周辺で多用される「えらい」はどのような意味で使われることが多い?
名古屋弁の「えらい」は身体的な疲労やしんどさを表す。「今日はえらいでかんわ」は「今日は疲れて仕方ない」という意味。古語の「労る(いたわる)」や「依頼(えらい)」が変化したとする説があり、江戸時代の尾張方言資料にも確認できる。岐阜・三重など中部圏では通じるが他地域では「偉い」と誤解されやすく、テレビの街頭インタビューで「えらいで歩けん」と答えた高齢者の発言が全国放送され、視聴者の混乱を招いた例もある。仕事量の多さや夏の暑さなど、精神的・肉体的ストレス全般に幅広く使え、生活密着度の高い語だ。
Q3 : 博多弁の質問表現「とっとーと?」の意味として正しいものはどれ?
博多弁では動詞の連用形に完了を示す「とー」や「っとう」が付き、さらに疑問の終助詞「と?」が加わることで「取っているの?」を意味する「とっとーと?」となる。カフェで荷物が置かれた席を指し「この席、とっとーと?」と尋ねるのが典型例。相手が「とっとーよ(取っているよ)」と答えれば使用中、取っていなければ「とっとらん」と否定形で返す。福岡のテレビドラマや観光ポスターにも頻出し、リズミカルな響きが博多弁のアイデンティティを象徴する。活用例を覚えておくと現地でのコミュニケーションがスムーズになるため、旅行ガイドでも必須表現として紹介される。
Q4 : 福岡方言で強調に使う「ばり」の意味として最も近いものはどれ?
九州北部、とりわけ福岡市内の若者言葉として定着した「ばり」は、標準語の副詞「とても」「すごく」に対応する。「ばり寒い」「ばり楽しい」など形容詞・形容動詞を強めるほか、名詞に付けて「ばりテンション」などカジュアルに使う。語源は英語「very」説や荷を張って計る際の「張り」説など諸説あるが決着していない。1990年代の博多系バンドの歌詞で全国に知られ、現在も地元高校生の会話に頻繁に登場する。関西の「めっちゃ」、東京の「超」と同機能ながら語感が硬く勢いがあり、会話をエネルギッシュにする働きがある。県外では伝わりにくいが一言で地元色を演出できる便利な方言だ。
Q5 : 北海道弁「じょっぴんかる」は標準語で何をすること?
「じょっぴんかる」は北海道全域で高齢者を中心に用いられる動詞で「鍵をかける」の意。名詞形の「じょっぴん」は錠前を指し、そこから動作を表す「かる(掛る)」が付いた複合語とされる。開拓期に北前船で伝わった北陸方言「じょう(錠)」や英語「pin」が混ざった説があり、方言史研究でも注目される。冬の厳しい寒さと防犯意識が高い土地柄から戸締りを重視した結果、生活語として深く浸透した。使い方は「戸をじょっぴんかっといて」で依頼形、「じょっぴんかっとくわ」で完了形とバリエーション豊か。道外ではほぼ通じないが、バラエティ番組で紹介されることも多く北海道のユニークさを象徴する語になっている。
Q6 : 鹿児島など南九州で使われる「なんぼすっと?」は標準語で何を尋ねている?
南九州方言の「なんぼすっと?」は買い物などで値段を尋ねる際に使う。「なんぼ」は数値や価格を問う疑問詞で関西弁とも共通し、「すっと?」は「するのと?」が音変化したものと考えられる。魚市場で「このカツオはなんぼすっと?」と聞けば店主が価格を答えるのが日常風景。鹿児島弁は語尾が平板で語中が強く発音されるため、同じ言葉でも抑揚が異なり聞き取りには慣れが必要。歴史的に薩摩藩は琉球や中国大陸と交易が盛んで商取引の表現が発達したと言われる。観光客が覚えておくと値段交渉が和やかになり、地元の人との距離が縮まる便利なフレーズである。
Q7 : 宮崎弁の「てげてげ」という言葉の意味として正しいものはどれ?
「てげ」は宮崎弁で「とても」「大変」という意味を持つが、同じ語を重ねた「てげてげ」は逆に「ほどほどに」「適当に」という脱力したニュアンスを示す。作業を厳密にし過ぎず肩の力を抜いて行う場面で「てげてげでよか」と言う。鹿児島など隣県ではあまり用いられず宮崎特有とされる。強調語が重なることで「力を抜く」方向へ転化するという語の変化が方言らしい面白さを生んでいる。テレビや漫画でも紹介されるほど知名度は高く、県民の気質「おおらかさ」を象徴する言葉としても知られる。
Q8 : 北海道や関西でも使われる「わや」という方言の意味として正しいものはどれ?
「わや」あるいは「わやくちゃ」は上方ことばが北へ伝わったとされ、現在は北海道から関西圏まで幅広く使われる。「めちゃくちゃ」「台無し」「ひどいありさま」を指し、大雪で交通が麻痺した際に道民が「今日は道路がわやだわ」と言うように程度の大きさを表現するのが特徴。語源は古語の「無や(わや)」=むだ・無益とも言われる。若者から高齢者まで世代を問わず使うが、地域外では意味が通じにくく、状況説明の際に誤解が生じることもある。混乱ぶりや困難さを一語で強く印象づけられる便利な方言である。
Q9 : 岡山などで使われる方言「こわい」は標準語でどのような意味になる?
中国地方、特に岡山で「こわい」は身体がきつい、筋肉痛でだるいといった状態を指す。古語「こはし(強し)」が弱化して体がこわばる感覚を表すようになり、そこから疲労の意味へ転じたと考えられる。農作業後に高齢者が「今日はこわい」と言えば「今日は疲れた」という意味で恐怖とは無関係。医療現場で患者が「背中がこわい」と訴え、医師が痛みや凝りとして理解するなど、地域特有のコミュニケーションが成立している。県外者は「怖い」と誤解しやすいが、日常会話では極めて頻出する生活語彙である。
Q10 : 京都で耳にする「いけず」という言い回しの意味として正しいものはどれ?
京都ことばの「いけず」は相手の言動が意地悪であることを柔らかく、しかし辛辣に指摘する語で、標準語の罵倒語よりは婉曲ながら確かな非難を含む。たとえば道を尋ねられてわざと遠回りの経路を教えた人に対し「ほんま、いけずやわぁ」と言う。京都人の間では親しみを込め軽い冗談として使う場面もあるが、度が過ぎると本気の叱責になるので使い手のトーンでニュアンスを読み取る必要がある。古くは江戸期の文献にも見られ、京都の気質を象徴する語としてドラマや小説に頻出。全国的に有名なため観光客が真似して使うが、場合によっては角が立つこともあるので注意が必要だ。
まとめ
いかがでしたか? 今回は方言当てクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は方言当てクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。