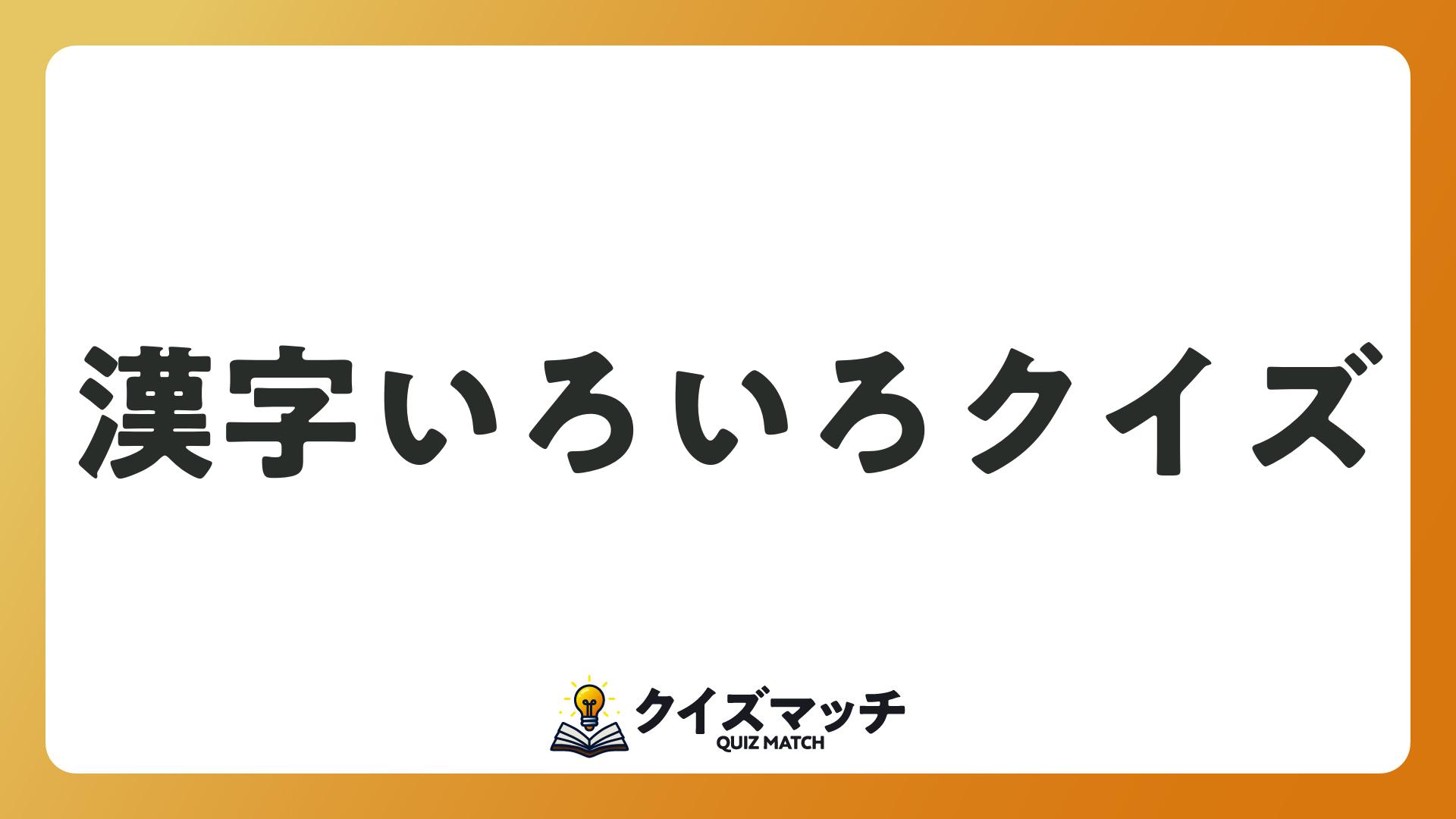日本語の中に潜む複雑な漢字の世界。『漢字 いろいろクイズ』では、見慣れた文字の中に隠された豊かな歴史や知識を発見していきます。部首、読み方、成り立ちなど、漢字の多様な側面に迫る全10問。漢字を深く理解することで、日本語の奥深さに新たな一歩を踏み出せるはずです。漢字の魅力を存分に堪能していただきたい、刺激的なクイズ特集です。
Q1 : 漢字『頰』の部首として正しいものはどれ?
『頰』はほおを意味し、部首は頁(おおがい)である。頁は人の頭部を象り、頭や顔に関する漢字に多用される。頰では頁が右側にあり、左の从は部首には数えられない。月はにくづきで身体一般、貝は財貨、顔は独立した形声文字なので部首にはならない。辞典の索引では部首が頁、画数は16画で引くことになる。頬の旧字体であり、公用文では常用外ながら人名用漢字として使用が認められている。
Q2 : 『杞憂』の『杞』の部首はどれ?
『杞』は木偏を持つ形声文字で、中国古代の杞国を示す国名漢字。故事『杞人天を憂う』から生まれた熟語『杞憂』は取り越し苦労の代表例として知られる。木は植物や木材を表す部首で、左に位置する偏は辞書編纂上も部首に採られる。禾は稲穂、欠は欠ける、心は心臓の象形で意味も配置も一致しない。漢字検定では部首と総画数を同時に問うパターンが多いので、杞が7画であることも併せて覚えると効果的である。
Q3 : 『躍起』などで用いられる漢字『躍』の総画数として正しいものはどれ?
『躍』は足偏と旁の翟から成る形声文字で、足偏が7画、翟が14画で合計21画となる。翟は長い尾を持つ鳥を描いた象形で、跳躍の意が派生し足偏と結び付いた。画数問題では足偏を6画と誤認したり、旁の点画を省略して18画や19画と数えるミスが頻出する。23画は最後の払いや点を重複して計算した例で典型的な誤答。漢検準2級以上では21画が正答とされ、正確な筆順と画数の把握が要求される。
Q4 : 魚へんに弱いと書く漢字『鰯』の部首はどれ?
『鰯』はイワシという魚を示す国字系の漢字で、左側の魚へんが意味を担う部首になる。魚へんは魚介類を表す偏で、鯛、鮪、鱈などと同じ系統に属する。漢和辞典では部首番号195に分類され、辞書検索の際も魚へんから探す。右側の弱の部分は形声文字における音を示す旁であり、部首とは見なされない。木へんや貝へん、金へんは意味的にも形状的にも一致しないため誤答となる。
Q5 : 次のうち漢字『梟』の読みとして正しいものはどれ?
『梟』は夜行性の猛禽フクロウを象形した漢字で、古代の甲骨文字では首を反転させた鳥の姿が刻まれている。音読みはキョウ、訓読みはフクロウで、現代日本語では主に訓読みで生物名を表記する。梟雄など比喩的表現では音読みが用いられるが、鳥自体を指す場合はフクロウが一般的。キジは雉、タカは鷹、スズメは雀と別の漢字を用いるため誤答である。
Q6 : 漢字『齎す』の読みとして正しいものはどれ?
『齎す』はもたらす、携えて行くという意味を持つ漢字で、古語では「結果を齎す」「吉報を齎す」のように使われる。形声文字で、齊が音を示し貝が財貨を運ぶ象形から財を携える意が転じ、何かを運び届ける一般動詞になった。つどうは集う、いそしむは勤しむ、うながすは促すで読みも意味も異なる。現代文では仮名書きが多いが、公用文でも使用可能な表外漢字である。
Q7 : 『檸檬』の正しい読みはどれ?
『檸檬』は中国語音を基に日本で作られた表記で、レモンを意味する。梶井基次郎の短編『檸檬』の題名としても著名で、文学的イメージが強い。音読みはレイモウだが慣用では外来語に合わせた訓読みレモンが定着した。ザクロは石榴、ダイダイは橙、ミカンは蜜柑と書き、いずれも別種の果物を指すので誤り。和名としては檸檬のほか檸檬果とも書くが、日常ではほぼカナ表記で流通する。
Q8 : 『あきらめる』という意味で用いられる一文字漢字はどれ?
『諦』は元々「あきらかに見る」を表したが、仏教の四諦に由来して執着を離れるという意味が派生し、日本語では「あきらめる」の訓が定着した。「諦観」は物事を見極め悟る態度を示す語である。憩は休む、慎はつつしむ、慰はなぐさめるで、いずれも断念の意を持たない。常用外ではあるものの、高校入試や漢検では頻出し、意味と読みを同時に問われるため注意が必要である。
Q9 : 四字熟語『侃々諤々』の一字目『侃』の読みとして正しいものはどれ?
『侃』は人偏に岸の右側が付いた形声文字で、強直、剛直を意味し音読みはカン。侃侃諤諤は正義を曲げずに堂々と意見を述べ合うさまを表す。中国史書にも剛直な人物を評する際にこの字が用いられる。ケンは倹や献、ゲンは言や玄、キンは謹などが代表で、侃に対応しない。常用外漢字ながら新聞では引用符付きで用いられる例もあり、政治討論などの語彙として覚えておくと理解が深まる。
Q10 : 『謳う』の読みとして正しいものはどれ?
『謳う』は口偏に区の字を配した形声文字で、訓読みはうたう、音読みはオウ。理念や主張を高らかに表明するニュアンスがあり、単に歌唱を示す『歌う』よりも格調高い印象を与える。となえるは唱える、かたるは語る、むさぼるは貪るで読みも意味も異なる。法律や条文では「基本的人権を謳う」など抽象的内容を示す場面が多く、表記の差異が試験で出題されやすいので注意したい。
まとめ
いかがでしたか? 今回は漢字 いろいろクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は漢字 いろいろクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。