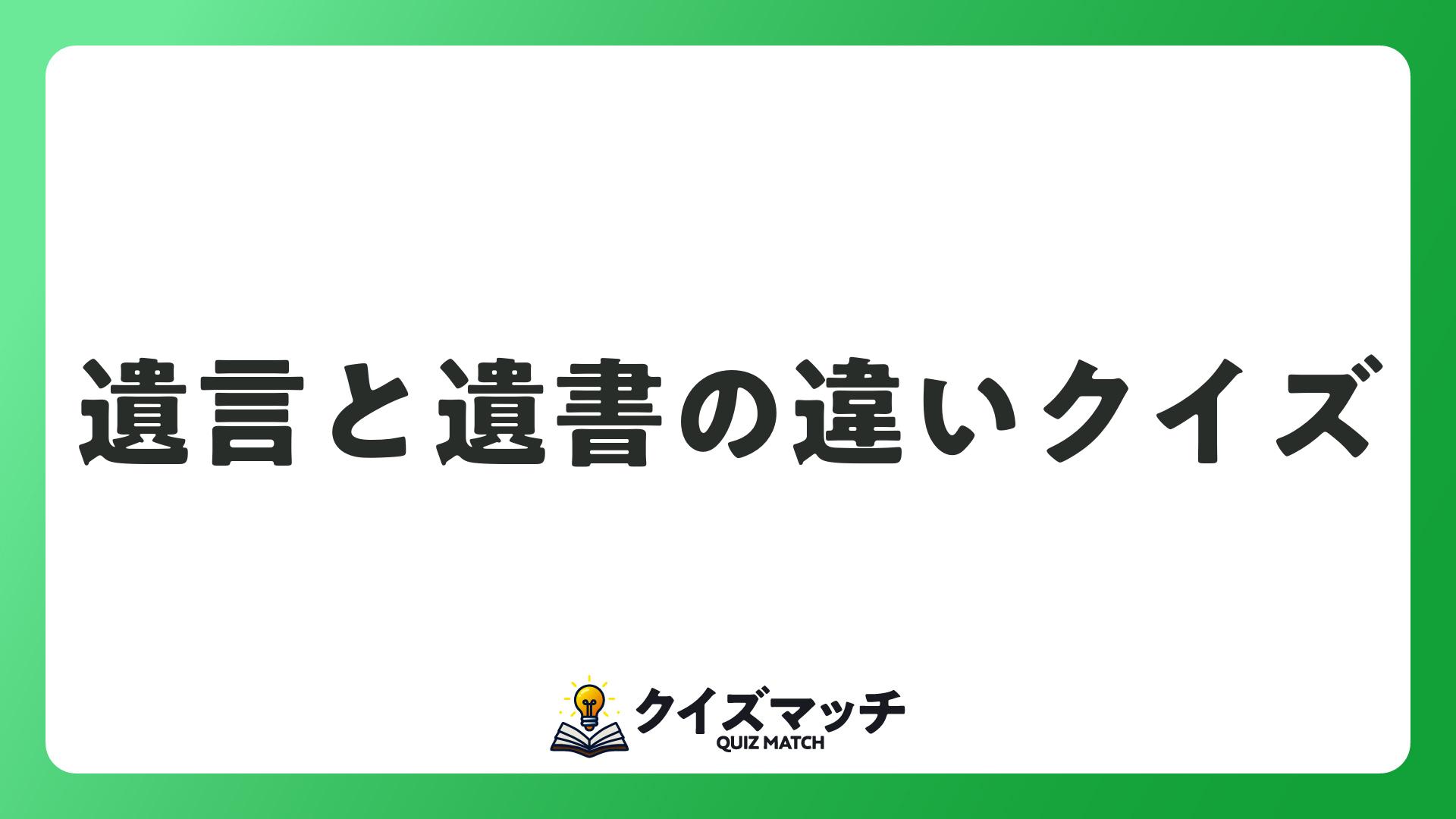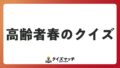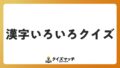遺言と遺書の違いを知っていますか?法律上、遺言は民法に定められた正式な方式を満たしていますが、遺書はそうした要件を欠いています。しかし、遺書にも故人の思いが込められていることがあります。本記事では、遺言と遺書の違いを10問のクイズで解説していきます。遺言の種類や検認手続、無効要件、そして遺書の取り扱いなど、相続に関する基本的な知識を確認できるでしょう。遺産相続をめぐるトラブルを未然に防ぐためにも、ぜひ最後まで読み進めてみてください。
Q1 : 封のある遺言書を家庭裁判所の検認前に開封した場合、民法で定められている制裁として正しいものはどれか。
民法1005条は、封印された遺言書は家庭裁判所で相続人立会いのもと開封しなければならないと規定し、これに違反して勝手に開封した者には5万円以下の過料が科されると定めている。刑法上の懲役や罰金刑ではなく、行政罰である過料である点が特徴で、前科にはならないが、公文書違反ではない。過料制度は検認手続の公正さを担保し、改ざんや紛失のリスクを抑制する目的で設けられている。従って正しい答えは5万円以下の過料である。
Q2 : 法律上無効と判断された遺書・遺言であっても、その内容を尊重して遺産を分けるために相続人全員の合意のもとで行われる手続として最も適切なのはどれか。
方式を欠く遺言は法的効力を持たないが、相続分は相続人全員が任意に変更できる。相続人全員が集まり遺産分割協議を行い、無効な遺言の内容を参考に協議書を作成すれば、法定分割と異なる配分でも有効に成立する(民法907条)。協議が整えばその内容が最終的な権利関係を決定し、登記や預金解約も可能となる。家庭裁判所の調停は合意ができない場合の補助的手続であり、検認は遺言の形式確認に過ぎず、無効な遺言を蘇らせる効力はない。したがって最も直接的かつ確実な方法は相続人全員による遺産分割協議である。
Q3 : 家庭裁判所での検認手続が法律で義務付けられている方式はどれか。
自筆証書遺言は民法1004条により開封前に家庭裁判所での検認が必要とされる。検認は遺言の真正を担保し、内容を確認する手続であって、効力の有無を判断するものではない。公正証書遺言は公証人が作成し原本が公証役場に保管されるので改ざんの恐れが低く、検認不要とされる。単なる遺書はそもそも遺言としての方式を欠くため、法的に検認の対象外である。したがって検認が必須なのは自筆証書遺言のみである。
Q4 : 自筆証書遺言が民法の方式を満たすために必ずしも必要ではない要素はどれか。
自筆証書遺言は民法968条により、遺言者がその全文、日付および氏名を自署し、押印することが要件とされる。証人の立会いや署名は求められていない。証人が必要となるのは公正証書遺言(証人2人)や秘密証書遺言(証人2人以上)の場合である。したがって証人2人の立会いは自筆証書遺言にとって必須ではなく、これがなくても方式に適合すれば有効な遺言となる。一方、遺書にはそもそも法律上の方式が定められていない。
Q5 : 遺言事項のうち、遺言執行者がいない場合は相続人や利害関係人が家庭裁判所に選任申立てを行う場面が特に多いとされるのはどれか。
推定相続人の廃除は民法893条以下に定める手続で、遺言によって行う場合、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求を行わなければならない(民法894条2項)。遺言執行者がいないと、利害関係人が改めて選任の申立てをしなければ手続が進まないため、遺言内容の実現が大幅に遅れる。祭祀承継者の指定や遺贈は相続開始と同時に効力を生じ、認知も届出さえされれば足りるため、執行者がいなくても実務上の支障は比較的小さい。よって推定相続人の廃除が最も煩雑になりやすい。
Q6 : 次のうち、遺書の形で作成した文書を法律上有効な遺言として確実に残すため、最も直接的に活用できる制度はどれか。
2020年7月に開始した自筆証書遺言保管制度では、法務局が書面を形式チェックのうえ保管し、原本紛失や改ざんを防止する。自筆証書遺言は全文を自書し日付・署名押印があれば足りるので、もともと遺書として書かれた文書を要件に合わせて書き直せばそのまま受付可能である。検認手続は死亡後に行うもので、作成段階では遺言の有効性を担保しない。確定日付や弁護士預託も参考にはなるが方式要件の確認や検認省略にはつながらない。したがって最も直接的なのは自筆証書遺言保管制度である。
Q7 : 遺言が方式や要件を欠いて無効になる典型例として、次のうち誤っているものはどれか。
遺言能力は民法961条により15歳に達した者に認められており、15歳以上であれば成年に達していなくても単独で有効な遺言を作成できる。したがって18歳未満の者が遺言を書いたというだけで当然に無効になるわけではなく、15歳以上なら有効となり得る。それ以外の選択肢は無効事由に該当する。公序良俗違反の内容は無効、日付欠落は自筆証書遺言として無効、本文を自書せずパソコン印字では民法968条の自書要件を満たさず無効となる。
Q8 : 遺書として残された文書が遺言の方式を満たすかが争われた裁判例で、主な争点となった要素はどれか。
自筆証書遺言か否かを巡る訴訟では、全文を自書したか否かが核心となるため、手書きかワープロ打ちかが最重要論点になることが多い。平成12年3月10日最高裁判決は、ワープロ打ちされた遺言書が自筆証書遺言の要件を欠くとして無効と判断した。紙の大きさや文字数、印鑑の種類などは真意や改ざん防止に関わる補助的事情に過ぎず、方式要件を左右しない。従って、手書きか打ち込みかが判例上も最大の焦点となった。
Q9 : 被相続人の死後、家族が遺書のようなものを見つけられない場合、まず公的に有無を確認する方法として最も適切なのはどれか。
自筆証書遺言保管制度では、遺言者の死亡後、相続人等が法務局に対して『遺言書情報証明書』の交付を請求できる。この請求を行えば、生前に保管されていたかどうかを確認でき、存在する場合は内容の写しも取得できるため、遺言の有無を迅速かつ確実に判定できる。公証役場の検索は公正証書遺言が対象だが、相続人が直接端末で自由に閲覧することはできず、照会手続にも委任状などが必要で即時性に欠ける。遺言不存在確認訴訟や分割協議は、遺言の有無を確認した後に行うべき手続である。
Q10 : 民法で定められた正式な方式を満たしておらず、亡くなった人の思いやメッセージを書き残しただけの文書一般を指すものはどれか。
遺言は民法960条以下に方式が定められており、方式を欠くと無効となる。公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言はいずれも法律上の遺言の種類で、相続分の指定や遺贈などが法的効力を持つ。一方、遺書という言葉には正式な定義がなく、単に本人の思いを伝える手紙に留まることが多い。方式を満たさない限り相続財産の分配を左右する効力は生じず、慰謝や感情の伝達を目的とした私的文書として扱われることが多い。
まとめ
いかがでしたか? 今回は遺言と遺書の違いクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は遺言と遺書の違いクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。