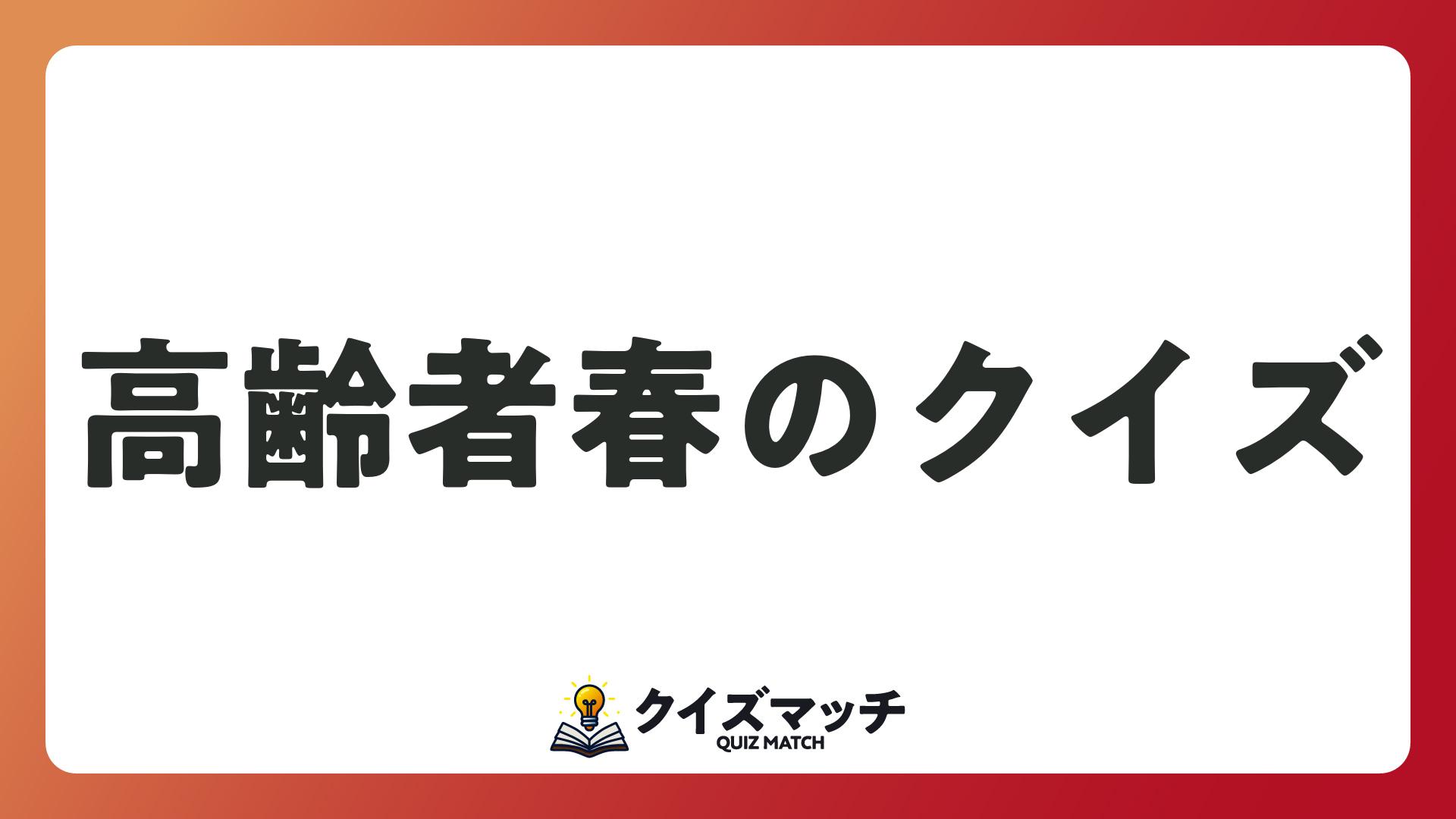春爛漫の季節がやってきました。春の訪れを感じさせる自然の兆しや行事がいくつもありますが、そんな春ならではの出来事をご存じでしょうか。気象庁の桜開花発表や伝統的な雛祭り、そして春告鳥ウグイスのさえずりなど、春の風物詩にまつわる知識を試すクイズを10問ご用意しました。季節の変化を感じながら、楽しみながら回答いただければと思います。春の情景をより深く理解できる一助となれば幸いです。
Q1 : 俳句の季語『春告鳥』といえば何という鳥?
『春告鳥』はウグイスの雅称で、古くは万葉集にもうたわれた日本人になじみ深い鳥です。2月頃から鳴き始める練習声は『さえずり未熟』と呼ばれ、3月頃に澄んだ『ホーホケキョ』が完成します。梅の枝にとまる緑の小鳥はメジロであることが多く外見で混同されがちですが、ウグイスは地味な褐色でヤブの中に潜む習性が強く、鳴き声で存在を示します。春を告げる象徴として多くの俳句で季語に選ばれ、耳から季節を感じる日本独特の自然観を育んできました。
Q2 : 新年度が始まる時期に行われる『春の全国交通安全運動』は通常何月に実施される?
春の全国交通安全運動は毎年4月6日から15日まで行われ、入学式直後の児童や新社会人が街に出るタイミングで交通事故を防ぐことを目的としています。重点項目には高齢運転者の事故防止、自転車ヘルメット着用促進、飲酒運転根絶などが掲げられ、警察・自治体・地域団体が街頭啓発やパレードを実施します。秋には9月に同様の運動がありますが、春は生活環境の変化で注意力が散漫になりやすいため特に重要とされます。全国一斉に取り組むことで交通安全意識を高め、事故抑制に寄与しています。
Q3 : 憲法記念日やこどもの日などが連続する大型連休を一般に何と呼ぶ?
4月末から5月初めに祝日が集中する期間は、1950年代に映画会社が興行成績の良さを宣伝するため『ゴールデンウィーク』と名付けたのが始まりです。現在は4月29日の昭和の日、5月3日の憲法記念日、4日のみどりの日、5日のこどもの日が並び、土日や有給休暇と組み合わせて長期休暇にする人が多いのが特徴です。行楽・帰省・イベントが活発化し、交通機関は繁忙期ダイヤを敷くなど経済効果も大きく、春の観光シーズンを代表する言葉として定着しています。
Q4 : 春の七草の一つ『ナズナ』の別名として最も一般的なのはどれ?
春の七草はセリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベラ・ホトケノザ・スズナ・スズシロの七種です。ナズナはアブラナ科の越年草で、三味線のばちのような三角形の種子袋がぶら下がる姿から『ペンペングサ』の名で親しまれています。道端や畑に自生し、古くから解熱や利尿に用いられた民間薬でもあります。1月7日の七草粥に若い葉を加えることで冬の不足しがちなビタミンを補い、独特のほろ苦さが早春の季節感を食卓に届けてくれる、日本の食文化に根付いた野草です。
Q5 : 3月3日の桃の節句に飾られる伝統的な人形は何?
3月3日の上巳の節句は平安時代の流し雛行事が起源とされ、江戸時代に女児の成長と厄払いを願う雛祭りとして定着しました。雛人形は内裏雛を最上段に三人官女や五人囃子を飾る段飾りが一般的で、桃の花・ひし餅・白酒など春の象徴を添えます。端午の節句で用いる五月人形や鯉のぼりとは対になる行事で、日本の年中行事の中でも豪華な装飾文化を誇ります。雛人形には厄を人形に移して守るという意味もあり、飾り終えた後は早めに片付けることで良縁を招くと伝えられています。
Q6 : 二十四節気で立春の次に当たる節気はどれ?
二十四節気は太陽黄経を15度ごとに分けた中国由来の暦で、日本でも農事暦の指標となってきました。立春(黄経315度)の次が雨水(黄経330度)で、現行暦では2月19日頃に相当します。雪が雨に変わり氷が解けて水になるころという意味で、古くは農耕の準備開始の目安でした。続く啓蟄、春分、清明へと暖かさが増し、梅や早咲き桜がほころびる季節です。雨水に雛人形を飾ると良縁に恵まれるなど生活習俗にも影響し、本格的な春の入口として重要視されています。
Q7 : 春告鳥とも呼ばれるウグイスが最も盛んに鳴くのはいつ頃?
ウグイスのさえずりは繁殖期における縄張り宣言と雌への求愛が目的で、音がよく通り外敵が少ない早朝に集中します。この時間帯は鳥類全体が合唱するモーニングコーラスが起きるため、ウグイスの『ホーホケキョ』も澄んで聞こえやすく、古来より春の風物詩として和歌や俳句に詠まれてきました。夜間は休息、日中は採餌に当てるため鳴き声は減少し、昼の勘違い鳴きは警戒時が多いとされています。早朝の静かな里山で耳を澄ますと、春の到来を感じるウグイスの声を堪能できます。
Q8 : 北海道で桜前線の最終到達を告げる主な品種は?
桜前線は1月の沖縄から北上し、5月上旬に北海道へ達します。寒冷地の北海道では園芸種のソメイヨシノが育ちにくいため、野生種のエゾヤマザクラ(オオヤマザクラ)が主流です。札幌管区気象台もこの品種の標本木で開花を判定します。花は濃いピンクで葉と同時に開くため赤茶色の若葉が混ざるのが特徴です。寒さや潮風に強く、街路樹・公園樹として広く利用され、道内各地の花見名所を彩ります。南北に長い日本列島の気候差が品種と開花時期の多様性を生み、観光資源としても価値を高めています。
Q9 : 立春から春分までの間に吹く強い南風を指し、気象庁が最大瞬間風速を基準に発表する現象は?
春一番は立春から春分の間に日本海を進む低気圧に向かって吹く暖かい南寄りの強風で、最大瞬間風速15メートル以上など複数条件を満たすと気象庁が発表します。漁船転覆など海難事故が多発した江戸時代の長崎県壱岐の漁師が使った言葉が語源とされ、発表は1868年以降の気象記録を参考にしています。強風により気温急上昇・花粉大量飛散・交通乱れを招くため注意喚起が行われます。条件を満たさない年は発表がないこともあり、毎年必ず起こるわけではない自然現象です。
Q10 : 桜の開花宣言で気象庁の標本木が設置されている東京の場所はどこ?
気象庁は東京都千代田区の靖国神社境内にあるソメイヨシノの標本木で開花を判定します。基準は5輪以上の花が咲くことで、同一個体を長年観測することで統計の連続性を保っています。靖国神社の標本木は戦前から存在し、戦後に正式採用されました。報道各社はここで開花情報を中継するため、東京の桜開花の代名詞として全国に広まりました。標本木は各気象台の周辺にもありますが、東京の靖国神社はとりわけ知名度が高く、花見シーズンの指標となっています。
まとめ
いかがでしたか? 今回は高齢者春のクイズをお送りしました。
皆さんは何問正解できましたか?
今回は高齢者春のクイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!
次回のクイズもお楽しみに。