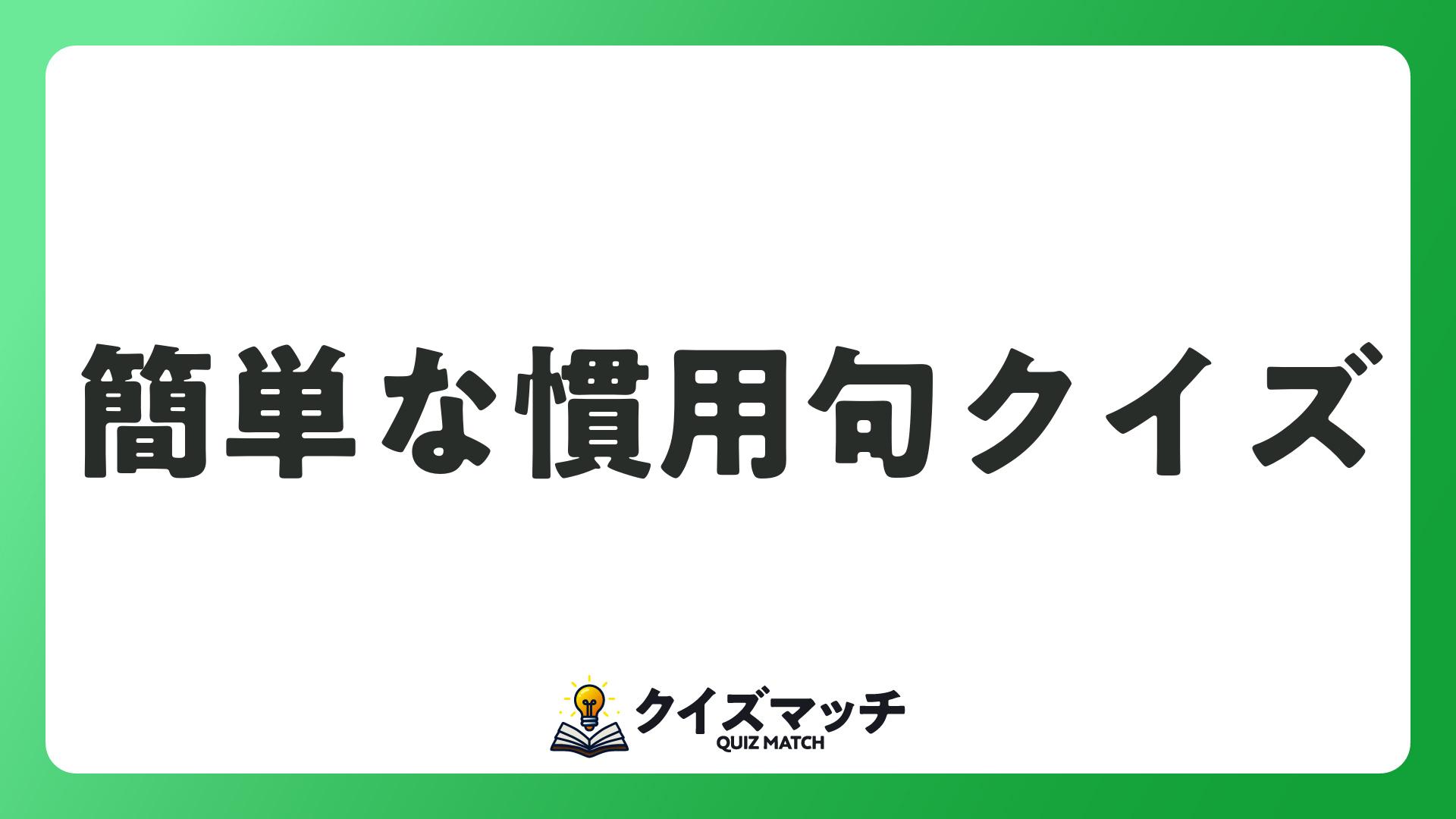慣用句を巧みに使ってお題に沿った楽しい問題を作ることができそうですね。以下が記事のリード文案です。
日本語の慣用句には、長年の歴史と文化が凝縮されています。意味が直接的ではなく、隠喩的な表現が多いのが特徴です。今回は、そんな慣用句の面白さを10問のクイズでお楽しみいただきます。意味の取り違えや知られざる由来など、日本語の妙味を感じていただければと思います。慣用句に詳しくない方も、きっと新しい発見があるはずです。さあ、あなたの慣用句力を試してみましょう!
Q1 : 次の慣用句の意味として最も近いものを選びなさい:『雲をつかむよう』 はっきりしている つかみどころがない とても簡単だ 確実に成功する
「雲をつかむよう」は雲という形の定まらないものをつかむ行為を喩えにし、物事が漠然として実態がつかめないさまを言う。鎌倉期の文学にも例があり、手がかりが乏しく、目標や状況が不明瞭であることを示す。転じて計画が曖昧、話が現実味に欠けるといった否定的文脈で使われることが多い。対義的な表現は「地に足がつく」「筋道が立つ」などで、雲という自然現象の手に負えなさが比喩の核心となっている。
Q2 : 次の慣用句の意味として最も近いものを選びなさい:『耳を疑う』 目を閉じる 聞き間違える 信じられない思いになる 静かにする
「耳を疑う」は信じがたい情報を聞いたとき、本当に自分の耳に入ったのかと疑念を抱くことを示す。古くから「耳」は情報の入口とされ、その感覚器自体を疑うほど衝撃を受ける様子を誇張して表現する。歓迎すべき朗報にも悪い知らせにも使えるが、特に常識を覆すニュースや予想外の発言に対し使われる。英語の“can’t believe my ears”に相当し、驚愕や動揺を含む点が大きな特徴である。
Q3 : 次の慣用句の意味として最も近いものを選びなさい:『気が置けない』 遠慮が要る 心許ない 遠慮が要らない 油断できない
「気が置けない」は本来「遠慮する必要がないほど親しい」という肯定的な意味を持つ。しばしば「油断できない」と誤用されるが、正しくは相手に対して気兼ねや形式張った配慮をする必要がなく、打ち解けている状態を指す。語源は平安期の和歌で、相手との間に「気(心遣い)」を置かない関係から転じた。用例として「彼とは気が置けない仲だ」のように使われ、親友や家族、同僚など近しい間柄を示す。
Q4 : 次の慣用句の意味として最も近いものを選びなさい:『顔が広い』 知り合いが多い 顔が大きい 自信がある 顔色が悪い
「顔が広い」は「顔(存在)が世間に知れ渡っている」という比喩で、人脈が豊富で多方面に知り合いがいることを表す。古くは能役者や商人の評判を示す言い回しとして用いられ、現代ではビジネスや芸能界などで交友関係の広さを称える語として使われる。単に人気者というより、利害関係を含む幅広いネットワークを持ち、困った時に助力を得やすいニュアンスがある。反意表現は「顔が狭い」。
Q5 : 次の慣用句の意味として最も近いものを選びなさい:『のどから手が出る』 とても欲しい 叫びたい むせる 手が疲れる
「のどから手が出るほど欲しい」と続けて使われ、非常に強く欲するさまを誇張的に示す慣用句。身体の内部である喉から手が突き出るというありえない状況を想像させることで、欲求の激しさを強調する。江戸後期の滑稽本にも見られる古い表現で、金品だけでなく情報や機会を切望する場合にも使う。単なる「欲しい」より切実さが強い点が特徴で、願望の度合いを示す指標として広く用いられている。
Q6 : 次の慣用句の意味として最も近いものを選びなさい:『足を引っ張る』 協力する 邪魔をする 急いで進む 足を怪我する
「足を引っ張る」は、他人の進行や成功を妨げる行為を指す。古くは相撲や捕物で相手の足を掴み転倒させる行為から転じたと言われ、現代ではチームや組織で成果を下げる行動や、妬みからの妨害を指す比喩として用いられる。意図的・無意識の両方で使われ、単に遅れを取るだけでなく、他者の成長や計画を阻むニュアンスが強い。ビジネスやスポーツ、政治など様々な場面で耳にする身近な表現である。
Q7 : 次の慣用句の意味として最も近いものを選びなさい:『腕を上げる』 技術が向上する 腕を負傷する 腕相撲をする 手を挙げ降参する
「腕を上げる」は腕力ではなく技能・技量が向上することを示す。職人の作業や芸事で上達すると称賛する際に用いられ、腕前=実力という転義から生まれた慣用句である。中世の武家社会でも「武芸の腕を上げる」と使われ、現代でも料理、スポーツ、趣味など多分野で用いられる。行為の結果として得られた実力向上を評価する表現で、客観的成果や周囲の認知が伴う点がポイント。
Q8 : 次の慣用句の意味として最も近いものを選びなさい:『猫の手も借りたい』 時間に余裕がある 非常に忙しい 誰とも話したくない 散歩したい
「猫の手も借りたい」は、どんなに役に立たない存在でも助けが欲しいほど多忙である様子を表す。猫は一般に手伝いにならない存在の象徴として用いられるが、それほど人手が足りず切迫している状況を強調する。江戸時代の商家の帳面にも見られる表現で、現代でも職場や学業で多忙を極めるときに使われる。単なる忙しさではなく、処理しきれないほど仕事が山積みしているニュアンスを含む。
Q9 : 次の慣用句の意味として最も近いものを選びなさい:『二の足を踏む』 勇んで行動する 決断をためらう 後悔する 急いで逃げる
「二の足を踏む」は「二歩目を踏み出せない」という比喩から来ており、物事を始める段になって尻込みし、決断や行動をためらうことを指す。古語の「二の足(にのあし)」は次の一歩を意味し、最初の意欲はあるが、危険や損失を恐れて前進できない状態を示す。ビジネスや交渉、進学など重要な選択で心が揺れるときによく使われ、単なる遅延より心理的ブレーキが強調される点が特徴である。
Q10 : 次の慣用句の意味として最も近いものを選びなさい:『腹が立つ』 驚く 怒る 感謝する 迷う
「腹が立つ」は怒りの感情がこみ上げることを表す語で、古くは「腹」は心や感情が宿る場所と考えられていた。怒りで体内の気がせり上がることから「腹が立つ」と言う。相手の行為や言動に不満や憤りを覚えた時に使われ、単に気に入らない程度の軽い不快感ではなく、かなり強い怒りを示す。日常会話でも頻繁に用いられるごく一般的な慣用句であり、同義語に「頭に来る」「かんかんになる」などがある。
まとめ
いかがでしたか? 今回は簡単な慣用句クイズをお送りしました。
今回は簡単な慣用句クイズを出題しました。
ぜひ、ほかのクイズにも挑戦してみてください!